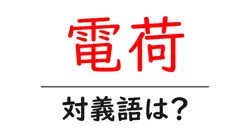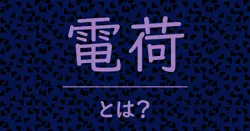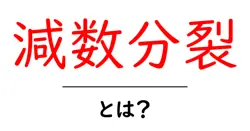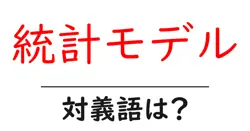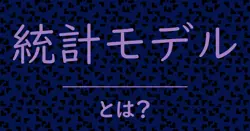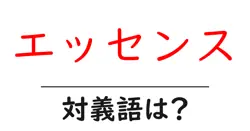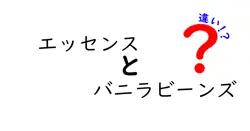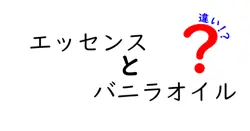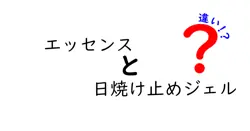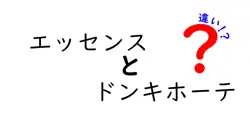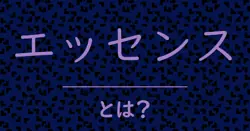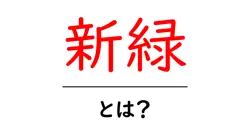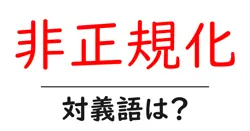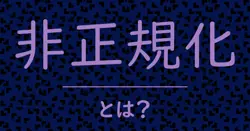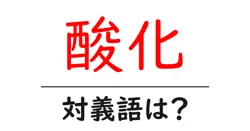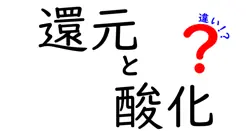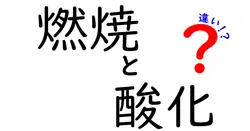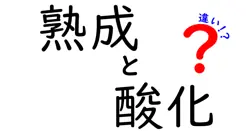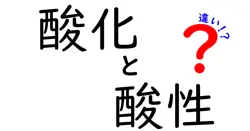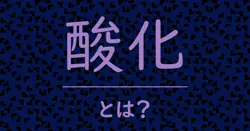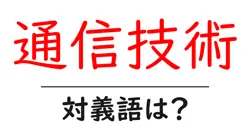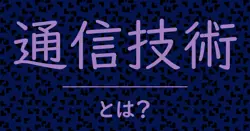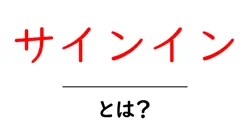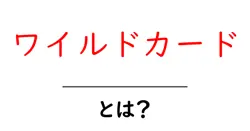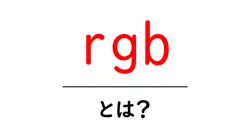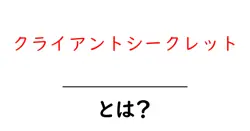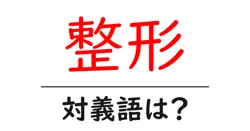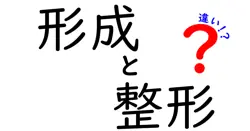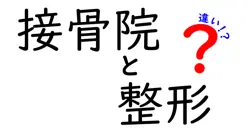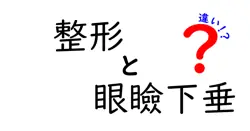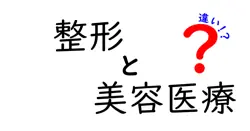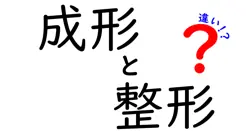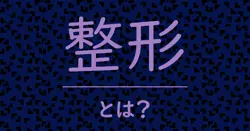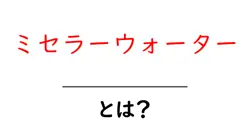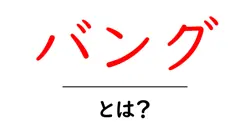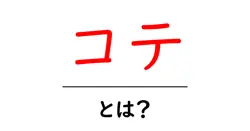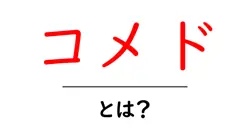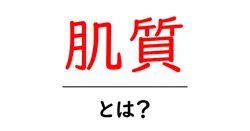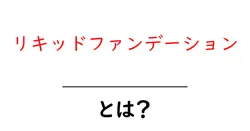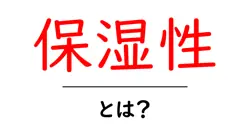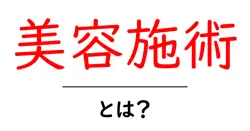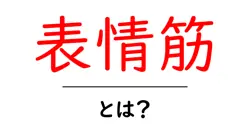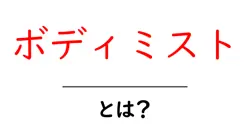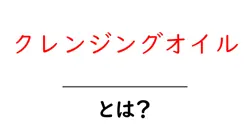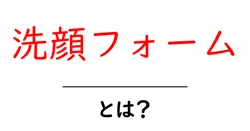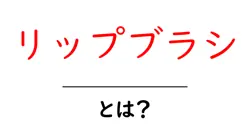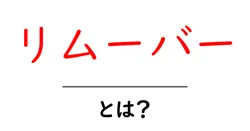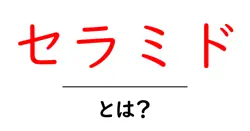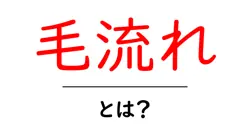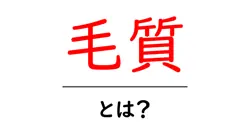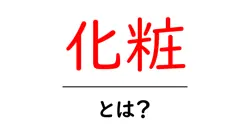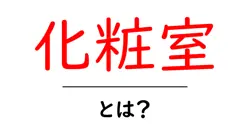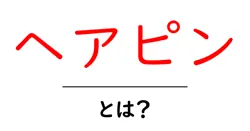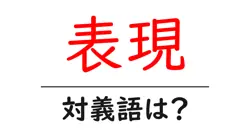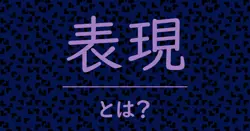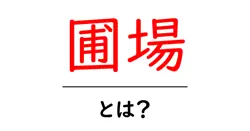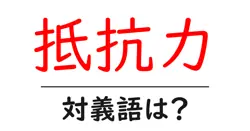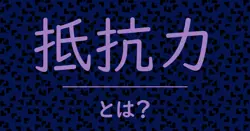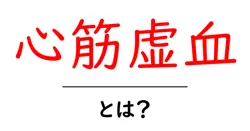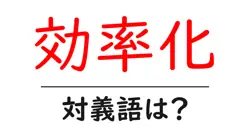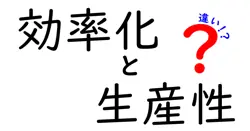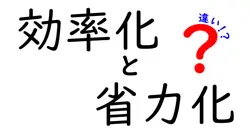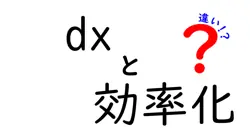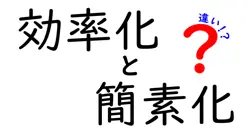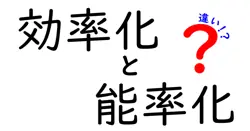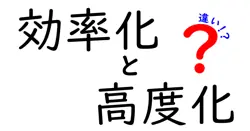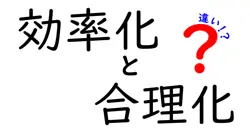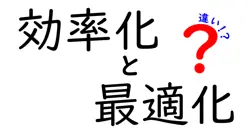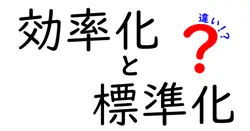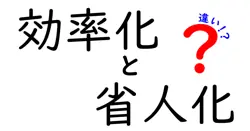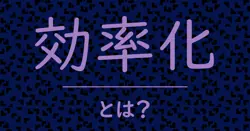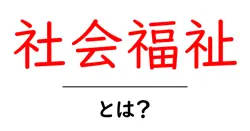電荷とは?
日常生活の中で、私たちは電気を利用することが多いですが、電気の基本的な仕組みを理解することは非常に重要です。その根本にあるのが「電荷」です。電荷は物質の基本的な性質の一つで、電気的な力を持っています。いったい電荷とは何なのでしょうか?このブログでは、中学生でもわかりやすく、電荷について説明していきます。
1. 電荷の基本概念
電荷は物質の中に存在し、それによって静電気や電流などの電気現象が起こります。電荷には2つの種類、すなわち「正の電荷」と「負の電荷」があります。正の電荷を持つ物質には陽子が含まれ、負の電荷を持つ物質には電子が含まれています。物質が持つ電荷の量は同じですが、種類が異なると互いに引き合い、同じ場合は反発し合います。
2. 電荷の単位と測定
電荷は「クーロン」という単位で測定されます。1クーロンは約6.24×1018個の電子を持つ量に相当します。このことから、私たちの身の回りの物質の電荷の量は非常に小さいことがわかります。
電荷の概念を表にまとめると:
| 電荷の種類 | 電荷の記号 | 特徴 |
|---|---|---|
3. 電荷の実生活での例
電荷はおばあさんの毛布をたたくときの静電気や、風船を髪の毛で擦ったときに風船が髪の毛を引き寄せる現象など、日常の中で目にすることができます。このように、電荷は私たちの生活と密接に関係しています。
4. 電荷の重要性
電荷の理解は、様々な科学技術の基盤となります。例えば、スマートフォンやコンピュータの動作は、全て電荷が関与しています。電荷を理解することで、これらのテクノロジーの開発や進化に寄与できるのです。
まとめ
今まで見てきたように、電荷は物質に存在し、大きな影響を持つものです。正と負の電荷の働きを理解することで、電気の仕組みや日常生活の中での電気現象が少しずつわかるようになってくると思います。電気は私たちの生活に欠かせないものですので、これからも電荷について学んでいきましょう。
div><div id="saj" class="box28">電荷のサジェストワード解説
イオン 電荷 とは:イオンとは、原子が電子を失ったり、得たりすることによって生じる粒子のことです。普通の原子は中性で、プラスの電荷を持つ陽子とマイナスの電荷を持つ電子が等しい数だけ存在しています。しかし、電荷を持つイオンができると、原子の性質が変わります。イオンは、失った電子の数だけプラスの電荷を持つ「陽イオン」と、得た電子の数だけマイナスの電荷を持つ「陰イオン」に分かれます。例えば、ナトリウム原子が1つの電子を失うと、ナトリウムイオン(Na⁺)となります。この電荷を持つイオンは、他の物質と強く引き寄せ合う性質があります。このため、イオン同士が結びついて化合物を作ったり、電気を通すことができたりします。イオンに関する理解は、化学や生物、さらには電気の基本にとても重要です。理解を深めるために、身近な事例や実験を通じて、イオンの特性を観察してみると良いでしょう。
電荷 とは わかりやすく:電荷(でんか)とは、物質の持つ特別な性質のことです。私たちが普段触れる物質は、原子という小さな粒でできています。原子の中には、陽子(ようこ)と呼ばれる正の電荷を持つ粒子と、電子(でんし)と呼ばれる負の電荷を持つ粒子が存在します。陽子は原子の中心にある原子核の中にいて、電子はその周りを回っています。電荷は物体が持つ引力や斥力を生み出し、例えば、静電気を感じることがあります。髪の毛をブラシでとかしたときに、ブラシが髪の毛にくっつくことや、風船で静電気をためて壁にくっつけることができるのは、この電荷の働きです。また、電荷にはプラスとマイナスがあり、プラス同士やマイナス同士は反発し合い、プラスとマイナスは引き合います。このような性質を理解することで、電気がどのように生まれるか、またどのように生活の中で利用されているのかを学ぶことができます。
電荷 とは 化学:電荷とは、物質に存在する特定の性質のことで、主に電子や陽子に由来します。電荷には二種類あり、正の電荷と負の電荷があります。正の電荷は主に陽子が持ち、負の電荷は電子が持っています。この二つの電荷は互いに引き合い、異なる性質を持つ物質同士を結びつける役割を果たします。化学反応においては、電荷が大きな影響を与えます。例えば、化学結合を形成する際には、電子の移動や共有によって、物質同士が結びつきます。このときの電荷のバランスが重要で、正と負の電荷がうまく組み合わさることで安定した物質ができあがります。逆に電荷の偏りがあると、反応が進まなかったり、物質が不安定になったりします。このように、電荷は化学の基礎を理解する上で、欠かせない要素となっています。
div><div id="kyoukigo" class="box28">電荷の共起語電気:物質内の電子の移動によって生じるエネルギーのこと。電荷が動くことで電気が発生し、さまざまな電気的な現象を引き起こします。
電子:負の電荷を持つ非常に小さな素粒子です。原子の構成要素であり、化学反応や電気伝導に重要な役割を果たします。
陽子:正の電荷を持つ素粒子で、原子の核を構成しています。陽子の数が原子番号を決め、元素としての性質を左右します。
中性子:電荷を持たない素粒子で、陽子とともに原子核を形成します。中性子の数によって、同じ元素でも異なる同位体が存在します。
静電気:物質に電荷が静止している状態を指します。摩擦などにより物質が電気を帯びる現象です。
電場:電荷が作り出す空間で、その中にある他の電荷に力を及ぼす場のことです。電場の強さは電圧や距離に依存します。
電流:電荷が回路内を流れることを指します。電流は電気エネルギーの移動を表し、止まることなく流れることが重要です。
抵抗:電流の流れに対する妨げのことを言います。抵抗の大小によって、電流の流れやエネルギーの消費量が変わります。
誘導:電荷の移動や再配置によって、周囲の電場や磁場が変化する現象のことです。例えば、導体が磁場の中に置かれた時に起こることがあります。
荷電:物体が電荷を持っている状態を指します。プラスまたはマイナスの電荷を帯びている場合に使われる用語です。
クーロン:電荷の単位で、電気的な力を測るのに使われます。1クーロンは、1秒間に1アンペアの電流が流れる時に運ばれる電荷の量を表します。
div><div id="douigo" class="box26">電荷の同意語電気量:物体が持つ電気の量を表す言葉で、電荷とも呼ばれます。
荷:電荷の略称として使われることがあります。特に文脈に応じて電気的性質や電気の動きを示します。
電気的荷:物体が持つ電気に関する特性を強調した言葉で、特定の電気現象を示します。
電気的エネルギー:電荷が持つエネルギーを指し、電気回路や静電気において電荷が関与する力を示します。
プラス電荷:正の電荷を持つことを表す言葉で、例えばプロトンなどの素粒子が該当します。
マイナス電荷:負の電荷を持つことを表す言葉で、例えば電子が該当します。
div><div id="kanrenword" class="box28">電荷の関連ワード電荷:電気的なエネルギーを持った粒子の性質で、正の電荷と負の電荷があります。電荷は物体間の電気的引力や反発力を生じさせます。
正電荷:プロトンが持つ電荷のことです。正の電荷を持つ粒子は、他の正電荷粒子とは反発し、負電荷粒子とは引き合います。
負電荷:電子が持つ電荷のことです。負の電荷を持つ粒子は、他の負電荷粒子とは反発し、正電荷粒子とは引き合います。
電場:電荷の周囲に存在する空間のことで、電場内では他の電荷が受ける力があります。電場の強さや方向は、電荷の大きさや配置によって決まります。
クーロンの法則:2つの電荷間に働く力は、電荷の大きさに比例し、距離の二乗に反比例するという物理法則です。この法則により、電荷間の相互作用を理解する基礎が築かれます。
帯電:物体が電荷を持つようになる現象です。摩擦や接触、誘導などによって帯電が起こることがあります。
導体:電気を通しやすい物質のことです。金属などが有名で、自由に動く電子が豊富です。
絶縁体:電気を通しにくい物質のことです。ゴムやプラスチックなどが該当します。電子が自由に動くことができません。
中性:正電荷と負電荷が等しい場合、物体は電荷を持たない状態、すなわち中性と呼ばれます。
div>