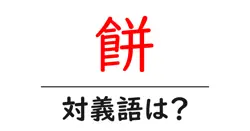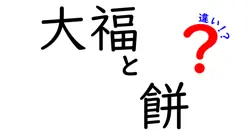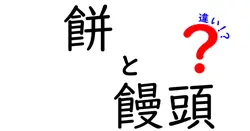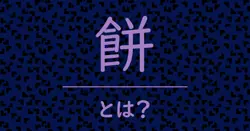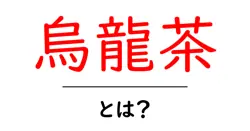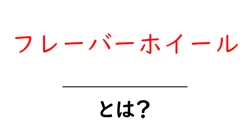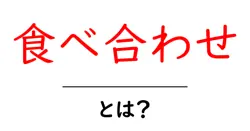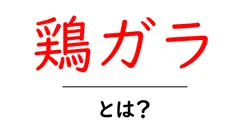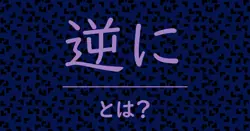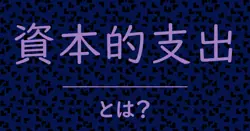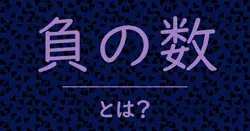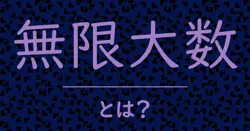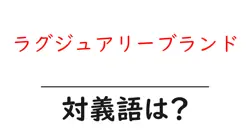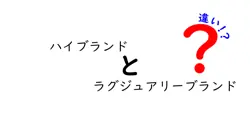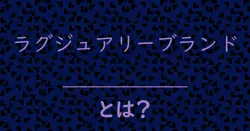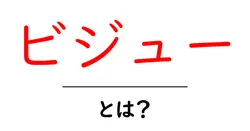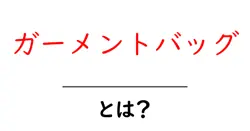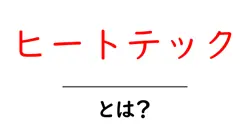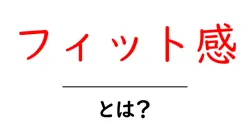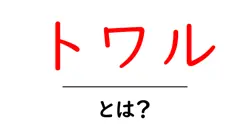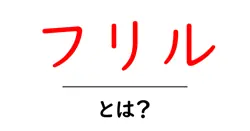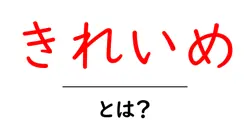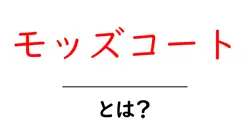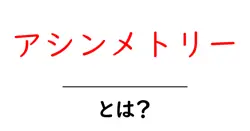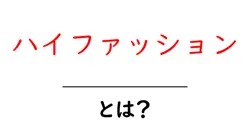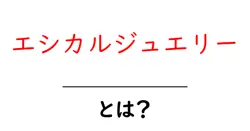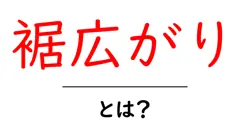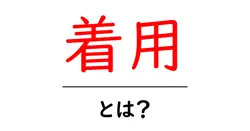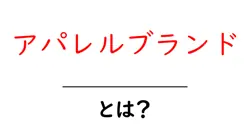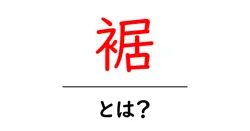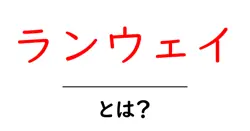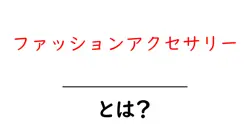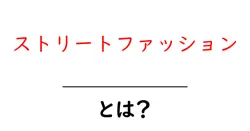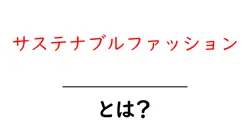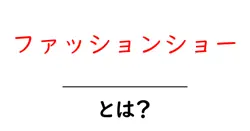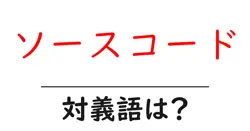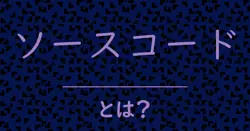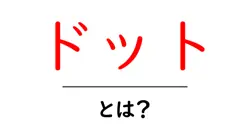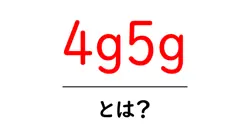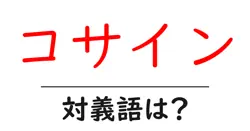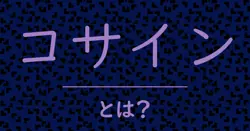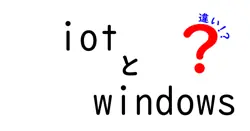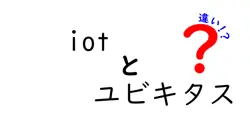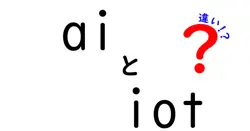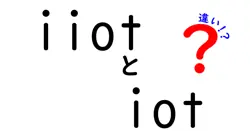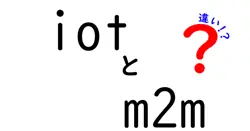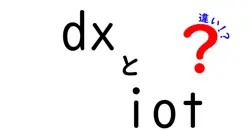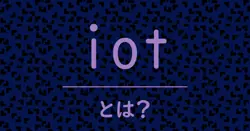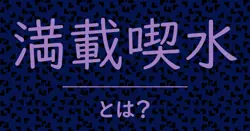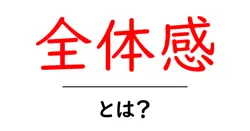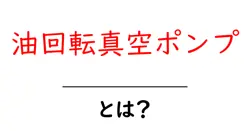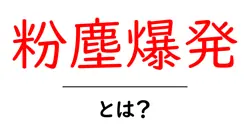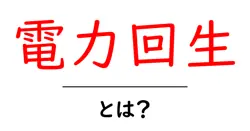餅とは?その魅力と食べ方を徹底解説!
日本の伝統的な食べ物の一つである「餅」。餅は、もち米を蒸してついた後に形成された、柔らかくて弾力のある食感が特徴的な食品です。一般的には、正月や特別な行事で食べられることが多いですが、実は日常的にも楽しむことができるおいしい食べ物です。今回は、餅の歴史や特徴、様々な食べ方をご紹介します。
餅の歴史
餅の起源は古代日本に遡ります。約2000年前から食べられているとされ、当時は神様へのお供え物として重要な位置を占めていました。餅は、米の栽培が盛んだった日本の気候に適しており、食料としての価値が高かったため、広く普及しました。
餅の種類
餅には様々な種類があります。代表的なものを以下の表にまとめました。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 白餅 | シンプルな味わい。甘いあんことの組み合わせが人気。 |
| 赤飯 | 小豆を使ったお祝いの餅。 |
| 草餅 | よもぎを混ぜた香りの良い餅。 |
| お餅入りのスイーツ | アイスクリームやケーキに使われる。 |
餅の食べ方
餅は様々な方法で楽しむことができます。ここでは、人気の食べ方をいくつか紹介します。
1. 餅入り汁粉
甘いあんこ入りの汁粉は、冬の寒い日にぴったりです。温かい汁に柔らかい餅を加えて、心も体も温まる一品になります。
2. 餅の焼き物
焼いた餅に醤油をかける簡単な料理も人気です。香ばしい香りと甘じょっぱい味が絶妙に絡みます。
3. お餅のデザート
もち米を使ったアイスや大福など、デザートとしても楽しめます。特に、苺大福は多くの人に愛されています。
餅の栄養価
餅は炭水化物が主成分ですが、たんぱく質やミネラルも含まれています。エネルギー源としても優秀で、活動的な日常生活を送るために役立ちます。ただし、食べすぎには注意が必要です。特に、高齢者や子どもは誤飲の危険があるため、小さく切って食べることをおすすめします。
以上、「餅」についての基本的な情報と魅力をご紹介しました。餅は日本の食文化を象徴する食べ物であり、食べ方次第で美味しさが広がります。ぜひ、いろいろな餅を楽しんでみてください!
餡:餅と一緒に食べることが多い甘いあんこで、主に赤豆から作られます。
お雑煮:餅を入れた日本の伝統的なスープで、地域によって具材や味付けが異なります。
もち米:餅を作るために使われる特別な米で、粘り気が特徴です。
鏡餅:正月の飾りとして用いられる二段重ねの餅で、家族の健康と繁栄を願う意味が込められています。
きな粉:焼いた餅に振りかける粉で、大豆を焙煎して細かく挽いたものです。
大福:餅の中にあんこなどを包んだお菓子で、もちもちとした食感が楽しめます。
草餅:よもぎなどの草を混ぜた餅で、香りと色が特徴的です。
餅つき:餅を作るための伝統的な作業で、米を蒸してから杵でつく工程を指します。
お餅:日本の伝統的な食べ物で、粘り気のある食感が特徴の米の加工品です。
餅料理:餅を使ったさまざまな料理やお菓子のことを指し、種類が豊富です。
モチ:餅の音読みで、同じくお正月や特別な行事に食べるお餅を指す。
もち米:餅を作るために使う特別な種類の米。粘り気が強く、餅を作るのに最適。
団子:主にうるち米やもち米を粉にして水で練り、丸めた食品。餅と似ているが、食感や用途が異なる。
粘り餅:特に粘り気が強い餅を指し、食べるときの食感が特徴的。
上新粉:白い米の粉で、主に餅や団子作りに用いられる。餅とは異なるが、関連性が強い。
お餅:お餅(おもち)は、もち米を蒸してついた後に形成される、弾力のある食品で、主に日本の伝統的な食材です。
もち米:もち米(もちごめ)は、通常の米とは異なり、粘り気が強い特別な種類の米のことを指します。この米を使ってお餅が作られます。
杵:杵(きね)は、もち米をつくために使う道具で、木製の棒でもち米をつくために使います。
臼:臼(うす)は、もち米をつく際に杵を使ってつく場所のことです。通常、円形の石または木製の器でできています。
鏡餅:鏡餅(かがみもち)は、正月に飾るための特別なお餅で、上下二段重ねて鏡の形にしたものです。
草餅:草餅(くさもち)は、よもぎなどの草を混ぜて作ったお餅で、香りが良く、春の訪れを感じさせる食べ物です。
お雑煮:お雑煮(おぞうに)は、お餅が入ったお汁料理で、日本各地で異なるスタイルや具材を使います。
団子:団子(だんご)は、米粉や上新粉を使用し、形を作って茹でたお菓子で、お餅と似ていますが、一般的に柔らかさが異なります。
餡:餡(あん)は、甘さを加えた豆のペーストで、お餅と一緒に使われることが多いです。特に大福などに詰められます。
もち米の特徴:もち米は通常の米に比べて水分を吸収しやすく、柔らかくなるため、つきやすいという特徴があります。