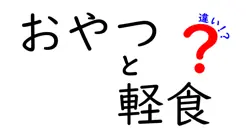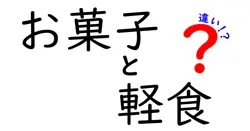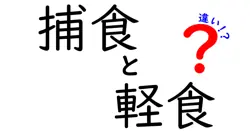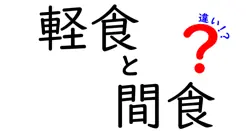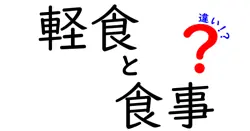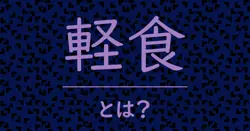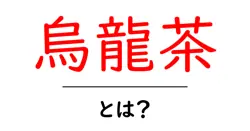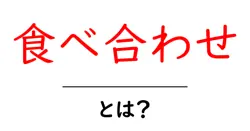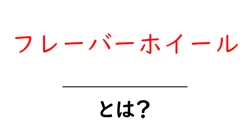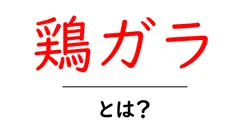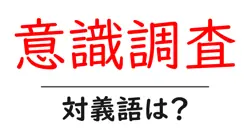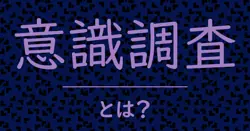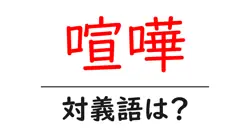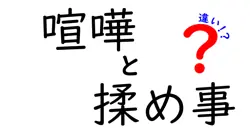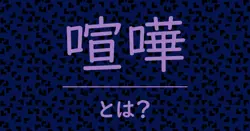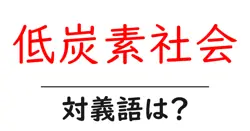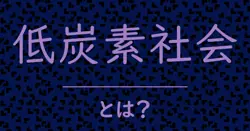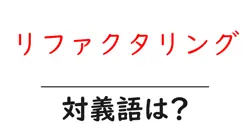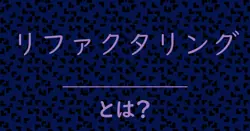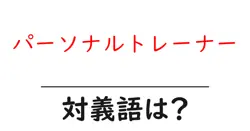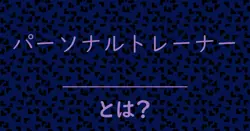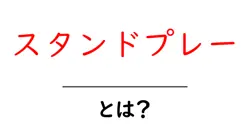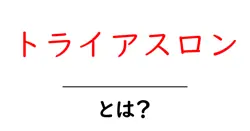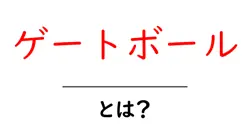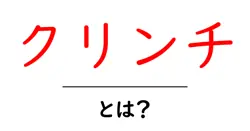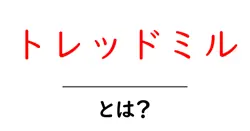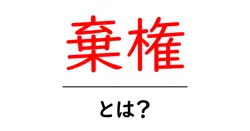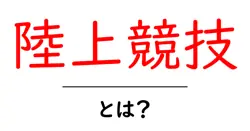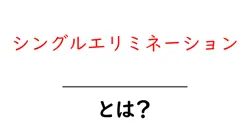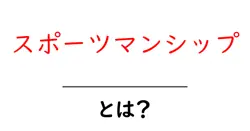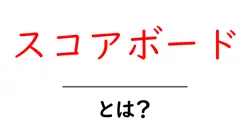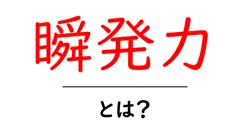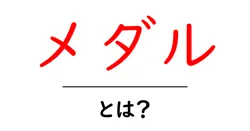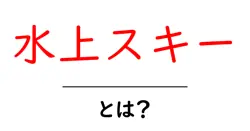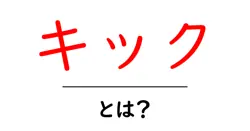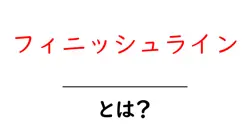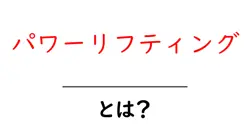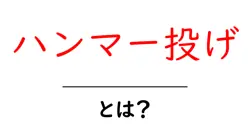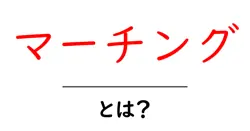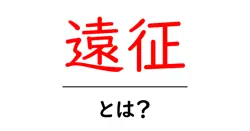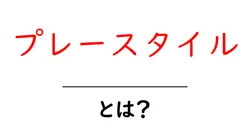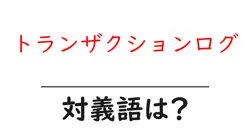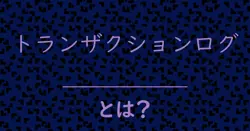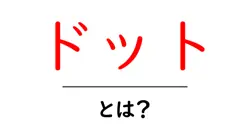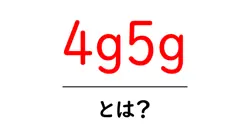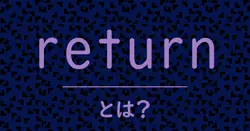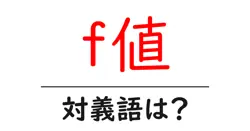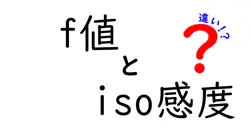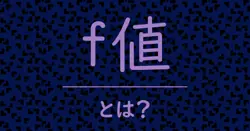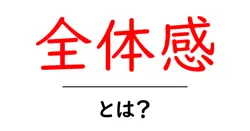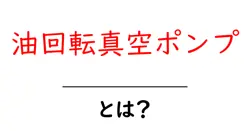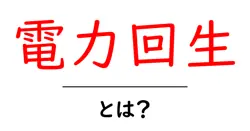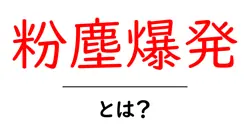<div id="honbun">「return」とは?
コンピュータやプログラムを学ぶ上で、特に重要な用語の一つが「return」です。プログラミングをしていると何度も目にしますが、実際にはどんな意味があるのでしょうか?この言葉の使われ方や重要性についてわかりやすく解説します。
1. returnの基本的な意味
英語で「return」は「戻る」という意味です。コンピュータのプログラミングにおいては、ある関数(計算や処理を行うコードの塊)が結果を返すときに使われます。
2. returnが使われる場面
例えば、計算を行う関数を考えてみましょう。以下のような簡単なプログラムを考えてみます。
de>def add(a, b):
return a + bde>
このプログラムは、2つの数字を足す関数です。「return a + b」の部分が「計算した結果を返す」という役割を果たしています。
3. returnの重要性
プログラミングでは、結果を「return」することで、他の地点でその結果を再利用できるようになります。これは非常に重要で、コードの効率を上げるために欠かせません。
4. returnの例
具体的な例を見てみましょう。以下は、数字のリストから最大値を返す関数です。
de>def max_value(numbers):
max_num = numbers[0]
for num in numbers:
if num > max_num:
max_num = num
return max_numde>
この関数も、リストから最大値を見つけ出してそれを「return」しています。
5. returnと出力の違い
出力(print)とreturnの違いも理解しておきましょう。出力は画面に結果を表示することですが、returnは計算結果を次の処理に渡すことです。
d>
| 機能 |
return |
print |
d>
dy>
d>使用目的d>
d>結果を返すd>
d>結果を表示するd>
d>次の処理に影響d>
d>ありd>
d>なしd>
dy>
「return」はプログラミングにおいて非常に重要な役割を果たします。関数が計算した結果を他の部分で利用できるようにするため、この概念を理解することは非常に重要です。これからプログラミングを学ぶ際には、「return」の使い方についてしっかりと把握していきましょう。
div>
<div id="saj" class="box28">returnのサジェストワード解説annual return とは:年率リターンとは、投資の結果として得られる利益の割合のことを指します。投資を行うと、年ごとにどれだけお金が増えたり減ったりするかを知るため、この指標が非常に大切です。たとえば、10万円を投資して、1年後に11万円になった場合、年率リターンは10%です。これは、1年間で元の投資額の10%にあたるお金が増えたことを示しています。年率リターンは、異なる投資の成果を比べるときにも役立ちます。2つの投資があった場合、一方が年率リターン5%で、もう一方が7%であれば、後者のほうがより良い選択と言えます。ただし、年率リターンはあくまで過去の数字であり、未来の利益を保証するものではありません。投資をする際はリスクがあるため、自分に合った投資先を選ぶことが大切です。年率リターンを理解することで、賢い投資判断ができるようになります。ぜひ、投資の基本として覚えておきましょう。
federal tax return とは:federal tax return(連邦税申告書)とは、アメリカの国に支払う税金を計算し、申告するための書類のことです。この手続きは、毎年4月15日までに行う必要があります。アメリカに住んでいる人や、アメリカで収入を得ている人は、選ばれた所得について申告する義務があります。例えば、アルバイトや仕事で得た給料、不動産の売却益などが該当します。税務署に正確な情報を申告することで、過剰に支払った税金が戻ってくることもあります。一方で、税金を少なく支払うために必要な控除やクレジットを申請することもできるため、しっかりと情報を整理して申告することが大切です。もちろん、難しそうに感じるかもしれませんが、多くの人が毎年この申告を行っており、オンラインツールや専門家の支援を受けることもできます。正しい申告をすれば、自分の権利を守ることにもつながります。あなたもぜひ理解を深めてみてください。
income tax return とは:income tax return(インカムタックスリターン)とは、個人が一年間に得た収入や支出をまとめて税務署に報告することを指します。日本では毎年、所得税の申告をする必要があり、これを「確定申告」とも呼びます。たとえば、あなたがアルバイトをして得たお金や、特別な収入があった場合、それを税務署にきちんと報告することで税金が正しく計算されます。この申告をすることで、支払いすぎた税金が戻ってくることもあります。申告は、自分の会社で働いている人や、副業をしている人、自営業を営んでいる人にとって非常に大切です。もし、初めて申告をするのであれば、税務署が提供するガイドや様々なウェブサイトの情報を参考にすると良いでしょう。また、周りの大人に聞いてみるのも手です。正確に申告することができれば、後から余計な税金を払うことを避けることができます。難しそうに感じるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に進めていけば大丈夫です。
open return とは:「open return」とは、往復の航空券に関する用語で、特に柔軟性を求める旅行者に人気のあるオプションです。通常の往復航空券は、出発日と帰国日が決まっているため、予定が変わった場合には追加の手数料がかかることがあります。しかし、open returnを選ぶと、帰国日を自由に変更できるため、旅行途中での予定変更がしやすくなります。このため、例えば、自分の予定があいまいな旅行や、長期間の滞在を考えている人にはとても便利です。flight tickets(航空券)を購入する際には、こうしたオプションについても検討してみることをおすすめします。open returnの航空券は特に、忙しいビジネスマンや旅行を楽しみたい方々から高い評価を得ています。このように、open returnはフレキシブルな旅行を可能にする素晴らしい選択肢です。
return とは c言語:C言語には「return」というとても大切な命令があります。これは、関数が処理を終えたときにその結果を呼び出し元に返すために使います。プログラムを考えるとき、関数は特定の仕事をするものだと思ってください。例えば、数字を足す関数を作ったとします。この関数が計算を終えたら、計算結果を呼び出し元に戻す必要があります。そのときに「return」を使います。「return」の後に返したい値を書くことで、その値が呼び出し元に返ります。たとえば、関数で2つの数字を足す場合、計算した結果を「return」で返せば、呼び出し元はその値を使うことができます。このように、return文を使うことで、プログラムが使いやすくなり、他の処理にもその値を使えるようになります。returnは、C言語を使う上で覚えておくべき重要なポイントです。ぜひ、いろいろなプログラムで活用してみてください!
return とは java:Javaプログラミングを学んでいると、よく目にするのが「return」という言葉です。これは、関数やメソッドから値を返すための重要なキーワードです。たとえば、何か計算をして、その結果を得たい場合に使います。return文を使うことで、計算した結果を呼び出し元の場所に返すことができるのです。具体的には、次のように使います:
```java
int sum(int a, int b) {
return a + b;
}
```
この例では、sumというメソッドが二つの整数を受け取り、それらの合計を計算します。そして、計算結果をreturn文で返しています。こうすることで、sumメソッドを呼び出した場所で、合計の値を利用できるようになります。
さらに、return文は単に値を返すだけでなく、メソッドの処理を終了する役割も持っています。つまり、returnが実行されると、そのメソッドはそれ以上のコードを実行しません。
このように、return文はJavaプログラミングの中で非常に重要な役割を果たします。もしプログラミングを続けていくなら、ぜひきちんと理解しておくことをおすすめします。
return とは python:Pythonにおけるreturn文は、関数から結果を返すための重要な機能です。関数を使うと、何かを計算したり、データを処理したりできますよね。例えば、数字を2倍にする関数を作ってみましょう。関数の中で計算を行い、その結果をreturn文を使って戻します。こうすることで、関数を呼んだ場所でその結果を使うことができます。また、returnがない場合、関数はNoneを返します。これは、何も返さない場合のデフォルトの結果です。returnを使うことで、プログラムがより効率的に動き、デバッグもしやすくなります。なので、自分の作った関数がどんな結果を返すのかしっかり理解することが大切です。return文をうまく使うことで、複雑な処理もスッキリまとめられるので、これからプログラミングを学ぶ人にとって、ぜひ覚えておいてほしいポイントです。
return とは プログラミング:プログラミングを学ぶ中で、「return」について知ることはとても大切です。「return」とは、関数が処理を終えたときに、計算結果や値を呼び出し元に返すための命令です。例えば、計算機のような関数を作るとします。この関数は、入力された数値に基づいて結果を計算し、その結果を「return」を使って返します。これにより、他のプログラムの部分でその結果を利用できるようになります。この「return」を使わないと、関数内で計算した結果を他で使うことができず、効率的なプログラムを作ることが難しくなります。皆さんも、自分で関数を作るときは、必ず「return」を使ってみてください。そうすることで、プログラムの完成度がグッと上がります。「return」は単なるコマンドではなく、プログラミングの中で非常に重要な役割を果たしていることをぜひ理解してください。
tax return とは:tax return(タックスリターン)とは、税金の申告をするための書類のことです。一般的に、税金は年に一度、前年の収入や支出に基づいて計算されます。あなたが働いて得た給料や、副業で得た収入などをもとに、どれだけの税金を納めるべきかを決める役割を果たしています。例えば、あなたが働いていて、会社から給料が支払われると、その中には所得税が引かれています。しかし、払いすぎた税金がある場合は、税金を取り戻すことができるかもしれません。これが税金の還付であり、tax returnを通じて行います。税務署に申告書を提出することで、過剰に納めた税金を返してもらう手続きが始まります。申告書には、年収や経費などを記入します。正しく記入すれば、還付金を受け取れるチャンスが増えます。このようにtax returnは、自分が納めた税金を見直す大切な手続きなのです。税務署から返信があると、税金が過剰に支払われていた場合、その金額を口座に振り込んでもらえることになります。これがtax returnの基本的な流れです。
div><div id="kyoukigo" class="box28">returnの共起語戻り:何かを元の場所や状態に戻すことを指します。プログラミングでは、関数が処理を終えた後に出力として返す値を意味します。
値:プログラムやデータベースで使用される具体的なデータのこと。関数が戻すことができる情報の一部を指します。
関数:特定の処理を実行し、結果を返すためのコードの集合です。プログラミングにおいて、再利用可能な部品として使用されます。
出力:プログラムが外部に返す情報のこと。関数からの戻り値や結果として現れます。
処理:データや情報に対して行われる計算や操作のこと。プログラムが何かを実行する際に行います。
呼び出し:関数を実行するためにその関数の名前を使って呼ぶ作業のこと。戻り値を受け取るためには、関数を正しく呼び出さなければなりません。
プログラミング:コンピュータに特定の指示を与えるためのコードを書く行為のこと。様々な言語を用いて行います。
API:アプリケーションプログラミングインターフェースの略で、異なるソフトウェアプログラムが相互に通信するための手段や契約を指します。
バグ:プログラムのエラーや誤動作のこと。戻り値や処理に影響を及ぼすことがあります。
デバッグ:プログラムのバグを見つけて修正するプロセスのこと。正常な動作を保証するために重要です。
div><div id="douigo" class="box26">returnの同意語返す:物や人を元の場所に戻すこと。例えば、本を図書館に返すことなど。
戻す:何かを以前の状態や場所に戻すこと。例えば、資料を机の上に戻すこと。
返還:所有権を持っていた物を元の持ち主に返すこと。例えば、貸し借りした物品を返すこと。
返却:借りた物を返す行為。図書館やレンタルショップで使われる言葉。
戻り:元の位置や状態に戻ること。例えば、旅行から帰ってくることを指すこともある。
復帰:元の状態やポジションに戻ること。特に、仕事や社会生活において以前の状態に戻ること。
div><div id="kanrenword" class="box28">returnの関連ワードリターン:プログラムや関数からの戻り値のこと。特定の処理が完了した後に、結果や値を呼び出し元に返す機能を指します。
関数:特定の処理を実行するための命令の集合。関数は、引数を受け取り、処理を行い、結果をリターンすることができます。
戻り値:関数がリターンする値のこと。関数の実行結果として何らかのデータを返します。
API:アプリケーションプログラミングインターフェースの略で、プログラム同士が相互にデータをやり取りするための方法や規約のこと。リターンが重要な役割を果たすことが多いです。
エラーハンドリング:プログラムの実行中に発生する可能性のあるエラーを管理するための技術。リターン値を使用して、エラーの有無を示すことがよくあります。
シグナル:特定のイベントを通知するためのメカニズム。リターン値を利用して、シグナルを受け取ることができます。
コールバック:他の関数に引数として渡される関数のこと。処理後にリターンされる結果を受け取るために使用されることが多いです。
スコープ:変数や関数がアクセス可能な範囲のこと。リターンを使う場合、スコープに注意する必要があります。
div>returnの対義語・反対語
returnの関連記事
学問の人気記事

1742viws

1483viws

1919viws

1274viws

2015viws

2292viws

1011viws

2110viws

1233viws

5514viws

1228viws

2261viws

1848viws

1355viws

1347viws

1380viws

2136viws

2237viws

1812viws

981viws