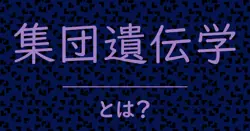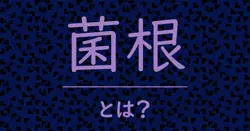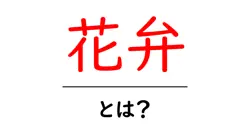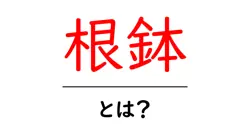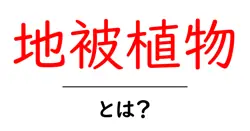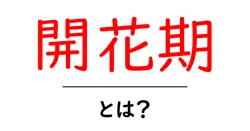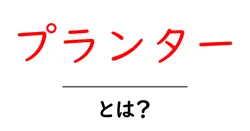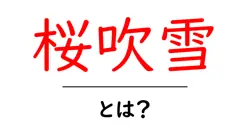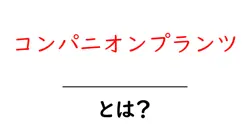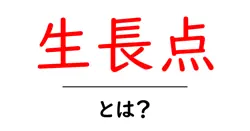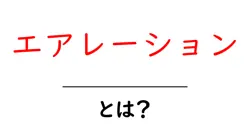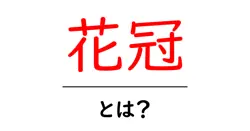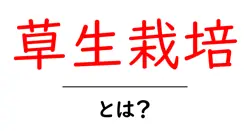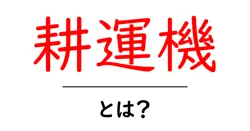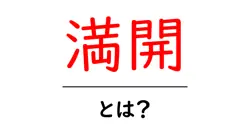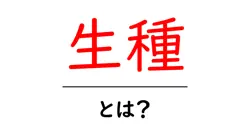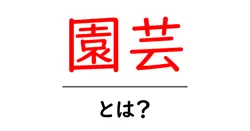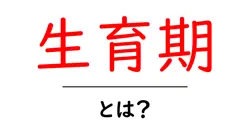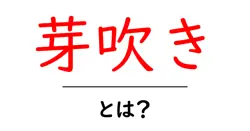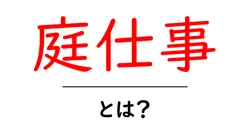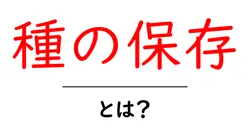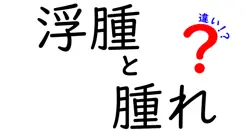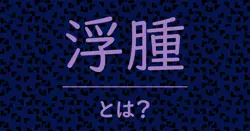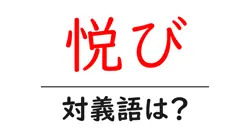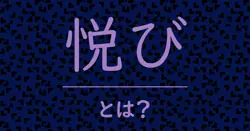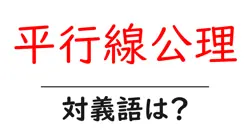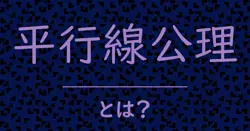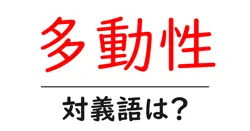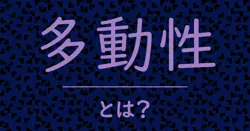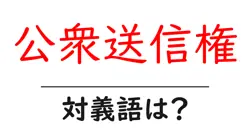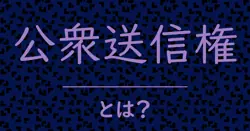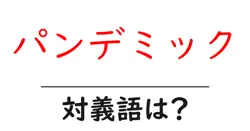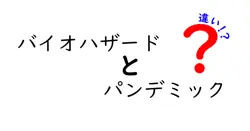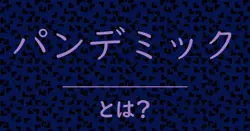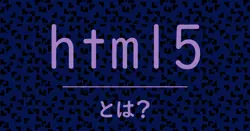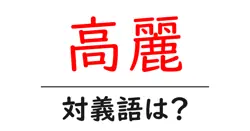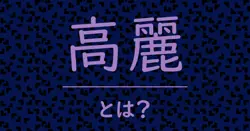<div id="honbun">高麗とは?歴史や文化の魅力を解説!
「高麗」とは、韓国の歴史に登場する重要な王朝の名前です。高麗王朝は918年から1392年まで続きました。この時代は、韓国の文化や技術が大きく発展した時期でもあります。特に、高麗時代には素晴らしい陶磁器や文学が生まれ、後の韓国文化に強い影響を与えました。
高麗は、元々は高句麗と呼ばれていた地域に登場した王朝で、李氏朝鮮の前身にあたります。918年に王建という人物が高麗を建国し、その後長い時代を経て1392年に李氏朝鮮が成立するまで続きました。高麗時代は、多くの戦争や内部の争いがありましたが、文化が栄えた時期でもありました。
高麗の文化
高麗時代には、さまざまな文化が発展しました。例えば、高麗焼きという陶磁器が有名です。この焼き物は、優れた技術で作られ、美しい青色や絵模様が特徴です。また、絵画や詩も盛んで、多くの文化的遺産が残っています。
高麗の影響
高麗王朝は、韓国の文化や伝統を形作る上で重要な役割を果たしました。その後の李氏朝鮮への移行により、高麗の文化も受け継がれ、今日の韓国の基盤が築かれました。例えば、高麗時代の美術品や文学は、今でも韓国の重要な文化財として大切にされています。
高麗を知るためのポイント
d>
| ポイント |
内容 |
d>
dy>
d>建国年d>
d>918年d>
d>終了年d>
d>1392年d>
d>主な文化d>
d>高麗焼き、文学、絵画d>
dy>
高麗王朝は、韓国の歴史と文化を理解するための大切な要素です。高麗の時代に生まれた文化遺産や技術は、今でも多くの人々に影響を与えています。これからも高麗の魅力を知ることで、韓国文化への理解が深まることでしょう。
div>
<div id="saj" class="box28">高麗のサジェストワード解説coma とは:「coma(コーマ)」とは、主に医学の分野で使われる言葉で、意識が失われている状態を指します。例えば、交通事故や重い病気の後に人が目を覚まさない場合、その人は「コーマ」にあると言えます。この状態では、患者は周囲に反応せず、自分の意志を伝えることもできません。そのため、家族や医療スタッフは非常に心配になります。コーマには軽度のものから重度のものまでありますが、しばしば長期間続くこともあります。コーマに入っている人がいつ目を覚ますかはわからず、時には回復することもありますが、完全に回復しない場合もあります。コーマの原因は様々で、脳への損傷や病気、薬物中毒などが考えられます。医療技術の進歩によって、コーマから回復する可能性が高くなっていますが、それでも予測が難しい状態です。家族や友人は患者のために日々心の支えとなり、希望を持ち続けることが大切です。
こま とは:「こま」とは、主に木やプラスチックなどで作られた円盤状の玩具で、回転させて遊ぶものです。日本の伝統的なおもちゃの一つですが、世界中で様々な形や素材のこまが存在します。こまを回すのは、手軽に楽しめる遊びで、友達や家族と競い合ったり、技を披露したりすることもできます。こまにはいくつかの種類があり、日本の「凧揚げこま」や、「紙こま」、また、海外の「トム・コマ」などがあります。それぞれのこまは、見た目や回し方が違い、特別な技を持っているものもあります。例えば、古くからの伝統的なこまでは、独特の模様やデザインが施されているものもあり、見ているだけでも楽しめるでしょう。遊び方も簡単で、まずこまの紐を巻きつけ、強く引っ張ると回り始めます。この時、回転が安定していると長く回り続けます。小さなお子さんから大人まで楽しめるこま遊びを通じて、有効な道具を使ったり、友達とのチャレンジを楽しんだりすることができます。こまは、単に遊ぶだけでなく、集中力やバランス感覚を養うためにも役立つ素晴らしいおもちゃです。
こマ とは:「こマ」という言葉は、特にオンラインの場面でよく使われる言葉の一つです。実は「こマ」は、他の言葉と組み合わせて使われることが多いのですが、単独でも注目されています。たとえば、「こマ」は「小さいまま」「こまめに」といった言葉の短縮形です。このような表現は、特にSNSやチャットでカジュアルに使われています。最近では、若者を中心にこの言葉が急速に広まりました。例えば、友達との会話で「こマに何かした?」や「こマで待ってるね」と言ったりします。使い方も簡単で、状況に応じてさまざまな意味合いを持たせることができます。例えば、時間がなくて急いでいる時に「こマ!」と言うと、「小さいことにこだわっている時間なんてない!」という意味になります。このように、「こマ」という言葉は日常の中で身近に感じられる存在です。ぜひ友達との会話などで使ってみてください!
コマ とは:「コマ」とは、日本で非常に人気のある伝統的なおもちゃの一つです。コマは小さな円盤の形をしていて、回すことによってその魅力を発揮します。コマを早く回すと、土台となる部分が地面から離れず、長い時間回り続けることができるのです。この現象は、バランスや重力の働きから生まれるものです。コマには木製やプラスチック製、金属製などさまざまな種類があります。遊び方も多様で、友達と競争したり、どれだけ長く回せるか挑戦したりすることが楽しめます。コマを回転させるという単純な動作の中に、科学的な原理がたくさん隠れているのを知ると、さらに楽しめるかもしれません。また、最近ではアニメやゲームに登場するキャラクターが使うこともあり、若い世代にも人気を集めています。コマを通じて、古き良き遊びを体験し、新しい楽しみを見つけることができるのです。
小間 とは:「小間」とは、特に展示会などで使われる用語で、ブースやスペースのことを指します。たとえば、会社が新しい商品をアピールするために展示会に参加する際、展示するための場所を小間と言います。この小間は、どれだけの面積を占めるかによって、企業の宣伝力にも影響を与えます。小間のレイアウトやデザインは非常に重要で、訪れる人の視線を引くために工夫されます。たとえば、色や形を工夫した看板を使ったり、商品の並べ方にこだわったりします。小間はただのスペースではなく、企業のイメージを表現する場所でもあるのです。そのため、展示会での成功を収めるためには、小間の使い方をしっかりと考えることが求められます。小間の管理や運営がうまくいくと、多くの来場者を引き寄せ、ビジネスチャンスを広げることができるでしょう。
狛 とは:「狛」とは、狛犬(こまいぬ)の略称で、日本の神社や寺院の入り口によく見られる石像のことです。狛犬は、通常、1対で置かれ、片方は口を開け、もう片方は口を閉じています。その形やデザインは地域や時代によって異なりますが、基本的には神社を守る存在として信じられています。
狛犬の起源は古く、中国から伝わったとされています。日本国内では、仏教の影響を受けて、神道の神社にも取り入れられました。狛犬は、悪霊や不運を追い払う役割を果たし、訪れる人々に幸福や安全をもたらすと信じられています。
また、狛犬の表情や姿勢にも意味があります。口を開けている方は「阿(あ)」、口を閉じている方は「吽(うん)」と呼ばれ、これは仏教の世界観を象徴しています。「阿吽」は、始まりと終わり、という意味を持ちます。狛犬を通じて、人々は神聖さや安らぎを感じ、神社に訪れることが多いです。
さらに、最近では狛犬をモチーフにしたキャラクターやグッズも人気です。こうした文化は、狛犬が単なる石像ではなく、日本の伝統や歴史の一部であることを示しています。こうした神秘的な存在「狛」は、知れば知るほど面白いものです。
独楽 とは:独楽(こま)は、一般的に木やプラスチックで作られた回転するおもちゃです。独楽は、細長い軸の上にあって、指先や糸を使って回転させることができます。古くから日本や世界のさまざまな文化で遊ばれてきたこのおもちゃは、単に遊ぶためだけでなく、独楽を正確に回す技術やバランスを使って、競技や芸術的なパフォーマンスにも利用されています。
独楽の歴史は非常に古く、実際には何千年も前から存在しています。さまざまな形やサイズがあり、地域によってその形や遊び方が異なります。たとえば、和式の独楽は回転させる方法によってさまざまな技があり、特にお正月や祭りの時に人気があります。最近では、風や摩擦で回る独楽や、音楽に合わせて踊る独楽なども登場しており、より多くの人々に楽しまれています。
独楽は回すことが簡単で、誰でも楽しめる遊びです。友達や家族と一緒に競争することもでき、楽しいひとときを過ごすことができます。そして、独楽を回す際には集中力や腕の力が必要になるため、遊びながら体や心を鍛えることもできます。独楽の魅力を知って、その歴史や遊び方を一緒に楽しんでみてください!
駒 とは:「駒」という言葉にはいくつかの意味がありますが、一番よく知られているのは将棋やチェスなどのボードゲームで使われる「駒」です。駒は、相手と対戦するために使うキャラクターのようなもので、それぞれの駒には特別な動き方や能力があります。たとえば、将棋では王将、飛車、角行などの駒があり、それぞれの役割が違います。駒をうまく動かして相手の王を取ることが勝利の目標です。
また、「駒」はもう一つの意味として、馬などの動物のことを指すこともあります。たとえば、乗馬をする時に使う馬を「駒」と呼ぶことがあります。
さらに、「駒」は比喩的に、計画やプロジェクトを進めるための小さな部分や段階を指すこともあります。仕事を進める際に、「このプロジェクトの次の駒は何か考えよう」と言ったりします。要するに、「駒」という言葉は状況によっていくつかの意味を持っていて、とても便利な表現です。
div><div id="kyoukigo" class="box28">高麗の共起語高麗人参:高麗人参は、韓国を代表する薬用植物で、体力を強化し、免疫力を高める効果があるとされています。主に根の部分が使用され、健康食品や漢方薬に活用されています。
韓国:高麗は古代の朝鮮半島に存在していた国で、その後の韓国の前身となります。高麗という名前は、韓国文化や歴史に深く根ざしているため、関連する話題でよく使われます。
高麗茶:高麗茶は、高麗人参を使ったお茶で、健康効果が期待される飲料です。人参の爽やかな香りと風味が特徴で、リラックス効果や活力を与えるとされています。
歴史:高麗は935年から1392年まで続いた王朝で、文化や技術の発展がありました。陶芸や印刷技術、文学などが栄え、韓国の歴史に深い影響を与えています。
高麗の食文化:高麗時代の食文化は、米や野菜、魚介類が中心で、発酵食品やスープ類も多く取り入れられていました。この食文化は現代の韓国料理にも影響を与えています。
美術:高麗時代は美術が発展した時期で、特に陶磁器が有名です。高麗青磁という独特の色合いの陶器は、今でも高く評価されています。
王朝:高麗は朝鮮半島の王朝の一つで、政治的・文化的に重要な役割を果たしました。高麗の後は李氏朝鮮が続き、その時代にも高麗の影響が見られます。
div><div id="douigo" class="box26">高麗の同意語朝鮮:高麗は古代の朝鮮王国の一つであり、朝鮮半島全体を指すこともあります。
高麗王朝:これは高麗が王朝として存在していた時期を指し、918年から1392年までの間に栄えていました。
高麗文化:高麗時代に発展した独自の文化を指し、特に陶磁器や文学が著名です。
高麗美術:高麗時代に創造された美術作品を指し、工芸品や絵画が含まれます。
高麗茶:高麗時代に飲まれていたお茶のことで、独特な風味が特徴的です。
高麗人参:高麗人参は、特に高麗地域で育てられた人参で、健康や美容に良いとされています。
div><div id="kanrenword" class="box28">高麗の関連ワード高麗人参:高麗人参は、韓国や中国で広く栽培される薬草です。特に滋養強壮や免疫力向上に効果があるとされ、健康食品やサプリメントに利用されています。
高麗王朝:高麗王朝は、918年から1392年まで続いた韓国の王朝です。この時代に多くの文化や技術が発展しました。
高麗青磁:高麗青磁は、高麗王朝時代に作られた青い陶器のことです。美しい色合いと優れた技術で知られ、世界的にも評価されています。
高麗茶:高麗茶は、高麗人参を使ったお茶のことです。健康効果が期待できるとされ、特に疲労回復やリラックス効果があります。
高麗風:高麗風は、高麗文化に影響を受けた建築様式やデザインのことを指します。特に自然と調和した美しさが特徴です。
高麗山:高麗山は、埼玉県にある山の名前ですが、また「高麗」という言葉がつく地域や文化の象徴として使われることがあります。
div>高麗の対義語・反対語
高麗の関連記事
学問の人気記事

1788viws

1527viws

1956viws

1315viws

2046viws

2325viws

1044viws

1272viws

5550viws

2142viws

1261viws

2292viws

1394viws

1879viws

1379viws

1020viws

4237viws

1410viws

2167viws

2268viws