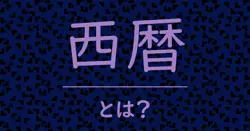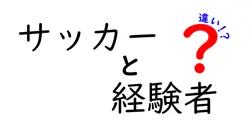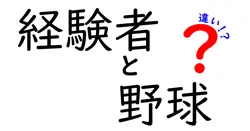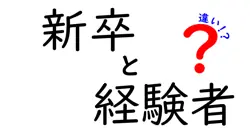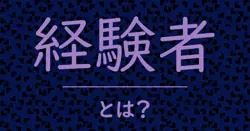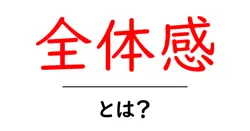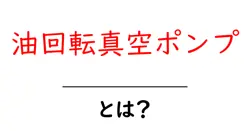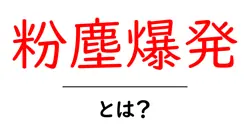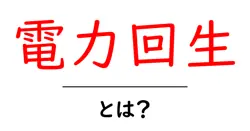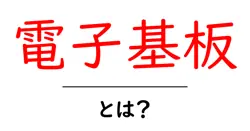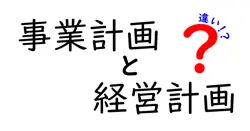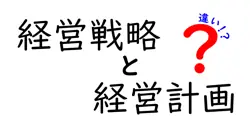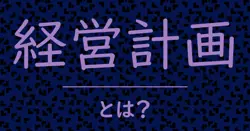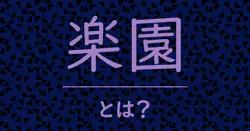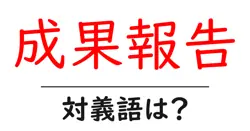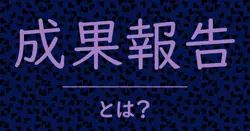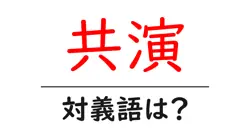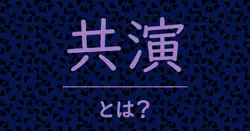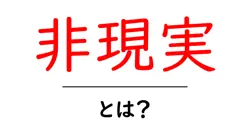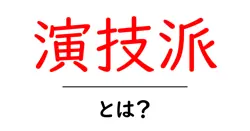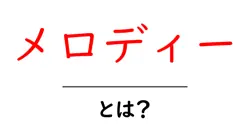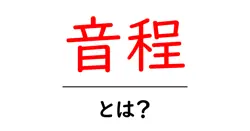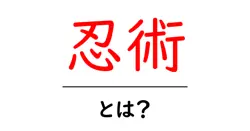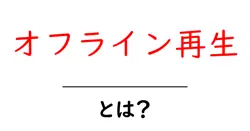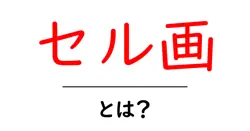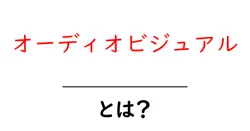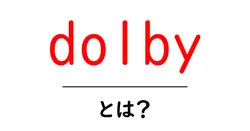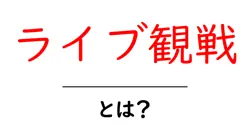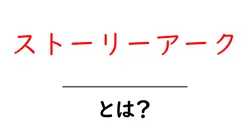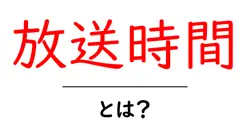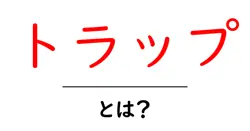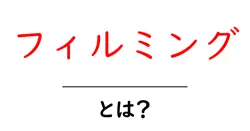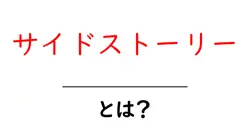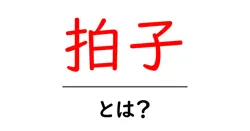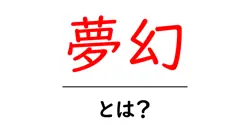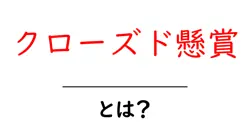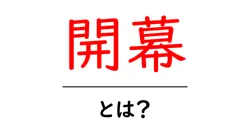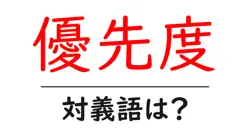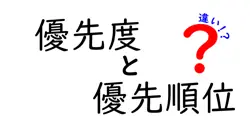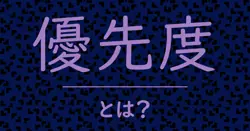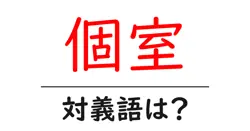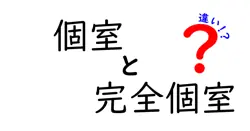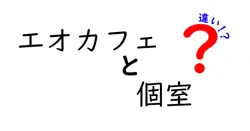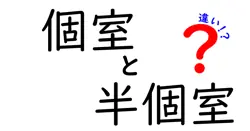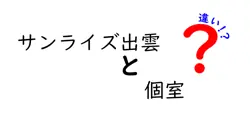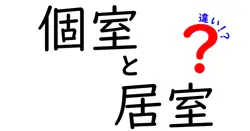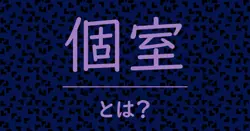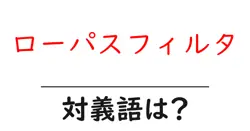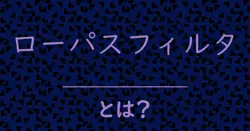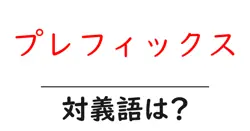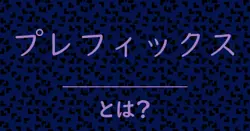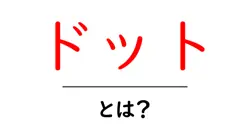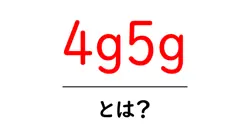西暦とは?歴史と使い方をわかりやすく解説
「西暦」という言葉を聞いたことがありますか? 西暦は世界中で使われている日付の数え方の一つで、特にキリスト教の影響を受けた国々で広く使われています。このブログでは、西暦の意味や歴史、使い方についてご説明します。
西暦の基本
西暦は、キリスト教の創始者であるイエス・キリストの誕生を基準にして日付を数える方法です。イエス・キリストが誕生した年を「紀元元年」とし、その後の年を順に数えていきます。例えば、2023年はイエス・キリストの誕生から2023年目という意味になります。
西暦の歴史
西暦は元々ローマ帝国の時代に始まりました。最初に西暦を制定したのはローマの司祭、ディオニシウス・エクシグウスです。彼は、紀元前525年にイエス・キリストの誕生を元年とする西暦を作りました。その後、この西暦の数え方が広まり、現在ではほぼ全世界で使われています。
西暦の表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1年 | イエス・キリストの誕生 |
| 476年 | 西ローマ帝国の滅亡 |
| 1492年 | コロンブスがアメリカ大陸を発見 |
| 2023年 | 現在(2023年) |
西暦の使い方
日常生活では、生年月日や出来事の日付などさまざまな場面で西暦が使われます。例えば、あなたの誕生日や友達の誕生日を表すとき、「1990年2月3日」といった具合に使います。また、歴史を学ぶときも、出来事があった年を書くときに西暦を使うことが一般的です。
西暦と他の暦との違い
西暦の他に、日本では「和暦」や中国の「干支」など、様々な種類の暦が存在します。和暦の場合、現在の令和や平成など、年号が使われます。例えば、2023年は令和5年にあたります。
まとめ
西暦は、世界中で共通して使われている日付の数え方です。その歴史は古く、キリスト教の影響を受けた文化圏で特に根付いています。日常生活や歴史を学ぶ上で、西暦の知識は役立つものです。これからは、日付を考えるときにぜひ西暦に注目してみてください。
ad とは 西暦:「AD」は「Anno Domini」というラテン語の略で、訳すと「主の年」という意味です。この言葉はキリスト教の歴史に基づき、西暦(西暦は英語で「AD」)を数えるために使われます。例えば、AD 2023年は主の年2023年と同じです。「AD」はイエス・キリストの誕生を基準としていて、イエスが生まれた年を1年目として、その後の年を数えていきます。これに対して、イエスの誕生の前の年は「BC」(Before Christ)という表記を使用します。BC1年の翌年はAD1年であり、そこには0年は存在しません。つまり、西暦はイエス・キリストの誕生を中心にした年のカウント方法なのです。このように、ADという言葉は宗教的な背景が強いですが、今では世界中で一般的に使われています。学校の授業や歴史の本でも頻繁に見かける用語です。そのため、ADの意味を知っていると、歴史を学ぶ際にとても役立ちます。
元号 西暦 とは:日本では、時代を区切るために「元号」という独自のカレンダーシステムを使っています。元号は天皇が変わると新しいものに切り替わり、今までの歴史を認識するのに役立ちます。例えば、最近の元号は「令和」です。一方、西暦は世界共通のカレンダーで、キリストの誕生を基準としています。これにより、例えば2023年は西暦で表すと「2023年」となり、元号で表すと「令和5年」となります。元号のほうが、日本の文化や歴史を感じることができるため、特に日本人には親しみがあります。逆に、西暦は国を問わず使われるため、国際的に分かりやすいという特徴があります。この二つのカレンダーを上手に使いこなすことで、日本の歴史をより深く理解できるかもしれません。元号と西暦、どちらも大切な時間の数え方ですので、ぜひ覚えておいてください。
入居年(西暦)とは:「入居年(西暦)」とは、建物や住宅に実際に住み始めた年のことを指します。例えば、2020年に入居した場合、その住宅の入居年は2020年になります。この情報はとても大切です。なぜなら、建物の状態や価値を判断するのに役立つからです。また、入居年が新しいほど、設備や内装が現代的であったり、メンテナンスがまだ行き届いていることが多いです。一方、古い入居年の住宅ではリフォームが必要だったり、老朽化が進んでいる可能性もありますので、注意が必要です。これから住宅を選ぶ際には、入居年をしっかり確認して、自分に合った住まいを見つけることが重要です。入居年の情報は、不動産の広告や契約書にも記載されていますので、しっかりチェックしてみてください。
和暦 西暦 とは:和暦と西暦は、私たちの日常生活でよく使われる日付の表し方です。まず、西暦について説明します。西暦はキリストの誕生を基準にしており、現在は2023年です。一方、和暦は日本独自の年号を使い、日本の歴史や文化に深く結びついています。例えば、令和という和暦は、2019年から使われているものです。和暦の元号は、天皇が変わることで新しくなります。和暦は「令和5年」などと表記しますが、これを西暦に直すと2023年になります。和暦を使うと、日本の歴史を感じることができますが、西暦の方が国際的には多く使われています。学校や仕事の場面では、どちらの表現も知っておくことが大切です。和暦と西暦の両方を理解して、場面に応じて使えるようになりましょう!
年号 西暦 とは:「年号」と「西暦」という言葉、皆さんはそれぞれどういう意味か知っていますか?年号は日本の古いカレンダーシステムで、天皇の治世に基づいて年を数えます。例えば、2023年は令和5年にあたります。一方、西暦は世界中で使われているカレンダーの基準で、キリスト誕生を起点に年を数えます。同じ年でも、年号と西暦とでは名前が違うため、混乱することがあります。特に日本では、年号が使われる場面も多くありますが、海外では西暦が主に使われます。それぞれのシステムには歴史的背景があり、年号は日本の文化を表す一方、西暦は国際的な基準となっています。しかし、両方を理解することができると、自分の生活や歴史をより深く理解する手助けになります。年号と西暦、この二つの違いを知っておくことは、今後の生活にも役立ちますし、友達との会話でも話題になるかもしれません。ぜひ覚えておきましょう!
生年月日 西暦 とは:生年月日を西暦で表すとは、自分の誕生日や他の人の誕生日を「西暦」という形式で示すことを指します。西暦とは、キリスト教のカレンダーに基づいている年の数え方で、例えば「2023年」というように表現します。日本では生年月日を「年、月、日」で表現することが一般的です。 西暦は、私たちの生活の中で非常に重要な役割を果たしています。たとえば、学校の入学年や卒業年、年齢の計算など、様々な場面で使われます。生年月日を西暦で表記することで、誕生日をより具体的に理解することができ、年齢を計算するのも簡単になります。例えば、1990年4月1日生まれの人は、2023年の時点で「33歳」となります。 また、国によっては旧暦(和暦)を使うこともありますが、国際的には西暦が一般的なので、英語の文献や国際的な会議、ビジネスメールなどでは、西暦で生年月日を記載することが重要です。このように、生年月日を西暦で表すことは、私たちのコミュニケーションをスムーズにし、様々な場面で役立っています。
西暦 fy とは:「西暦 FY」という言葉は、主にビジネスの世界で使われる用語です。ここでのFYは「Fiscal Year」の略で、日本語では「会計年度」と言います。西暦と組み合わせることで、その年度を特定の年に対して示すことができます。たとえば「2023 FY」と書くと、2023年の会計年度を指します。会計年度とは、企業や団体が予算を立てたり、経営計画を策定したりするための期間で、通常は1年間です。この期間は、カレンダー年と異なることもあり、いろいろな企業や国で異なる場合があります。日本の多くの企業は4月から翌年の3月までを会計年度として設定していますが、アメリカでは1月から12月までのことが一般的です。したがって、FYを理解することは、企業の報告書や業績発表を理解するために非常に重要です。特に、投資を考えている人や企業の動向に興味がある人は、FYを意識しておくと良いでしょう。
西暦 とは どっち:「西暦」は私たちが日常生活でよく使う年代の数え方の一つです。例えば、2023年や1999年などの数字がそれにあたります。西暦はキリストの誕生を基準にしていて、イエス・キリストが生まれたとされる年が「西暦1年」です。なので、私たちが今いる年を考えると、2023年はイエス・キリスト誕生から2023年目ということになります。西暦は特に国際的に使われているため、他の国の人とコミュニケーションをとる際には非常に便利です。例えば、日本では元号(明治、大正、昭和など)も使いますが、西暦の方が多くの人に通じやすいです。西暦の使い方は簡単で、年だけの表記でなく、月や日を付け加えてもOKです。例えば、2023年1月1日は「2023年1月1日」となります。予定を立てるときや、歴史を学ぶときなど、さまざまな場面で使われますので、覚えておくと役立ちます。西暦を使うことで、過去や未来の出来事を把握しやすくなるので、是非、この便利さを実感してみてください。
西暦 とは 今年:西暦(せいれき)とは、私たちが普段使っている年の数え方の一つです。大昔、キリスト教の誕生を基にして、年が数えられるようになりました。現在のカレンダーでは、キリストが生まれた年を「西暦元年」とし、そこからの年数を数えていきます。たとえば、2023年は「キリストが生まれてから2023年目」という意味です。西暦は世界中で広く使われており、特にビジネスや国際関係において、とても重要です。今年が何年かを知ることは、日付を理解するためにも欠かせないポイントです。学校の授業や友達との会話でも頻繁に出てくるので、しっかりと覚えておきましょう。そして、年が変わるときは、新しい年号をよく聞きますが、その年号も西暦と合わせて使うことが多いので、年の数え方を知ることは役立ちます。これからも、西暦について理解を深めていきましょう。
年号:特定の年を示すために用いる名称で、西暦と対比されることが多い。日本では主に元号が使用されています。
西暦元年:西暦の最初の年を指し、紀元前0年から計算して1年が西暦元年とされています。
紀元:歴史の年数を数えるための基準点。西暦はイエス・キリストの誕生を基準にしています。
暦:年月日を数えるためのシステムやカレンダーのこと。西暦はグレゴリオ暦に基づいています。
BC(Before Christ):イエス・キリストの誕生以前の年を示す表記。通常、紀元前の年を指します。
AD(Anno Domini):ラテン語で「主の年」を意味し、西暦元年を含む年を表すための表記。
カレンダー:日付を表示するためのシステムや表。西暦などのさまざまな年号を使って作成されます。
世代:特定の年代の人々の集まり。西暦を使って世代の区分が可能です。
時間軸:出来事や年を直線で示すための視覚的な表示。西暦はしばしば時間軸上での位置づけに使われます。
紀元:キリスト生誕の年を基準にした年数の数え方。西暦と同じく、さまざまな歴史的出来事などを年に基づいて示す際に使用される。
西暦年:西暦を具体的に示す際に使われる表現。例として、2023年のように、年数の後ろに「年」を付けることで、より明確に示すことができる。
AD:ラテン語の「Anno Domini」を略したもので、英語で「主の年」を意味する。キリストの誕生を基準とした年を示すのに使われ、西暦と同じ意味で用いられる。
キリスト紀元:キリストの誕生を基準にした年の数え方で、西暦の基本的な概念を示す。教会などの宗教的な文脈でよく使われることがある。
年号:特定の時代や元号を示す表現。ただし、年号は主に日本の元号の場合に使用され、西暦とは異なるが、同様に時間を示す方法の一つである。
紀元前:西暦の前の年を表す言葉で、主に歴史的出来事を記録する時に使用されます。例えば、西暦500年の100年前は紀元前400年となります。
紀元後:西暦元年以降の年を指します。つまり、西暦1年から数え始める年で、現在の西暦はすべて紀元後に該当します。
ユリウス暦:古代ローマで使用されていた暦で、西暦の基となり、主に西洋の歴史の計算に使われました。現在のグレゴリオ暦の前身とも言えます。
グレゴリオ暦:現在広く使用されている暦で、1582年に Pope Gregory XIII によって導入されました。西暦はこの暦に基づいて数えられています。
干支:中国の伝統的な時間の数え方で、西暦との関連性もあります。12の動物と10の天干が組み合わさって、60年のサイクルを作ります。
元号:日本特有の年号の表現方法で、天皇の即位や在位の期間に基づいて名付けられます。西暦と並行して使用されます。例えば、令和は西暦2019年から始まります。
西暦元年:紀元前1年の次の年で、キリスト教の歴史において重要な年とされています。この年を起点に西暦が計算されます。
時代:歴史を特定の期間に区分するための用語で、その時代を西暦で表記することもあります。例えば、古代、中世、近代などがあります。
西暦の対義語・反対語
該当なし