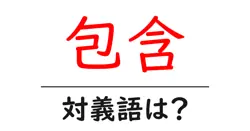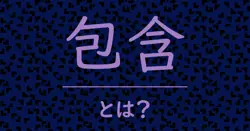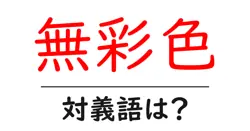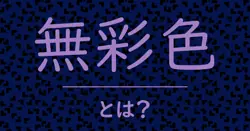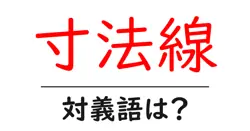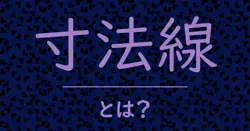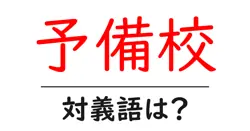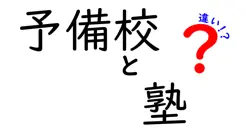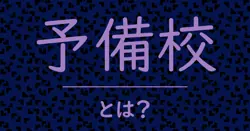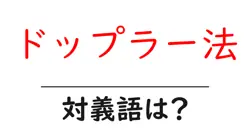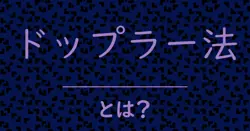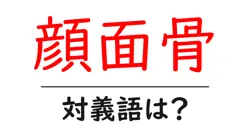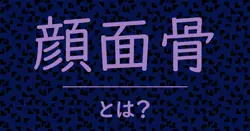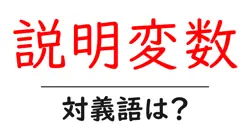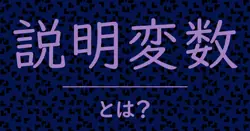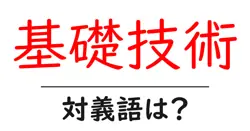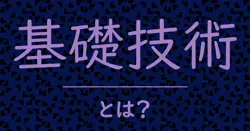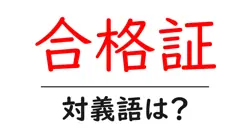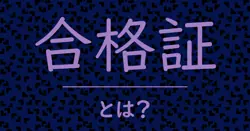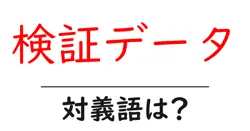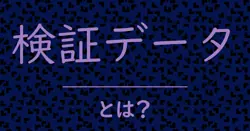包含とは?
包含(ほうがん)という言葉は、あるものが他のものを含む、あるいはその中に存在するという意味を持っています。特に、数学や論理学の分野でよく使われます。例えば、AがBを包含するというと、Aの中にBが含まれているということです。
具体例
身近な例を考えてみましょう。お弁当の箱を想像してください。お弁当の箱(A)の中には、ご飯やおかず(B)が入っています。この場合、お弁当の箱は、その中にあるものを包含しています。
包含の種類
包含には主に以下の2つの種類があります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
包含と集合について
数学では、集合が一つの重要な概念とされています。例えば、集合Aが集合Bを包含する場合は、Aのすべての要素がBに含まれている必要があります。この時、AはBの「超集合」と呼ばれます。一方、逆にBがAを包含する場合、BはAの「部分集合」となります。
例え話
この概念をそれぞれの果物で考えてみましょう。果物の集合をAとし、その中にリンゴやバナナなどがあるとします。この時、リンゴという部分集合Bは、Aに含まれています。これが包含の基本的な考え方です。
まとめ
包含という言葉は、物事の関係性を理解する上で非常に重要な概念です。数学だけでなく、日常生活の中でも頻繁に目にすることがあります。例えば、パソコンのフォルダやファイルにもこの概念が使われていることがあります。しっかり覚えておくと役立つでしょう。
div><div id="kyoukigo" class="box28">包含の共起語
包括:特定のものを包み込む、または全体を含むという意味で、より広い範囲を指す言葉です。
関連:何かが他のものとつながりや関係性があることを指します。包含の考え方では、あるものが他のものに寄与することが多いです。
全体性:事象や存在の完全な状態や性質を指し、包含の概念と深く関わっています。すべてが集まって一つの全体を形成する様子を表す言葉です。
包括的:多くの要素や側面を含むことを表します。特に、様々な領域や範囲を考慮する場合に使われることが多いです。
網羅:すべてのものをすきまなく含むこと、またはすべての項目を取り込むことを意味します。
包摂:あるものが他のものに含まれることを示す言葉です。通常は、より小さいものがより大きなものに含まれるという意味合いがあります。
包含性:ある対象が他の対象を含む性質を指します。特に、数学や論理学などの分野で使われることが多い用語です。
統合:異なる要素や部分を一つにまとめることを指します。包含によって、個々の要素が結びつく過程を表します。
接続:2つ以上のものが繋がりを持つことを表します。包含の考え方では、要素どうしの相互関係を示す重要な概念です。
相互作用:複数の要素が互いに影響を与え合うことを指し、包含の文脈での動的な関係を示します。
div><div id="douigo" class="box26">包含の同意語含有:ある物の中に他の物が含まれていること。特に成分や要素が内部に存在する場合に使われる。
包含する:あるものの中に他のものをすべて含んでいる状態を示す言葉。全体を包み込むようなニュアンスがある。
内包:ある概念や範囲の中に他の要素が含まれること。抽象的で、特に理念や思想に対して使われることが多い。
包含性:あるものが他のものを含む性質や特性を指す。特に、包括的な性質を持っていることを表現する。
含む:ある物の中に他のものを持っている状態を示す。一般的に使われる表現で、広範囲にわたる。
div><div id="kanrenword" class="box28">包含の関連ワード包含関係:包含関係とは、ある集合が別の集合の一部であることを示す関係のことです。例えば、AがBに含まれる場合、AはBの部分集合といいます。
サブセット:サブセットは、ある集合の部分集合のことを指します。つまり、ある集合に含まれる要素のうちの一部のみを集めた集合です。
集合論:集合論は、集合の性質や関係を研究する数学の一分野です。包含は集合論の基本概念の一つです。
要素:要素とは、集合に含まれる個々の項目のことです。例えば、A={1, 2, 3}において、1, 2, 3はすべてAの要素です。
共通部分:共通部分は、二つの集合に共通して含まれる要素を指します。二つの集合の交点として考えられます。
交わる:交わるとは、二つの集合に共通の要素があることを意味します。たとえば、AとBの集合が交わるとき、それはA∩Bで表されます。
補集合:補集合とは、ある集合に含まれないすべての要素を集めた集合のことです。集合Aの補集合は通常、A'やA^cで表されます。
ユニオン:ユニオンとは、二つ以上の集合を合わせたものです。例えば、集合AとBのユニオンは、A ∪ Bとして表され、両方の集合のすべての要素を含みます。
div>