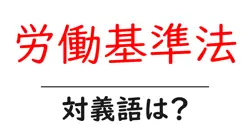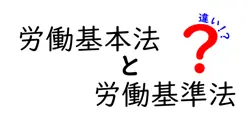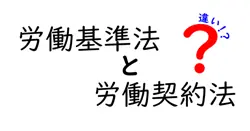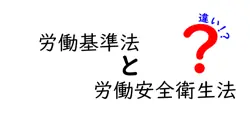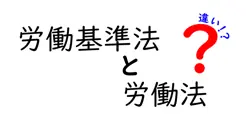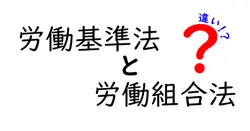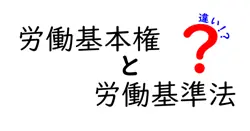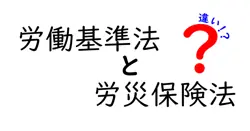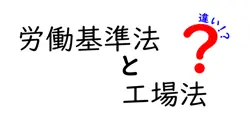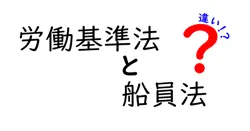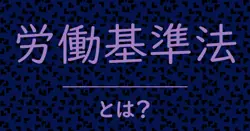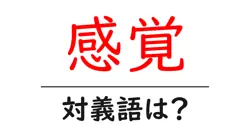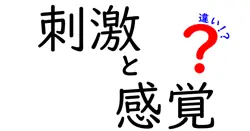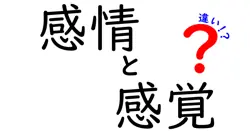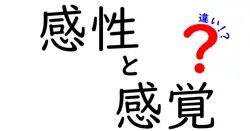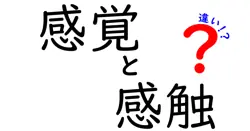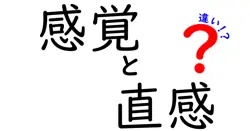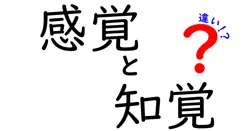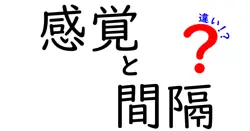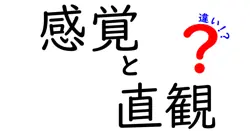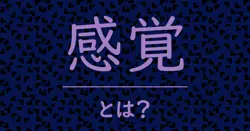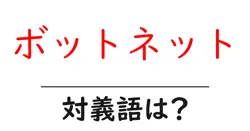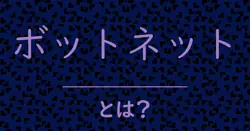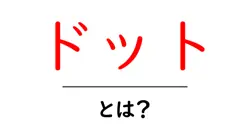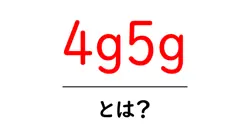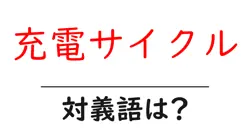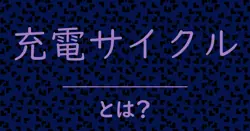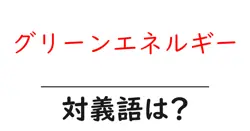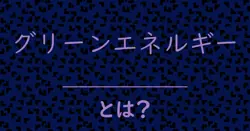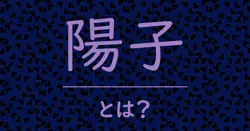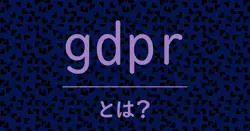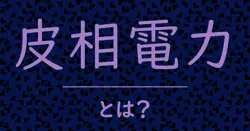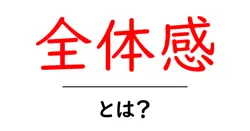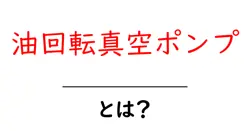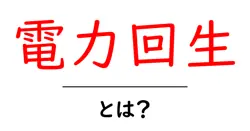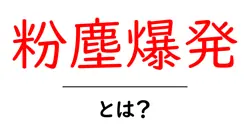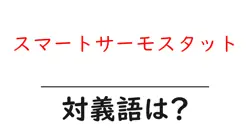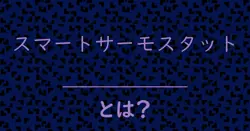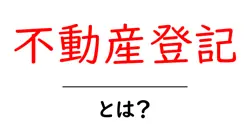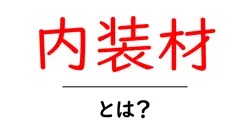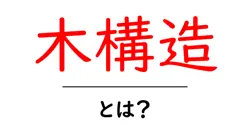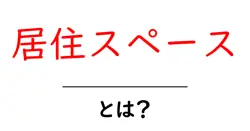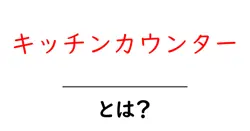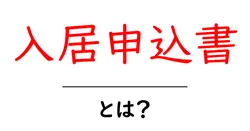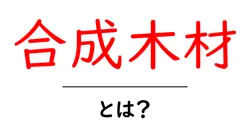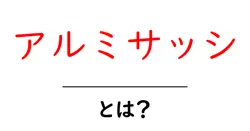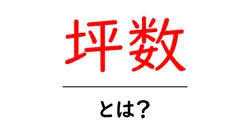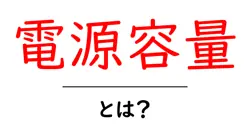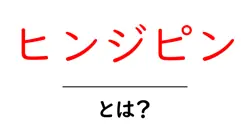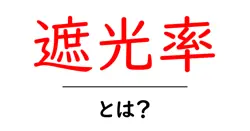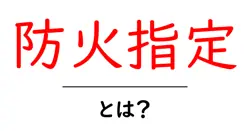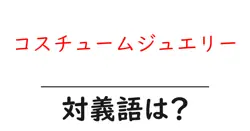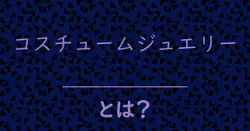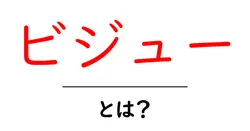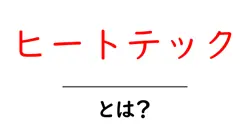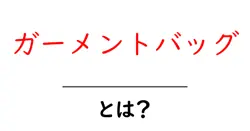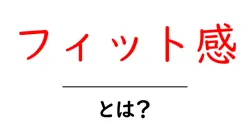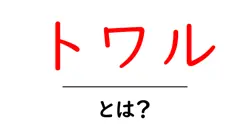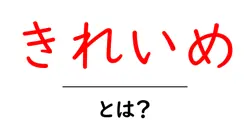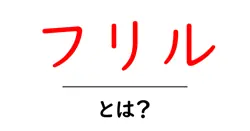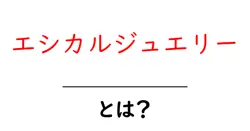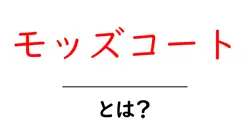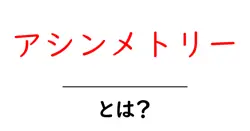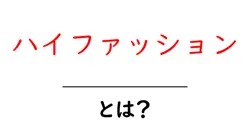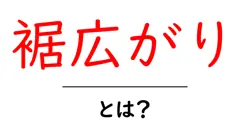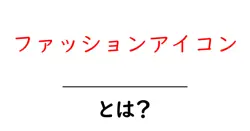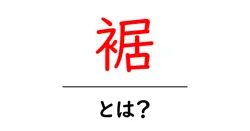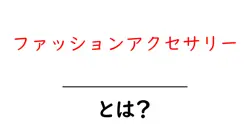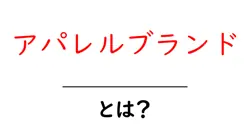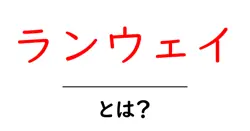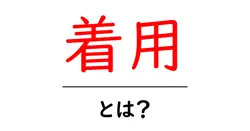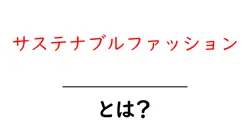労働基準法とは?基本的な内容
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)は、日本で働く人たちの権利を守るための大切な法律です。この法律は、労働者が安全で快適に働くことができるように、働き方や労働条件についての基準を定めています。1959年(昭和34年)に制定されて以来、労働者の権利を保護するために改正が行われています。
なぜ労働基準法が必要なのか?
労働基準法が必要な理由は、働く人たちが不当に扱われないようにするためです。例えば、労働時間が長すぎたり、給料が少なすぎたりする場合、働く人たちの生活に大きな影響を与えます。労働基準法は、こういった問題を防ぐために作られました。
労働基準法に定められた主な内容
労働基準法には、以下のような重要な内容が含まれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 1日の労働時間は8時間、週40時間を超えてはいけないと定めています。 |
| 休暇 | 毎週必ず1日の休息日を与えることが求められています。 |
| 賃金 | 最低賃金を定め、労働に対して適切な報酬が支払われることを保証しています。 |
| 安全衛生 | 職場の安全や衛生を保つための基準が定められています。 |
労働基準法の重要性
労働基準法があることで、働く人たちはより良い労働条件を得ることができるようになります。また、企業もこの法律を守ることで、安心してビジネスを行うことができます。労働基準法は、働く人と企業との間の信頼関係を築くためにも重要な法律なのです。
まとめ
労働基準法は、私たちが働く環境を良くするための法律です。働く人たちの権利を守り、安全で快適な職場を作るためには不可欠な存在といえます。これから働く人たちは、この法律のことを理解し、自分の権利を守るために知識を深めていくことが大切です。
休日 とは 労働基準法:休日とは、仕事を休む日を指します。日本の労働基準法では、働く人たちが安心して休めるように、様々な規定が設けられています。労働基準法では、労働者は週に1回以上の休日をとる権利があります。この休みの日は、心の健康を維持するためにも、とても大切です。また、休日にしっかりと休むことで、仕事のパフォーマンスも向上します。たとえば、疲れを取り、新しいアイデアを考える時間にもなります。さらに、休日の取り方には、自由な時間を楽しむことや、家族と過ごすこと、友達と遊ぶことなどがあります。このように、休日は労働者の生活において大きな意味を持っています。労働基準法は、労働者を保護し、健全な働き方を推進するために重要な役割を果たしています。
労働基準法 とは 簡単に:労働基準法は、働く人々の権利を守るために作られた法律です。この法律は、例えば働く時間やお休み(休暇)、給料の最低額(最低賃金)などについてのルールを定めています。ここで知っておきたいのは、労働者は自分の働き方について知る権利があるということです。たとえば、労働基準法によると、8時間を超えて働かせる場合、企業は時間外労働の手当を支払わなければなりません。また、週に1日はお休みを与えなければならないという決まりもあります。これらはすべて、働く人々が安心して仕事を続けられるようにするための大切なルールです。もし何か問題があった際には、自分の権利を主張することが重要です。労働基準法は、私たちの生活に密接に関わっているものなのです。だから、これを知っておくことはとても大切です。自分の権利を守るためにも、この法律について学んでいきましょう。
労働基準法 使用者 とは:労働基準法における「使用者」という言葉は、労働者を雇っている人や会社を指します。つまり、労働者と契約を結んで、仕事を与える立場の人のことです。たとえば、あなたがアルバイトをしている場合、その職場の店長や経営者が使用者にあたります。使用者は、労働者に対して基本的な雇用条件や賃金を約束し、労働環境を整える義務があります。労働基準法は、使用者が守らなければならないルールも定めていて、労働者の権利を守るために重要な役割を果たします。使用者は、労働時間や休暇、賃金の支払いなどを適切に行う必要があります。これにより、労働者が安心して働ける環境が整えられます。このように、使用者は労働者と直接関わる重要な存在であり、法律に基づいて責任を持った行動を求められています。労働基準法を理解することで、自分の権利を知り、安心して働くための知識を持つことができます。知っておくと、とても便利な情報です。
労働基準法 打切補償 とは:労働基準法における打切補償(うちきりほしょう)とは、主に契約社員やパートタイマーなどの短期間で働いている人たちが、会社から突然仕事をやめるように言われたときに受け取れるお金のことを指します。例えば、契約があったのに途中で解雇された場合、その労働者がどれだけ働いたかに応じた金額が必要になります。これは、労働者が生活を維持できるようにするための保障のようなものです。打切補償は、その補償の内容や金額について法律で決まっていますので、働いている人たちには必ず知っておいてほしい重要な情報です。また、労働基準法では、使用者が労働者に対して不当な解雇を行った場合には、その労働者が訴訟を起こすことも可能です。このように、打切補償について理解を深めることは、とても大切です。
労働基準法 管理監督者 とは:労働基準法には「管理監督者」という特別な立場の人がいます。これらの人々は、企業内での仕事を管理したり、他の従業員の指導を行う役割を持っています。例えば、店長や部長などがこれに該当します。管理監督者は、通常の従業員よりも多くの権限を持っていますが、その分、働き方も通常の従業員とちょっと違います。つまり、労働基準法では、彼らは残業代が出ないことが多いのです。これが普通の従業員との大きな違いです。ですが、彼らの役割は非常に重要で、労働環境を良くするための責任も負います。管理監督者は、自分の部下が働きやすいように、働き方や雇用条件などを整えることが求められます。従って、管理監督者は職場内でリーダーシップを取ると同時に、高い倫理観や責任感も必要です。このように、管理監督者の役割を理解することで、労働環境の改善に向けた取り組みにもつながるでしょう。
労働基準法 限度時間 とは:労働基準法の限度時間とは、働く人が1日にどれくらい働いていいのか、また1週間でどれくらい働いていいのかを決めた法律のことです。この法律は、働く人が健康で快適に働けるようにするために作られています。通常、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間が基本とされています。この時間を超えて働くことがある場合、会社は特別な理由が必要で、労働者としっかり話し合わないといけません。また、残業をした場合、追加でお金をもらえるルールもあります。しかし、中には超えられない限度時間として、「特別条項」というものがある場合もあります。これは、特別な理由があるときに限り、決められた限度時間を越えて働くことができるという仕組みです。でも、この特別条項を使うときには、事前に労働者と相談することが求められます。つまり、労働基準法の限度時間は、私たちが安心して働ける環境を守るための大切なルールなのです。
有給休暇 とは 労働基準法:有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)は、働く人が取ることができるお休みの一種です。これは、労働基準法という法律によって決められています。もう少し詳しく説明すると、有給休暇は働いている期間に応じて、会社から与えられるお休みのことです。このお休みを取ると、普通に働いているときと同じように給料が支給されます。労働基準法では、従業員は入社から6ヶ月以上経つと、有給休暇が与えられることが定められており、その後も働き続けることでだんだんと有給休暇の日数が増えていきます。たとえば、6ヶ月働いた場合には10日の有給休暇がもらえます。その後の勤務年数に応じて、最大で年20日まで増やすことができます。また、有給休暇を取る際には、あらかじめ会社に申請する必要があります。会社が承認することで、お休みを取ることができるのです。これにより、働く人は心身をリフレッシュすることができ、仕事のパフォーマンスを向上させることも期待できるのです。また、有給休暇は法律で守られているため、使わなかった分を翌年に持ち越すこともできるのが特徴です。知識として知っておくことで、将来のためにも役立つでしょう。
管理職 とは 労働基準法:管理職とは、会社や組織において他の従業員を指導し、業務を管理する役割を担っている人のことを指します。労働基準法では、管理職は一般的に労働時間や休日の規定に関して特別な扱いを受けることがあります。例えば、管理職は基本的に残業代が支給されないケースが多いです。これは、管理職の役割が単なる作業指示だけでなく、業務の計画や運営、部下の育成などが含まれるためです。そのため、労働基準法上、管理職は「職務内容」が重視され、一般の従業員とは異なる扱いを受けることがあります。さらに、管理職は組織の業務を推進するための責任もあるため、労働時間が長くなることがよくあります。このように、管理職には多くの責任が伴いますが、その分やりがいも大きいです。もしも管理職を目指しているのなら、こうした特性や法律を理解することが重要です。
労働者:働く人々を指し、企業や組織で労働を提供する人々のことです。労働基準法は特に労働者の権利を保護するために制定されています。
使用者:労働者を雇用する企業や個人のことです。労働基準法では使用者に対する義務も定められています。
賃金:労働に対して支払われる報酬のことです。労働基準法では賃金の最低額や支払方法についても規定があります。
労働時間:働く時間のことを指します。労働基準法では労働時間の上限や休憩時間の取り方についても詳細に定めています。
休日:労働者が働かない日、つまり休みの日のことです。法律により、労働者には年間の最低休日数が設定されています。
残業:通常の労働時間を超えて働くことを指します。労働基準法では残業に対する賃金の取り決めがあり、時間外労働には割増賃金が支払われます。
労働条件:労働者が働く際の条件全般を指し、賃金、労働時間、休日などが含まれます。これらは法律で守られています。
安全衛生:職場の安全を保ち、労働者が健康に働けるようにするための環境や取り組みのことです。労働基準法には、労働環境の安全性向上に関する規定もあります。
労働法:労働者の権利や義務について定めた法律の総称で、労働基準法もその一部です。
雇用基準法:雇用に関する基本的な基準を定めた法律です。労働者の雇用条件に関するルールも含まれています。
労働契約法:労働者と雇用者との間の労働契約に関するルールを定めた法律です。労働基準法と併用されることが多いです。
労働安全衛生法:労働者の安全と健康を守るための法令で、労働環境の改善に関する基準が示されています。
職業安全衛生法:職場における安全と衛生を確保するための法的規制で、労働者の作業環境を守ることを目的としています。
最低賃金法:労働者に支払われる賃金の下限を定めた法律で、労働者の生活を保障するための基準を設けています。
雇用保険法:失業時の保険や給付を定めた法律で、労働者のセーフティネットを形成する役割があります。
育児休業法:育児のための休業に関する法律で、育児を支援する規定が設けられています。
労働者:労働基準法の適用を受ける人々で、企業や組織で働く人のことを指します。
使用者:労働者を雇用する側、つまり会社や雇用主のことを指します。
労働時間:労働基準法では、労働者が仕事をするための時間のことを定義しており、常に適正な管理が求められます。
賃金:労働者に支払われる報酬のことで、労働時間や仕事の内容に応じた金額が設定されます。
休暇:労働基準法によって保障される、労働者が一定期間仕事を休むことができる権利のことです。
労働条件:労働者が働く際の環境や給与、労働時間などの条件を指し、法律で守られるべき基準があります。
解雇:使用者が労働者との雇用契約を一方的に終了することを指しますが、労働基準法では正当な理由が必要とされます。
労働組合:労働者が集まり、労働条件の改善や権利の保護を目的とした組織のことを指します。
労働基準法の対義語・反対語
労働基準法違反とは?罰則や企業名公表制度について事例付きで解説
労働基準法とは?概要やルールを分かりやすくご紹介 - テンプスタッフ
労働基準法とは|基準の内容や、違反摘発の仕組みをわかりやすく