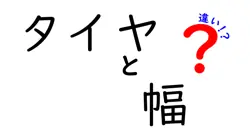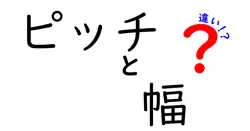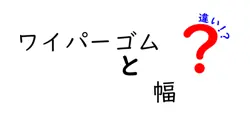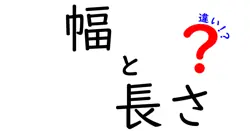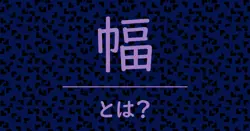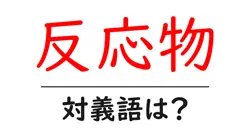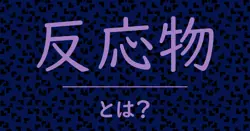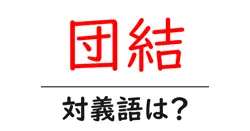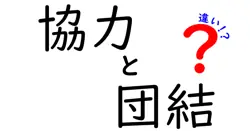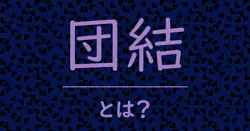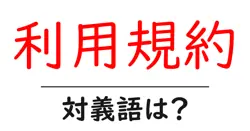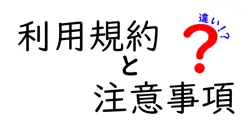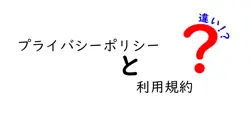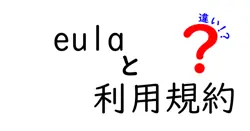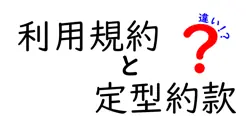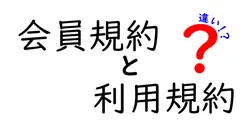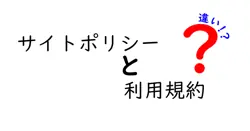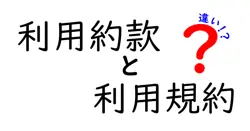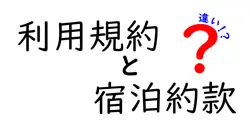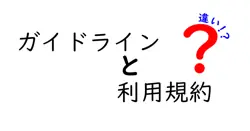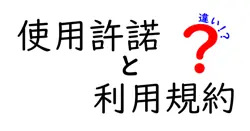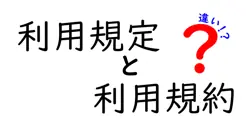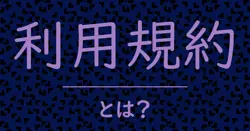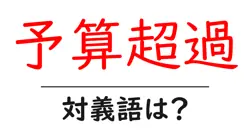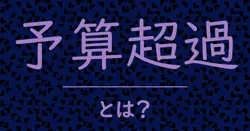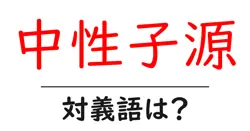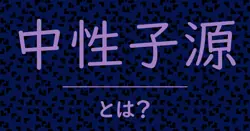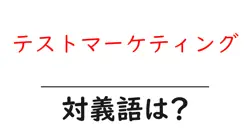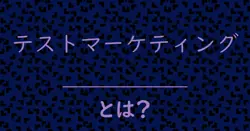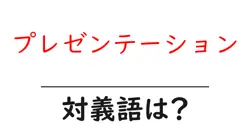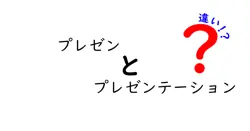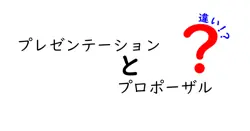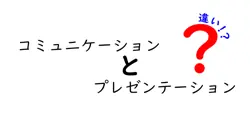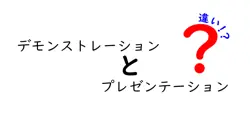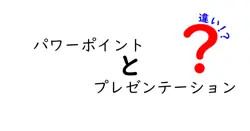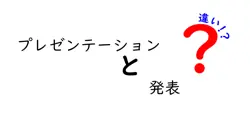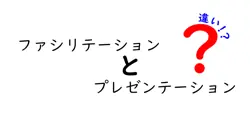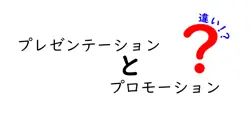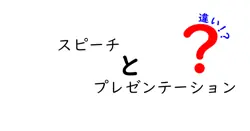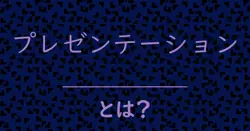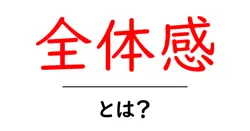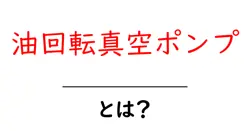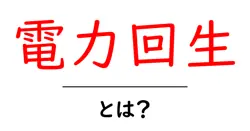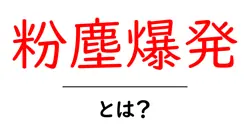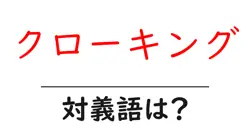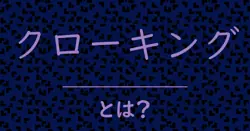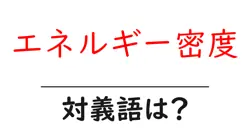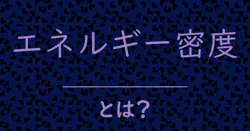幅とは?
「幅」とは、物の横の広さを表す言葉です。私たちが毎日見るものや使うものには、幅という概念が当てはまります。たとえば、机や本棚の幅、道路の幅、さらには布や板の幅など、多くの場面で使われる言葉です。
幅の使い方
幅は、ある物体の大きさを測る際によく使われます。幅が大きいと、たくさんのものを置けたり、多くの人が通れたりします。逆に幅が小さいと、スペースが限られてしまいます。たとえば、幅が狭い通りは、大きな車が通るのが難しくなることがあります。
幅の例
以下の表に、幅に関するいくつかの例を示します。
| 物の種類 | 幅の単位 | 幅の具体例 |
|---|---|---|
| 机 | cm | 75cm |
| 道路 | m | 8m |
| 布 | cm | 150cm |
| 本棚 | cm | 90cm |
幅が重要な理由
物の幅を理解することは、私たちの生活において非常に重要です。たとえば、家具を選ぶときには、その幅が部屋に合うかどうかを考えなければなりません。また、道路の幅が狭いと、交通渋滞が起こりやすくなります。このように、幅は私たちの周りの様々な事象に影響を与えています。
まとめ
以上のように、幅は私たちの日常生活において非常に大切な概念です。物の形や大きさを理解するためにも、幅を知っておくことは大切です。これからも幅について考えてみてください。
w とは 幅:「wとは幅」という表現は、特にデザインやプログラミングの分野でよく使われます。ここでの「w」は、英語の「width」の略称で、直訳すると「幅」を意味します。これを具体的に理解するには、例えばウェブサイトのレイアウトを考えてみましょう。ウェブページを作るとき、画像やテキストボックスの幅を調整することが重要です。ここで「w」を設定することで、デザインが整ったり、見やすくなったりします。また、プログラミングの世界でも「w」は、オブジェクトや要素の幅を制御する際に使われます。特にCSS(カスケーディングスタイルシート)では、ボックスの幅を指定するのに「width」というプロパティを使います。このように、「w」は多くの場面で幅を決めるための大切な要素となります。デザインやプログラミングに興味があるなら、ぜひ「wとは幅」について理解を深めてみてください。
インデント 幅 とは:インデント幅とは、文章の中で段落の開始部分をどれくらい左からずらすかということを指します。よく小説やエッセイで見かけるスタイルですが、これにより文章がより整然と見え、読みやすくなる効果があります。たとえば、インデントを使うことで新しい段落をはっきりと区別でき、読者は視覚的に内容を追いやすくなります。インデントの幅は、その文章に合わせて調整できますが、一般的には2文字分から5文字分ぐらいが使われます。ただし、あまりにも大きすぎると逆に見づらくなるので注意が必要です。インデントはパソコンの文書作成ソフトやプログラムでも設定できるので、ぜひ試してみましょう。文章を書くときに、インデント幅を使うことで、読者にとって魅力的でまとまりのある文章を作り上げることができます。
カーテン 幅 とは:カーテンの幅とは、カーテンの横の長さのことを指します。カーテンを選ぶとき、この幅を考えることはとても大切です。カーテンの幅は、取り付ける場所のサイズに合わせて決める必要があります。通常、カーテンは窓の幅よりも広めに選ぶことが推奨されています。これにより、カーテンを閉じたときに隙間ができず、外からの視線や光をしっかりと遮ることができます。さらに、カーテンを開けたときでも、窓の両側に十分な幅があると、部屋全体が明るく広く感じられます。カーテンの幅は、カーテンレールやリングから窓の端までの距離を測って決めると良いでしょう。このとき、少し余裕を持たせると、より美しい仕上がりになります。例えば、窓が100cmの幅なら、カーテンの幅は130cmから150cm程度が良いでしょう。カーテンの幅をしっかり考えることで、見た目だけでなく快適な空間づくりにも繋がります。
巾 とは 幅:「巾(はば)」とは、日本語で「幅(はば)」のことを指しています。日常生活では、どのようなものにも「巾」や「幅」という言葉が使われています。例えば、布や紙の広さを表す時に「巾が広い」や「幅が狭い」と言ったりします。しかし「巾」という言葉は、特に伝統的な物や、和風のものに使われることが多いです。たとえば、着物の生地の幅を言うときに「巾」という言葉を使います。実は、「巾」と「幅」は同じ意味ですが、使用する場面が少し違うのです。現代では「幅」という言葉が広く使われていますが、和風や伝統的な文脈では「巾」が好まれることがあります。このように言葉を使い分けることで、より日本文化に根ざした表現ができるのです。将来的に和服を着る機会があったり、伝統工芸に興味を持ったりした時、ぜひ「巾」という言葉を使ってみてください。普段あまり意識しないこれらの違いに気付くことで、より豊かな日本語の理解が得られるでしょう。
幅 とは 縦:私たちが日常的に使う言葉には、「幅」という言葉と「縦」という言葉があります。幅は、物の横の広さを指します。たとえば、机や本棚の幅はどのくらいかというと、奥行きではなく横の長さを測ります。一方で、「縦」は物の高さを指します。例えば、人間の身長や木の高さを測るとき、「縦」を使います。これらの言葉は、物の大きさを表す重要な言葉ですが、ごちゃ混ぜになりやすいので注意が必要です。たとえば、机の幅が80センチだとすると、その机の横の部分が80センチということになります。同じように、机の高さを知りたいときには、「縦」の部分を考えます。最初は少し難しいかもしれませんが、幅と縦の違いを覚えておくと、様々な物の大きさを正確に把握できるようになります。
幅広い:広い範囲や多くの選択肢を持っている状態。例えば、幅広いジャンルの音楽とは、さまざまなスタイルの音楽が含まれることを指します。
幅狭い:限られた範囲や選択肢が少ない状態。幅狭い視野を持つとは、物事を多角的に見ることができないことを仄めかします。
幅員:道路や橋などの幅を示す用語。例えば、車道の幅員は交通の流れに影響を与える要素です。
幅測定:物体や空間の幅を計測すること。例えば、設計図を作成する際に必要な技術です。
幅調整:物の幅を調整すること。家具などを置く際にスペースに合うように調整することが多いです。
広さ:物体や空間の端から端までの距離を指し、特に左右に取った距離を示す言葉です。
幅員:道路や橋などの幅のことを指し、交通の流れを円滑にするために必要な広さを示します。
横幅:物体の左右の広がりを表し、特に家具や衣類などのサイズを考える際に使われます。
範囲:何かが影響を及ぼす領域や範囲を示し、広がりを持つことを強調する言葉です。
スペース:物理的な空間や場所を指し、特に物が配置される空間の広さを表現します。
広がり:ある範囲や空間において、物事がどれだけ広く分布しているかを示す言葉です。
幅員:道路や橋などの幅を指し、交通の流れに関わる重要な要素です。幅員が広いと、多くの車両が通行できるため、交通渋滞の緩和に寄与します。
幅広:物やスペースが横に広がっている状態を指します。たとえば、幅広の本はページが多く、情報量が多いことを意味することがあります。
幅狭:物やスペースの幅が狭いことを指します。狭い幅は、例えば狭い通路や狭い椅子など、限られたスペースであることを示します。
視野幅:視覚的に見える範囲の広さを意味します。視野幅が広いと、多くの情報を一度に把握することができ、効率的に状況を判断できます。
幅調整:物の幅を調整する行為を指します。例えば、家具の配置やデザインで重要な要素になり、使いやすさや見た目に影響を与えます。
スライド幅:スライドショーやプレゼンテーションにおいて、各スライドが切り替わる際の画面の幅のことを指します。適切なスライド幅は、視覚的な一貫性を保つのに重要です。
幅優先:プロジェクトやプランにおいて、幅広い視点や意見を優先的に考慮することを意味します。これにより、さまざまな角度からのアプローチが可能になります。
幅出し:特にファッションや製品デザインで、物のデザインをより広く見せるための加工や工夫を行うことを言います。
幅の対義語・反対語
幅の関連記事
生活・文化の人気記事
次の記事: 抽象化とは?中学生でもわかる簡単解説共起語・同意語も併せて解説! »