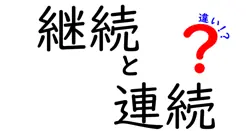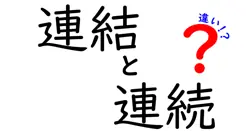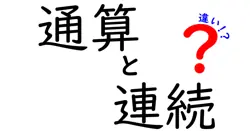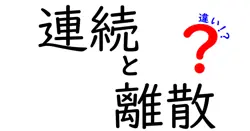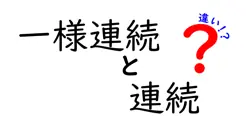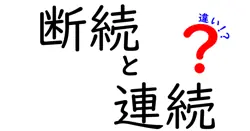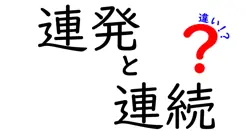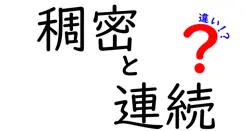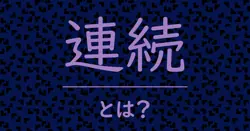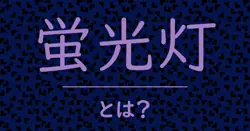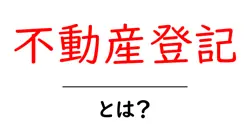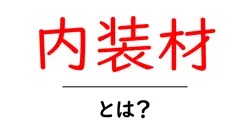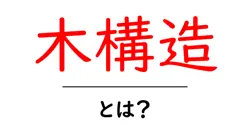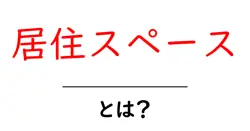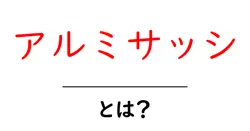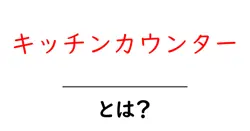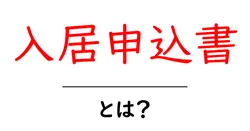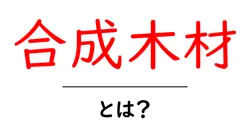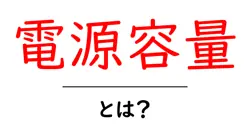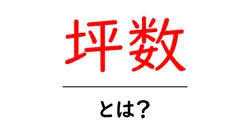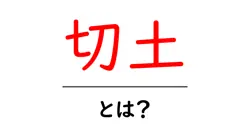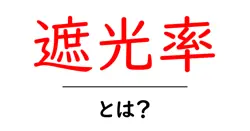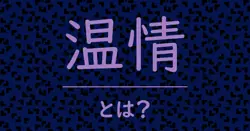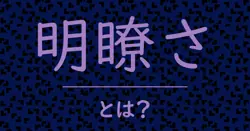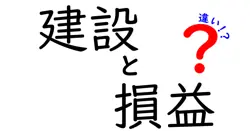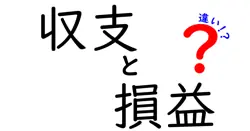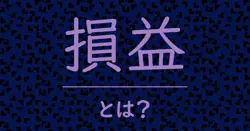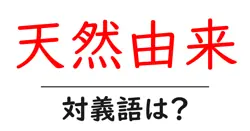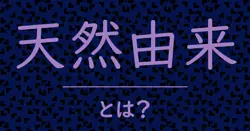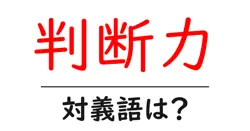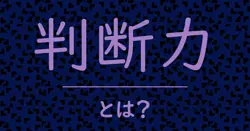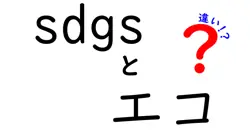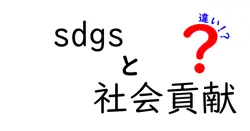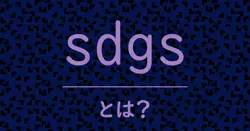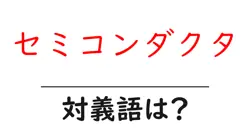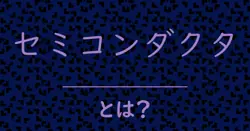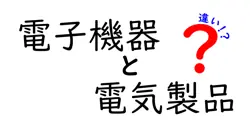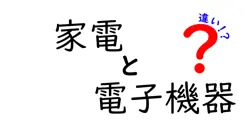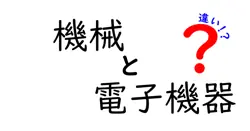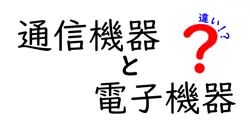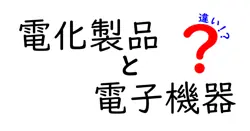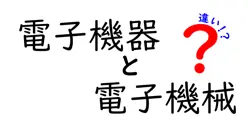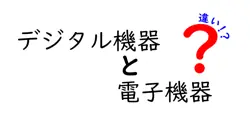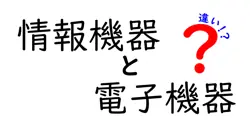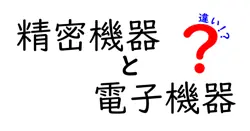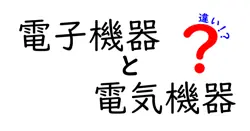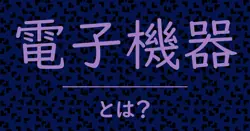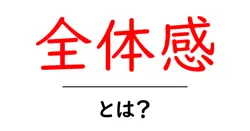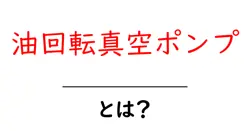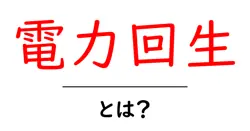連続とは?
「連続」という言葉は、何かが途切れずに続いている状態を指します。例えば、テレビのドラマで「今日のエピソードは前回の続きです」と言われる時、そのドラマは「連続」していると言えます。このように、連続という概念は私たちの生活の中で、様々な場面で使われています。
連続の基本的な使い方
連続という言葉は、日常生活の中でたくさんの使われ方をします。以下にいくつかの例を挙げてみましょう。
| 状況 | 使い方の例 |
|---|---|
| テレビ番組 | 「この番組は、連続して放送されています。」 |
| 学習 | 「彼は連続して3日間勉強しました。」 |
| 運動 | 「毎日連続してジョギングをしています。」 |
なぜ連続が大切なのか?
連続性は、物事を進める上で非常に重要です。あるタスクを毎日少しずつ続けることで、習慣化できます。例えば、勉強や運動は、連続して行うことで成果が得られます。また、連続して何かに取り組むことで、自信もつきます。これが「連続」することの重要性です。
連続することで得られるメリット
最後に
「連続」という言葉はシンプルですが、その意味や重要性を理解すると、日常生活に役立てることができます。ぜひ、あなたも何かを連続して続けてみてはいかがでしょうか?それによって、あなたの生活がより豊かになるでしょう。
ダイキン 加湿 連続 とは:ダイキンの「加湿 連続」という言葉は、湿度を高めるための技術や機能を指します。特に冬の時期、乾燥した空気が肌や喉に悪影響を及ぼすことが多いです。そこで、ダイキンの加湿器は連続して湿気を供給できる機能があり、これによって快適な湿度を維持しやすくなります。 例えば、仕事や勉強をしている部屋で長時間過ごすと、空気が乾いてきますが、ダイキンの加湿器を使うと、その悩みを解消できます。連続加湿機能を活用すると、湿度が一定に保たれるので、快適に過ごせる環境が整います。 また、ダイキンの加湿器にはフィルター機能もついていて、空気中のゴミやウイルスを除去しながら加湿してくれます。このように、ダイキンの加湿機能は健康にも良い影響を与えるのです。日常生活の中で、加湿器を上手に使って、心地よい湿度を保つように心掛けましょう。 ダイキンの加湿器で、冬でも快適な毎日を送りましょう。
ダイキン 湿度 連続 とは:ダイキンの「湿度連続」は、家庭やオフィスで快適に過ごすための機能です。この機能は、室内の湿度を一定に保つことを目的としており、特に夏や梅雨の季節に役立ちます。湿度が高すぎると、カビやダニが発生しやすく、健康に悪影響を及ぼすことがあります。他にも、ジメジメした空間は気分が悪くなる原因にもなります。ダイキンの湿度連続機能では、センサーで室内の湿度を常にチェックし、必要に応じて除湿を行います。これにより、湿度が快適なレベルに維持され、健康的で居心地の良い環境が保たれるのです。特に、赤ちゃんや高齢者がいる家庭では、この機能は非常に重要です。さらに、省エネ性能にも優れており、電気代の節約にもつながります。ダイキンの湿度連続機能を使うことで、快適で健康的な生活空間を手に入れることができるでしょう。
ダイキン 除湿 連続 とは:ダイキンの除湿機には「連続運転」という便利な機能があります。連続運転とは、一定の湿度を保ちながら、除湿をずっと続けられる状態のことです。この機能を使うことで、部屋の湿気をしっかりと取り除き、カビや臭いの原因を防ぐことができます。特に梅雨や夏の湿度が高い時期にはとても役立つ機能です。連続運転を使うには、まず除湿機の設定を連続運転モードに切り替えます。すると、湿度が設定した値以下になるまで、除湿機が自動で運転を続けます。ただし、連続運転をしていると電気代が高くなることがあるので、使用する時間帯や頻度には注意が必要です。ダイキンの除湿機は高性能なので、効率よく湿気を取り除いてくれます。さらに、フィルターも掃除しやすい設計になっているので、手間も少なくて済みます。家の中を快適に保ちたい方には、連続運転機能を活用することをおすすめします。
乗車券 連続 とは:乗車券の連続(じょうしゃけんのれんぞく)とは、特定の区間を連続して利用するための乗車券のことを指します。例えば、ある駅から別の駅までの距離が長い場合、一つの切符で連続して移動できるようになります。この制度は、通勤や旅行をスムーズにするためのものです。通常、乗車券はそれぞれの区間ごとに購入する必要がありますが、連続券を使うと、何度も切符を買わなくても済むので、非常に便利です。連続券には、特定の時間内に有効なものと、無制限で使えるものがあります。例えば、午前中の通勤ラッシュを避けるために朝早く出発するなら、連続券を利用して、いくつかの駅を経由して目的地に行くことができます。また、特別な旅行プランで提供されることもあり、観光地を訪れる際にも使えます。このように、乗車券の連続は無駄な時間を削減し、効率よく移動するための手助けをしてくれるのです。旅行や通勤を快適に過ごしたい方には、大変おすすめの制度です。
微分 連続 とは:微分と連続は、数学の中でも特に重要な概念です。微分とは、ある関数の変化の割合を表すもので、グラフの傾きを求めることに使われます。具体的には、ある点における接線の傾きを計算することです。これに対し、連続とは、関数が途切れずに滑らかに繋がっていることを指します。言い換えれば、連続な関数では、グラフが一筆書きで描けるイメージです。この二つは密接に関連しています。たとえば、連続な関数は、その点で微分可能であるという特性があります。しかし、逆に微分が可能だからといって、その関数が必ずしも連続であるとは限りません。つまり、微分ができる関数は滑らかに変化することが多いですが、連続性だけでは微分ができない場合もあるのです。高校に進むとさらに詳しく学びますが、まずは微分と連続の基本的なポイントを押さえておきましょう。
連続 とは 数学:数学における「連続」という言葉は、数や関数が途切れずに繋がっている状態を指します。例えば、数直線を考えてみると、0から1の間には0.1、0.2、0.3といった数が無限に存在します。このように、数直線にはある範囲の中に無限の数が存在することから、連続性があると言えます。また、関数においても連続性が大切です。例えば、y = x²という関数は、xが0から3まで動くとき、yの値も0から9まで途切れることなく変化します。このように、yの値はxの値が変わるたびにスムーズに変化し、どの点でも直線を描くことができるため、連続した関数といいます。反対に、もし関数に飛び跳ねる部分があった場合は、その関数は連続ではないと考えます。数学では、連続性がとても大事で、特に微積分や解析学といった分野で頻繁に登場します。これを理解することが、数学を学ぶ上で役立つ基礎知識となるでしょう。
連続 不連続 とは:「連続」と「不連続」という言葉は、私たちの周りでよく使われますが、意味はちょっと違います。連続というのは、物事が途切れずに続いている状態を指します。例えば、1から10までの数字は連続していますよね。1、2、3…と順番に続いているからです。しかし、不連続というのは、物事が途切れている状態です。たとえば、1、3、5、7のように、数字が飛び飛びになっているのが不連続です。連続と不連続は、数学だけでなく、私たちの日常生活でもよく見つけることができます。また、音楽の世界でも連続的なメロディと不連続なリズムがあります。このように、連続と不連続はさまざまな場面で使われる言葉で、どちらがどのように使われるかを理解することで、日常生活や勉強に役立てることができます。簡単に言えば、連続は切れ目がない状態、不連続は切れ目がある状態と覚えておくと良いでしょう。
酸素ボンベ 連続 とは:酸素ボンベ連続とは、酸素をボンベから連続して供給する方法を指します。一般的には、呼吸が苦しむ方やリハビリ中の方に利用されます。例えば、喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんが、自宅や病院で連続して酸素を吸入することで、必要な酸素を効率よく取り入れることができます。実際、酸素ボンベを連続して使用することによって、体に必要な酸素量を確保しやすくなり、安心して生活できるようになります。しかし、使用する際にはいくつかの注意点もあります。まず、ボンベの残量を定期的に確認することが大切です。そして、酸素は可燃性があるため、火の近くでは使用しないことが必要です。また、ボンベの扱い方や設置場所にも十分な配慮が求められます。酸素ボンベ連続使用によって、快適に過ごすためには、これらのポイントを意識して利用することが重要です。
継続:物事を続けること。特に、努力や活動を途切れずに行うことを指します。
繰り返し:同じ事を何度も行うこと。例えば、同じ練習を繰り返すことで上達することがあります。
一貫:途中で変わることなく、最初から最後まで同じ方針や態度を貫くこと。
連鎖:ある事象が次の事象を引き起こすこと。例えば、ある出来事が次々と関連して起こることを指します。
持続:ある状態を長く保ち続けること。そのためには努力や工夫が必要です。
連絡:人と人との間で情報を伝え合うこと。例えば、仕事の進捗や尋ねたいことを知らせること。
連帯:共通の目的や利益のために、人々が協力し合うこと。
連続性:物事が途切れることなく続いている状態。一定の流れが保たれていることを示します。
アクティブ:活動的であること。物事を積極的に続ける姿勢を表します。
習慣:日常的に行う行動や活動。連続して行うことで習慣化することがあります。
繰り返し:同じことや似たようなことが何度も行われることを指します。例として、毎日同じ時間に運動することが挙げられます。
続ける:何かを中断せずに続けて行うことです。例えば、勉強を毎日続けることは、知識をより深めるために重要です。
連係:いくつかの要素が互いに関係し合ってつながることを意味します。例えば、異なるプロジェクトが共同で目的を果たすために連係する場合です。
連結:複数の物や事象が一つに繋がることです。論文などで複数の研究結果を連結させ、全体の理解を深める手法が用いられることがあります。
連鎖:一つの出来事が次の出来事を引き起こすことを示します。ビジネスでは、ある商品が売れることで次の商品も売れるという連鎖的な効果が見られることがあります。
継続:ある行為を断たずに持続させることです。例えば、健全な生活習慣を継続することで、健康を維持することができます。
連鎖:ある事象や状態が次々と影響し合いながら変化することを指します。例えば、連鎖的な経済変動や連鎖反応といった形で使われます。
継続:ある行動や状態を途切れさせずに続けることを意味します。たとえば、毎日の運動や学習を継続することで、習慣化や成長につながります。
順序:物事の進行や配置が特定の順番であることを表します。連続性がある場合、その順序は重要で、結果や影響が前後関係で変わることがあります。
連結:物や事象が相互に結びつくことを意味します。例えば、ネットワークやシステムにおいて、異なる要素が連結されることで全体の機能が向上します。
持続:時間的にある状態が保たれることを表します。持続的な努力や持続可能な開発といったところで使われる言葉です。
直列:一つの物事が次に続く形の並びを指す言葉です。電気回路や生産ラインなど、直列に配置された要素によって影響を与え合います。
関連:二つの事柄が何らかの形で結びついていることを示します。例えば、連続性のある要素同士が関連していることで、より深い理解が得られます。
連続の対義語・反対語
該当なし