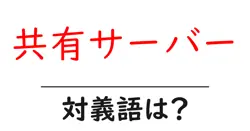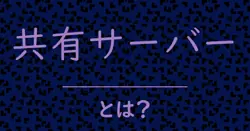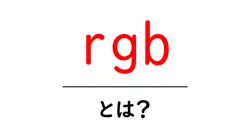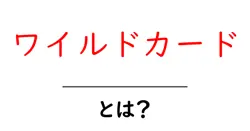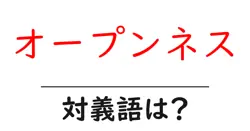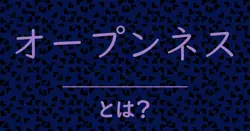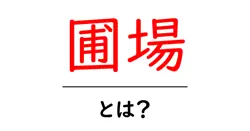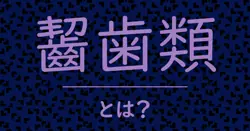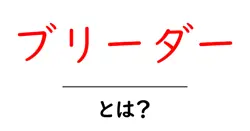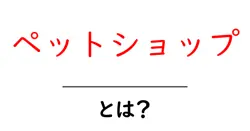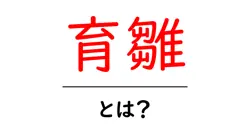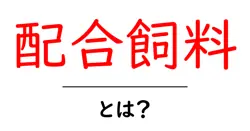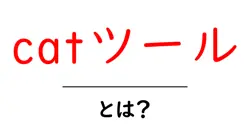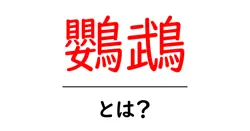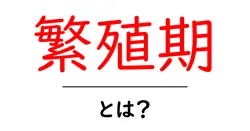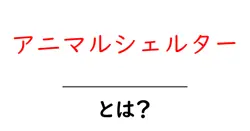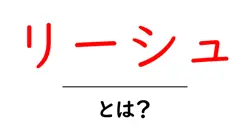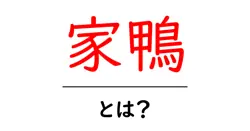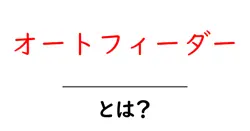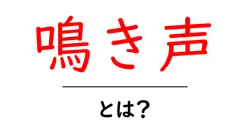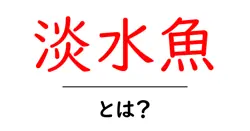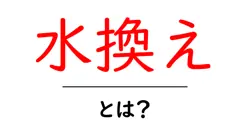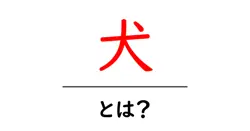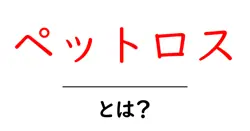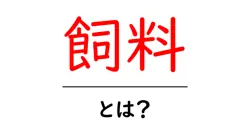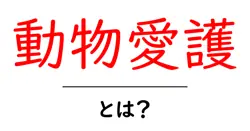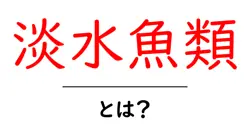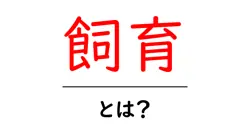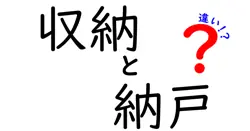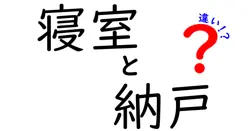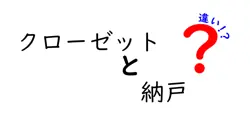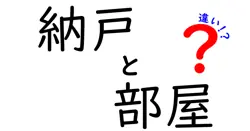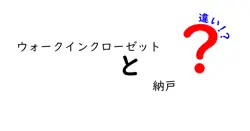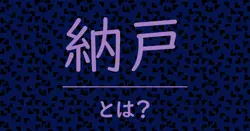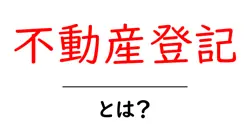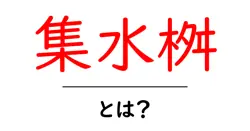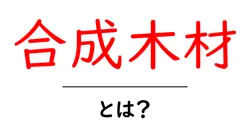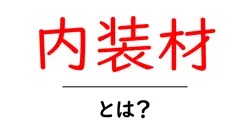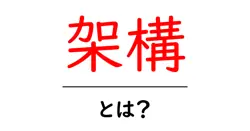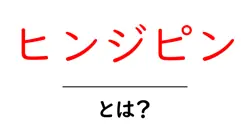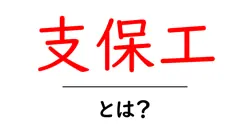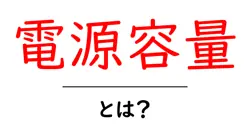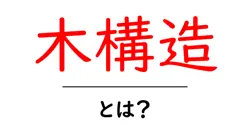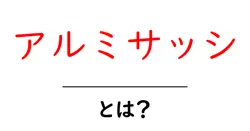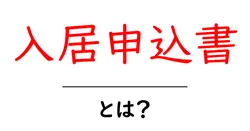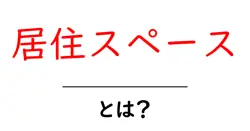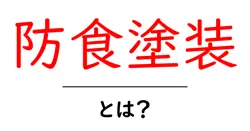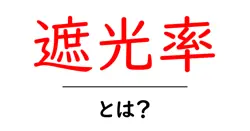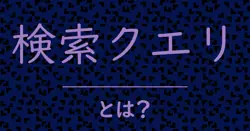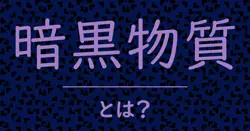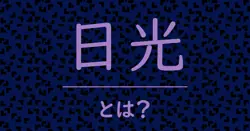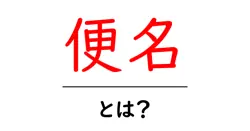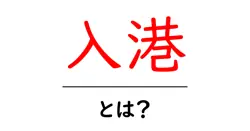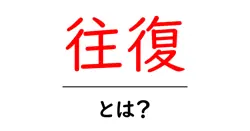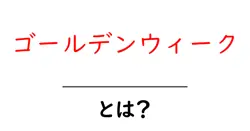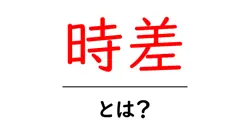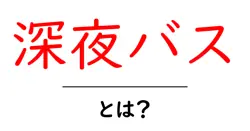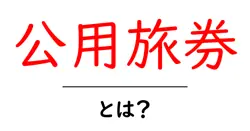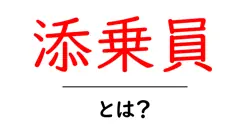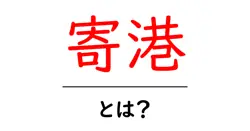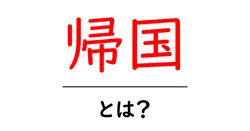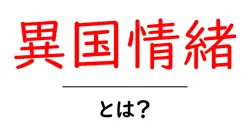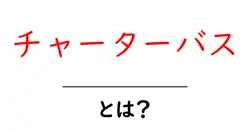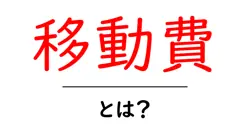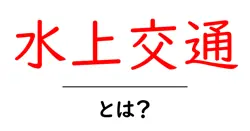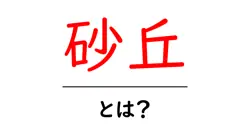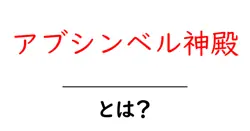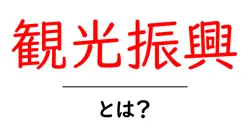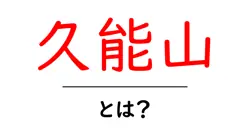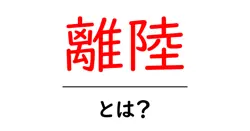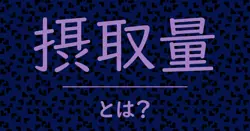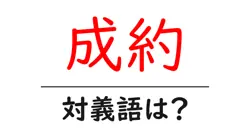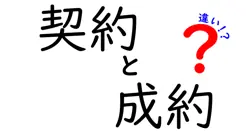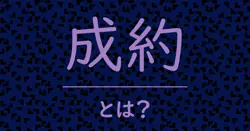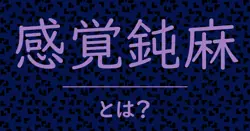インターネットを使っていると、「サーバー」という言葉をよく耳にしますが、今回はその中でも「共有サーバー」について詳しく解説します。
1. 共有サーバーの基本的な説明
共有サーバーとは、複数のユーザーが同じサーバーを利用する方式のことを指します。つまり、一台のサーバー上に何人かのユーザーが自分のウェブサイトやアプリケーションを置くことができるのです。
例えば、あなたが自分のブログを開設したいと思ったとき、共有サーバーを利用すると、他のたくさんの人のブログも同じサーバー上にあるというわけです。
2. 共有サーバーのメリット
共有サーバーには以下のようなメリットがあります:
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 安価な料金 | サーバーの運営費用を多数のユーザーで分担するため、料金が安くなる。 |
| 管理の簡単さ | サーバー管理をプロの業者が行うため、初心者でも扱いやすい。 |
| スケーラビリティ | 必要に応じてプランを変更しやすい。 |
3. 共有サーバーのデメリット
もちろん、メリットだけでなくデメリットもあります。以下の点には注意が必要です:
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| パフォーマンスの制約 | 他のユーザーがサーバーを利用することで、自分のサイトが遅くなることがある。 |
| セキュリティのリスク | 同じサーバー内でマルウェアが蔓延する可能性がある。 |
| カスタマイズの制限 | サーバーの設定に制限があるため、自由にカスタマイズできない。 |
4. どんな人におすすめ?
共有サーバーは、以下のような人におすすめです:
- 初めてウェブサイトを作成する人
- コストを抑えたい人
- 手軽にブログやホームページを開設したい人
まとめ
共有サーバーは、手軽にウェブサイトを運営できる便利な方法ですが、注意すべき点もあります。自分のニーズに合わせて選ぶことが大切です。これからウェブサイトを立ち上げたいと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
FTP:ファイル転送プロトコルの略で、ネットワーク経由でファイルを送受信するためのルール。共有サーバーにデータをアップロードする際によく使われる。
ドメイン:インターネット上の住所のようなもので、ウェブサイトにアクセスするための名前。共有サーバーを利用する場合にも、ドメイン名が必要。
ホスティング:ウェブサイトをインターネット上で公開するためのサービス。共有サーバーはホスティングの一種で、複数のユーザーが一つのサーバーを共有して利用する。
バックアップ:データのコピーを作成して保存すること。共有サーバーでは、何らかのトラブルに備えて、定期的にバックアップを取ることが重要。
SSL証明書:ウェブサイトの通信を安全にするための証明書。共有サーバーを使用する場合でも、SSLを導入することでセキュリティを高めることができる。
CMS:コンテンツ管理システムの略で、ウェブサイトのコンテンツを簡単に作成・管理できるツール。共有サーバーではWordPressなどのCMSが多く利用される。
帯域幅:インターネット接続の速度やデータ転送能力を示す指標。共有サーバーでは帯域幅が限られているため、他のユーザーとリソースを共有する必要がある。
サポート:技術的な問題が発生した際に提供される支援サービス。共有サーバーを利用する場合、サポート体制が重要なポイントとなる。
スケーラビリティ:システムの拡張性を指します。共有サーバーは小規模なサイトに便利ですが、トラフィックが増えた際にはアップグレードが求められることがある。
セキュリティ:データや情報を守るための対策。共有サーバーは複数のユーザーが同じサーバーを使用するため、セキュリティ対策が特に重要。
共用サーバー:複数のユーザーが同じサーバーを利用する型のサーバーで、コストを抑えられるのが特徴です。
マルチユーザーサーバー:一つのサーバーを複数のユーザーが同時に利用することを指し、リソースを分け合って使用します。
ホスティングサーバー:ウェブサイトやアプリケーションをインターネット上に公開するために提供されるサーバーの一種で、共有型のものがあります。
共用ホスティング:複数のウェブサイトが同じサーバー上に置かれ、管理されるサービスで、初めてのユーザーにおすすめです。
シェアードサーバー:英語の「shared server」をそのまま日本語にしたもので、ユーザーがサーバーのリソースを共有する形式です。
ホスティング:インターネット上でウェブサイトやアプリケーションを公開するためのサーバー環境を提供するサービスのこと。
VPS:Virtual Private Serverの略で、物理サーバーを仮想的に分割し、独立したサーバーとして利用できる環境のこと。共有サーバーとは異なり、リソースが他のユーザーによって影響を受けづらい。
ドメイン:インターネット上の住所にあたるもので、ウェブサイトにアクセスするために必要な名前。例: example.com.
SSL証明書:ウェブサイトとブラウザ間の通信を暗号化するための証明書。安全性を高め、ユーザーのプライバシーを保護する。
データベース:データを整理して保存し、効率よく取り出せるように管理するためのシステムのこと。一般的にウェブサイトでは、訪問者のデータやコンテンツを保存するために使用される。
バックアップ:データの損失に備えて、コピーを保存すること。定期的なバックアップを行うことが重要。
カスタマーサポート:ホスティングサービスやサーバーに関して質問や問題がある場合のサポートサービス。ライブチャットや電話、メールなどで受けられる。
帯域幅:インターネット接続の速度や容量を示すもので、特定の時間内にどれだけのデータを転送できるかを示す。高い帯域幅があれば、より多くのユーザーが同時にアクセスしてもスムーズに動作する。
スケーラビリティ:システムがユーザー数やトラフィックの増加に応じて容易に拡張できる能力のこと。共有サーバーの場合、リソースに制限があるため、急激なトラフィック増加に対しては限界がある。
リソース制限:共有サーバーでは複数のユーザーが同じサーバーを使うため、CPUやメモリ、ストレージなどのリソースに制限が設けられていることが一般的。
共有サーバーの対義語・反対語
ファイル共有サーバーとは?NASとの違いやクラウド化について解説
【徹底解説】社内サーバー(NAS)とは?クラウドとの違いとメリット
ファイル共有サーバーの特徴とは?NASとの違いやクラウド化の利点
ファイルサーバーとは? NASとの違いや活用法をわかりやすく解説