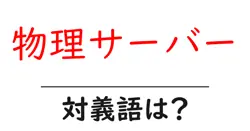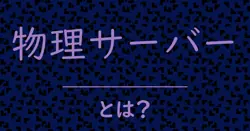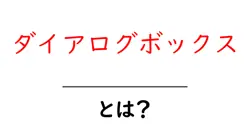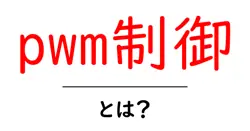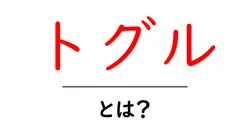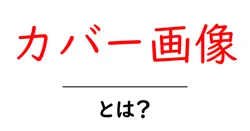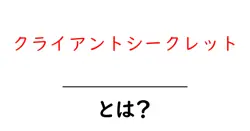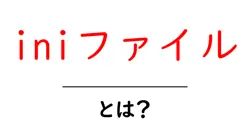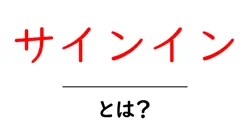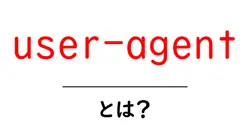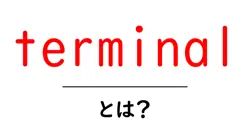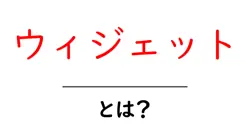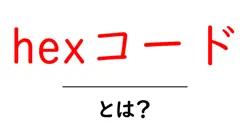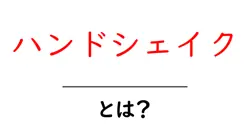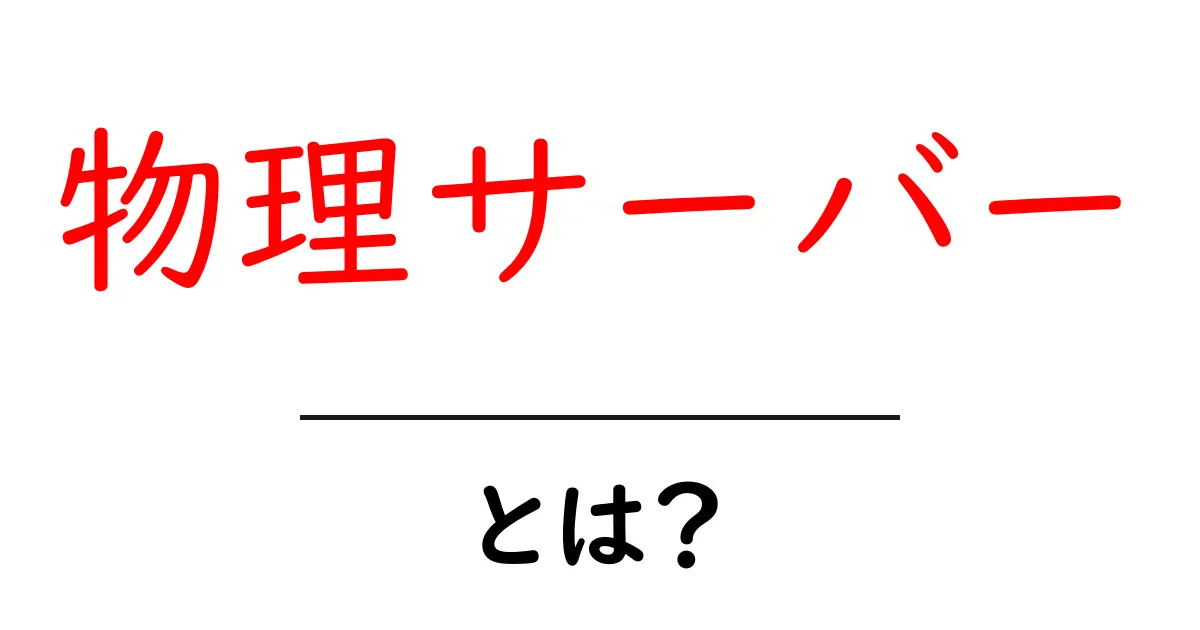
物理サーバーとは?初心者でもわかる基本解説!
私たちが普段使っているコンピュータやスマートフォンには、データを保存したり、アプリを動かしたりするための「サーバー」があります。ここでいう「物理サーバー」というのは、具体的に形があるサーバーのことを指します。
物理サーバーの基本
物理サーバーは、実際のハードウェア設備として存在していて、データセンターや企業のオフィスの中に置かれています。このサーバーは通常、特定のタスクを処理するために設計されていて、コンピュータの部品が組み合わさって作られています。
物理サーバーの特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 専用性 | 特定の目的に合わせて設計されている。 |
| 性能 | 高性能なプロセッサと大容量メモリを搭載することが多い。 |
| 管理の難しさ | 物理的に存在するため、メンテナンスやアップグレードが必要。 |
| コスト | 初期投資が高いが、長期的には安定した性能を提供。 |
物理サーバーと仮想サーバーの違い
物理サーバーとよく比較されるのが「仮想サーバー」です。仮想サーバーは、1台の物理サーバーの中で複数のサーバー環境を作る技術です。こちらは物理的な存在がなく、データ上でサーバーが作られるため、柔軟に使うことができるのがメリットです。
どんなところで使われているの?
物理サーバーは、例えばインターネットの大規模なサービスや企業のウェブサイト、データベース管理など、さまざまな場面で使用されています。これらのサービスが安定して動くためには、しっかりとした物理サーバーが必要不可欠です。
まとめると、物理サーバーは実際のハードウェアとして存在するサーバーで、特定の目的に高性能で設計されています。運用にはコストと手間がかかりますが、長期的には信頼性の高いサービスを提供します。
クラウドサーバー:インターネットを通じて利用されるリモートサーバーのこと。物理サーバーとは異なり、物理的なハードウェアに依存せず、スケーラブルなリソースを提供します。
仮想化:1つの物理サーバー上で複数の仮想サーバーを作成し、それぞれ独立して運用できる技術。物理サーバーの資源を効率的に利用できます。
データセンター:多くのサーバーやネットワーク機器を収容するための専門施設。物理サーバーはここに設置されることが一般的です。
ホスティング:サーバーを他者に提供し、ウェブサイトやアプリケーションを運営するためのサービス。物理サーバーもホスティングの一環として利用されます。
バックアップ:データの安全を確保するために、物理サーバーに保存されている情報を別の場所にコピーすること。万が一の際にデータを復元するために重要です。
ネットワーク:複数のコンピュータやサーバーが相互に接続され、情報を交換するためのシステム。物理サーバーはネットワークの一部として機能します。
セキュリティ:物理サーバーを保護するための技術や対策。データが不正にアクセスされることを防ぐために重要です。
パフォーマンス:サーバーが処理できる速度や効率を示す指標。物理サーバーはその設計によってパフォーマンスが異なります。
OS(オペレーティングシステム):サーバーのハードウェアを管理し、ソフトウェアを動かすための基盤。物理サーバーにインストールされ、さまざまなアプリケーションが使用されます。
メンテナンス:物理サーバーの動作を正常に保つための定期的な作業。これにはハードウェアのチェックやソフトウェアの更新が含まれます。
物理マシン:物理サーバーが実際のハードウェアを指すときの別の表現。仮想マシンではなく、実際の機器として運用されるサーバーを指す。
専用サーバー:一つのサーバーを特定の目的にのみ使用するシステムを指す。専用にリソースを割り当てるため、パフォーマンスが高い。
ホストサーバー:他のシステムやサービスを運営するために利用されるサーバー。物理サーバーがホスティングとして機能することもある。
サーバーハードウェア:サーバーとして機能するために設計された物理的な装置。物理サーバーはこのサーバーハードウェアによって動作する。
オンプレミスサーバー:企業などが自社で所有し、物理的に設置されているサーバー。クラウドと対比されることが多い。
一体型サーバー:すべての機能が一つの筐体にまとめられたサーバー。物理サーバーの一種で、使用が簡単。
仮想サーバー:物理サーバー上に複数の仮想環境を構築したもの。リソースを効率的に使え、必要に応じてサーバーの数を増やしたり減らしたりできる。
クラウドサーバー:インターネットを介して利用できるサーバー。物理サーバーを使用しているが、ユーザーはその管理を意識せずに利用でき、スケーラビリティに優れる。
データセンター:物理サーバーやネットワーク機器を集中管理する施設。高いセキュリティ、冷却、電力供給を備えた環境で、企業がサーバーを設置することが多い。
サーバー管理:物理サーバーやその上で動作するアプリケーションの運用、監視、メンテナンスのこと。専門知識が求められる役割であり、安定したサービス提供に欠かせない。
ホスティング:ウェブサイトやアプリケーションを物理サーバー上で運営するサービスのこと。個人や企業が自分のサイトを公開する際に利用する。
ベアメタルサーバー:他のサーバーや仮想化技術を使用せず、直接利用する物理サーバーのこと。高パフォーマンスが求められるアプリケーションに適している。
OS(オペレーティングシステム):物理サーバーの上で動作する基本ソフトウェア。ハードウェアとアプリケーションの橋渡しをし、サーバーの管理や操作を行うために不可欠である。
バックアップ:物理サーバー上のデータを保護するために行うデータの複製作成プロセス。障害時のデータロスを防ぐ重要な手段である。
冗長化:物理サーバーの信頼性を高めるために、複数のサーバーを使って同じサービスを提供すること。障害発生時にもサービスが継続できるようにする技術。
リモート管理:物理サーバーを物理的に現場にいなくても管理・メンテナンスする方法。リモートデスクトップやSSH(Secure Shell)などを使用することが一般的。
物理サーバーの対義語・反対語
仮想サーバーとは? 物理との違いやメリット・デメリットを解説
5分でわかる「サーバー」とは 意味や用途を解説 | クラウドエース株式会社