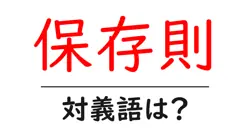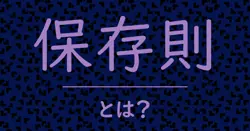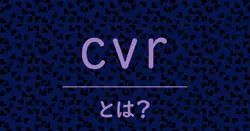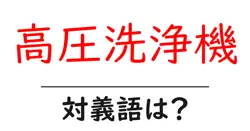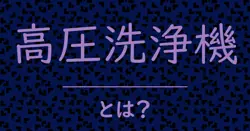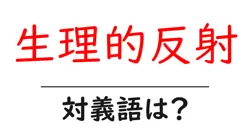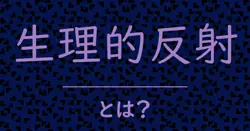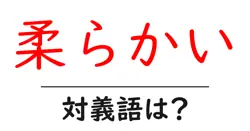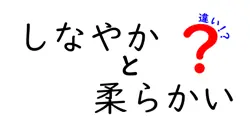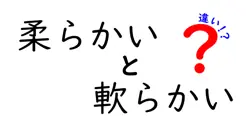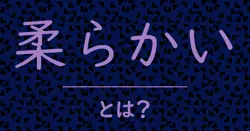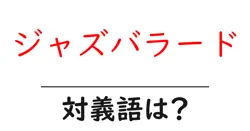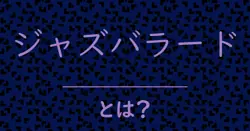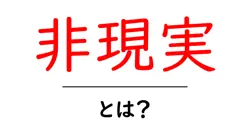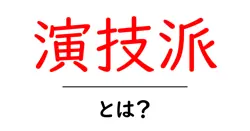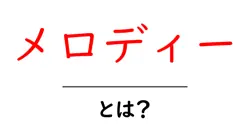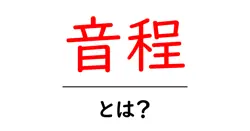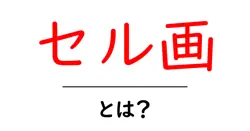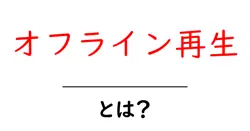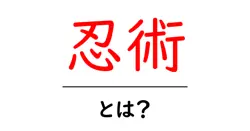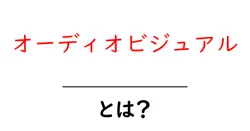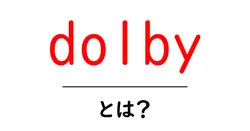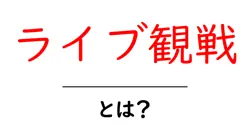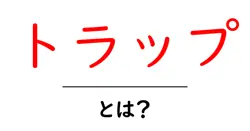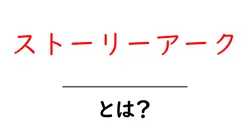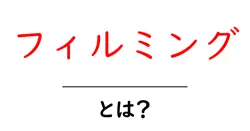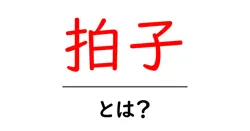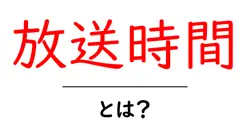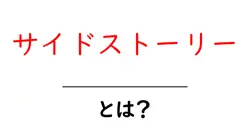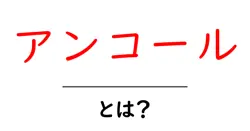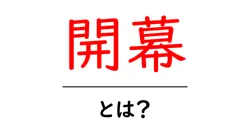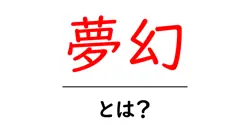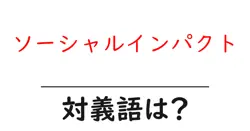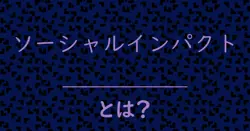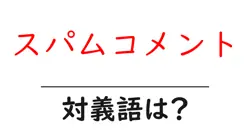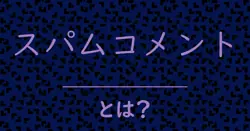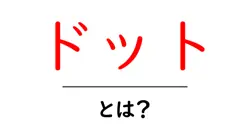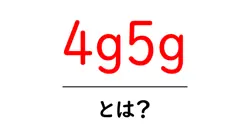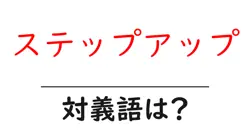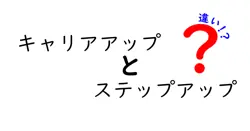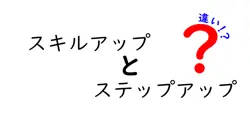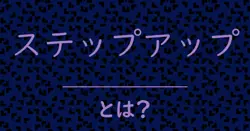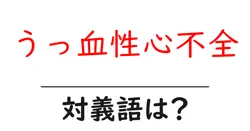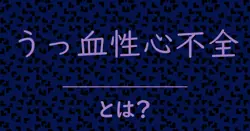「保存則」とは?
「保存則」という言葉は、物理学でよく聞かれる基本的な概念の一つです。保存則は、特定の物理量が時間が経過しても変わらない、つまり保存されることを示す法則のことを指します。物理学には、エネルギー、質量、運動量など、いくつかの種類の保存則があります。それぞれの保存則が築く土台は、自然の法則における大事な部分です。
エネルギーの保存則
まずは「エネルギーの保存則」について考えてみましょう。この法則によれば、閉じた系におけるエネルギーの総量は時間が経っても変わりません。例えば、自転車に乗ると、私たちがペダルをこいでエネルギーを加えることで、自転車が進むのです。このとき、自転車が進むために必要なエネルギーは、私たちがこいだエネルギーによって供給されます。しかし、自転車が止まると、ペダルをこいで加えたエネルギーはすべて消えたわけではありません。摩擦や空気抵抗によってエネルギーが散逸しますが、エネルギーは絶対にゼロになることはありません。このようにエネルギーは変換され続けます。
運動量の保存則
次に「運動量の保存則」です。運動量は物体の質量と速度を掛けたもので、物体が持つ運動の「量」を示します。この法則によると、外部から力が加わらない場合、運動量は常に一定に保たれています。例えば、二つのボールが衝突する場合、衝突前の運動量と衝突後の運動量の合計は同じになります。衝突によってボールの速度が変わりますが、運動量は保存されているというわけです。
質量の保存則
さらに「質量の保存則」についても知っておきましょう。これは、化学反応などにおいて、反応前の物質の質量の総和と反応後の物質の質量の総和が等しいという法則です。この法則は、化学実験や反応式を書くときに非常に重要になります。たとえば、酸とアルカリが反応して塩ができるとき、その反応に使われた酸とアルカリの質量は反応後に出来た塩の質量と合計として等しくなります。
なぜ「保存則」が大事なのか?
保存則は自然界の基本的な性質を示すものです。物理学や化学の多くの現象を理解するための基盤となります。また、さまざまな現象が保存則によって説明できるため、科学を学ぶ上でとても大切な概念です。
日常生活の中でも保存則は見られます。たとえば、自転車や車が走るとき、疲れないようなエネルギーの使い方をするために、私たちはいろいろな方法を考えるようになります。エネルギーを上手に利用することは、保存則を理解することでより容易になります。
| 保存則の種類 | 内容 |
|---|---|
<div id="kyoukigo" class="box28">保存則の共起語
エネルギー:物体やシステムが持つ仕事をする能力のこと。保存則ではエネルギーが創造されず、消失しないことを指します。
運動量:物体の運動の「量」を表すもので、質量と速度の積のこと。運動量保存則では、外部から力を受けない限り、全体の運動量は一定であることを示します。
質量:物質の量を表すもので、物体が持つ重さのこと。質量保存則では、反応や変化があっても質量は変わらないとされます。
力:物体に加えられる影響のこと。力が作用すると物体の状態が変わりますが、保存則は基本的に力と時間の関係についての考え方です。
化学反応:物質が別の物質に変わる過程のこと。化学反応においても質量保存則が適用されます。反応前後で質量の総和は変わりません。
熱エネルギー:物質の温度に関連するエネルギーで、運動エネルギーの一種。保存則においては、エネルギーの形が変わっても、総エネルギー量は一定です。
閉じた系:外部と物質やエネルギーの出入りがない系のこと。保存則は主に閉じた系で成り立ちます。
仕事:力が物体を動かすことによって行われるエネルギーの転送。保存則では、エネルギーの変換が行われる際に仕事も影響します。
熱力学:エネルギーとその変換を扱う物理学の一分野で、保存則は重要な基本原則の一つです。
div><div id="douigo" class="box26">保存則の同意語保存法則:物理学や化学で使われる概念で、エネルギーや質量が時間とともに変化しないという法則を指します。
エネルギー保存の法則:エネルギーは創造されず消失することもないという原理で、閉じた系においては全エネルギーの合計が一定であることを示しています。
質量保存の法則:化学反応などにおいて、反応物の質量の合計は生成物の質量の合計と等しいことを示す法則です。
保存定理:特定の物理的量が時間に対して変化しないことを示す理論的な原則のことです。
保存則則:物理学や数学における一般的な原則を指し、特定の条件下で一定の性質が保たれることを示します。
div><div id="kanrenword" class="box28">保存則の関連ワードエネルギー保存の法則:エネルギーはどんな形態に変換されても、全体のエネルギーの総和は変わらないという法則。例えば、運動エネルギーやポテンシャルエネルギーが相互に変化しても、エネルギーの総量は一定です。
運動量保存の法則:外部からの力が作用しない場合、物体の運動量は時間とともに一定であるという法則。運動量は物体の質量と速度の積で表されます。
質量保存の法則:化学反応などの過程で、反応前後の物質の質量の総和は変わらないという法則。たとえば、物質が合成されたり分解されたりしても、全体の質量は常に同じです。
熱力学第一法則:エネルギーの保存に関する法則で、エネルギーは創造も消失もしないというもの。システムに加えられた熱は、内部エネルギーの増加や仕事をするために使われる。
閉じた系:エネルギーや物質の出入りがない系のこと。保存則が適用される対象として、閉じた系は非常に重要です。
保存則の応用:保存則は物理学だけでなく、工学や化学などさまざまな分野で応用されています。例えばエネルギー効率の改善や、化学反応の設計などに使用されます。
非保存力:摩擦力や空気抵抗のように、エネルギーを失わせる力のこと。保存則が成り立たない場合の要因になります。
力学的エネルギー:運動エネルギーと位置エネルギーの合計を指します。力学的エネルギー保存の法則が適用される条件下では、このエネルギーは一定です。
エネルギー変換:エネルギーの形態が一つの形から別の形に変わる過程です。例えば、化学エネルギーが熱エネルギーに変わることなどが含まれます.
div>