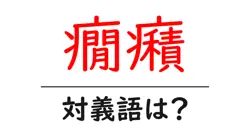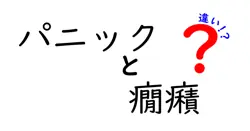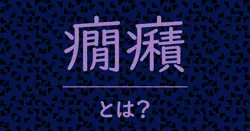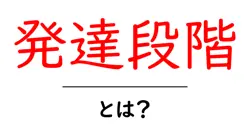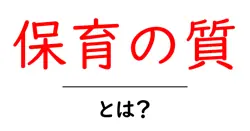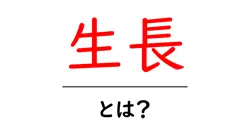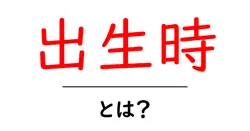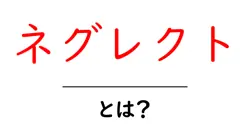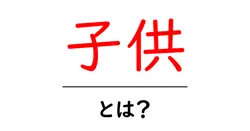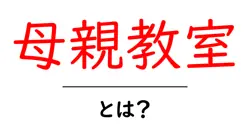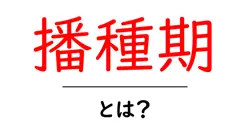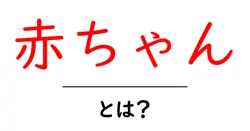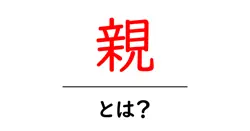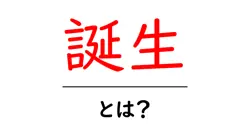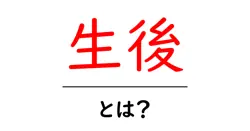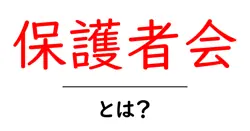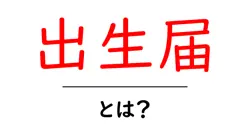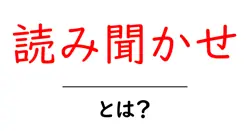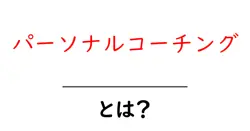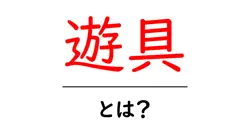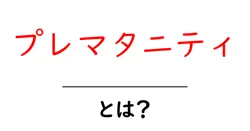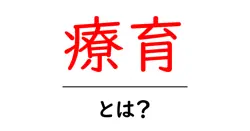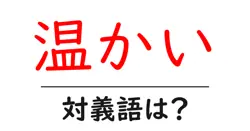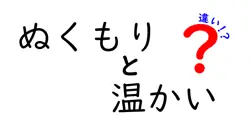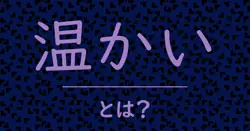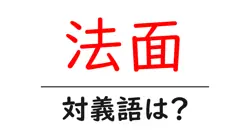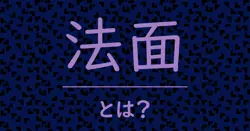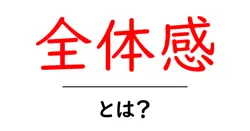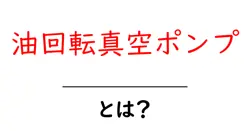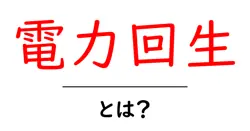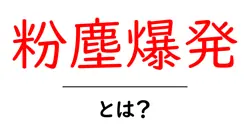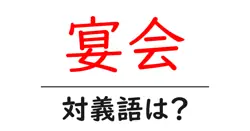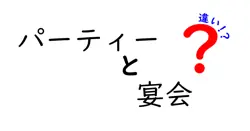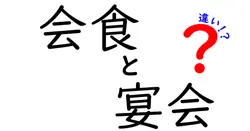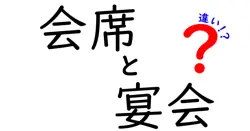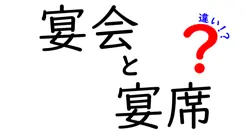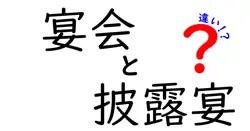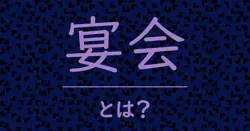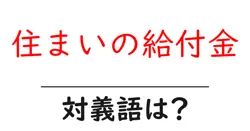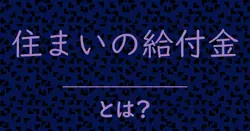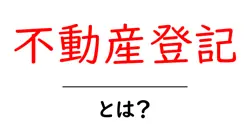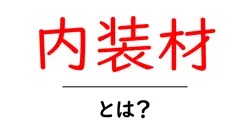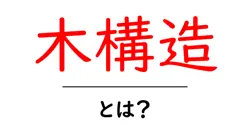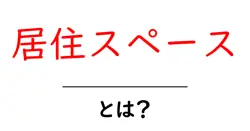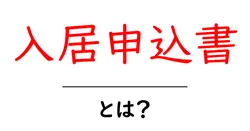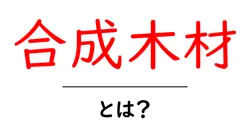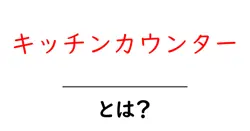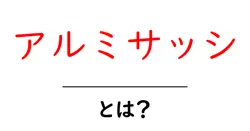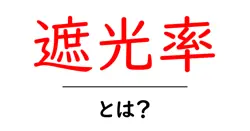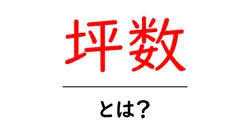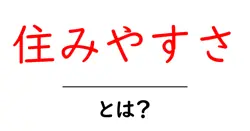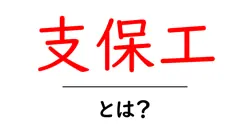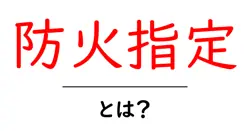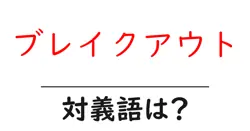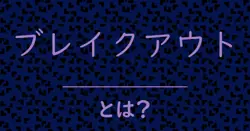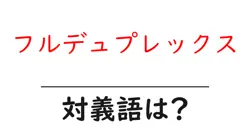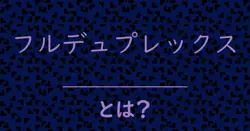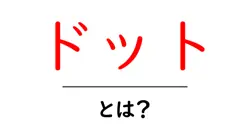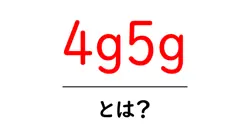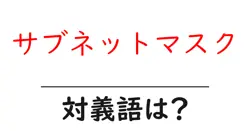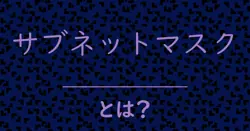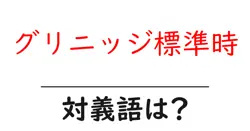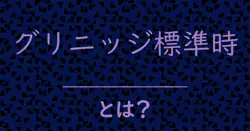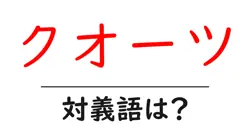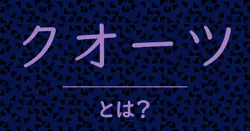癇癪とは?
「癇癪」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。癇癪(かんしゃく)とは、主に子供が急に怒り出したり、泣いたりするような感情の爆発のことを言います。大人でも時々イライラして感情を抑えきれないことがありますが、癇癪は特に子供に多く見られる現象です。
癇癪の原因
癇癪にはいくつかの原因があります。主なものを以下の
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 疲れ | 子供が疲れていると、感情をコントロールするのが難しくなります。 |
| ストレス | 環境の変化や新しいことに対する不安などがストレスとなり、癇癪を引き起こすことがあります。 |
| 欲求不満 | 欲しいものが手に入らない時や、してほしいことができない時に癇癪が起きやすいです。 |
癇癪の症状
癇癪を起こすと、以下のような行動が見られます:
- 大声で泣く
- 床に転がる
- 物を投げる
- 親や周りに対する攻撃的な態度
癇癪をどう対処するか
癇癪を起こした時の対処法は、いくつかあります。まずは、子供の気持ちを理解し、共感することが大切です。次に、次のポイントを参考にしてください。
- 冷静になる:自分自身も感情が高ぶるかもしれませんが、冷静に対応することが重要です。
- 安全な環境を提供する:周りの物を片付け、危険なものがないようにします。
- 気持ちを落ち着ける:深呼吸をしたり、少し時間を置いて冷静になるのを助けます。
- 話を聞く:癇癪が収まったら、何が原因だったのか、一緒に考えてあげましょう。
まとめ
癇癪は通常、子供に見られる感情の反応ですが、大人でもその傾向があることがあります。癇癪が起きる原因や対処法を知っておくことで、より良いコミュニケーションができるようになります。子供が癇癪を起こした時は、優しく寄り添い、理解し合うことで、信頼関係を築いたり、感情をうまくコントロールできるようにサポートしてあげましょう。
1歳 癇癪 とは:1歳の子どもが癇癪を起こすことはよくあります。癇癪とは、思い通りにならないことに対する激しい感情の発露で、泣いたり、怒ったりすることが含まれます。1歳児は言葉がまだ未熟なので、自分の気持ちをうまく伝えられず、フラストレーションが溜まることが多いのです。例えば、おもちゃを奪われたり、お気に入りのものが取られてしまったりすると、癇癪を起こしやすくなります。そうした場合、まずは子どもに寄り添ってあげることが大切です。抱きしめたり、声をかけたりすることで、安心感を与えることができます。また、癇癪の原因を見つけることも重要です。子どもが何に不満を持っているのかを理解し、その場面での対応を考えることが役立ちます。時には、原因を取り除いてあげることが最も効果的です。癇癪は成長過程の一部であり、すべての子どもが経験することですので、焦らずに対処していきましょう。
2歳 癇癪 とは:子どもが2歳になると、癇癪を起こすことが増えます。癇癪とは、感情のコントロールができずに泣いたり暴れたりすることを指します。この時期の子どもは、まだ言葉も十分に話せず、自分の気持ちを上手に表現できません。そのため、思い通りにならないときに感情が爆発することがあります。例えば、おもちゃを取られたり、遊びたいのに時間が来てしまったりすると、つい癇癪を起こしてしまいます。親としては心配になりますが、これは成長の一部であり、多くの子どもが経験することです。対処法としては、まずは落ち着いて子どもの気持ちを受け止めてあげることが大切です。そして、できるだけ具体的に説明し、子どもが次に何をすべきか考えさせることが効果的です。また、怒るのではなく、子どもがどのように気持ちを伝えたらいいか、一緒に考えるのも良いでしょう。癇癪が成長と共に減っていくことも多いため、辛抱強く見守ることも重要です。
かんしゃく とは:「かんしゃく」とは、突然に激しい怒りやイライラを感じることを指します。特に小さなお子さんがかんしゃくを起こすことが多いですが、大人でも感じることがあります。例えば、思い通りに物事が進まなかったり、ストレスがたまったりすると、かんしゃくを起こすことがあります。それは、「こうしたいのに、できない!」という気持ちから来ていることが多いです。かんしゃくを起こしてしまうと、自分をコントロールできずに周りに迷惑をかけてしまいます。では、どうしたらいいのでしょうか?まず、深呼吸をして落ち着くことが大切です。次に、何が原因でかんしゃくを起こしたのか考えてみましょう。そして、大切なのは話をすることです。友達や家族に不満を伝えることで、気持ちが楽になります。かんしゃくは誰にでもある感情ですが、上手にコントロールすることで、より良い人間関係を築くことができるのです。
完尺 とは:「完尺」という言葉は、映像制作やテレビ業界でよく使われる専門用語です。簡単に言うと、完尺とは「完成した映像の長さ」を意味します。例えば、テレビ番組や映画がすべて完成したとき、その作品が何分何秒の長さになったのかが完尺です。映像制作では、時間を正確に計ることがとても大切です。なぜなら、放送時間や上映時間に合わせて作品を作る必要があるからです。もし、番組や映画が予定の時間を超えてしまうと、他の番組や映画のスケジュールに影響が出てしまいます。また、完尺を調整することで、作品の流れをスムーズにしたり、視聴者が飽きずに楽しめるようにすることも大事です。たとえば、長すぎるシーンはカットしたり、逆に短すぎるシーンは追加したりします。このように、「完尺」は映像制作の根幹を支える重要な概念なのです。映像に興味がある人は、ぜひこの用語を覚えておいてください。
官爵 とは:官爵(かんじゃく)とは、国家や官庁で働く人々の地位や階級を示す称号のことを指します。日本の歴史では、大昔から官嶋(かんじょう)という制度があり、さまざまな役職に応じた爵位が存在していました。官爵には、特定の権限や義務、さらには社会的な地位がついてきます。 例えば、平安時代には貴族が持つ官爵が非常に重要視され、地位の高い人ほど影響力が強かったのです。これにより、社会の中での役割分担がなされ、時には政治的な権力争いの要因となることもありました。 一般的に「爵」という言葉は、階級を示すものですが、官爵は特に政府の機関に関連するものであり、政治や行政に深く関わっています。現代では、官爵はあまり使われなくなりましたが、当時の制度や文化を理解するためには重要なキーワードとなります。官爵について知ることで、日本の歴史や文化がどのように形成されてきたのかを考える手助けになるでしょう。
癇癪 とは 大人:「癇癪」とは、感情が高ぶって激しい怒りや興奮を示す状態のことを指します。子どもに多いイメージがありますが、実は大人にもこの症状は現れることがあります。大人の癇癪は、ストレスや疲れ、不安などが原因で起こることが多いです。例えば、仕事や人間関係での悩みが積み重なり、ちょっとしたことで爆発してしまうことがあります。大人の場合、癇癪を起こすと周りの人たちに迷惑をかけたり、信頼を失ってしまうこともあります。そこで、癇癪を防ぐ方法や対処法が大事です。まずは、ストレスをため込まないために自分の趣味を楽しむことや、友達と話をすることが効果的です。また、癇癪が起きそうなときは、深呼吸をすることで気持ちを落ち着けることができます。自分の感情をコントロールし、建設的なコミュニケーションができるように心がけることで、癇癪を防ぐことができるでしょう。
癇癪 とは 意味:「癇癪」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?癇癪とは、特に子供が突然に感情を爆発させることを指します。例えば、おもちゃを取り上げられた時に大声を出して怒ったり、泣いたりすることが癇癪の一例です。このような行為は、感情をうまくコントロールできないために起こります。 癇癪の原因は、その時の状況や子供の性格によって異なります。欲しいものが手に入らなかったり、自分の思い通りに事が進まないときに、癇癪が起こることが多いです。また、疲れている時やお腹がすいている時も癇癪が生じやすくなります。 癇癪をしっかりと理解し、対処することは大切です。まずは、子供の気持ちを理解し、共感することが大切です。冷静に話を聞いてあげることで、少しずつ気持ちを落ち着ける手助けができます。そして、場合によっては、環境を整えてあげることで癇癪を防ぐこともできます。たとえば、事前にお腹を満たしておくことや、子供が安心できる場所を作ることが効果的です。癇癪が起こったときは、感情に任せて叱るのではなく、落ち着くまで待ってあげることもポイントです。
赤ちゃん 癇癪 とは:赤ちゃんの癇癪とは、赤ちゃんが急に泣き出したり、機嫌を損ねたりすることを指します。これは、赤ちゃんがまだ言葉で自分の気持ちを表現できないために起こることが多いです。赤ちゃんは自分の欲求が満たされないと、フラストレーションを感じます。そのため、癇癪を起こすことで、親に注意を引こうとします。癇癪は成長過程の一部であり、多くの赤ちゃんが経験することです。では、どのように対処すれば良いのでしょうか?まずは赤ちゃんの気持ちを理解することが大切です。何が原因で泣いているのかを探り、抱っこしたり、おしゃぶりを与えたりして、安心させてあげましょう。また、環境を変えて気を散らすのも効果的です。例えば、外に出かけたり、遊び道具を出したりすると、赤ちゃんの気分が変わることがあります。重要なのは、赤ちゃんが癇癪を起こすことは、成長の一環であることを理解し、根気よく接することです。親も時には大変ですが、優しく接してあげると、赤ちゃんも安心して気持ちを表現できるようになります。
感情:心の動きや反応のこと。癇癪は強い感情の表れである。
怒り:不快な出来事に対して感じる強い感情。癇癪はしばしば怒りから引き起こされる。
ストレス:精神的または肉体的な圧力。癇癪はストレスが原因で発生することが多い。
無力感:自分の力が及ばないと感じること。癇癪は無力感から起こることもある。
衝動:思い立った瞬間に行動したくなる欲求。癇癪は衝動的な行動として現れることがある。
コミュニケーション:人と人の情報のやり取り。癇癪が起きると、効果的なコミュニケーションが難しくなる。
子供:幼い年齢の人。癇癪は特に子供に見られる行動であり、成長段階の一部。
発達:成長または進展すること。子供の癇癪は通常、発達の過程で見られる。
対処法:問題や状況に対応する方法。癇癪を和らげるための対処法が必要である。
心理:心の動きや機能に関する学問。癇癪は心理的な要因にも深く関与している。
怒り:感情の高まりや強い不快感を表す状態で、癇癪とも関連があります。
かんしゃく:癇癪と同じ意味で使われる言葉で、特に子供が突然興奮してしまう様子を指すことが多いです。
短気:ちょっとしたことでイライラする性格を指し、癇癪を起こしやすい人のことを意味します。
ヒステリー:過度の感情的反応を示す状態で、時には癇癪と同じような状況を引き起こすことがあります。
興奮:強い感情の変化や高ぶりを表現する言葉で、癇癪は興奮の一種と考えられます。
感情:感情は、人間が経験する様々な心理状態のことです。これには喜び、怒り、悲しみ、驚きなどが含まれ、癇癪も一つの感情の表れです。
ストレス:ストレスは、外部からの圧力や要求に対する心理的または身体的な反応です。感情のコントロールが難しいとき、ストレスが原因で癇癪を起こすことがあります。
自己制御:自己制御とは、自分の感情や行動を抑えたりコントロールしたりする能力です。良好な自己制御があれば、癇癪を防ぐことができます。
発達障害:発達障害は、脳の発達に影響を及ぼし、コミュニケーションや行動に特有の課題を持つ状態を指します。癇癪はしばしば発達障害の子どもに見られる行動の一つです。
情緒:情緒は、感情の一部で、特に気分や感情の安定性に関連しています。情緒が不安定なとき、癇癪が起こりやすくなります。
社会的スキル:社会的スキルは、他者と効果的にコミュニケーションしたり、関係を築いたりするための能力です。癇癪が多い場合、社会的スキルに悩みを抱えていることがあります。
行動療法:行動療法は、特定の行動を変更するための心理療法の一種です。癇癪を軽減するための方法として、行動療法が役立つことがあります。
感情表現:感情表現とは、自分の感情や思いを言葉や行動で表すことです。適切な感情表現ができると、癇癪が起こる頻度が減ることがあります。
トリガー:トリガーは、特定の感情や反応を引き起こすきっかけのことです。癇癪を引き起こすすぐる場合、トリガーを把握することが重要です。
フラストレーション:フラストレーションは、何かを達成できないことで感じる苛立ちや焦りの感情です。癇癪の多くは、フラストレーションから生じることがあります。