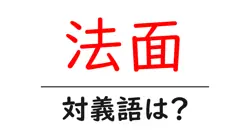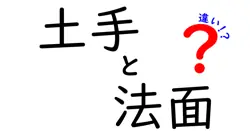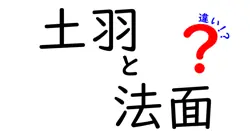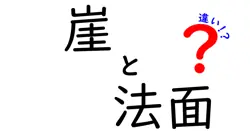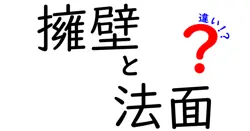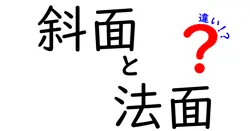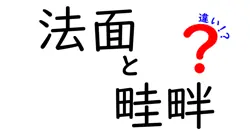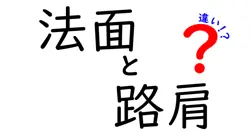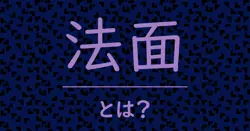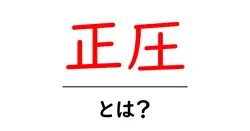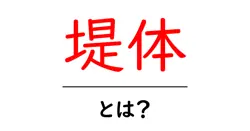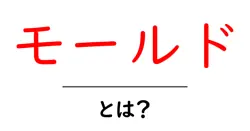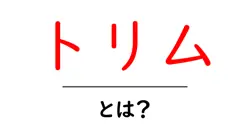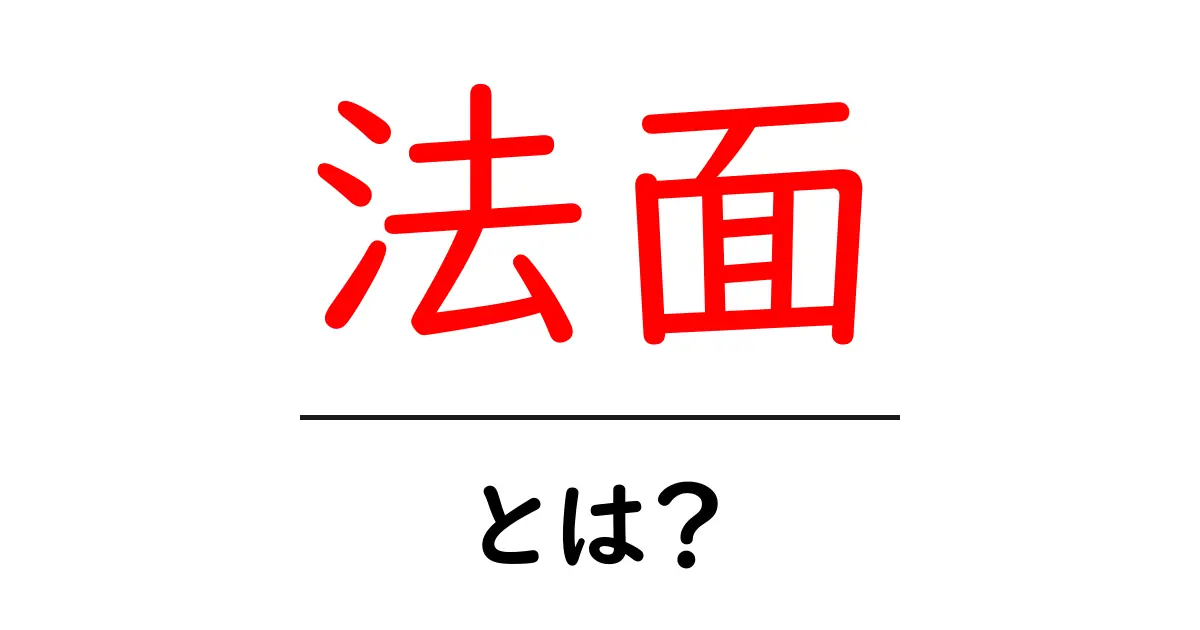
法面とは?
法面(のりめん)とは、土や岩などが斜めに傾斜した部分を指します。道路や鉄道、ダムなどの建設において、地形の変化に対応するために作られることが多いです。法面は自然にできることもありますが、人の手によって整えられる場合もあります。
法面の種類
法面には、主に三つのタイプがあります。まずはそれぞれの特徴を見てみましょう。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自然の法面 | 雨や風による侵食でできた地形。 |
| 人工法面 | 道路などを作る際に人が整えた斜面。 |
| コンクリート法面 | 崩れにくくするためにコンクリートで固めた斜面。 |
法面の重要性
法面は、崩れを防ぐために非常に重要です。特に雨が降った時や地震があった時に、土が滑りやすくなります。法面がしっかりしていると、土地や建物の安全性が高まります。
法面の管理
法面の管理には、定期的に点検することが必要です。崩れやすい部分には、植樹や水の流れを変える工夫を施します。また、冬の雪の影響を受けやすい地域では、雪の重みで崩れないように注意する必要があります。
もし法面が崩れてしまうと、周りの道路や建物にも影響が出ます。地元の人々の生活にも影響を与えるため、しっかりとした管理が求められます。
法面についての理解を深めることで、安全に暮らすための基礎知識を身につけることができます。自然と共存し、安全を守るための大切な知識です。
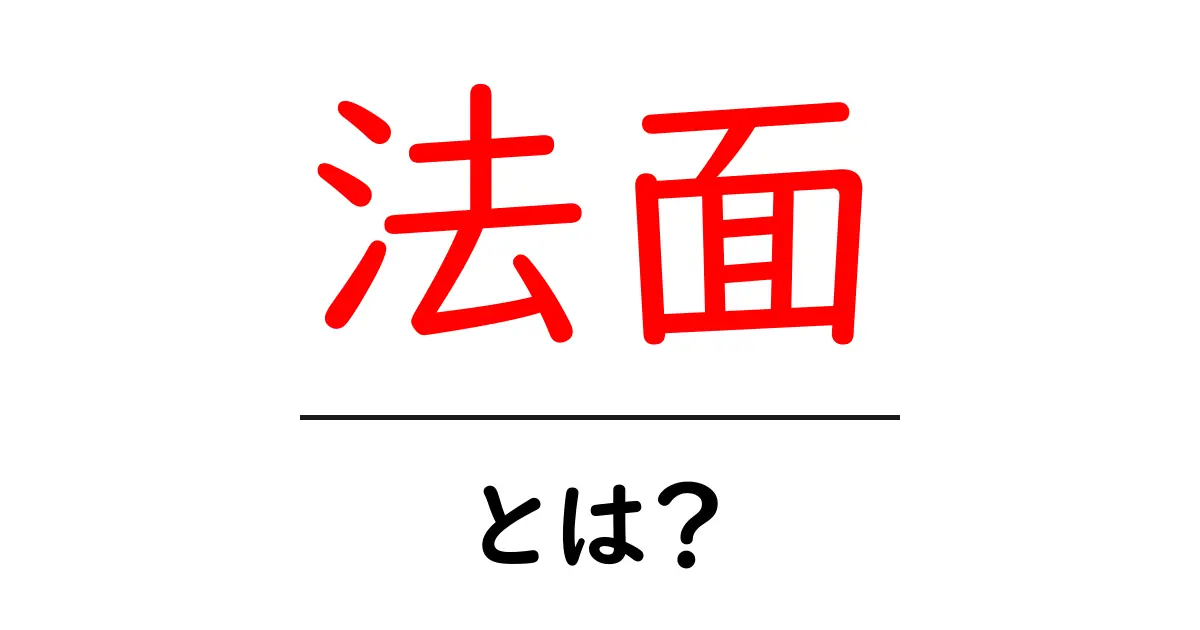 archives/9451">併せて解説!">
archives/9451">併せて解説!">土砂:土や砂などの地質材料のこと。法面では、土砂の安定性が重要となります。
斜面:地面が傾斜を持つ部分。法面は斜面のことを指し、土木工事や造成において重要です。
防 erosion:土壌や石材が風や水の強力な作用で削られないようにする対策。この処置は法面の保護に役立ちます。
法面安定:法面の崩壊を防ぐための技術や対策のことで、特に斜面が急な場所では重要です。
重力:物体が地球に引き寄せられる力。法面の設計や安全性はこの重力を考慮して行われます。
植生:植物の生育状態のこと。法面の安定化のために草木を植えることがよくあります。
土留め:土が崩れないように支えるための構造物。法面の安全性向上に貢献します。
測量:土地や地形を正確に測る行為。法面の設計や施工には正確な測量が必要です。
切土:地面を削って平坦にする工事。このプロセスで法面が形成されることがあります。
盛土:土を盛り上げて高くする工事。法面の構築には切土と盛土の技術が重要です。
斜面:傾斜がついている面のこと。定義としては地表面が傾斜している部分を指します。
土留め:土が崩れないように支える構造物。法面を安定させるために使われることが多いです。
地山:自然に存在する土や岩などの地面のこと。法面は地山の一部として形成されます。
土砂:土や砂の混ざった物質のこと。法面では土砂の流出を防ぐことが重要です。
擁壁:土砂などを支えるために設けられた壁。法面の保護にも使われます。
傾斜地:傾いた地面を指し、法面がこの一部として機能することがあります。
外壁:建物の外側を構成する面で、法面と相互作用する場合があります。
archives/19121">法面工:法面を保護・整備するための建設工事のこと。土砂崩れや erosion を防ぐための方法が含まれる。
法面保護:法面の劣化を防ぐために行う措置で、コンクリートや植生などを用いて安定させること。
土砂災害:土砂の崩落や流出によって引き起こされる災害。法面の管理が重要。
法面照査:法面の状態を調べ、適正な保護がなされているかを確認すること。
archives/14234">法面緑化:法面に植物を植えて、土壌の侵食を防ぎ、景観を改善すること。
archives/14067">急傾斜地:角度が急な山や崖のこと。法面の工事や保護が特に必要。
erosion (侵食):風や水によって土や岩が削られる現象。法面では特に注意が必要。
archives/17803">工事管理:archives/19121">法面工事の進行状況や品質を監督・管理するプロセス。
archives/12921">地すべり:土や岩が重力によって滑り落ちる現象。法面の安定性に関わる。
安全指針:法面の工事や管理に関する安全基準を記載した指針。
法面測量:法面の形状や状態を測定し、計画を立てるための作業。