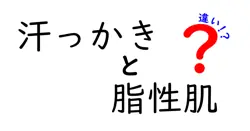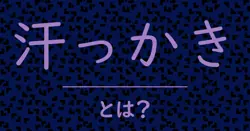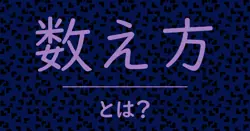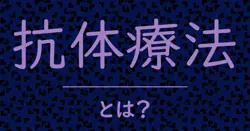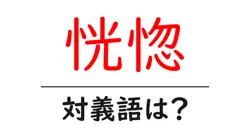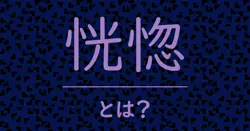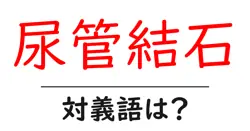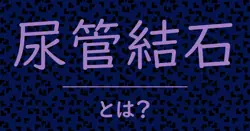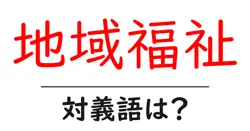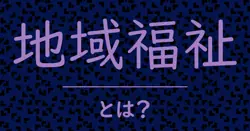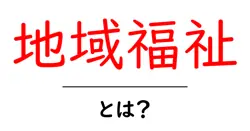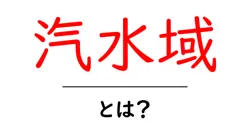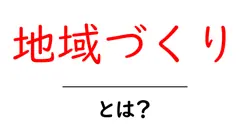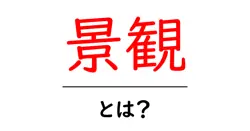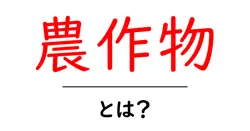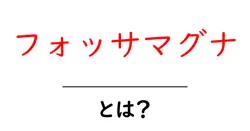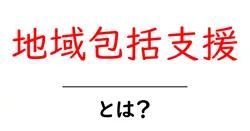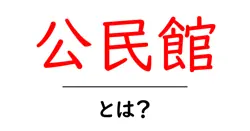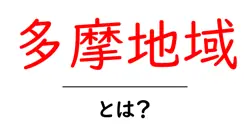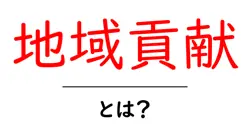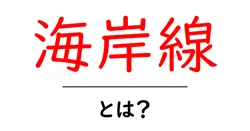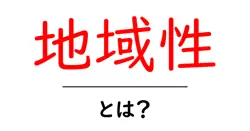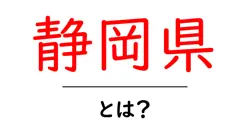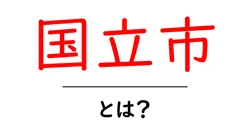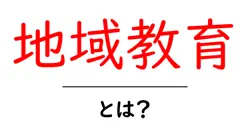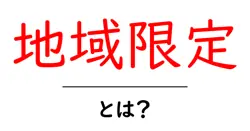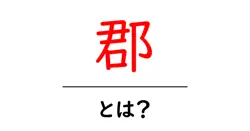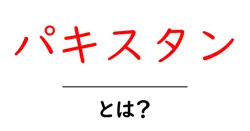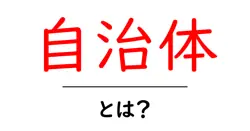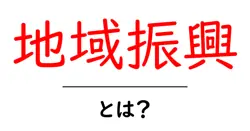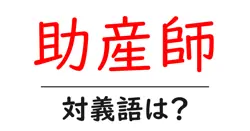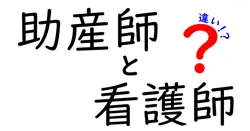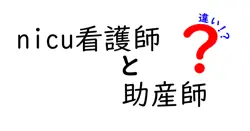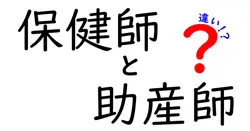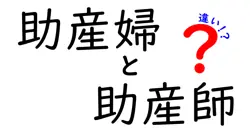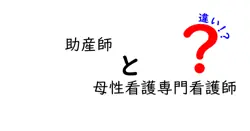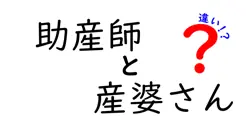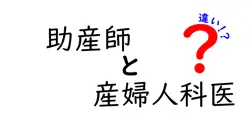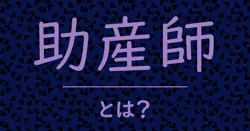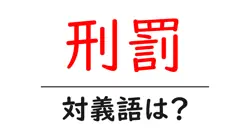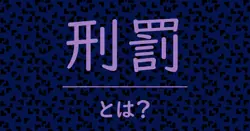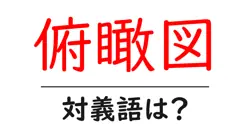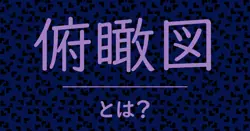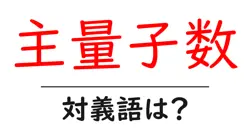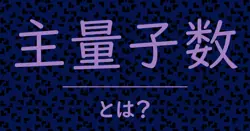<div id="honbun">数え方とは?
数え方は、物を数えるときの方法やルールのことを指します。日本語には特有の数え方がいくつもあります。物の種類や形によって、使う助数詞(助詞)が異なることが多いです。例えば、冊(さつ)で本を数えたり、個(こ)でリンゴを数えたりします。
数え方の基本
日本語の数え方には以下のような基本があります。
d>| 物の種類 | 使用する助数詞 | 例 |
|---|
d>dy>d>本などの冊d>d>冊(さつ)d>d>3冊の本d>
d>リンゴなどの果物d>d>個(こ)d>d>5個のリンゴd>
d>人d>d>人(にん)d>d>4人の友達d>
d>車などの台d>d>台(だい)d>d>2台の車d>
dy>
数え方の変化
物によっては、数え方が変わるだけでなく、数によっても形が変化することがあります。例えば、「一冊」「二冊」のように、助数詞の頭に数字がつくときの形が異なります。これを「数詞の活用」と呼びます。
活用の例
以下の表に助数詞の例を示します。
d>| 数字 | 助数詞(冊) | 助数詞(個) |
|---|
d>dy>d>1d>d>一冊d>d>1個d>
d>2d>d>二冊d>d>2個d>
d>3d>d>三冊d>d>3個d>
d>4d>d>四冊d>d>4個d>
dy>
日常生活での数え方
例えば、買い物の際には、ジュースやパンを数えるときにそれぞれの数え方を使います。買うものが多いと、数え方を間違えないように気をつけなければなりません。
数え方を正しく使うことは、日本語を使う上で非常に重要です。助数詞や数詞の使い方に気をつけて、自然に会話や文章に取り入れていきましょう。日常生活の中でも、数え方を学ぶことで、よりスムーズにコミュニケーションが取れるようになります。
div>
<div id="saj" class="box28">数え方のサジェストワード解説周年 とは 数え方:「周年」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?周年は、ある出来事が起こった日からの経過年数を数えるための言葉です。たとえば、会社の設立日や結婚記念日など、何か特別なことがお祝いされる時に、その年数を数えて周年を祝います。基本的には、初めての年を1周年と数え、その後、2年目を2周年、3年目を3周年といったふうに、1年ごとに数えていくのが一般的です。注意したいのは、1周年は最初の出来事が起こった「1年後」のお祝いということです。たとえば、2020年に会社が設立された場合、2021年が1周年、2022年が2周年と数えます。でも、1周年を迎えた時点で、会社はすでに1年経っているのだから、何かお祝いしたい!と思う人もいるかもしれませんね。でも、初心者でもわかりやすく言うと、1周年は最初の1年を祝う、2周年はその次の1年、というふうに数えていくだけなのです。お祝いの方法は特別なパーティーを開いたり、記念品を用意したりと様々です。周年を祝うことで、その出来事をより大切に思う気持ちを実感できるのではないでしょうか。
従業員 とは 数え方:従業員という言葉は、ある会社や組織で働いている人々のことを指します。でも、一体どうやってその数を数えるのでしょうか?まず、従業員を数える時には、正社員、契約社員、パートタイムの人など、さまざまな雇用形態があることを理解することが大切です。一般的には、これらすべてを合わせた人数を「従業員数」として表示します。また、企業によっては、特定の役職や部門ごとに従業員を数えることもあります。例えば、営業部には何人、開発部には何人といった具合です。これにより、どの部門が多くの人手を必要としているのかを把握することができます。さらに、企業の規模を比べるためや、採用計画を考える上でも、従業員の正確な数を知ることが重要です。これらを踏まえると、企業の活動をよりスムーズに進めるための計画が立てられるようになります。新しい会社を立ち上げるときや、経営を見直すときに、従業員数を正確に把握することは、成功への第一歩となるのです。
通 とは 数え方:こんにちは!今日は「通」という数え方についてお話しします。「通」は、何かの個数や回数を数えるときに使う言葉です。例えば、「1通」と言った場合、それは1つの手紙や郵便のことを指します。手紙だけでなく、電話や電子メールのやり取りの数を数えるときにも使われます。このように、「通」という単位は「通信」の意味から来ていて、もともとは送りものやメッセージを数えるために使われることが多いのです。では、実際の例を見てみましょう。「昨日、友達に手紙を1通送りました。」という文では、「通」という単位が使われています。また、電話が1通であったり、メールが1通という表現も同じように使えます。このように、私たちの日常生活の中でよく使われる「通」という数え方を知っておくと、よりスムーズにコミュニケーションが取れるようになります。これからも数え方に注目してみてくださいね!
div><div id="kyoukigo" class="box28">数え方の共起語数え方:物の数量を数える方法やルールのこと。日本語には物の種類によって異なる数え方が存在します。
単位:数を表すための基準や量の表し方を指す。例としては、個や本、枚などがある。
助数詞:日本語に特有の数詞に付いて、数えられる物の種類を示す言葉。たとえば、本を数えるときは「冊」、動物を数えるときは「匹」を使う。
数詞:数を表現するための言葉のこと。例として、「一」「二」「三」などの言葉がある。
数える:物の数量を確認する行為のこと。少ない数量から多い数量まで、様々な場面で使うことができる。
集合:特定の条件を満たす物の集まりを指す。数え方はその集合の特徴によって異なる場合がある。
対象物:数える対象となる物のこと。具体承知している対象物によって数え方も変わる。
分け方:物を種類や性質によって分ける方法。分け方によって数える際のルールや助数詞が変わることがある。
数量:物の数量を具体的に示す言葉。数え方や単位と密接に関連している。
カウント:数を数えることを英語で表した用語で、特にカジュアルな言い回しやデータ分析の文脈で使われることが多い。
div><div id="douigo" class="box26">数え方の同意語数え方:物や人を数える際に用いる方法や基準。例えば、1つ、2つ、3つなどの数える単位や、特定のカテゴリーによる数え方を指します。
カウント方法:物や出来事を数える際の具体的な手法や手順。例えば、投票のカウントや、データのカウント方法などがあります。
数量の測定:特定の物の数や量を測る行為。通常、重さや体積といった他の測定単位も含まれますが、数を知るための重要な要素です。
算出方法:数値を計算するための方法論。特定の条件下で数を導き出す際のプロセスや公式を指します。
計数法:数えるための技術や方法。特に、効率的に物を数えるための手法やシステムに関連しています。
数える方式:物の数量を確認するために用いる設定された方法。自然数や特殊な数え方などがあります。
カウントシステム:数をカウントするための組織化された方法や基準。例えば、音楽のビートを数える方法や、特定の規則に基づいた数え方がカテゴライズされます。
div><div id="kanrenword" class="box28">数え方の関連ワード数詞:数を表す言葉のことです。たとえば、「一」、「二」、「三」などが数詞にあたります。
数え方:物や人を数える際の方法のことです。同じ物でも数え方が異なる場合があります。
単位:数え方によって物の数量を示すために使う基準のことです。例えば、「個」、「本」、「枚」などが単位になります。
計量:物の数量や重さを測ることを指します。定義された単位を使って行います。
数量:ある物や人の数や量のことを指します。数え方に基づいて数量を求めることができます。
数える:物の数を正確に把握するために、一つずつ確認する行為のことです。
分類:物や人を特定の基準に基づいてグループ分けすることです。数え方によって、分類の仕方も変わることがあります。
カウント:英語の「count」を取り入れた言葉で、主に数を数える行為を指します。
集計:複数のデータや数を一つにまとめることを指します。特に統計データを扱う際に用いられます。
個数:特定の物の数量を表す言葉です。「個」を使って数えた数量を示します。
div>数え方の対義語・反対語
該当なし
数え方の関連記事
学問の人気記事

1860viws

1596viws

2020viws

1389viws

2104viws

2386viws

1105viws

1332viws

5611viws

2205viws

1322viws

2355viws

1448viws

1455viws

1086viws

4305viws

1937viws

2330viws

2226viws

1468viws