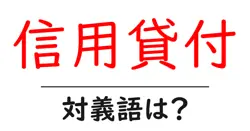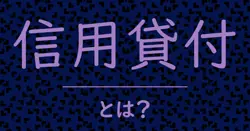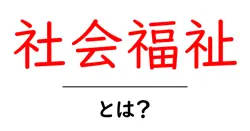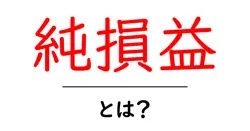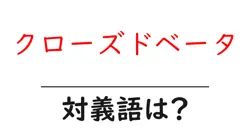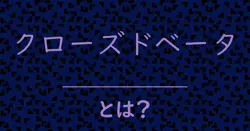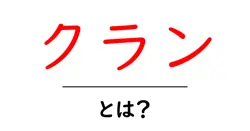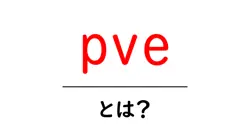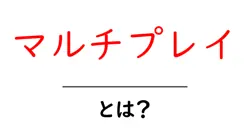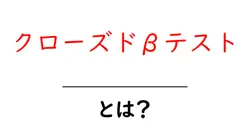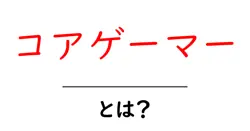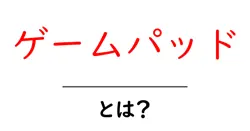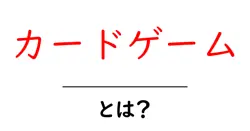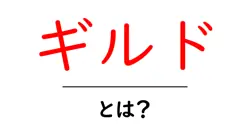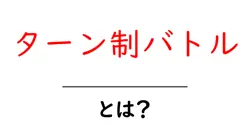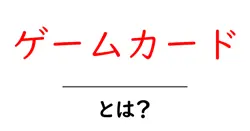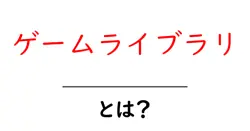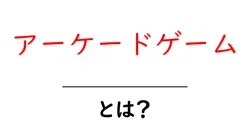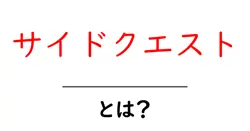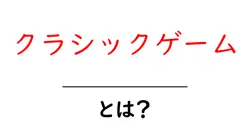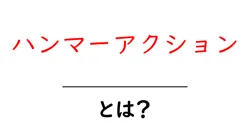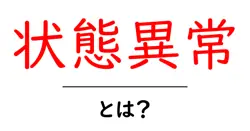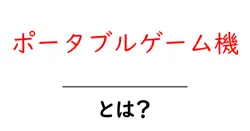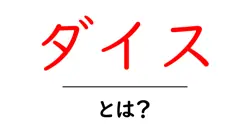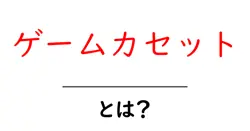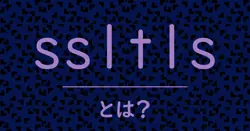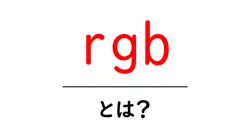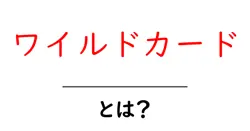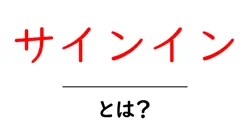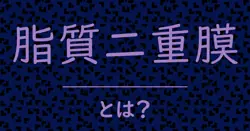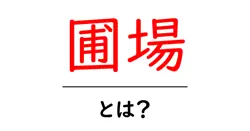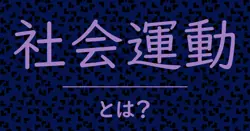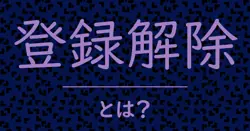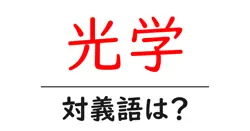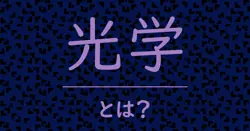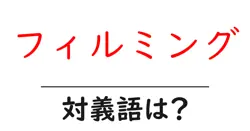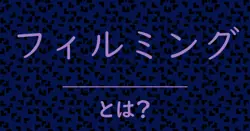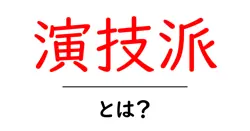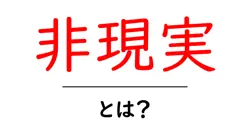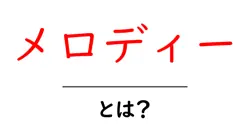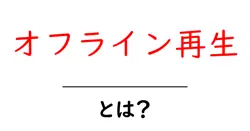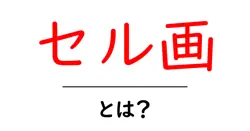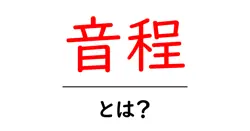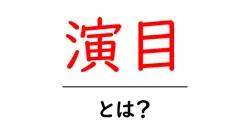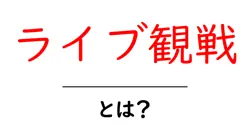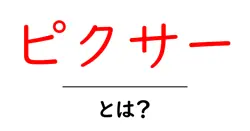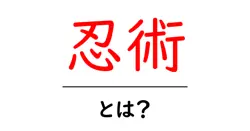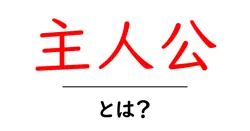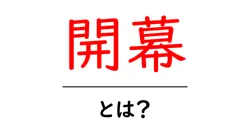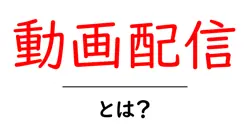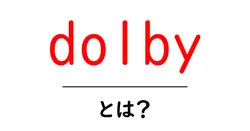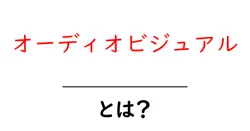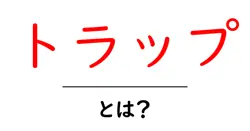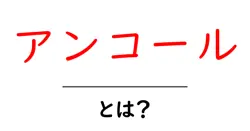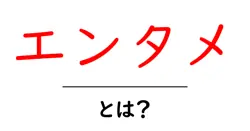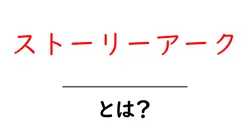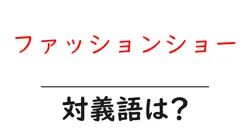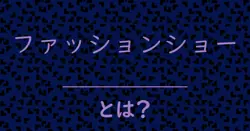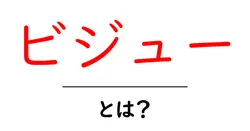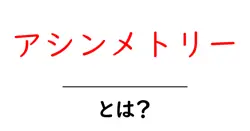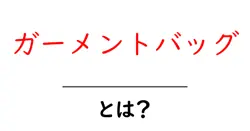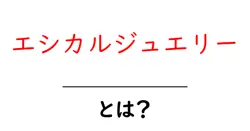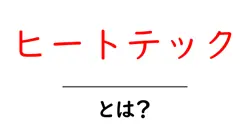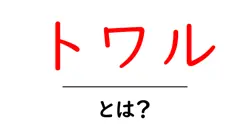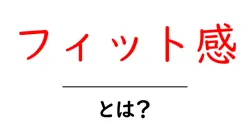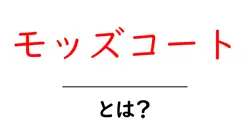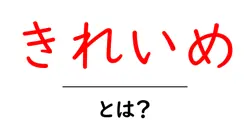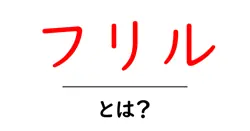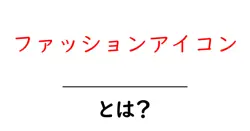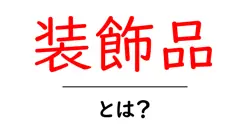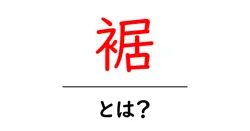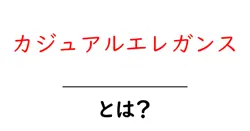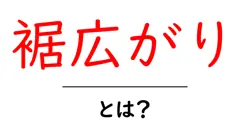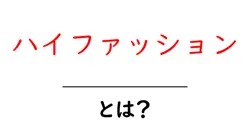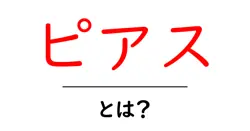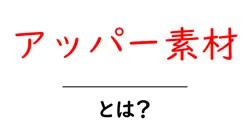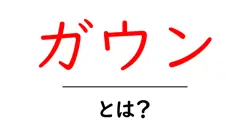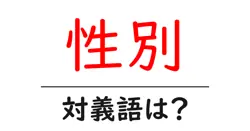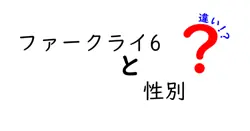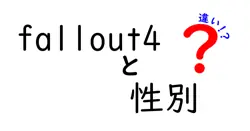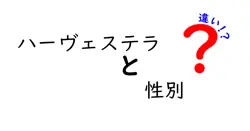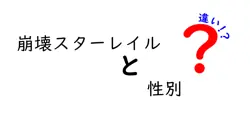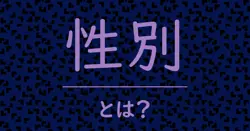<div id="honbun">光学とは?
光学とは、光の性質やその振る舞いを研究する学問です。私たちの周りの世界は光によって見えるため、光学は非常に重要な役割を果たしています。例えば、眼鏡やカメラ、望遠鏡など、光を利用した多くの道具が私たちの生活を便利にしてくれています。
光の性質
光は目に見える電磁波の一部であり、様々な性質を持っています。主な性質は以下の通りです。
dy>| 性質 | 説明 |
|---|
d>反射d>d>光が物体に当たって戻る現象。d>
d>屈折d>d>光が異なる媒質を通るときに進行方向が変わること。d>
d>干渉d>d>複数の光が重なり合って明暗の模様を作ること。d>
d>回折d>d>光が物体の隙間や端を通るときに広がる現象。d>
dy>
光学の応用
光学はさまざまな分野で応用されています。ここでは、いくつかの代表的な例を紹介します。
1. 医療
光学は内視鏡やレーザー治療など、医療分野でも広く使われています。これにより、精密な診断や治療が可能になります。
2. 通信
光ファイバーを利用した通信技術は、高速で大容量のデータ伝送を実現しています。これによってインターネットがより便利になりました。
3. エンターテインメント
映画やゲームなどの映像制作も光学技術が重要です。カメラやプロジェクターは、光を使って映像を表示するため、光学の知識が活かされています。
光学は光の性質を学び、それを応用する学問です。私たちの生活に欠かせない技術がたくさんあり、今後もさらなる発展が期待されます。光学の世界をもっと深く学ぶことで、身の回りのテクノロジーを理解し、楽しむことができるでしょう。
div>
<div id="saj" class="box28">光学のサジェストワード解説doe とは 光学:「DOE」という言葉は光学の分野でよく使われる用語で、特に「Diffractive Optical Element(回折光学素子)」の略称です。これにより光の進み方を変えたり、光の性質を調整したりすることができます。たとえば、私たちがよく知っているレンズやプリズムのように、光を集めたり分けたりする役割を果たすことができるのです。DOEは、一般的なレンズよりも軽量で薄いため、コンパクトなデバイスに使われることが多く、スマートフォンのカメラやプロジェクターに応用されています。この技術はまた、レーザー光を巧妙に制御するためにも利用されており、医療や産業などでも広がりを見せています。将来の技術革新において、DOEはさらに重要な役割を果たすことでしょう。私たちの日常生活でも、変わらぬ進化を続ける光学技術を通じて、新しい便利さや楽しさを体験できる日は近いのです。
mtf とは 光学:MTFとは「Modulation Transfer Function」の略で、光学機器(特にカメラやレンズ)による画像の解像度や鮮明さを評価するための指標です。MTFを使うと、写真がどれだけシャープに写るか、つまり細かい部分がどれだけはっきり見えるかを測ることができます。例えば、風景写真を撮るとき、細かい木の葉や遠くの山の輪郭がきれいに見えるのは、高いMTF値を持つレンズのおかげです。MTFは0から1までの値で表され、1に近いほど高解像度でクリアな画像を得られます。MTFを理解することは、カメラやレンズを選ぶときにとても大切です。これを知ることで、自分にぴったりの機器を見つける手助けになります。例えば、旅行の思い出をきれいに残したいなら、MTFの高いレンズを選ぶことがオススメです。映像制作や写真に興味があるなら、ぜひこのMTFを意識した機器選びをしてみてください。
na とは 光学:光学というのは、光の性質やその運動を研究する学問です。この中で「na」という言葉は、特に「屈折率」を表す際に用いられます。光が異なる物質を通るとき、光の進む速度が変わるため、その物質の屈折率が重要なのです。「na」は「屈折率」の一種で、特にある素材の光の進みやすさを示しています。たとえば、透明なガラスや水の中では、光は空気中よりも遅く進みます。これにより、光が物体を通過する際に、どのように曲がって見えるかが決まるのです。これを利用して、眼鏡やコンタクトレンズなど、視力を補正する製品が作られています。さらに、カメラレンズや望遠鏡などの光学機器にも「na」を活かした設計がされているため、私たちの生活に大きく影響を与えています。このように、「na」が示す光学の原理を理解することは、私たちが日常で使う様々な道具を知るために役立つのです。
od とは 光学:光学(こうがく)というのは、光の性質やその振る舞いを研究する学問のことです。そして、「OD」という言葉は「光学密度(Optical Density)」を表すことが多いです。光学密度は、ある物質が光をどれだけ遮る(さえぎる)かを示す指標です。たとえば、サングラスのレンズやフィルターなど、光を通すものの中には、特定の波長の光を遮るものがあります。これが光学密度によって評価されます。光学密度が高いと、光がより少なく通過し、逆に低いと通過しやすくなります。この特性を理解することは、さまざまな光学機器の設計や使用に役立ちます。さらに、光学密度はカメラや望遠鏡などでも重要な役割を果たしています。だから、ODという言葉を知っておくことは、光を利用する道具の理解を深める手助けになります。光について学ぶことで、自然の現象やテクノロジーに対する理解が広がりますし、科学の世界がもっと面白く見えてきますよ。
カメラ 光学 とは:カメラ光学とは、カメラがどのように光を集め、映像を作るかに関する学問や技術のことを指します。カメラは、レンズを通じて光を収集し、画像センサーにその光を届けることで写真を撮ります。例えば、レンズの形や素材によって、光の集まり方が変わります。このため、レンズの設計が非常に重要です。また、レンズの焦点距離という言葉もよく使われますが、これはレンズから被写体までの距離を示しています。焦点距離が短いレンズは広い範囲を写せ、多くの場合、風景やグループ写真に適しています。逆に焦点距離が長いレンズは遠くのものを大きく写すことができ、野鳥撮影などに向いています。カメラ光学は、写真の品質や表現力に大きな影響を与えるため、カメラを使用する上で知識を深めることはとても大切です。色や明るさの違いも光学的な要素に影響されるため、カメラの選び方にも関わってきます。普段の写真撮影がより楽しくなるために、カメラ光学について知識を増やすことをおすすめします。
プリズム とは 光学:プリズムという言葉を聞いたことがありますか?プリズムは光を使って様々な色に分けることができる不思議な道具です。主に透明な素材、例えばガラスやプラスチックで作られています。プリズムに光が当たると、光はその素材の中を通る際に屈折(くっせつ)と呼ばれる現象を起こします。この屈折により、白色の光が色とりどりに分かれ、虹のような美しい景色が生まれます。よく知られているのは、三角形の形をしたプリズムです。この形が、特に光を分けるのに効果的です。プリズムは光学の実験や、光の性質を学ぶために使われることが多く、科学の授業でもよく登場します。また、プリズムを使って色の組み合わせを学ぶこともでき、アートやデザインの分野でも役立っています。光の不思議さを楽しみながら、プリズムの世界に触れてみましょう!
レンズ 光学 とは:レンズ光学は、光の動きや性質を利用して物を見るための重要な技術です。レンズは光を曲げたり集めたりすることで、像を大きくしたり、ピントを合わせたりします。例えば、カメラや眼鏡、望遠鏡など、私たちの日常生活の中で使われる多くの機器にレンズが使われています。レンズには大きく分けて凸レンズと凹レンズの2種類があります。凸レンズは光を一点に集める性質があり、視力が悪い人が使用する眼鏡やカメラレンズで重要な役割を果たします。一方、凹レンズは光を広がらせる性質があり、近視の人が使う眼鏡に多く見られます。レンズの形状や材料によって、光の屈折率が変わり、さまざまな効果を持たせることができます。このように、レンズと光学は私たちの視覚体験を豊かにするための重要な科学です。理解することで、日常生活の中でレンズに対する関心が深まるでしょう。
div><div id="kyoukigo" class="box28">光学の共起語レンズ:光を屈折させることで、物体の像を明確にするための透明な媒体。カメラや眼鏡に使用される。
光線:光の流れを指し、直線的に進む性質を持つ。光学の基本的な要素として重要。
反射:光が物体の表面に当たったときに、元の方向とは異なる方向に跳ね返る現象。鏡などに見られる。
屈折:光が異なる媒質を通るとき、その速度が変わることで光の進行方向が変わる現象。レンズの動作に関連。
波長:光の波の一周期の長さを示す指標。異なる波長は異なる色として認識される。
フレネルレンズ:軽量で薄型のレンズで、大きな収束力を持つ。ヘッドライトや投影機などに使用される。
偏光:光の波が特定の方向に振動するように整えられた状態。サングラスや写真撮影で使われることが多い。
プリズム:光を屈折させて分光するための透明な固体。白色光を虹色に分解するのに使われる。
顕微鏡:細かい物体の詳細を観察するための光学機器。生物学や材料科学で広く利用される。
光学機器:光を利用して物体を観察または測定するための装置の総称。例えば、カメラや顕微鏡が含まれる。
div><div id="douigo" class="box26">光学の同意語光学:光の性質や光を利用する技術を研究する学問分野のこと。主にレンズや鏡、光の干渉などの現象を扱います。
オプティクス:光学の英語表現で、光の性質やその挙動に関する科学的な研究を指します。
光線学:光の流れやその特性を解析・研究する学問。光が物質と相互作用する仕組みを探究します。
光波学:光を波として理解し、その性質や動きについて研究する分野。特に光の波動性に着目します。
光学技術:光学の知識を応用し、レンズや光学機器などを製作・利用する技術のこと。カメラや顕微鏡などに使われます。
光学療法:光を用いて治療を行う方法。主に皮膚科や眼科で用いられる治療技術です。
光学機器:光の性質を利用して画像を生成・解析するための装置。例としてはカメラ、望遠鏡、顕微鏡などがあります。
光学フィルター:特定の波長の光だけを透過させたり、反射させたりするための手段。撮影や実験で多用されます。
div><div id="kanrenword" class="box28">光学の関連ワード光学レンズ:光を屈折させることによって像を形成するための透明な媒介物。カメラやメガネなどに使われ、光学機器の基本要素です。
反射:光が物体の表面に当たった際に、その方向を変えて跳ね返る現象。鏡や水面で良く見られます。
屈折:光が異なる媒体を通る時に進行方向が変わる現象。例えば、水に入れた鉛筆が曲がって見えるのは屈折によるものです。
干渉:二つ以上の光が重なることによって新たな光の模様や強度が生まれる現象。これにより、色の変化やパターンが見られます。
分光:光を波長ごとに分けることで、特定の色や成分を分析する技術。これにより、化学物質の識別や天体観測が可能になります。
光速:真空中を進む光の速さで、約30万キロメートル毎秒。光学ではこの速度が重要な役割を果たします。
コヒーレンス:光の波が同じ位相関係を保ちながら伝播する性質。レーザー光などが高いコヒーレンスを持っています。
光子:光の最小単位であり、電磁波の粒子モデルに基づく存在。光の伝播やエネルギー伝達に関与します。
光学顕微鏡:光を利用して微細な物体を拡大して観察するための装置。生物学や材料科学などで広く使用されています。
レンズの焦点:光学レンズにおいて、入射光が集まる点のこと。焦点距離により、レンズの特性が決まります。
div>光学の対義語・反対語
光学の関連記事
学問の人気記事

2507viws

2247viws

2669viws

2057viws

1994viws

1743viws

806viws

3014viws

6246viws

2085viws

2709viws

4947viws

2829viws

2085viws

1714viws

1387viws

4303viws

2098viws

1926viws

2958viws