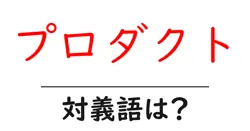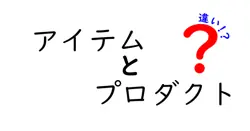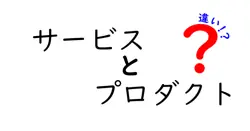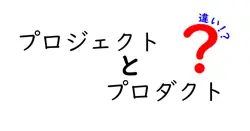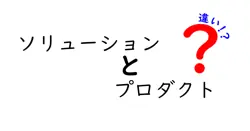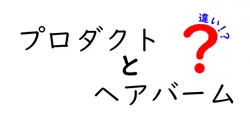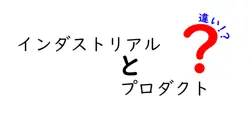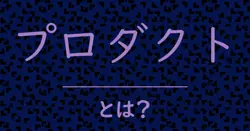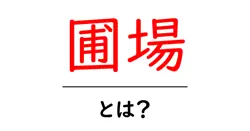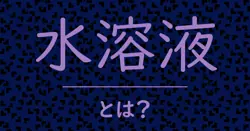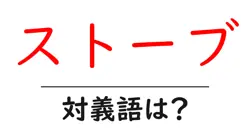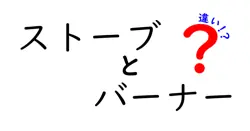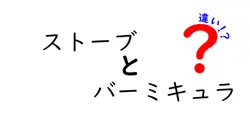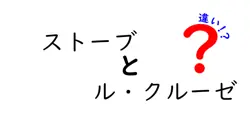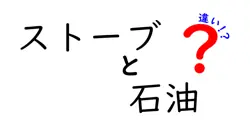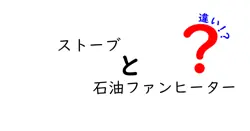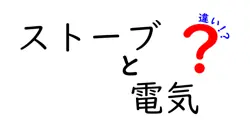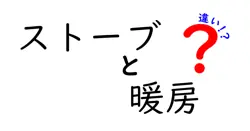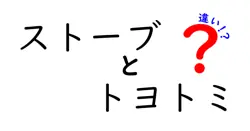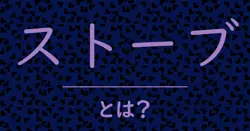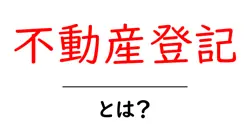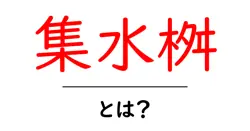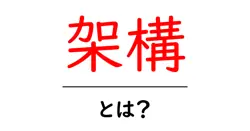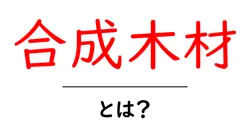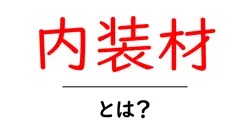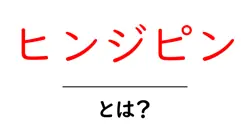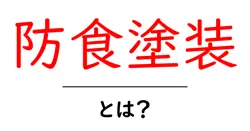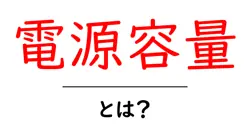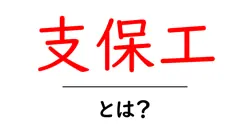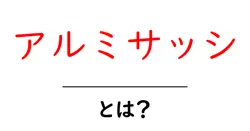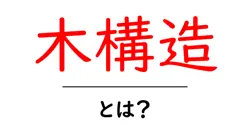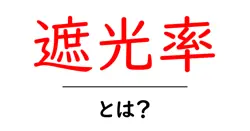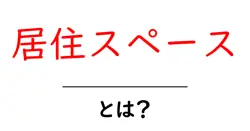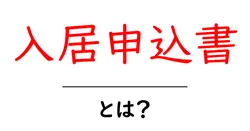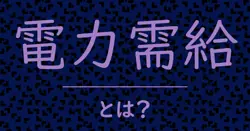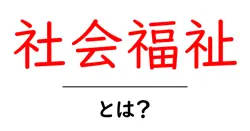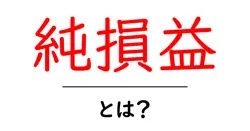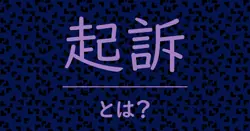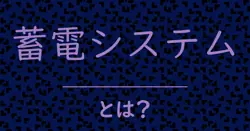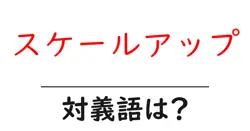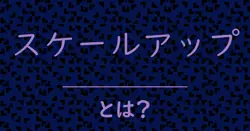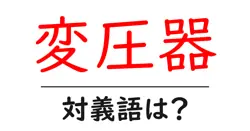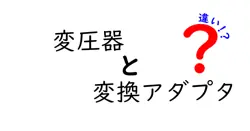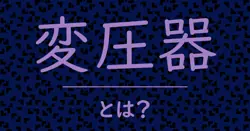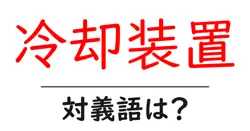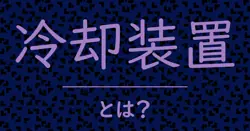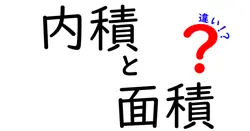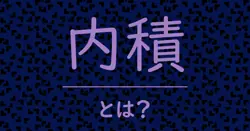プロダクトとは何か?
「プロダクト」とは、私たちが日常的に使っている「商品」や「サービス」を指す言葉です。商業の世界では、製品そのものだけでなく、その製品が提供する価値や経験についても考えます。具体的には、スマートフォンや衣類、食べ物といった具体的な物だけでなく、映画、音楽、ソフトウェアなどもプロダクトに含まれます。
<archives/3918">h3>プロダクトの種類archives/3918">h3>プロダクトは主に以下の3つのカテゴリに分けられます。
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 物理的商品 | スマートフォン、家具、衣類 |
| サービス | 美容院、飲食店、旅行会社 |
| デジタル商品 | アプリ、音楽、映画 |
プロダクトが重要な理由は、私たちの生活に密接に関わっているからです。良いプロダクトは人々の生活を便利にしたり、archives/11796">喜びを与えたりします。archives/8682">また、企業にとっても、自社のプロダクトがどれだけの顧客を惹きつけるかが成功のカギとなります。
プロダクトのデザインとマーケティング
プロダクトの成功は、そのデザインやマーケティングにも大きく依存します。消費者がどのように感じ、どのように使うかを考えた上で、魅力的なデザインや効果的な広告を作ることが重要です。
まとめ
プロダクトとは、単なる商品やサービスではなく、その背後にある価値や体験を含む広い概念です。プロダクトを理解することで、私たちの生活やビジネスの世界をより良くするためのヒントを得られるでしょう。
it ot プロダクト とは:IT(情報技術)とOT(運用技術)は、現代社会において非archives/4123">常に重要な分野です。ITは、コンピュータやarchives/6944">インターネットを利用して情報を処理する技術で、私たちの日常生活に深く関わっています。一方、OTは工場や製造業などで使われる設備やシステムの運用に関連する技術です。 最近では、これら2つの分野が融合した「IT-OT統合」が注目されています。これは、ITがOTのプロダクトに接続されて、リアルタイムでデータを取得したり、archives/128">分析したりすることで、効率的な運用が可能になる技術です。たとえば、工場のロボットがarchives/6944">インターネットを通じてデータを送信し、その情報をITでarchives/128">分析してarchives/2645">工程を最適化することが挙げられます。 このように、ITとOTのプロダクトは、それぞれの良いところを活かしながら、より良い社会を築いていく手助けをしています。技術が進化する中で、私たちもこの新しい世界を理解し、活用していくことが大切です。
プロダクト id とは:プロダクト ID(プロダクトアイディー)とは、商品やサービスを特定するために用いられる一意の識別番号のことです。たとえば、オンラインショッピングをする際、各商品にはそれぞれarchives/2481">異なるプロダクト ID が付けられていて、これによって何万点もある商品を正確に区別することができるのです。プロダクト ID は、商品情報をデータベースに登録したり、在庫管理を行ったりする際にも使用されます。 例えば、スーパーマーケットでは、レジで商品をスキャンする時にこのプロダクト ID を利用します。このように、プロダクト ID は商品の管理や流通に欠かせない要素となっているのです。archives/8682">また、顧客が特定の商品を簡単に検索できるため、利便性も高まります。最近では、電子商取引が盛んになり、たくさんのプロダクト ID を持つ商品が流通していますが、これによって消費者も満足のいく買い物ができるようになっています。つまり、プロダクト ID は私たちの生活をより便利にするための大切な仕組みなのです。
プロダクト とは it:「プロダクト」という言葉は、ITやビジネスの世界でよく使われますが、具体的に何を指すのでしょうか?簡単に言うと、プロダクトとは、ある目的を持って作られた製品やサービスのことです。たとえば、スマートフォンやアプリ、archives/2745">ウェブサイトなどがその例です。 ITの分野では、プロダクトは技術やデザイン、ユーザー体験をarchives/7564">考慮して作られます。それにより、使いやすくて、人々の生活を便利にするものが生まれます。プロダクトを成功させるためには、まず市場のニーズを理解し、どのような問題を解決できるかを考えなければなりません。 プロダクトが完成したら、次はマーケティングが重要です。どのようにして多くの人に知ってもらうかを計画し、宣伝を行います。いいプロダクトを作るだけではなく、それを届ける力も大事です。 このように、プロダクトとは単なる製品やサービスではなく、設計から開発、マーケティングまでの一連のプロセスを含む言葉です。これを理解することで、IT業界についてより深く知ることができます。今後のキャリアや学びにも役立つ知識ですので、ぜひ覚えておきましょう!
プロダクト とは ソフトウェア:ソフトウェアとは、コンピュータに指示を出して、動かすためのプログラムやデータのことです。そして「プロダクト」とは、ソフトウェアなどの製品を指します。例えば、私たちがスマートフォンで使うアプリや、パソコンで動かすソフトウェアもプロダクトの一種です。プロダクトは、開発者が特定の目的を持って作り出し、それを使う人たちに便利さや楽しさを提供します。たとえば、ゲームアプリは遊ぶ楽しみを、学習アプリは勉強の手助けをすることで、多くの人々に役立っています。プロダクトには、ユーザーのニーズを考えて開発されたものが多く、使いやすさやデザインにも工夫がされています。これらのプロダクトは、私たちの生活をより便利にし、日常の中で必需品となっているのです。このように、プロダクトとは、ソフトウェアが私たちの生活にどのように関わっているのかを理解するために重要な概念です。
プロダクト とは ビジネス:「プロダクト」という言葉は、ビジネスにおいてとても重要な意味を持っています。簡単に言えば、プロダクトは「商品」や「サービス」のことです。たとえば、私たちが毎日使うジュースやスマートフォン、オンラインゲームなど、すべてがプロダクトになります。ビジネスでは、このプロダクトが顧客にどのように受け入れられるかが大切です。良いプロダクトがあると、多くの人が買いたいと思い、その結果、ビジネスは成功します。archives/2446">逆に、プロダクトが魅力的でなかったり、必要とされていなかったりすると、売上が伸び悩んでしまうこともあります。だから、企業はarchives/4123">常に市場調査を行い、顧客が何を求めているのかを理解しようとしています。archives/8682">また、プロダクトを改善するためにフィードバックを受け取ることも大切です。要するに、プロダクトはビジネスの心臓部とも言える存在で、成功するためにはしっかりと考える必要があります。
プロダクト アウト とは:プロダクト アウトとは、企業が商品を作り出す際に、まずその商品自体に力を入れる考え方のことです。つまり、商品を開発したり改良したりすることを重視し、archives/9635">その後でそれをどう売るかを考えます。この考え方は、人気のある商品や成功するサービスを生み出すために重要です。例えば、テクノロジーの世界では、良い商品を開発することがとても大切です。archives/6393">それによって、消費者が本当に必要とするものを提供することができます。多くの企業は、最初に消費者のニーズを調査して、そのニーズに基づいて商品を作る「マーケットイン」というスタイルを選びますが、プロダクトアウトは、まず自分たちが良いと考える商品を作り、それを市場にarchives/5605">投入することを目指します。このようなarchives/1270">アプローチによって、独自性や革新性のある商品が生まれることもあります。成功するためには、プロダクト アウトとマーケットインのバランスを取ることが大切です。自分たちの創造力や技術力を信じ、良い商品を生み出し、archives/9635">その後で市場の反応を見ながら戦略を練ることが、企業の競争力を高めるのに繋がります。
プロダクト キー とは:プロダクトキーとは、ソフトウェアをちゃんと使うために必要な特別な番号のことです。この番号は、数桁の英数字からできていて、ソフトウェアの購入者だけが使えるものです。例えば、WindowsやOfficeなどのソフトをインストールする時、プロダクトキーを入力する必要があります。これは、不正にソフトを使ったり、コピーしたりすることを防ぐためです。プロダクトキーがないと、正しくソフトウェアを使うことができなかったり、機能が制限されたりします。だから、購入した際にプロダクトキーをしっかりメモしておくことがとても大切です。archives/8682">また、他の人と共有しないように気を付けましょう。もしプロダクトキーを紛失してしまったら、購入した会社に連絡して再発行してもらうことができますが、場合によっては手数料がかかることもありますので注意が必要です。プロダクトキーは、ソフトウェアを安心して使うための重要なアイテムです。
プロダクト archives/7017">デザイナー とは:プロダクトarchives/7017">デザイナーとは、商品やサービスのデザインを考える仕事をしている人のことです。この職業は、見た目だけでなく、使う人にとってどれだけ便利か、使いやすいかを大切にしています。たとえば、新しいスマートフォンや家庭用品などをデザインするとき、まずはその商品のarchives/5589">コンセプトを考えます。次に、実際に触ってみてどう感じるか、どんな機能が必要かを調べます。これにはユーザーの意見を集めたり、競合他社の製品を研究したりします。そして、最終的にはビジュアルや機能をまとめたプランを作ります。プロダクトarchives/7017">デザイナーは、形状や色、大きさなどを考えるだけでなく、商品の使われ方や流通のこともarchives/7564">考慮します。結果として、人々の生活をより良くするものを作り上げるための仕事だと言えるでしょう。デザインのプロとして、多くのことを学び、実際に見せることができる非archives/4123">常にやりがいのある仕事です。
プロダクト デザイン とは:archives/9558">プロダクトデザインとは、製品やサービスの見た目や使い方を考える仕事のことです。たとえば、スマートフォンや家具、車など、私たちが日常で使うものをデザインすることを指します。archives/7017">デザイナーは、見た目を美しくするだけでなく、使いやすさや安全性、環境への配慮など、さまざまな要素をarchives/7564">考慮します。archives/9558">プロダクトデザインのプロセスは、アイデアを出すことから始まります。archives/9635">その後、スケッチや模型を作り、実際に製品を作るための計画を立てます。archives/15541">最後には、消費者のニーズに応じた製品を市場に送り出します。archives/9558">プロダクトデザインは、私たちの生活を便利で楽しくする重要な要素です。そして、人々が貴重な時間をより快適に過ごせるように、デザインは大切な役割を果たしています。魅力的なarchives/9558">プロダクトデザインによって、多くの人がその商品に惹きつけられ、使ってみたくなるのです。
サービス:プロダクトが提供する機能や価値を含む、顧客に向けたサービス全般を指します。
製品:プロダクトの一形態で、物理的な商品を指します。プロジェクトやサービスも含めて製品と呼ぶことがあります。
市場:プロダクトが販売される環境やarchives/95">領域を指します。特定のユーザー層やニーズに応じた市場があります。
マーケティング:プロダクトを顧客に効果的に届かせるための戦略や活動を指します。
ユーザー:プロダクトを実際に使用する人々のことです。彼らのニーズやフィードバックがプロダクトの改善に重要です。
開発:プロダクトを作成する過程を指します。企画から設計、製造までの一連の流れが含まれます。
機能:プロダクトの特性や能力を指します。利用者がどのようにそのプロダクトを使うかを形作ります。
戦略:プロダクトを市場において成功させるための長期的な計画やarchives/1453">方向性を指します。
ブランディング:プロダクトの認知度や価値を高めるための活動や戦略を指します。
価格:プロダクトを購入する際の費用を指し、市場価値や競合に基づいて設定されます。
フィードバック:ユーザーから得られる意見や感想で、プロダクトの改善に活用されます。
競合:同じ市場で競う他のプロダクトやサービスのことを指します。競合archives/128">分析は戦略策定に重要です。
売上:プロダクトの販売によって得られる収益を指します。
archives/1317">リリース:プロダクトを市場にarchives/5605">投入すること、archives/8682">または新機能のarchives/3256">公開を指します。
顧客:プロダクトを購入archives/8682">または利用する人や組織を表します。
製品:商業的に販売される物品やサービスのこと。特にarchives/5227">工業用に製造されたものを指すことが多い。
商品:売買される対象となる物品の総称。プロダクトよりも広い意味で使われることがある。
アイテム:特定の目的や用途に使われる物品や要素。archives/17003">一般的でarchives/2326">幅広い意味を持つ。
ビジネス:商業活動や経済活動全般を指す用語。プロダクトはビジネスの一部として存在する。
サービス:提供される行為や機能。製品とは異なり、物理的な形を持たないことが多い。
提供物:他者に提供されるあらゆる物やサービスを指す言葉。特にビジネスシーンで用いられる。
開発物:主に新しく開発された製品や技術のこと。特にイノベーションに関連する。
成果物:プロジェクトや作業の結果生み出される具体的な物や成果。特定の目標に対する結果を指す。
商品:販売される具体的な物品やサービスのこと。消費者に提供される最終的な製品を指します。
サービス:顧客のニーズに応じて提供される無形の価値。例えば、コンサルティングやサポートなどが含まれます。
ブランディング:企業や製品の特徴や価値を消費者に伝え、認知度を高めるための戦略。信頼性や魅力を強化する手段です。
マーケティング:市場調査、広告、プロモーションなどを通じて、製品やサービスを効果的に消費者に届ける活動。
セールス:製品やサービスを実際に販売するプロセス。顧客とのやり取りや取引完了までの流れを含みます。
市場調査:消費者のニーズや市場の動向を把握するために行う調査活動。これにより、適切な製品開発やマーケティング戦略が可能になります。
競合archives/128">分析:同じ市場に存在する競合他社の状況や戦略を調査し、自社の立ち位置を理解するためのarchives/128">分析。
ユーザーエクスペリエンス (UX):製品やサービスを利用する際のユーザーの体験やarchives/9484">感じ方。使いやすさや満足度が重要な要素です。
プロダクトarchives/2681">ライフサイクル:製品が市場に出てから廃止されるまでの過程を示すarchives/80">モデル。導入期、成長期、成熟期、衰退期の4つの段階があります。
フィードバック:顧客からの意見や反応を指し、製品改善やサービス向上に役立てる重要な情報源です。
プロダクトの対義語・反対語
プロダクトとは?IT初心者でも分かる解説 - PM Club
プロダクトとは?IT初心者でも分かる解説 - PM Club
productとは・意味・使い方・読み方・例文 - 英ナビ!辞書 英和辞典
「プロダクト」とはどんな意味? IT・広告業界などでの使い方を紹介