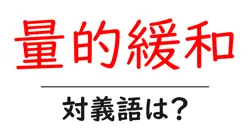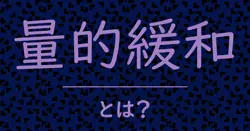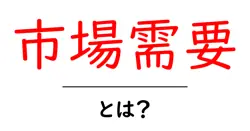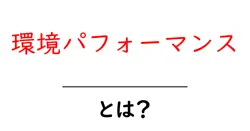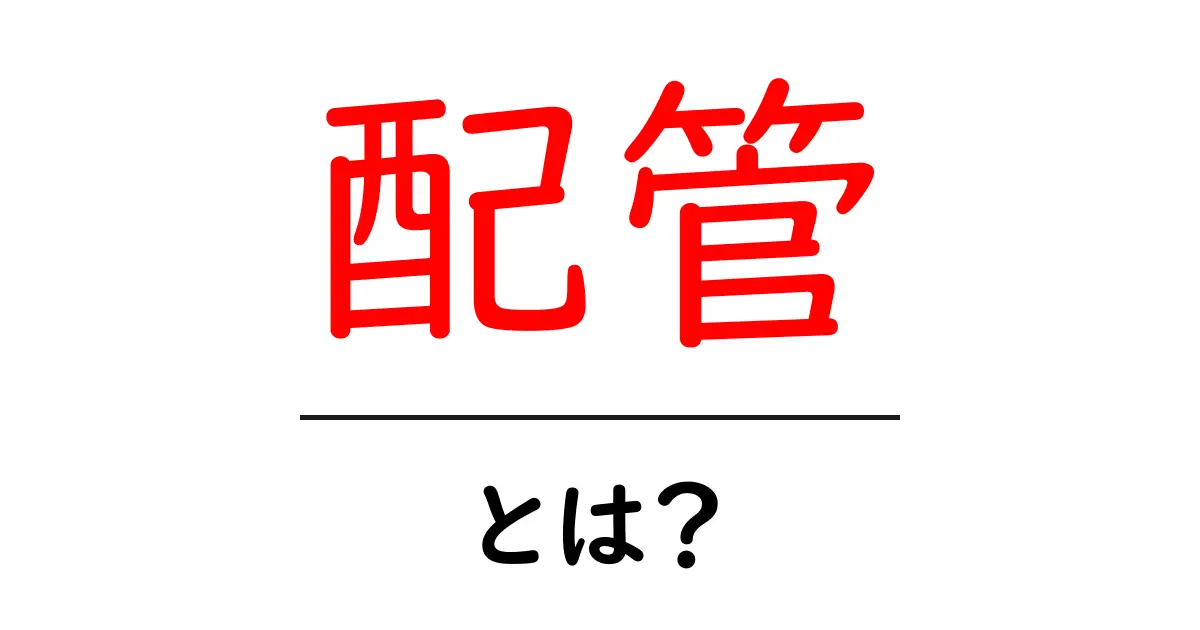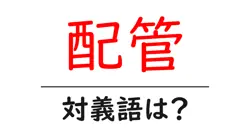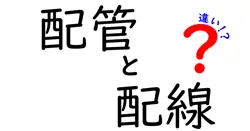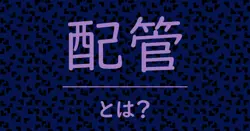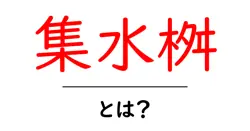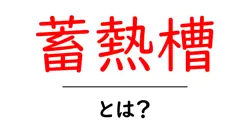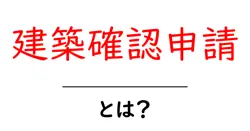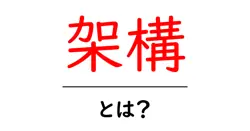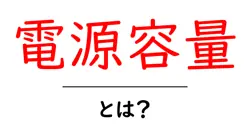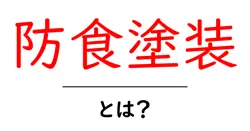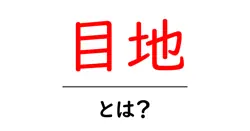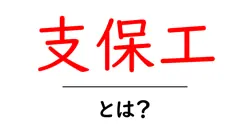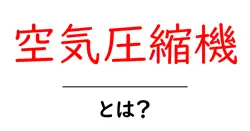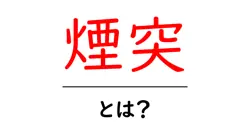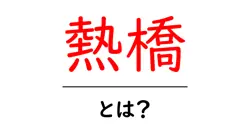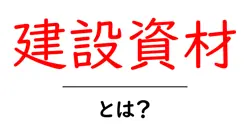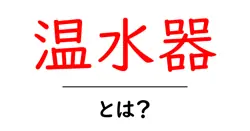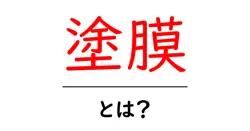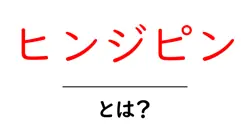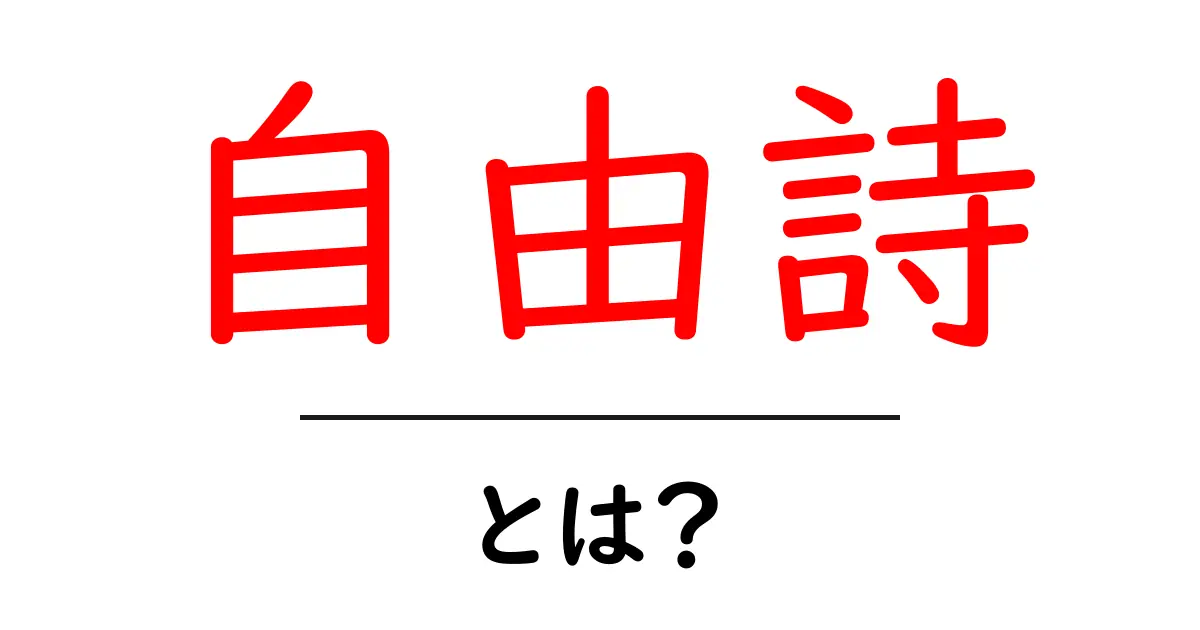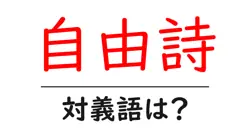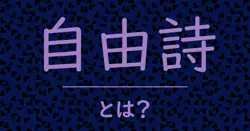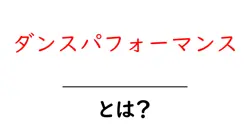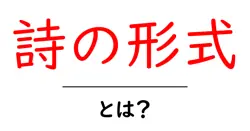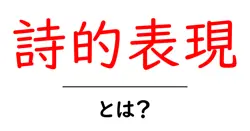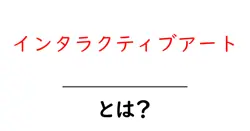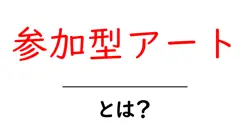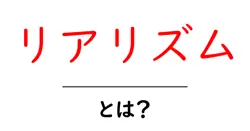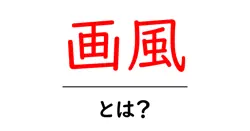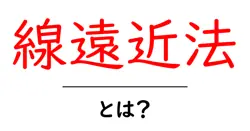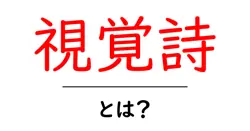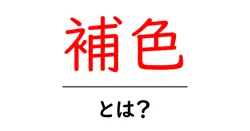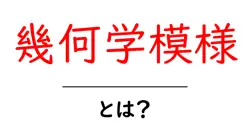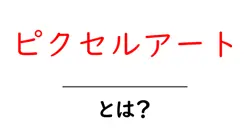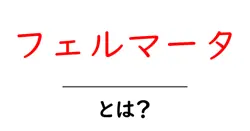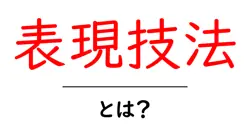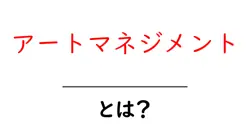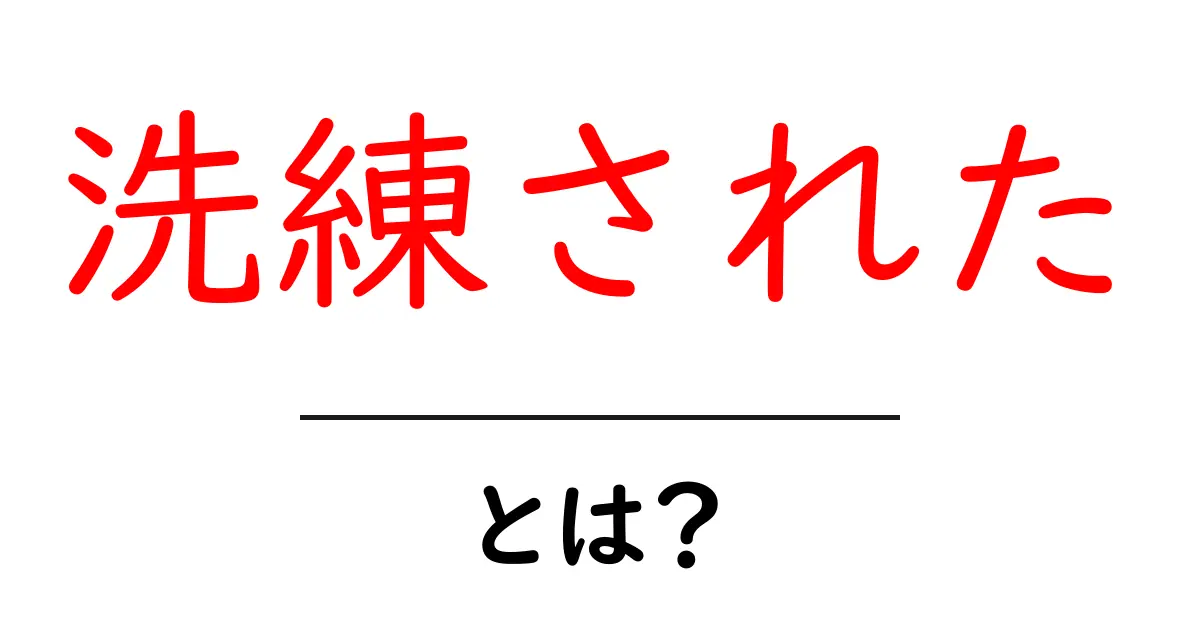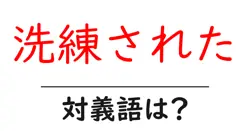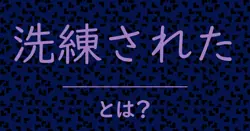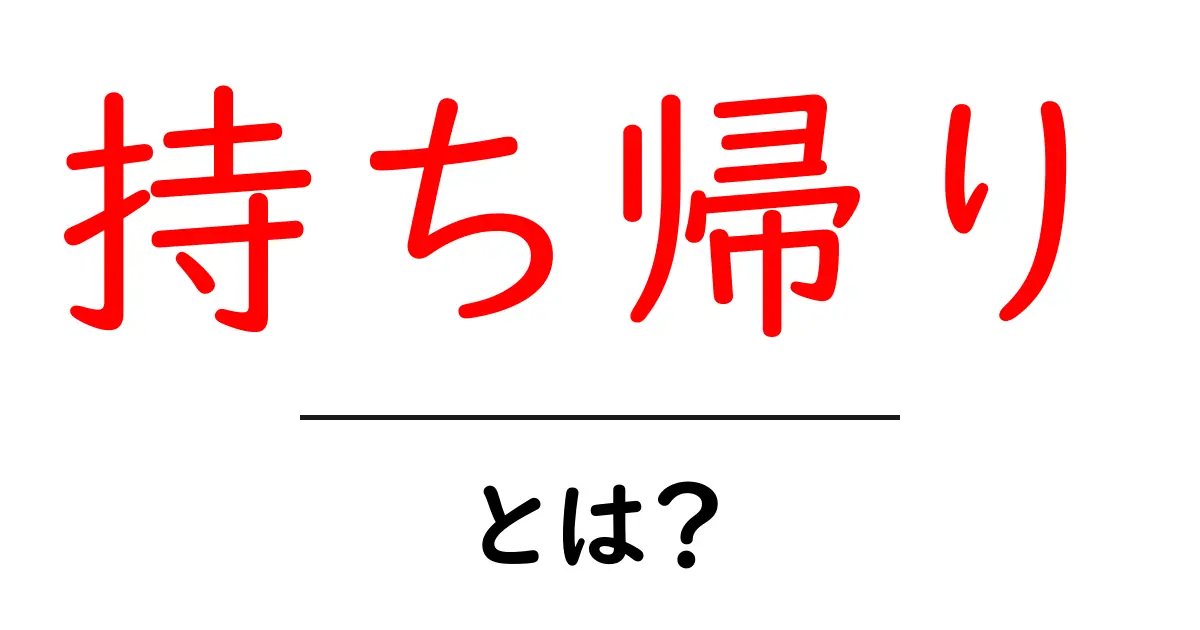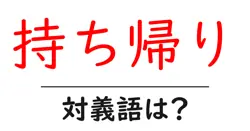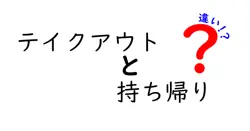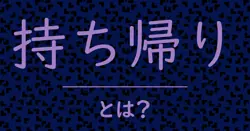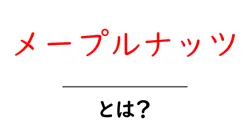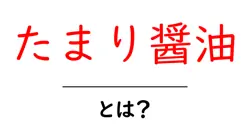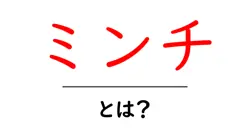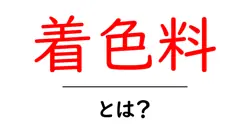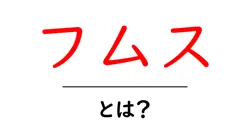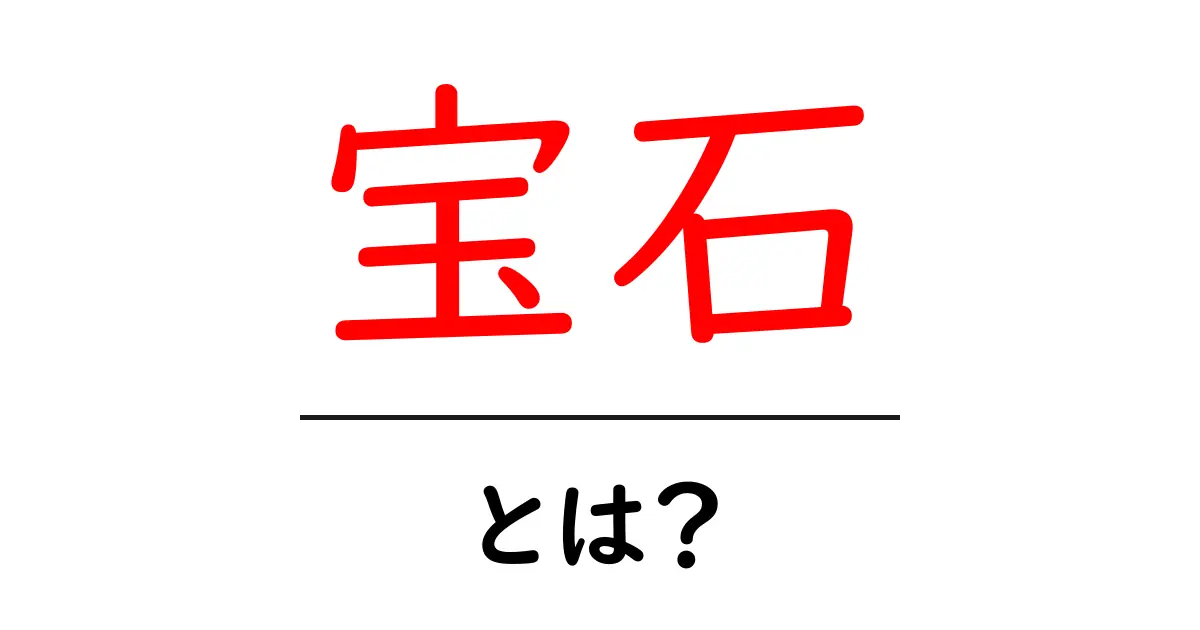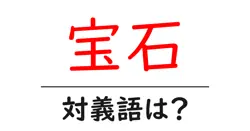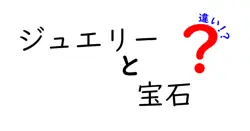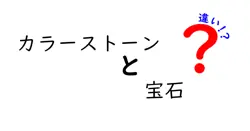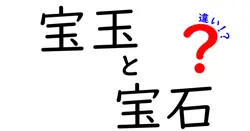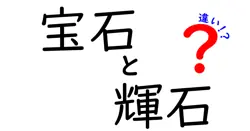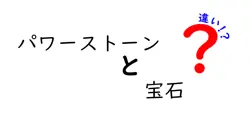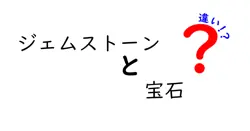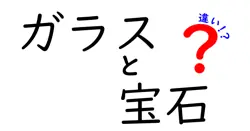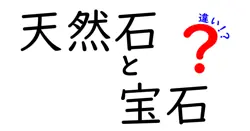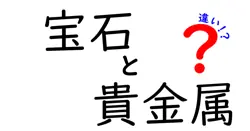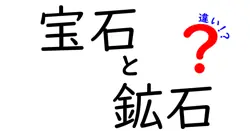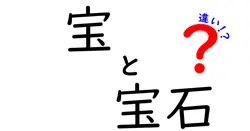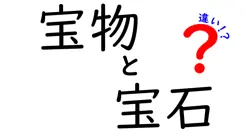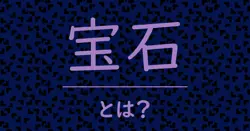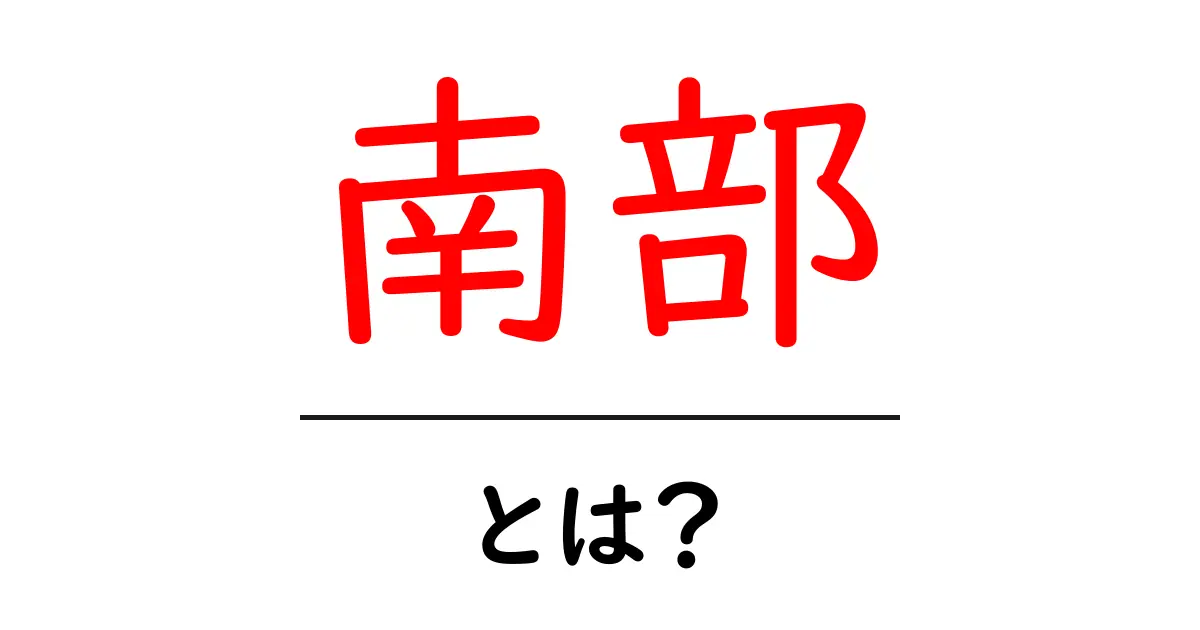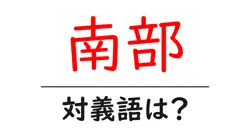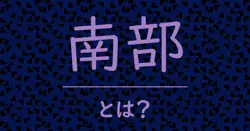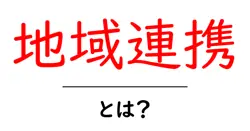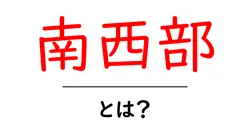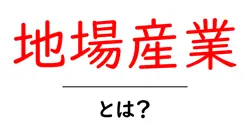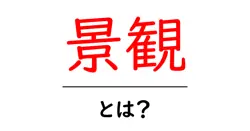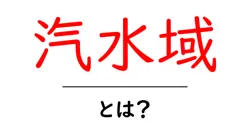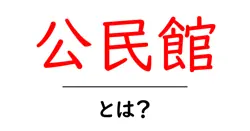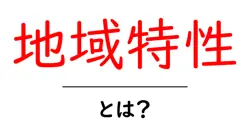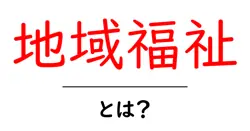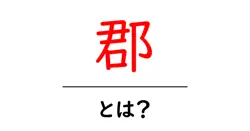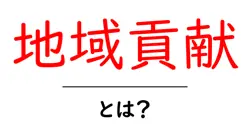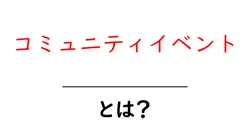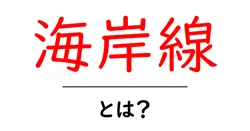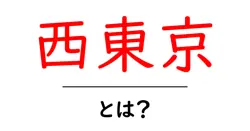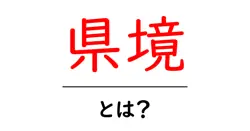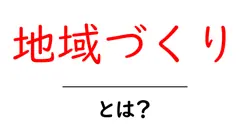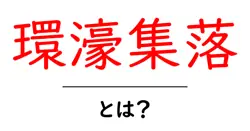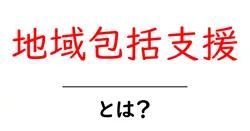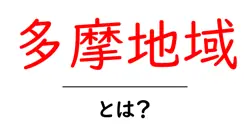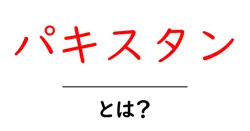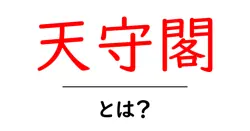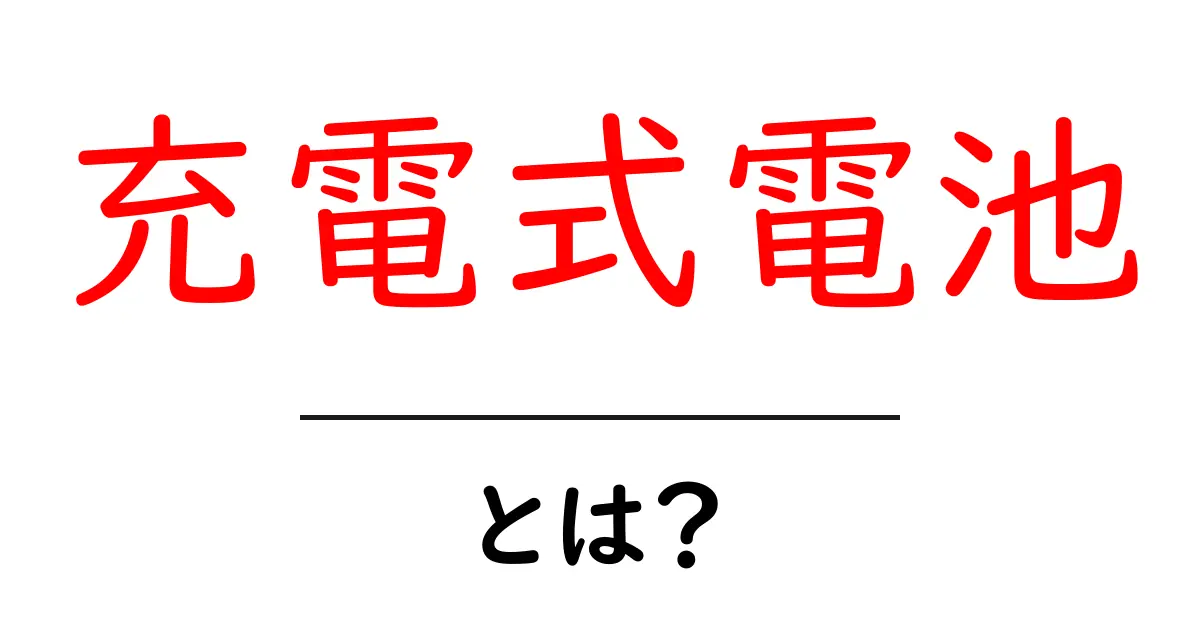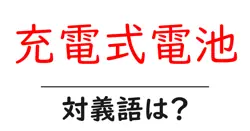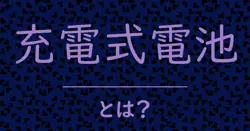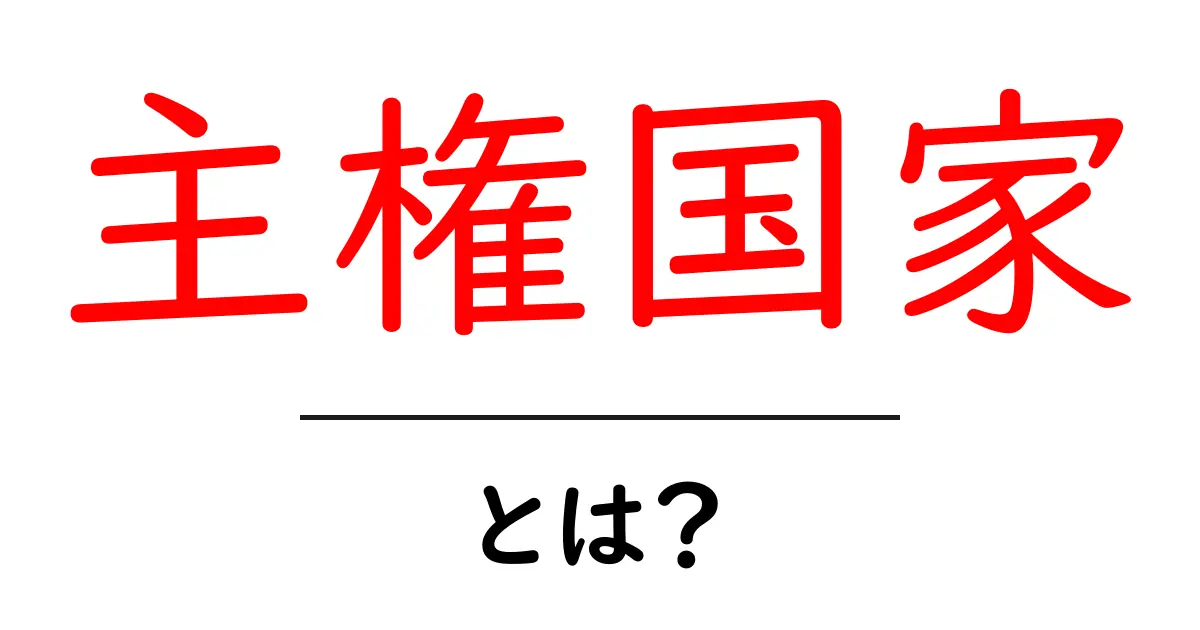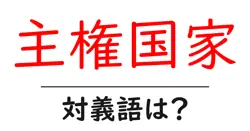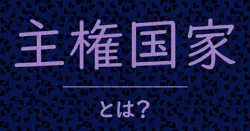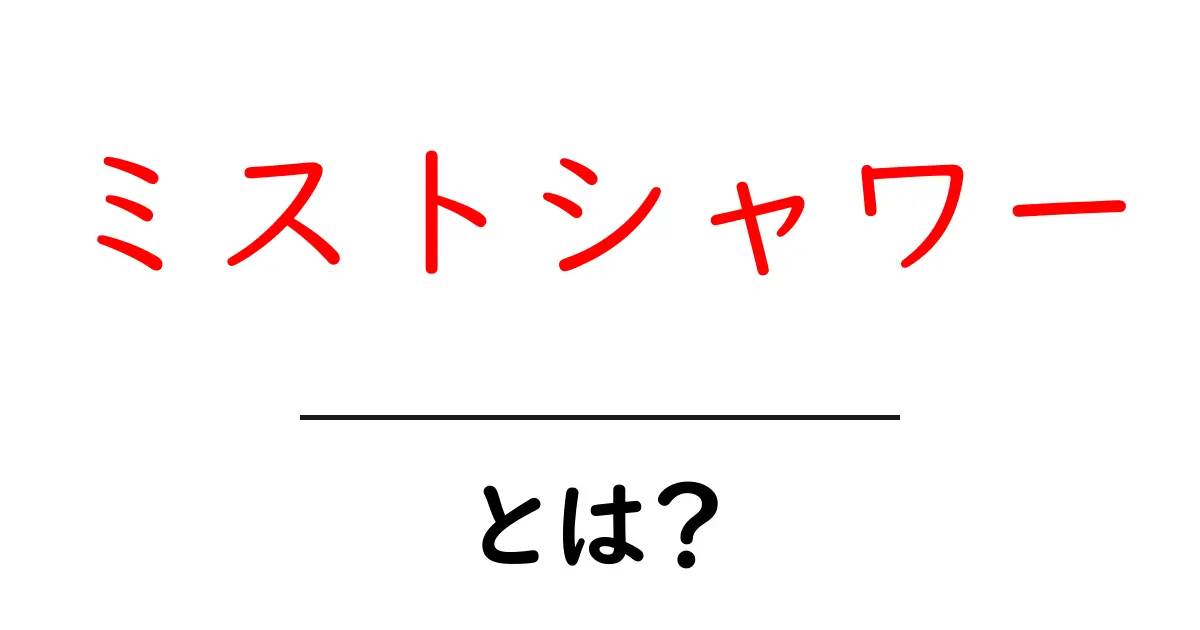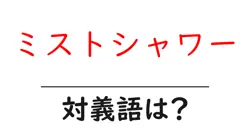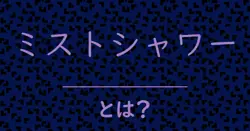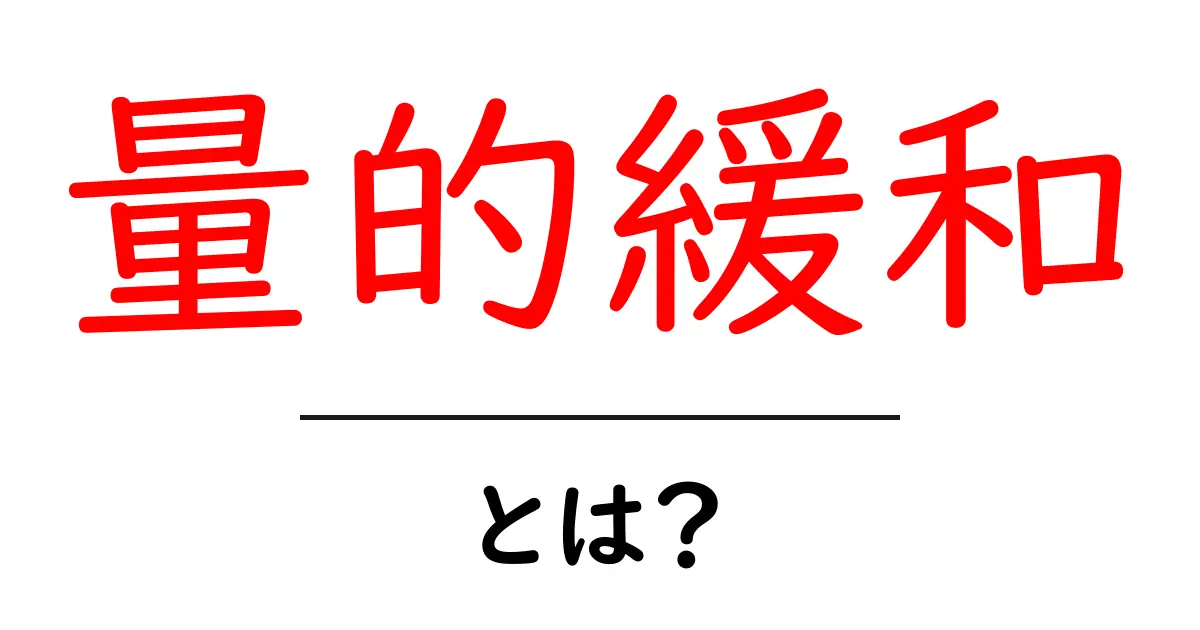
量的緩和・とは?
こんにちは!今回は「量的緩和」という言葉についてわかりやすく解説します。経済のお話しですが、難しいことはありませんので安心してくださいね。
量的緩和の基本
量的緩和(りょうてきかんわ)とは、国が行う経済対策の一つです。特に景気が悪いときに、国の中央銀行が市場にお金を流すことで、経済を活性化させようとする仕組みなんですね。
どうして量的緩和が必要なのか?
私たちの生活では、お金の流れが大切です。お金が流れていないと、企業は物を作れず、仕事も減ってしまいます。そうなると、私たちの生活も厳しくなりますよね。そこで量的緩和が行われるんです。
量的緩和の仕組み
具体的には、中央銀行が金融機関から国債などの資産を購入します。すると、金融機関にはたくさんのお金が入ってきます。それによって、金融機関は企業にお金を貸しやすくなります。
量的緩和の効果
量的緩和を行うとどんな良いことがあるのでしょうか?以下にその効果をまとめました。
| 効果 | 説明 |
|---|---|
| 景気回復 | お金が流れることで、企業の活動が活発になり、仕事が増える。 |
| インフレの促進 | 物価を上げることで、企業が利益を得やすくなる。 |
| 失業率の低下 | 企業が多くの人を雇い、働く人が増える。 |
量的緩和の限界
しかし、量的緩和には限界もあるんです。お金が増えすぎると、インフレが進みすぎて物の値段が高くなり、生活が苦しくなることもあります。また、量的緩和を続けると、国の借金が増えてしまうことも心配です。
まとめ
量的緩和は、経済を良くするための大切な手段の一つですが、使い方には注意が必要です。景気が良くなると私たちの生活も豊かになりますが、無理にお金を流しすぎると別の問題が起きることもあります。これからも経済の動きを見ていきましょう!
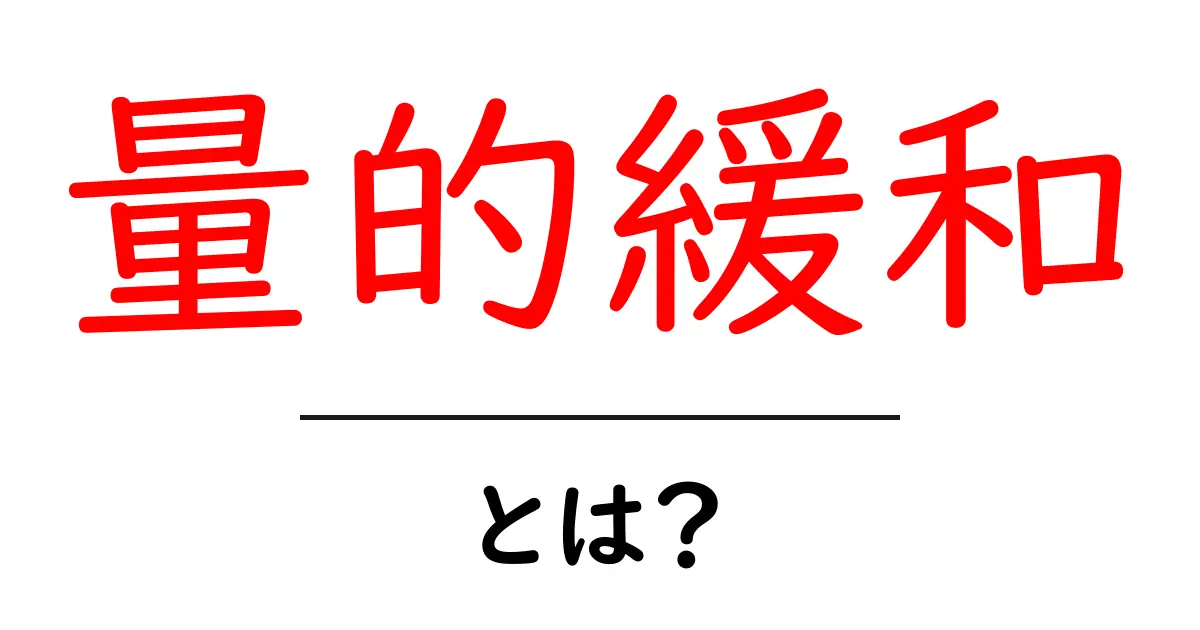
アベノミクス 量的緩和 とは:アベノミクスとは、2012年から始まった日本の経済政策のことです。この政策の主な目的は、景気を良くして、国の経済を活性化させることです。その中でも特に重要なのが「量的緩和」です。量的緩和は、日本銀行が市場にお金を大量に供給することを指します。具体的には、日本銀行が国債や株式などを買って、銀行にお金を流します。このお金が銀行から企業や個人に貸し出されることで、消費や投資が増えていくのです。この仕組みは、景気を良くするための一つの方法として使われます。量的緩和によってお金が増えると、人々は安心してお金を使うことができ、その結果として経済が活気づくというわけです。しかし、量的緩和には注意も必要です。お金が増えすぎると、物の値段が上がる「インフレーション」が起こる可能性もあります。このように、アベノミクスと量的緩和は、日本の経済にとって大切な政策の一つです。理解しておくことで、日本がどのように経済を回しているのかがわかりますよ。
金融政策:中央銀行が金利や通貨供給量を調整することで、経済を安定させるための方針や手段です。量的緩和はその一つです。
資産買入:中央銀行が政府の債券やその他の金融資産を購入することで、流動性を高める手法で、量的緩和の実施に関連しています。
マネーサプライ:経済内に流通しているお金の総量を指します。量的緩和によってマネーサプライの増加が期待されます。
インフレーション:物価の上昇率を示し、量的緩和は経済におけるインフレーションを促進する可能性があります。
金利:借りたお金に対して支払う利息の割合です。量的緩和により金利が低下することが一般的です。
経済成長:国や地域の経済がどれだけ成長しているかを示す指標で、量的緩和は成長を促す手法の一つとされています。
中央銀行:国家の通貨政策を担う銀行で、主に金利や通貨供給を管理します。量的緩和は通常、中央銀行によって実施されます。
景気刺激:経済活動を活性化させるための措置で、量的緩和は景気を刺激する手段の一つとして用いられます。
デフレ:物価が継続的に下落する現象で、量的緩和はデフレの回避や克服のために行われることがあります。
流動性:資産をすぐに現金化できる度合いを示し、量的緩和は市中の流動性を高める目的で行われます。
金融緩和:中央銀行が市場にお金を多く供給し、金利を下げることで、経済活動を刺激する政策。
非伝統的金融政策:通常の金利政策以外の手段を用いて経済を活性化させる政策。量的緩和もこの一部。
マネタリーベースの拡大:流通しているお金の量を増やし、銀行に資金を供給することで、経済を活性化させること。
公開市場操作:中央銀行が国債などの金融資産を売買することで、市場の資金量を調整する手法。
資産購入プログラム:中央銀行が特定の資産を購入することで、経済に資金を供給する政策のこと。
流動性供給:市場に対してお金を供給し、取引をスムーズに行えるようにすること。
金融政策:国家や中央銀行が経済を調整するために行う政策で、金利や通貨供給量を操作することによってマクロ経済をコントロールします。
中央銀行:国家の通貨政策を担う銀行で、金利の設定や通貨の発行、金融システムの安定化などを行います。日本では日本銀行がこれにあたります。
インフレーション:物価が持続的に上昇し、通貨の購買力が低下する現象。量的緩和はインフレを促進する手段として用いられることがあります。
デフレーション:物価が持続的に下落し、通貨の購買力が上昇する現象。量的緩和はデフレを克服するための対策として用いられます。
金利:お金を借りる際に支払う利息の割合で、金融政策の一環として、中央銀行が設定することができます。量的緩和によって金利を引き下げることが試みられます。
資産購入:中央銀行が国債やその他の金融資産を購入することにより、通貨供給量を増やす手法です。量的緩和の実施において中心的な役割を果たします。
流動性:資産がどれだけ容易に現金に変えられるかを示す指標。量的緩和によって流動性を高めることが目的の一つです。
日本銀行:日本の中央銀行で、金利政策や為替介入の他、量的緩和政策を実施する役割を持っています。
経済成長:国や地域の経済規模が拡大すること。量的緩和は経済成長を促進するために用いられることがあります。
マネタリーベース:通貨供給の基盤となる貨幣の総量で、中央銀行がコントロールすることで経済に流通させるお金の量を示します。量的緩和によってマネタリーベースが増加します。
金融緩和:金利を引き下げたり、資金供給を増やしたりすることで、経済を刺激しようとする政策の総称。量的緩和も金融緩和の一種です。