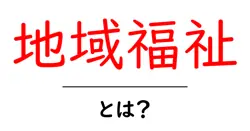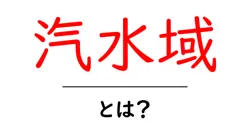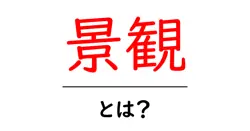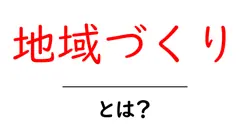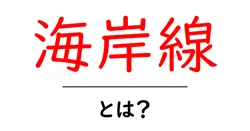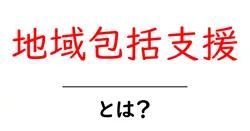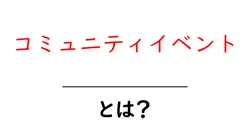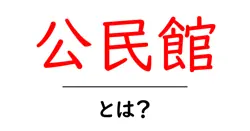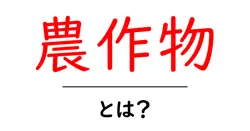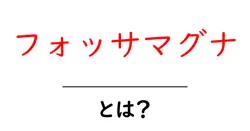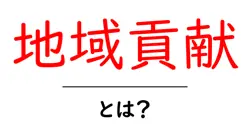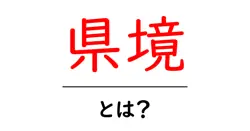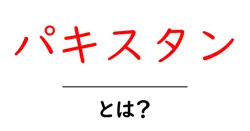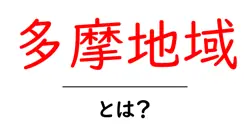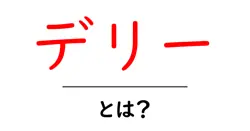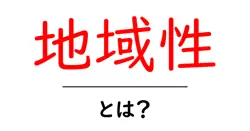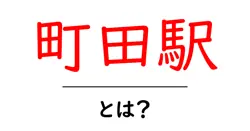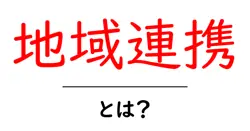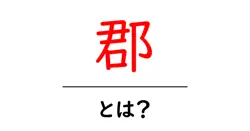環濠集落とは?
環濠集落(かんごうしゅうらく)とは、古代の日本で見られた集落の一形態です。この集落は、周囲を堀で囲まれた形をしていて、主に防衛のために作られました。歴史的には、弥生時代から存在しており、農耕社会が発展する中で人々が住み始めた場所です。
環濠集落の構造
環濠集落の特徴的な点は、集落の周囲を囲む堀と、その内側に建物が立ち並ぶ形状です。この堀は敵の侵入を防ぐためだけでなく、水を供給する役割もありました。ここでは、環濠集落の基本的な構造について詳しく見ていきましょう。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 堀 | 集落を囲む防御構造 |
| 集落の建物 | 主に農業用の住居や倉庫 |
| 水源 | 堀が水の供給源となる |
環濠集落の歴史
環濠集落は、初めは日本の各地で見られましたが、特に九州や中国地方に多く分布しています。弥生時代には富の集積が進み、人々が集まるようになりましたが、それに伴い、外敵からの攻撃も増えました。そのため、環濠集落が発展していったと考えられています。
現在の環濠集落
現在でも、環濠集落の遺跡が発見されており、考古学者たちが研究を続けています。これにより、当時の人々の生活や文化を知る手がかりが得られています。また、観光スポットとしても注目されています。
環濠集落は、単に防御のためだけでなく、人々が共に助け合いながら生活するための共同体でもありました。このような集落の形は、私たちがコミュニティや共同体について考える際にも大切なヒントを与えてくれます。
集落:人々が居住する地域や村のことを指します。環濠集落では、住居が集まっている状態を示します。
環濠:周囲に掘られた堀のことです。環濠集落はこの堀によって外敵から守られている集落を意味します。
防御:敵から身を守るための手段や仕組みのこと。環濠集落は、その構造が防御目的で設計されています。
縄文時代:日本の先史時代の一つで、環濠集落はこの時代に見られる特徴的な集落形態の一つです。
集団:複数の人々が集まった状態やグループのこと。環濠集落は、集団で生活するための場でもあります。
生活:人間が日常的に行う活動や営みのこと。環濠集落は、人々の生活が成り立つ場所です。
遺跡:過去の人々の生活の痕跡が残る場所。環濠集落に関する遺跡は、歴史的な価値があります。
農業:作物を育てたり家畜を飼ったりする活動。環濠集落では、農業が重要な生活の一部を占めていたと考えられています。
水管理:水の供給や排水を行うこと。環濠集落では、堀が水の管理にも関与しているため、重要な要素です。
祭り:地域やコミュニティが行う伝統的な行事やイベント。環濠集落では、住民が集まって祭りを行うこともあったでしょう。
環濠:外部からの侵入を防ぐために、集落の周囲に掘られた堀のこと。通常、敵からの防衛や水の供給、農業用水としても利用されることがある。
集落:一定の地域に住む人々の集まりのこと。環濠集落の場合は、環濠によって防御された特定の集団の生活空間を指す。
縄文時代:日本の先史時代の一つで、約縄文時代の初めから始まり、数千年続いた時代であり、環濠集落はこの時代に多く見られる。
防衛:敵の攻撃から身を守るための行動や手段。環濠はその一環として、集落を外敵から守る役割を果たす。
水資源:飲み水や農作物の潤いに必要な水のこと。環濠は水資源を集落内に取り入れる役割も持つことがある。
土器:土を原料にして焼き固めた器。縄文時代の人々が使用していた文化の一環として、環濠集落から出土することが多い。
遺跡:過去の人々の生活や文化を示す物的証拠が残った場所。環濠集落は重要な遺跡として研究されることがある。
農業:食料を作るための活動。環濠集落は農業が行われていたことを示す証拠が多く見つかる。
居住空間:人々が生活するための場所。環濠集落は周囲が堀で囲まれた特定の居住空間を持っている。
考古学:過去の文化や社会を研究する学問。環濠集落は考古学的な研究材料として非常に重要な位置を占める。
環濠集落の対義語・反対語
該当なし