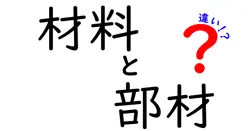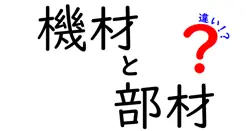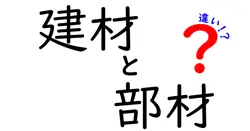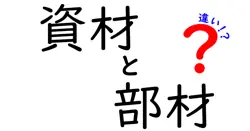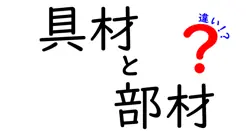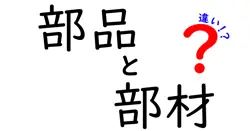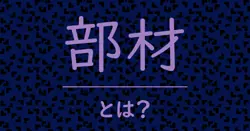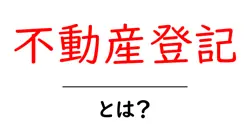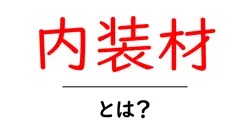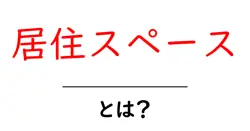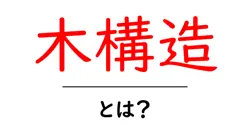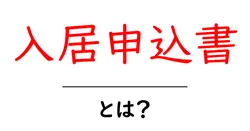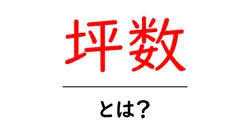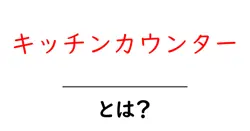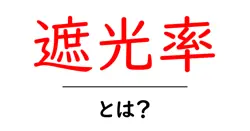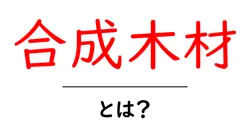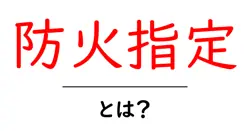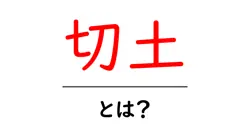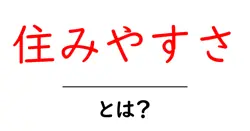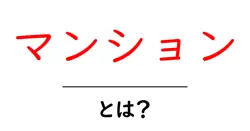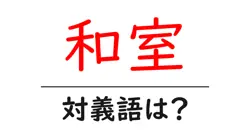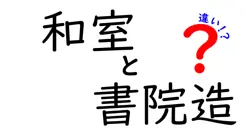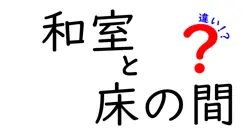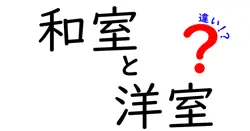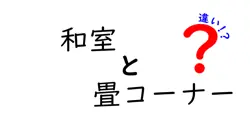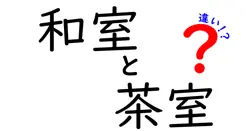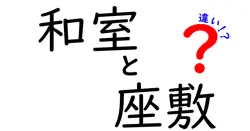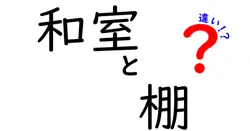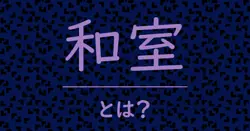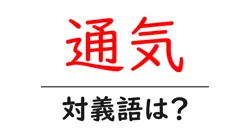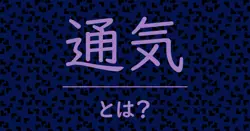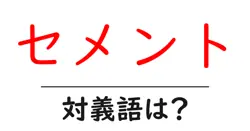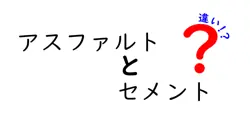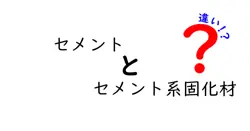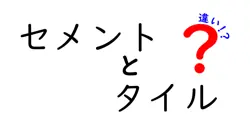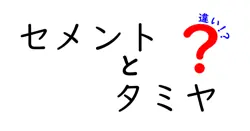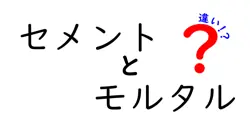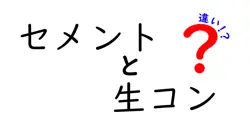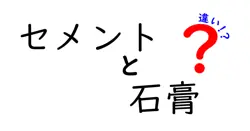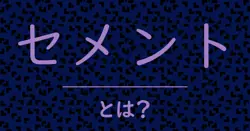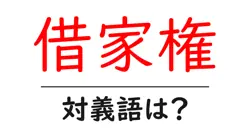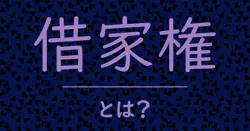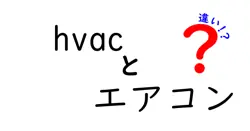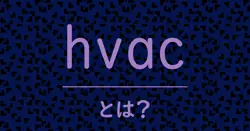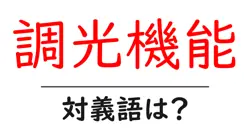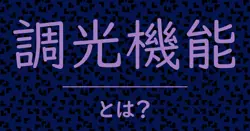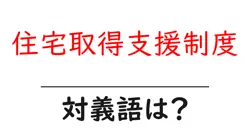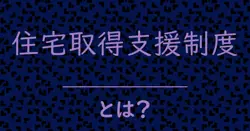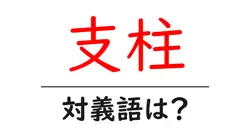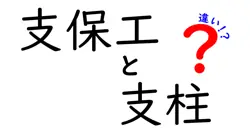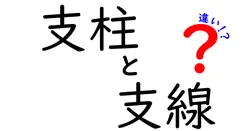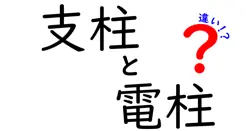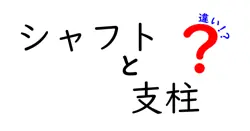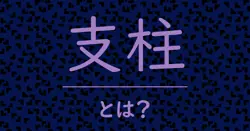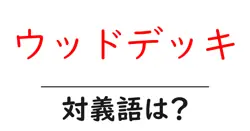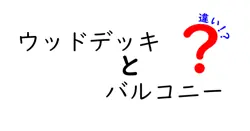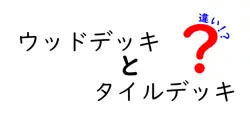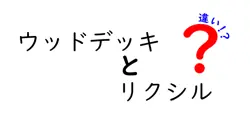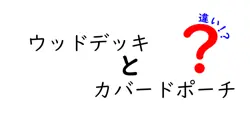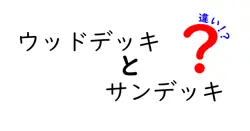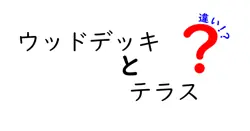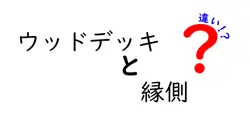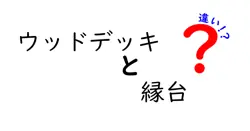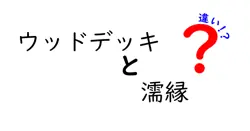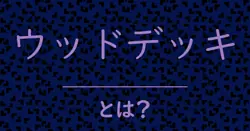和室とは?
和室(わしつ)は、日本の伝統的な部屋のスタイルのことで、主に畳(たたみ)で床が敷かれ、襖(ふすま)や障子(しょうじ)などの特徴的な建具が使われます。和室は、日本の文化や歴史を色濃く反映している空間として、多くの日本人に親しまれています。
和室の特徴
和室にはいくつかの特徴があります。具体的に見ていきましょう!
| 特徴 |
説明 |
| 畳 |
和室の床に敷かれている草でできたマット。心地よい感触が特徴。 |
| 襖 |
部屋を仕切るための扉。開け閉めができる。 |
| 障子 |
木の枠に和紙を張ったもの。光を柔らかく通す。 |
| 縁側 |
外と内をつなぐスペースで、くつろぎの場として使われることが多い。 |
和室の使用例
和室は、さまざまな場面で利用されます。たとえば、家族が集まるリビングとしてはもちろん、お茶を楽しむためのお茶室、さらには客間としても使用されます。また、畳の上で寝る文化もあり、寝室としても利用されています。
現代の和室
最近では、現代的な家にも和室が取り入れられることが増えてきました。和モダンとも呼ばれるスタイルで、洋風の家具やインテリアと組み合わせて独特な雰囲気を作り出しています。これにより、若い世代にも和室の魅力が広がっています。
和室の魅力
和室の最大の魅力は、日本の伝統や文化を感じることができる点です。また、畳の香りや温かみ、静寂な空間は、心を落ち着けるのに最適です。訪れる人々に癒しを与える空間が、和室の魅力です。
和室のサジェストワード解説らんま 和室 とは:「らんま和室」という言葉を聞いたことがありますか?これを理解するためには、まず「らんま」が何かを知る必要があります。らんまとは、和室の中にある格子状の半透明の仕切りのことです。この特徴により、空間を仕切るだけでなく、光を取り入れる役割も果たしています。
和室は日本の伝統的な居住空間で、畳が敷かれた部屋が特徴的です。和室には、さまざまなデザインによる家具や装飾が施され、シンプルで落ち着いた雰囲気を持っています。最近では、和室にらんまを取り入れることで、部屋の明るさや開放感を増すことができると人気です。
たとえば、家族が集まるリビングに和室を作ったり、お客さんを招くためのスペースとして和室を設けたりすることができます。その中にらんまを入れることで、視覚的にも美しく、さらに日光を取り入れた明るい部屋を作ることができます。和室は懐かしさだけでなく、現代的なデザインに柔軟に対応できるため、多くの人に愛されています。これが「らんま和室」の魅力なのです。
和室 地板 とは:和室の地板(じばん)とは、和室の床のことを指します。和室は、日本の伝統的な部屋で、通常は畳が敷かれていますが、その下には地板が存在しています。この地板は、建物を支える重要な部分であり、様々な役割を果たしています。地板は通常、木材で作られており、自然素材であるため、湿度の調整が得意です。また、和室の心地よさや、足触りの良さにも大きく貢献しています。地板は、畳を支える基盤だけでなく、床下の空気を通し、カビなどの発生を防ぐ役割もあるのです。和室においては、地板の状態を良好に保つことで、居住空間を快適に保つことができます。たとえば、定期的な掃除や湿度管理、さらには地板の張替えが必要な場合もあります。これらは、長期間にわたって快適に和室を使うためには欠かせないポイントです。
和室 天袋 とは:和室には独特の空間があり、利用するための工夫がされています。その一つが「天袋」と呼ばれる部分です。天袋とは、和室の壁の上部にある収納スペースのことを指します。天井に近い位置に取り付けられていて、普段は目に見えない場所に存在しますが、和室の利用目的やデザインを考える上でとても重要な要素になります。天袋は、季節ごとに使うものや普段あまり使わないものを収納するために使われます。特に、着物や布団、冬のこたつ布団など、場所を取るアイテムを整理するのに便利です。和室は一般的に狭い空間が多いため、天袋のように上下を活用することで、部屋をスッキリと保つことができます。また、天袋は和室の美しいデザインの一部でもあり、収納だけでなく見せることも意識した作りになっています。ですので、和室をより快適に、効率的に使いたいと考えるなら、天袋の存在を知っておくことはとても大切です。
和室 床の間 とは:和室にある床の間(とこのま)は、日本の伝統的な部屋の一部で、主に床に置かれる装飾的なスペースです。床の間は、客人を迎えるために設けられた場所で、そこに花や掛け軸を飾ることが一般的です。床の間の高さは、部屋の他の部分と比べて少し高めに設定されていて、目を引くように設計されています。この特別な場所は、和室の雰囲気を引き立てる役割を果たします。また、床の間は日本の文化を感じることができる場所でもあり、これを通じて日本の美意識や季節感を表現することができます。例えば、春には桜の花、秋には紅葉など、季節に応じた飾りつけがされることが多く、その時々の美しさを楽しむことができます。床の間はただのスペースではなく、そこに込められた日本の伝統や心を理解することで、和室全体の魅力が増すのです。
和室 書院 とは:和室の書院(しょいん)は、伝統的な日本の住宅やお寺などに見られる特別な部屋の一つです。書院は、本を読むためや書道をするためのスペースとして使われています。この部屋は、特に静かで落ち着いた雰囲気が大切にされており、和室の中でも特別な存在です。
書院は通常、畳(たたみ)で覆われた床を持ち、障子(しょうじ)や襖(ふすま)といった和風の仕切りがあります。書院の壁には、掛け軸(かけじく)や屏風(びょうぶ)が飾られることが多く、これにより、空間がより美しく演出されます。また、書院には通常、中心にテーブルがあり、そこに本や道具を置いたり、友達とお茶をすることがあります。
このように、書院は単なる作業スペースではなく、文化や芸術を感じる特別な空間でもあります。和室の中でも、多くの人に親しまれる場所として、訪れた人々に静けさや美しさを提供しています。日本の伝統文化に興味がある人にとって、書院はぜひ訪れてみる価値のある場所です。
和室 長押 とは:和室の「長押(なげし)」とは、壁と天井の間に取り付けられる横木のことを指します。この長押は、和室特有のデザインや機能を持ち、間取りを統一感のあるものにします。また、長押は主に柱と柱を結ぶ役割を果たし、部屋全体の強度を高める役割も持っています。長押の素材には木材が使われることが一般的で、仕上げによってさまざまな表情を持つことができます。例えば、天然の木の風合いを活かしたものや、塗装を施したものがあります。さらに、長押は掛け物を掛けるためのアイデア次第で、インテリアとしても楽しむことができます。和室をより魅力的に演出するためには、長押の色やデザインを選ぶことが大切です。自分の好みに合わせた空間を作るために、ぜひ長押の役割を理解して活用してみましょう。
和室 長押し とは:和室の「長押し」(なげし)とは、和室の壁に取り付けられる横長の木材のことです。日本の伝統的な建築に多く見られ、主に部屋の装飾と壁の強度を保つ役割があります。長押しは、畳の上に掛けた襖(ふすま)や障子(しょうじ)が倒れないように支えるための重要な部分でもあります。また、長押しには、飾りや絵を飾るための利点もあります。この木材があることで、部屋にアクセントが加わり、より美しい雰囲気が生まれます。一般的には、木材の質感や色合いが和室の落ち着いた印象を強調します。長押しはシンプルだけれども、和室の美しさを引き立てる要素として、多くの人に愛されています。もし和室を作ることを考えているなら、この長押しにもぜひ注目してみてください!
和室 鴨居 とは:和室の鴨居(かもい)とは、部屋の上部に取り付けられる横木のことです。主に天井の高さを整える役割を持っていて、和室特有のデザインの一部でもあります。鴨居は、和室の入口や障子との接触部分に置かれ、空間に独特の雰囲気をもたらします。 さらに、鴨居は障子や襖(ふすま)などの建具を吊るすために必要な部分でもあります。これらのルーバーや障子を適切に支えることで、部屋全体の調和が取れ、機能的にも美しさを保つことができます。 和室には伝統的な要素が多く含まれており、鴨居もその一部です。和風の家で見られる鴨居は、木材でできており、優雅で落ち着いた印象を与えます。鴨居のデザインには様々なスタイルがあり、それぞれの家の雰囲気に合わせたものが選ばれます。和室で過ごす時には、このような細部に注目して見ることで、より深い理解が得られます。和室と鴨居の関係を知ることで、古き良き日本の文化を感じることができるでしょう。
水屋 とは 和室:水屋(みずや)とは、和室に設けられる特別な空間のことを指します。通常、水屋は茶道に関連する場所であり、お茶や茶道具を収納したり、準備したりするために使用されます。日本の伝統文化において、茶道はとても重要な位置を占めており、そのため水屋も大切な役割を果たしています。水屋は和室の一部として、畳の間と一体になっていることが多いです。水屋内には、茶碗や急須(きゅうす)、お菓子などのお茶に必要な道具がきちんと整理されています。また、水屋は他にも、食器や日用品を収納することもできます。このように、水屋は和室において非常に多機能な空間であり、使い方によってさまざまな役割を果たします。もし、和室を持つことがあれば、水屋をぜひ取り入れてみてください。伝統的な日本の生活を楽しむことができることでしょう。
和室の共起語障子:和室に使われる日本の伝統的な戸や窓で、木の枠に和紙を貼ったもので、光を通しながらも外からの視線を遮ります。
畳:和室の床材で、い草を編んで作られたマットのこと。日本の伝統的な床材として、特有の香りや質感があります。
掛け軸:室内装飾として用いるもので、絵画や書道が描かれた巻物。和室の雰囲気を高める重要なアイテムです。
座布団:和室で座る際に使うクッションのことで、もっともポピュラーな形が低い円形や四角形のものです。
抹茶:日本の伝統的な緑茶で、特に和室での茶道などで用いられます。茶室の雰囲気にもぴったりです。
欄間:和室の天井と壁の間にある装飾的な開口部で、光や空気の通り道として使われます。
浴衣:夏に着用する軽装の和服で、和室でのくつろぎ時に着ることが多いです。
茶道:日本の伝統的な茶を点てて飲む文化で、和室はその重要な舞台となります。
盆栽:小さな鉢に植えられた樹木で、和室の美しい内装を引き立てる役割を果たします。
襖:和室の間仕切りに使われる扉で、通常は木の枠に障子紙や布を貼ったものです。部屋の空間を変えるのに便利です。
和室の同意語和室:日本の伝統的な部屋で、畳が敷かれている部屋。主に床は畳で、壁は和風の装飾が施され、障子や襖などの仕切りが特徴的です。
畳の間:主に畳が敷かれた部屋のこと。和室と同じ意味で使われることが多く、和風の家具や装飾が配置されます。
和風室:和室と同様に日本の伝統的なスタイルを持った部屋を指しますが、最近では洋風の要素が取り入れられることもあります。
日本間:日本の伝統的な居住空間を指す場合があり、和室とほぼ同義とされることが多いです。特に日本の家屋に見られる独特の空間を意味します。
茶室:茶道のために特別に設計された和室。茶会の執り行いや茶道の修練に使われる、小さくて静かな空間を指します。
座敷:主に客をもてなすために使われる和室を指し、格式が高いことが多い。伝統的な日本の住宅では、座敷が特別な意味を持つことがあります。
和室の関連ワード畳:和室の床に敷かれるマットのようなもので、主にい草で作られています。日本の伝統的な床材で、柔らかで温かい感触が特徴です。
襖:和室の仕切りや扉として使用される、軽い木の枠に紙を貼ったものです。部屋の間仕切りや、出入り口を装飾する役割があります。
障子:和室に多く見られる、木枠に紙が貼られた透けるような引き戸または窓です。自然光を取り入れつつ、プライバシーを守るデザインです。
不動明王:日本の和室では、神仏を祀る場所としても使われることがあります。不動明王は、仏教の守護神で、厄除けや商売繁盛のご利益があるとされています。
床の間:和室の一部に設けられた、畳よりも高いスペースで、花や掛け軸を飾るために使われます。客人を迎える際の格式を高める重要な場所です。
茶道:日本の伝統的なお茶を点てる儀式で、和室で行われることが多いです。茶道は、和室の雰囲気や美しさを生かした文化的な活動の一つです。
和風:日本的なスタイルやデザインを表す言葉です。和室はその代表的な例で、自然素材やシンプルな美しさが特徴です。
色彩:和室では、自然な色合いや抑えたトーンが重視されます。落ち着いた雰囲気を大切にするため、彩度の低い色が好まれます。
すだれ:夏の和室で使われる、竹や草で作られた窓のカーテンです。日差しを和らげ、涼を感じるために役立ちます。
漆:和室の調度品や障子などに使われる、日本伝統の塗料です。光沢感と耐久性があり、古くから重宝されています。
和室の対義語・反対語
和室の関連記事
住まいの人気記事

1310viws

3242viws
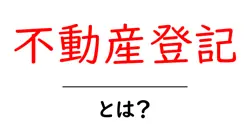
1714viws

1826viws
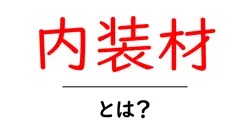
1826viws
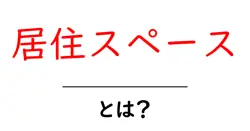
4235viws
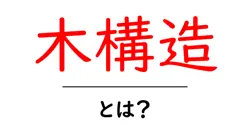
1065viws

471viws
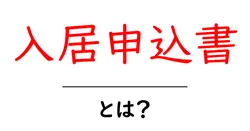
1344viws
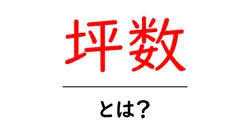
1961viws
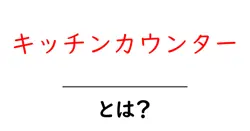
1822viws
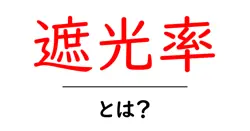
955viws
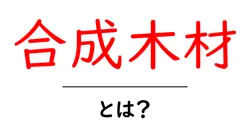
1158viws
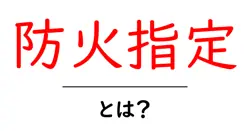
1815viws
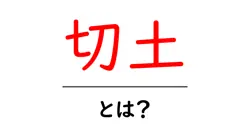
1378viws

1680viws
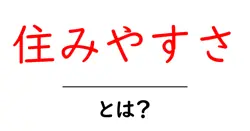
1796viws

1821viws

1283viws
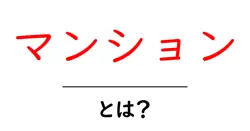
1794viws