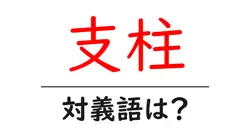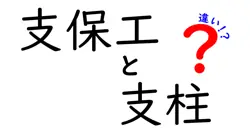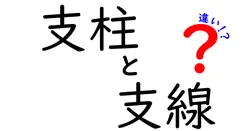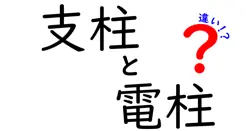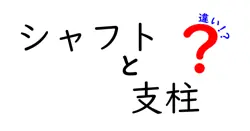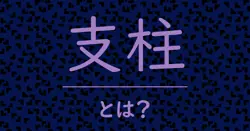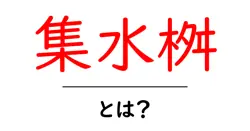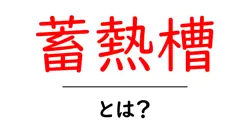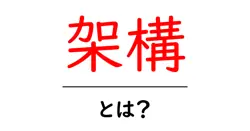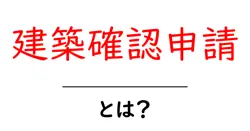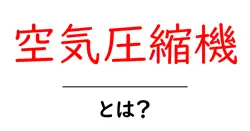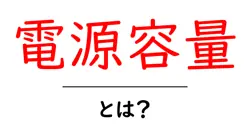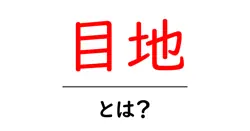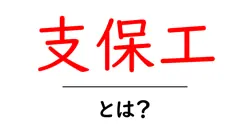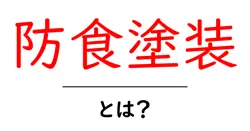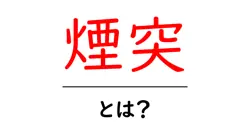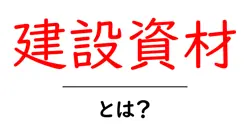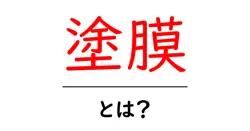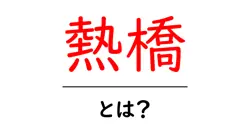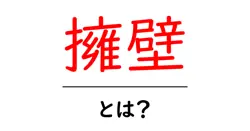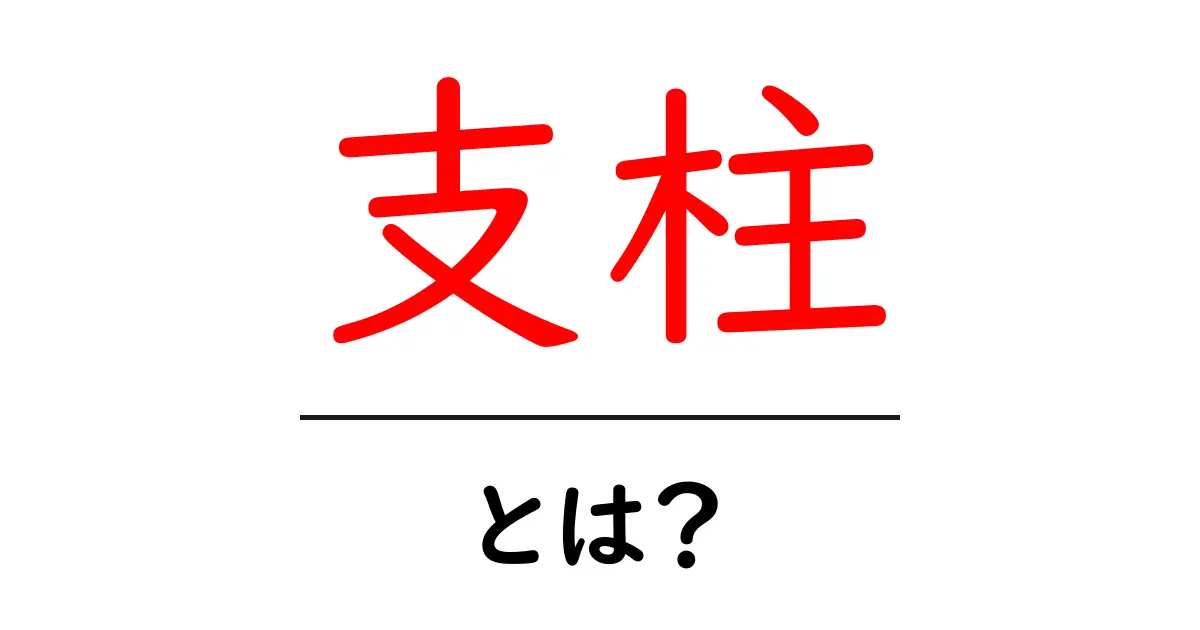
支柱とは?その基本的な意味
「支柱(しちゅう)」とは、物を支えるための柱や棒のことを指します。建物や植物、機械など、様々な場所で使われています。支柱は、重さを支えたり、倒れないようにしたりする大切な役割を果たしています。
支柱の具体的な使い方
支柱は、例えば以下のような場面で使われます。
| 使用場面 | 例 |
|---|---|
| 植物を支える | お花や野菜が成長する際、倒れないように支える支柱を使います。 |
| 建物の構造を強化する | ビルなどの建物では、柱が重さを支える大事な要素です。 |
| 物を固定する | テントやタープなどを立てる際に、支柱を使って安定させます。 |
支柱の種類
支柱には、いくつかの種類があります。以下にその一部を紹介します。
- 木製支柱 - 自然素材で作られ、植物を支えるのに最適です。
- 金属製支柱 - 強度があり、長持ちするため、建物などに使われることが多いです。
- プラスチック製支柱 - 軽量で扱いやすく、小規模な用途に適しています。
支柱が重要な理由
支柱は、物が壊れないように支える役割があります。例えば、皆さんの家や学校の教室には支柱があって、建物全体を支えていると考えてください。そのおかげで、安心して日常生活を送ることができるのです。
支柱がないとどうなる?
支柱がない場合、物が倒れたり、壊れたりする危険があります。特に、風が強い日や大雨のときには、支柱による安定が必要です。
まとめ
支柱は、物を支えるために非常に重要な要素です。多くの場面で活躍し、私たちの生活を支えています。支柱の種類や役割を理解することで、より安全で快適な生活を送ることができるでしょう。
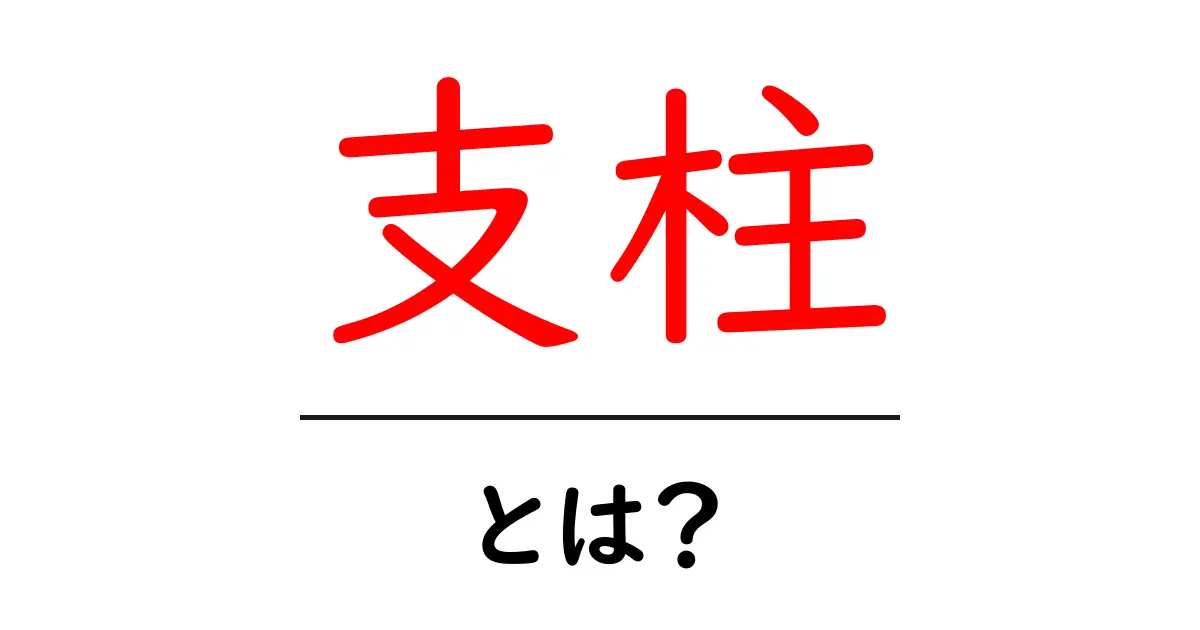
支柱 意味 とは:「支柱」という言葉は、物を支えるための柱や棒のことを指します。この支柱は、建物や植物、さらには社会の面でも使われる重要な概念です。例えば、庭に植えたトマトの木は、成長するにつれて自分の重さで倒れてしまうことがあります。しかし、そこに支柱を立てることで、しっかりと立ち上がり、元気に育っていくのです。このように、支柱は植物だけでなく、私たちの生活とも深い関係があります。私たちは支柱のように、人や物、考え方を支えることが大切です。また、支柱という言葉は比喩としても使われ、例えば「家族は私の支柱である」といった表現で愛や指導を示すことができます。支柱の意味を理解することで、私たちの生活における重要な要素を知り、感謝する気持ちを持てることにつながるでしょう。
電柱 支柱 とは:電柱(でんちゅう)と支柱(しちゅう)は、私たちが街中で見かける大切な構造物ですが、役割や使われる場所が異なります。まず、電柱は電気の送電を行うための柱です。一般的には高いもので、電線が張られていて、電気を家や工場に届ける役割を担っています。一方で支柱は、さまざまなものを支えるための柱です。例えば、道路標識やカメラ、サインボードなどを支えるために使われます。支柱は電柱と比べて低いことが多く、その用途は多岐にわたります。また、電柱は主に電気会社によって管理されていますが、支柱は自治体や企業によって管理されています。私たちの生活に欠かせない存在ですが、その役割を理解している人は意外に少ないかもしれません。今後、街を歩く際には電柱と支柱の違いにも注目してみると、いつもとは違った視点で街を楽しめるかもしれません。
支持:支柱が何かを支える意味で、支持することを指します。物体を安定させたり、力を加えたりする際に使われます。
構造:支柱が建物や構造物の一部として機能する際に関連します。全体の安定性を保つために重要な要素です。
強度:支柱が持つ耐久性や抵抗力のことを言います。重さを支えるためには十分な強度が必要です。
素材:支柱を作るために使用される材料のことです。木材、鉄、コンクリートなどさまざまな素材があります。
設計:支柱の配置や形状を決定するプロセスで、建物の安全性や機能性に直結します。
耐震:地震などの外部からの衝撃に対する支柱の耐性です。特に地震の多い地域では重要な要素となります。
バランス:支柱が全体の構造と均等に力を分散させることで、安定性を保つことを示します。
基礎:支柱を設置するための土台のことです。基礎がしっかりしていないと、支柱が正しく機能しない可能性があります。
施工:支柱を実際に設置する作業のことを指し、正しく行わなければ構造全体の安全性に影響を与えることがあります。
維持管理:支柱の機能を保つための定期的な点検や補修を含む、長期的な管理のことです。
柱:建物や構造物を支えるために立てられる縦の部分。支柱とほぼ同じ用途。
支え:物を支えたり支柱のように機能すること。物が倒れないように支えとなる部分。
サポート:英語から転用された言葉で、物を支える、助けるという意味。支柱的な役割を果たすこと。
支持:何かを支えること、もしくは支持すること。構造的な支えとしても使われる。
礎:基礎的な部分、もしくは物の土台を支えるもの。支柱と同様に、安定をもたらす役割。
支え棒:物を支えるための棒や器具。支柱と同じように、倒れないようにするために使われる。
足場:作業や建物を支えるために作る仮設の支え。特定の目的に特化した支柱的な存在。
柱:支柱とよく似た言葉で、建物や構造物を支えるための縦の構造物を指します。
支持:何かを支えたり、支柱のように安定させる行為を指します。特に、ある物体や考え方を奨励・支持することを意味します。
構造:支柱が使われる建物や物体の作りや形状のことです。支柱は構造の一部として機能します。
安定性:支柱が持つ重要な特性で、物体や構造が揺れたり崩れたりせずに安定している状態を指します。
耐荷重:支柱がどの程度の重さを支えられるかという能力を表します。耐荷重性能が高い支柱ほど、重い物体を安全に支えることができます。
補強:支柱がより強く、安定するために加える工夫や材料のことです。特に古い建物の支柱を強化するために用いられることがあります。
設計:支柱を作る際に必要な計画や構想のことです。支柱の形状や材料、配置などを決めることを指します。
工法:支柱を設置するために用いる方法や技術のことです。様々な工法があり、それぞれ特性や利点があります。
材質:支柱を作るために使われる材料のことです。木材、鉄、コンクリートなど、様々な材質が支柱に用いられます。
安全基準:支柱や建物全体が安全であることを保証するために設けられた規則や基準のことです。これに従うことで、建築物の安全性が確保されます。