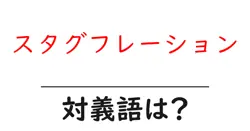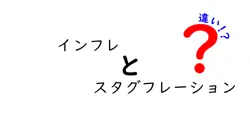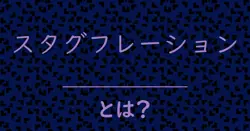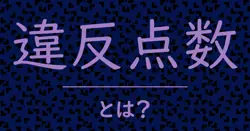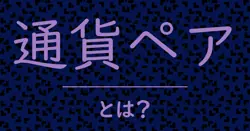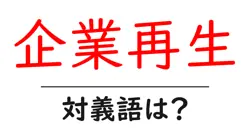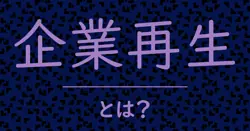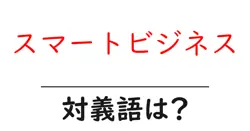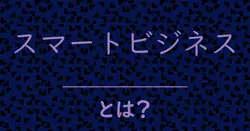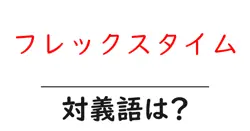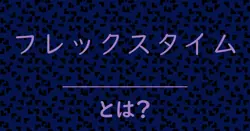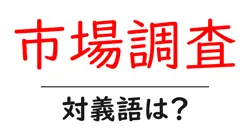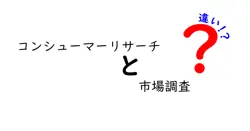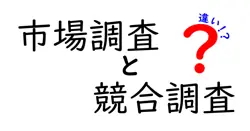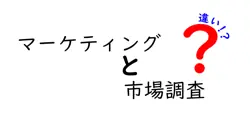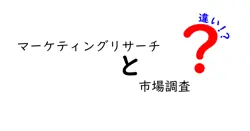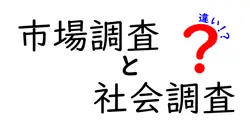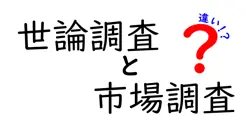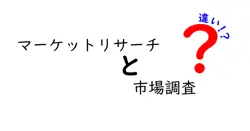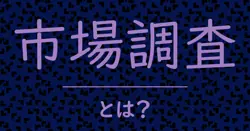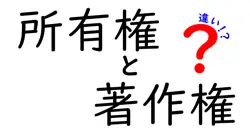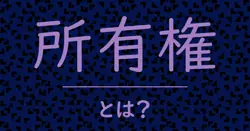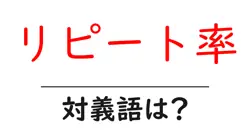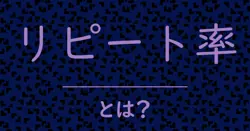スタグフレーションとは?
スタグフレーションとは、経済学用語の一つで、経済が停滞(スタグネーション)している状態でありながら、物価が上昇(インフレーション)するという現象を指します。この二つが同時に起こるため、経済にとって非常に厄介な状況です。一般的に、経済が成長しているときには物価も安定しているのが普通ですが、スタグフレーションはそれに逆行する状態です。
スタグフレーションの原因
スタグフレーションの原因は複数ありますが、主なものは以下の通りです。
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 供給ショック | 原材料やエネルギーの価格が急激に上昇すること |
| 政策の失敗 | 貨幣政策や財政政策が適切でないこと |
| 需要の低下 | 消費者の購買意欲が減少した結果、経済が停滞すること |
スタグフレーションの影響
スタグフレーションが発生すると、次のような影響があります。
- 失業率の上昇:経済が停滞することで企業は人員削減や雇用停止を進め、失業者が増える傾向にあります。
- 実質所得の低下:物価が上昇する中で、給料が上がらないことが多いため、実質的に手に入るものが少なくなります。
- 投資の停滞:経済の不安定さから企業は新たに投資を行いづらくなり、将来の成長が見込めなくなります。
スタグフレーションの対策
スタグフレーションに対処するためには、経済政策として以下のようなアプローチが考えられます。
まとめ
スタグフレーションは、経済の成長が停滞しながら物価が上昇する厄介な現象です。さまざまな要因が絡まり合って発生し、私たちの生活にも大きな影響を与えます。そのため、経済対策を講じることが重要です。
スタグフレーション とは 簡単に:スタグフレーションという言葉は、経済の状態を表すものです。これは、「スタグネーション」と「インフレーション」という二つの言葉が合わさったものです。「スタグネーション」は経済が成長せず停滞している状態を指し、「インフレーション」は物価が全体的に上がっていくことを意味します。つまり、スタグフレーションは、経済成長が停滞しているのに、物価が上がるという厄介な状況です。例えば、ご飯や服の値段が上がっているのに、働いても給料が増えない場合、私たちの生活は難しくなります。このような状況になると、みんなが買うものを減らしたり、お金を使わなくなったりするため、さらに経済が悪化する恐れがあります。スタグフレーションは歴史的に1980年代にあったような時期に見られることが多いです。これを理解しておくことは、経済の変化を知る上で大切です。
インフレーション:物価が継続的に上昇する現象です。購買力が下がるため、同じお金で買える商品の量が減少します。
景気後退:経済の成長が鈍化し、企業の売上や投資が減る現象です。失業率が上昇することもあります。
失業率:働きたいのに仕事が見つからない人の割合を示す指標です。スタグフレーション時には失業者が増えることが一般的です。
経済政策:政府や中央銀行が経済を安定させるために実施する方針や対策です。スタグフレーション対策には特に工夫が必要です。
需給バランス:売り手と買い手の関係を示す概念で、供給が需要に対してどのような状態にあるかを表します。これが崩れるとスタグフレーションが発生することがあります。
投資:資金を使って利益を得るための行動です。スタグフレーションの状況では、企業の投資活動が減少し、さらに経済が悪化するリスクがあります。
利上げ:金利を上げることです。スタグフレーションの際、インフレーション抑制のために行われることがありますが、景気をさらに冷やすリスクもあります。
物価上昇率:物価がどの程度上昇しているかを示す指標です。スタグフレーションではこの率が高いまま続くことが問題となります。
景気停滞:経済成長が鈍化している状態を指します。スタグフレーションに近い概念で、経済が成長しない中で物価が上がる状況を示します。
高インフレーション:物価が急激に上昇する現象を指します。スタグフレーションでは、高いインフレ率とともに経済成長が停滞するため、このワードが使われます。
景気後退:経済の成長がマイナスに転じることを指し、一時的な経済停滞とは異なり、長期的に経済が縮小する状態を表します。
ドルショック:1970年代の米国に見られたような、大規模な経済危機を通じてインフレとスタグフレーションが兼ねて発生した現象を指します。
コストプッシュインフレ:原材料費や労働力コストの上昇により、企業が価格を上げざるを得ない状況を意味します。この現象もスタグフレーションの一因となることがあります。
インフレーション:物価が持続的に上昇する現象で、貨幣の価値が下がり、同じ金額で買える商品の量が減少することを指します。
デフレーション:物価が持続的に下落する現象で、通貨の価値が上がることにより、同じ金額で買える商品の量が増加することを指します。
失業率:労働力人口に対する失業者の割合を示す指標で、経済の健康状態を測る重要な要素です。スタグフレーションでは、通常、失業率が高まります。
経済成長:国の経済がどれだけ成長しているかを示す指標で、通常はGDP(国内総生産)の増加によって測定されます。スタグフレーションの状態では、経済成長が停滞します。
フィリップス曲線:インフレーションと失業率の関係を示す理論で、通常はインフレーションが高いと失業率が低い逆相関の関係があるとされますが、スタグフレーションではこの理論が当てはまらなくなります。
供給側ショック:原材料やサービスの供給が突然減少することで経済に悪影響を及ぼす状態で、スタグフレーションの原因となることがあります。
金融政策:中央銀行が利子率や通貨供給量を調整することで経済をコントロールする手段で、スタグフレーションに対処する際に難しい判断を迫られます。
財政政策:政府が公共支出や税金を通じて経済に影響を与える政策で、スタグフレーションに対して効果的な手段となることがあります。
コストプッシュインフレーション:生産コストの上昇が原因で物価が上がる現象で、スタグフレーションの要因の一つです。原材料価格の高騰などが例です。
需要プルインフレーション:需要の増加が原因で物価が上がる現象で、通常の経済成長局面で見られますが、スタグフレーションでは見られません。