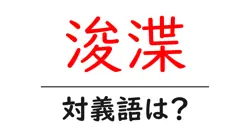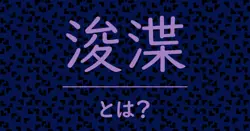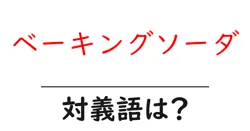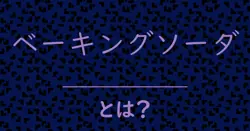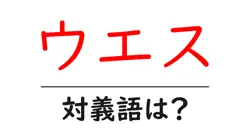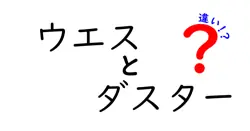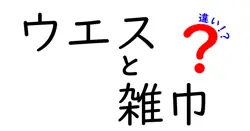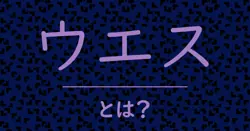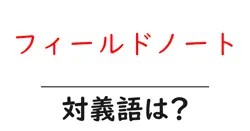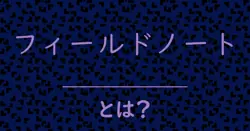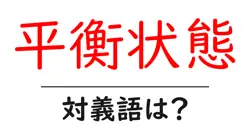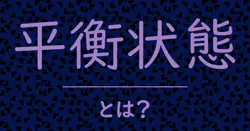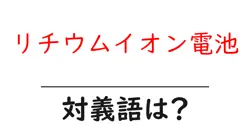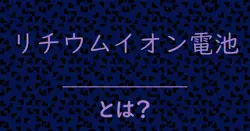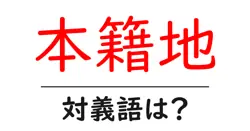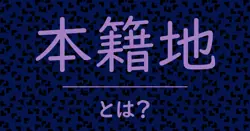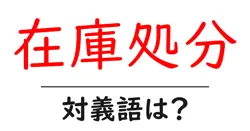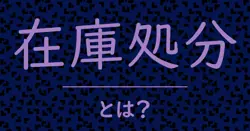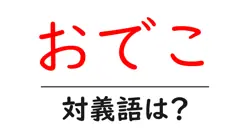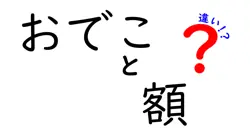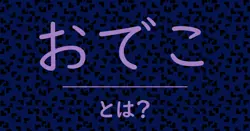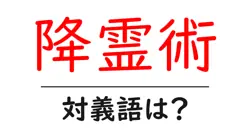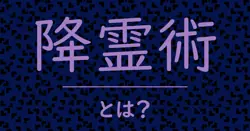浚渫(しゅんせつ)とは?
浚渫(しゅんせつ)は、主に川や湖、港などの水域の底にたまった砂や泥を取り除く作業のことを指します。この作業は、水の流れを良くし、水位を下げることで洪水を防いだり、漁業を助けたり、船が安全に通れるようにするために必要です。
浚渫が必要な理由
水域にたまった泥や砂は、さまざまな問題を引き起こします。たとえば、次のような理由が挙げられます。
- 洪水対策:浚渫を行うことで水の流れがスムーズになり、洪水のリスクを下げます。
- 生態系の保護:浚渫によって水質が改善され、魚や水生植物が育ちやすくなります。
- 交通路の確保:港や河川が浚渫されることで、大型船が航行できるようになります。
浚渫の方法
浚渫は一般的に以下のような方法で行われます。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 浚渫船を使用 | 特別な船を使って、泥を吸い上げて運び出します。 |
| 手作業 | 小さな水域では、人が手作業で泥を取り除くこともあります。 |
浚渫の影響
浚渫は、一時的に水域の様子が変わることがありますが、長期的には生態系改善や洪水対策に貢献します。しかし、過度な浚渫は逆に生態系を壊すこともあるため、適切な方法で行うことが重要です。
まとめ
浚渫は、水域の環境を保つために欠かせない作業です。これによって、洪水を防ぎ、生態系を守り、交通を円滑にすることができます。私たちの生活と自然環境を守るために、浚渫の重要性を理解して活用していきましょう。
土木 浚渫 とは:土木浚渫(どぼくしゅんせつ)とは、主に河川や湖岸などの水辺の土を取り除く作業のことを指します。普段は見えない水中で行われるので、あまり目にすることはないかもしれませんが、この作業はとても大切です。浚渫を行うことで、水の流れを良くしたり、洪水を防いだりすることができます。例えば、雨が降った時に川の水があふれないようにするためには、川底にたまった砂や泥を取り除くことが必要です。また、船が通るための水深を確保するのにも使われます。もし浚渫をしないでおくと、周りの環境や生態系に悪影響を与えることがあります。さらに、浚渫には丁寧に計画を立てながら行うことが求められます。現場の調査や、周辺環境への配慮も必要です。このように、土木浚渫は私たちの生活や自然環境を守るために欠かせない作業なのです。理解を深めることで、これからの環境保護やインフラ管理についての意識も高まるかもしれません。
土砂 浚渫 とは:土砂浚渫(どしゃしゅんせつ)とは、川や湖、港などの水域にたまった土砂を取り除く作業のことです。この作業は、使う場所の水位を調整したり、流れをスムーズにしたりするために行われます。去年、大雨が降ったあと、いろいろなところで土砂浚渫が行われたのを見かけたかもしれません。土砂やゴミがたまると、水の流れが悪くなり、氾濫や水害の原因になります。そうした危険を防ぐために、こうした作業がとても重要なのです。また、土砂浚渫は漁業にも関係しています。水底が整えられることで、魚が暮らしやすい環境が作られ、漁業のために良い影響を与えます。しかし、土砂浚渫を行う際には、生態系にも注意が必要です。無理に土砂を掘り起こすと、そこに住む生物に悪影響を与えることがあります。そのため、専門家が計画を立てて、環境に配慮しながら作業が行われることが求められます。皆さんも、土砂浚渫が私たちの生活に大切な役割を果たしていることを知っておくと良いでしょう。
土砂:水中や岸に堆積した泥や砂のこと。浚渫作業で取り除かれることが多い。
水深:水の深さのこと。浚渫を行うことで水深が深くなる場合がある。
環境保護:自然環境を守ること。浚渫作業は生態系に影響を与えるため、環境保護の観点が重要。
堆積物:地面などに積もった物質のこと。浚渫では堆積物を取り除く。
浚渫船:浚渫作業を行うための船。特別な装置を備えた船が使われる。
河川:川のこと。浚渫は河川の水流を改善するために行われることがある。
運搬:物を移動させること。浚渫で取り除いた土砂は運搬される。
工事:公共事業や建設作業のこと。浚渫は工事の一環として行われる。
河床:河川の底の部分。浚渫によって河床が変更されることがある。
調査:事実を確かめるための調べ。浚渫作業前には調査が必要。
安全対策:事故を防ぐための手段。浚渫作業では安全対策が重要。
施行例:実際に行った浚渫作業の具体例。参考になる情報。
地域振興:地域の発展を促進すること。浚渫は地域振興に貢献する場合がある。
掘削:土や砂を掘り起こすこと。特に、河川や湖の底を掘り進める行為を指します。
掘り起こし:土や砂などを掘り出して露出させること。浚渫のプロセスにおいて、大きな石や障害物を取り除くことを含む場合があります。
清掃:水中にたまったゴミや沈殿物を取り除くこと。浚渫作業の一環として行われる場合があります。
浚渫:水域の底や岸から土砂や沈殿物を取り除く作業。主に港や河川の水深を確保するために行われる技術で、船舶の航行を安全にすることが目的です。
水深:水面から水底までの距離。この距離は浚渫作業によって変更されることがあり、船舶が安全に通過できるようにするために重要です。
土砂:土や砂のこと。浚渫では、河川や港湾に溜まった土砂を取り除く作業が行われます。それにより水質改善や生態系の保全も期待できます。
浚渫機:浚渫作業を行うための専用機械。バケットや吸引装置を使用して土砂を取り除き、船舶が通行できるようにします。
環境影響評価:浚渫作業が生態系や周辺環境に与える影響を評価するプロセス。作業を実施する前に行われ、必要に応じて改善策を講じることが求められます。
河川工事:河川の改修や整備を目的とした工事全般。浚渫は河川工事において重要な工程の一つであり、水流を改善したり、洪水を防止するために行われます。
堤防:水域の周囲を囲むための防御壁。浚渫により水深を確保することで、堤防が効果的に機能し、Flood riskを軽減することができます。
生態系:生物とその環境が相互作用するシステム。浚渫作業は生態系に影響を与えることがあるため、慎重な配慮が必要です。
資源:経済活動や人間生活に利用される材料またはエネルギー源。浚渫によって取り除かれた土砂は、建設資材や土地造成に再利用されることがあります。
浚渫の対義語・反対語
浚渫工事とは?特徴や方法をご紹介します - 東日本海洋建設株式会社
浚渫(しゅんせつ)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説
浚渫(しゅんせつ)工事とは?種類・工法・費用・許可について解説