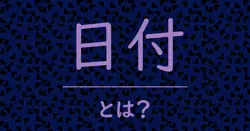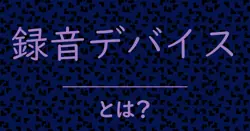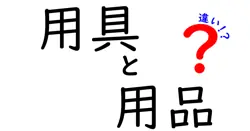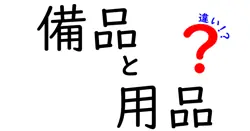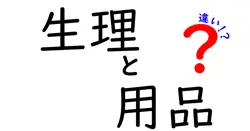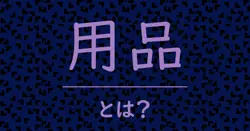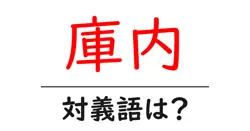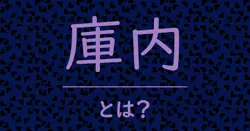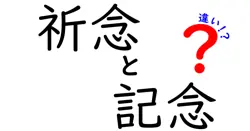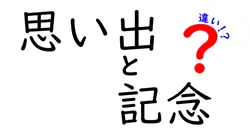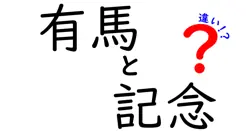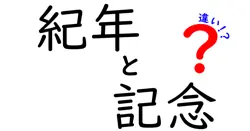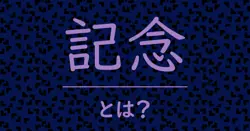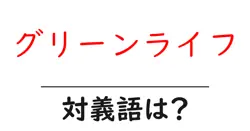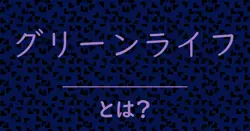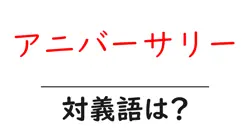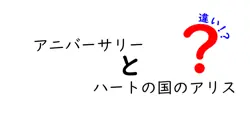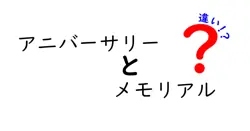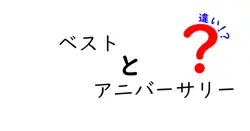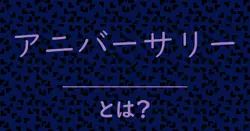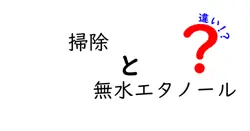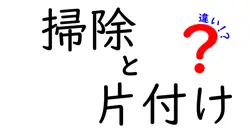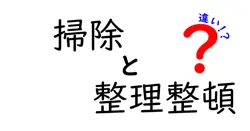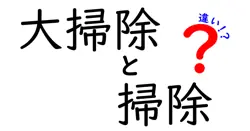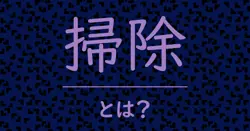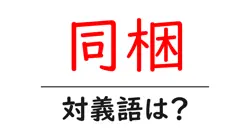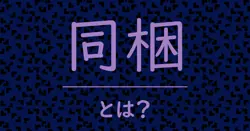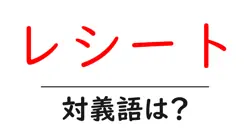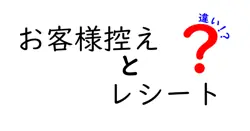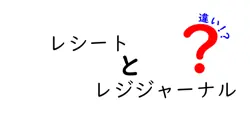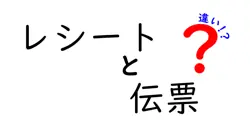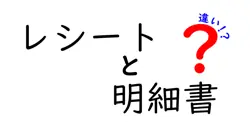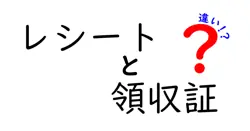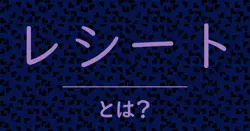「日付」とは何か?
「日付」という言葉は、私たちの生活の中でとても重要な役割を果たしています。日付は、特定の日を示す言葉で、たとえば「2023年10月1日」というように使われます。このように、日付は日常生活のさまざまな場面で利用され、私たちの時間を管理し、計画を立てるうえで欠かせないものなのです。
日付の使い方
日付は、カレンダーやスケジュール、手紙や文書などの中でも頻繁に使われます。たとえば、学校の行事や友達との約束をする時、日付を確認することで「明日」「来週」「今月」といった時間の感覚が生まれます。
日付の形式
日付にはいくつかの形式があります。一般的な日本の形式は「YYYY年MM月DD日」で、たとえば「2023年10月01日」があります。この形式では、数字の前に「年」「月」「日」を付けて、わかりやすく表示します。また、英語圏では「MM/DD/YYYY」の形式がよく使われます。
| 形式 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
| 日本式 | 2023年10月01日 | 年、月、日を漢字で表記 |
| 英語式 | 10/01/2023 | 月、日、年をスラッシュで区切る |
日付と時間の関係
日付は時間と密接に関わっていて、たとえば「2023年10月1日午前10時」というように、日付に時間を組み合わせて使うこともあります。このようにして、特定の瞬間を明確に示すことができます。
また、日付を使うことで、過去の出来事を振り返ったり、未来の予定を考えたりすることが可能になります。たとえば、「去年の10月1日はどんなことがあったかな?」と思い出すためには、日付がとても役立ちます。
まとめ
日付はただの日付だけでなく、私たちの生活における時間の流れを理解し、把握するための重要なツールです。日常生活の中で「日付」を意識することで、予定を立てたり、思い出を共有したりすることができます。これからも日付の重要性を理解して、うまく活用していきましょう!
dd とは 日付:私たちの日常生活では、日付を使う場面がたくさんあります。その中で「dd」という言葉を耳にすることもあるかもしれません。「dd」というのは、日付を表すための記号の一つで、特にプログラミングやデジタルデータの分野でよく使われます。例えば、「dd」は「day(日)」を指すことが多く、1日から31日までの数字が使われます。これを使うことで、より正確に日付を示すことができるのです。たとえば、「2023年06月05日」を「2023-06-dd」と記載することが可能です。この形式を使うことで、特にコンピューターやデジタルシステムとやり取りする際に混乱を防ぐ役割があります。また、「dd」はファイル操作やバックアップなどのコマンドでもよく使われます。日付の書き方や意味がわかることで、これからの学習や実務に役立てることができるでしょう。難しい用語は使わず、日常に通じる形で考えることが大切です。日付のことを知ることで、もっと便利でスムーズな生活を送れるかもしれません。
mm とは 日付:日付を表すときに、私たちはよく「mm」という言葉を使います。「mm」は、月を表すための略語で、特に数字で月を示すための記号です。たとえば、1月は「01」、2月は「02」となります。日付を表す際、通常は「yyyy-mm-dd」という形式が使われます。ここで「yyyy」は年を、「mm」は月を、「dd」は日を示します。この形式は、特にコンピュータやデータベースで扱う際に非常に便利です。なぜなら、数字で並べると自動的に日付の順番が整理されるからです。例えば、「2023-03-15」は、2023年3月15日を示し、この順番だと簡単に新しい日付と古い日付を見分けられます。日常生活でも、例えば旅行の計画を立てたり、予定を管理したりする際に、この「mm」の使い方を知っておくと役立ちます。だから、日付の記載をする際には、この「mm」の意味と使い方を理解して、正確に日付を表現できるようにしておきましょう。
日付 utc とは:日付 UTC とは、協定世界時(Universal Time Coordinated)のことを指します。UTCは、地球全体で共通の時間基準として使われており、特に国際的な通信や交通、インターネットサービスで重要な役割を果たしています。UTCは、時間の計測において地球の自転を基にしており、世界中の時間を統一するために考案されました。たとえば、日本はUTCよりも9時間進んでいるため、日本の時間はUTC+9時間という形で表現されます。これにより、異なった地域や国にいる人々が同じ瞬間を共有することができます。UTCは、夏時間(昼間の時間を長くするために時計を進める制度)とも関係があり、異なる地域で時間の扱いが変わることに留意が必要です。日常生活では、Longitudeを基にした時刻の異なりを理解するためのポイントとしても役立ちます。このように、UTCはコミュニケーションやビジネスを円滑に進めるための重要な要素と言えるでしょう。
日付 yyyy とは:「日付 yyyy」という表現を見たことがあるかもしれませんが、これは特定の年を表す時に使われる言い方です。ここでの「yyyy」は、年を4桁で表す形式を指します。たとえば、2023年の場合、yyyyは「2023」となります。このように書くことで、日付がどの年のことを指しているのかを明確にすることができます。また、これに月や日を加えることで、完全な日付を作ることができます。たとえば、「2023年5月1日」は、「yyyy-mm-dd」の形式で「2023-05-01」と表すことができます。この形式は、コンピューターやプログラムで日付を扱うときによく使われます。簡単に言えば、「日付 yyyy」は、年を明確にするための便利な方法なのです。これを使うことで、混乱を避けて正確な情報を伝えることができますので、ぜひ覚えておいてください!
日付 シリアル値 とは:「日付 シリアル値」という言葉は、特にパソコンやエクセルなどで使われることがよくあります。簡単に言うと、日付を数字で表したものが「シリアル値」です。例えば、2023年1月1日はシリアル値で「44818」となります。これは、1900年1月1日から数えて何日目かを示しています。このように、シリアル値を使うことで、エクセルなどのソフトで日付を計算したり、並べ替えたりするのが簡単になります。また、シリアル値は時間の計算にも使われます。時刻もシリアル値として表現されることがあり、これにより時間差を簡単に計算できるようになります。日付をシリアル値として扱うことで、日付の処理がスムーズになり、ビジネスや学びの場でも効率的に作業ができるのです。日常生活の中で、日付の管理や計算をするときに、このシリアル値の理解が役立つでしょう!
日付 昇順 とは:「日付 昇順」とは、日付のデータを古い順から新しい順に並べることを指します。この方法では、一番古い日付が最初に来て、一番新しい日付が最後にくるため、時系列でのデータ確認が簡単になります。この並べ方は、特にスプレッドシートやデータベースでよく使われる技術です。たとえば、日記をつけるときに、最初の日付から順番に内容を見返したい場合、「日付 昇順」にすることで、過去の出来事を簡単に振り返ることができます。この方法を使うことで、情報が整理され、混乱を避けられる上、データの分析や報告もスムーズに行えるのです。「日付 昇順」の操作は、コンピュータやスマートフォンのアプリでも簡単に行えるため、誰でも手軽に利用できます。ぜひ、あなたもこの便利な技術を使って、日付に基づくデータを効果的に管理してみてください。
日付 現在 とは:「日付 現在」とは、今の日時を表すための言葉です。私たちが普段使っているカレンダーや時計を使って、日付や時間を確認することができます。例えば、今日は何日なのか、今は何時なのかを知るために、「日付 現在」という言葉がよく使われます。日付は、年、月、日で表され、現在の時刻は時、分、秒で表されます。私たちが生活する上で、日時や時間を知っていることは非常に重要です。学校や仕事、友達との約束など、時間を守ることが大切だからです。また、インターネットを使っていると、更新された日付や時間が表示されることがありますが、それも「日付 現在」を知るために役立っています。このように、「日付 現在」という概念は、私たちの生活に深く関わっており、時間を意識することで計画的に行動できるようになります。これからは、日付や現在の時間を意識してみると良いでしょう。
日付 降順 とは:「日付 降順」という言葉は、データを日付の古い順番ではなく、新しい順番に並べることを指します。例えば、あるイベントの開催日を整理したいとき、最も最近のものを上に、古いものを下に並べるのが「日付 降順」です。 例えば、2023年1月1日、2022年12月25日、2022年10月1日の3つの日付があるとします。「日付 降順」に整理すると、2023年1月1日が一番上にきて、次に2022年12月25日、そして2022年10月1日が最後にきます。このように整理することで、最新の情報をすぐに確認できるため、多くの場面で使われています。 特に、データベースやExcelでの作業をする際に、「日付 降順」で並べることが多いです。これを知っておくと、業務や学校の作業が効率的になり、必要な情報を見つけやすくなりますよ。もし、逆に古い日付から並べたい場合は「日付 昇順」という言葉を使います。これを使いこなすことで、データ整理のスキルを上げることができるでしょう。
日付け とは:「日付け」という言葉は、物事が起こったり、予定されている日を示す言葉です。例えば、学校の行事や友達との約束、誕生日など、私たちの日常生活の中でたくさん使われています。しかし、一体「日付け」とはどのような意味を持っているのでしょうか?まず、「日付け」は年や月、日を組み合わせて示します。たとえば、2023年10月1日というのは、2023年の10月の1日を指します。このように日付けによって、私たちは特定の日を正確に示すことができます。また、日付けはスケジュールを整理するのにも役立ちます。カレンダーに日付けを書き込むことで、重要な予定を忘れずに管理することができます。これは、中学生の思春期の頃から始める勉強の一環とも言えます。友達との約束や部活動のスケジュール、テストの日付など、日付けを押さえることで、学校生活がもっとスムーズになります。日付けは単なる数字の組み合わせではなく、私たちの日常をサポートしてくれる大切な概念です。
カレンダー:日付を確認するための道具で、月ごとに分かれたページに日にちが書かれている。予定やイベントを管理するのに役立つ。
スケジュール:日付ごとの予定や活動を整理したもの。仕事やプライベートの計画を効率的に進めるために使う。
日付変更線:地球上で日付が変わる境界線。東側にいる人が日付を1日早く、逆に西側にいる人が1日遅くなる場所。
記念日:特定の日付に意味のある出来事を祝う日。誕生日や結婚記念日など個人にとって重要なもの。
タイムスタンプ:特定の日時を記録するための印。デジタルデータやブログ記事において、公開日時や更新日時を示すのに使われる。
西暦:キリスト教の伝承に基づいた年の数え方。多くの国で使われている日付の表記方法。
和暦:日本の伝統的な年の数え方で、元号に基づく。明治、大正、昭和など、天皇の即位により変わる。
収穫日:農作物を収穫する日付。農業において重要な予定で、作物の成熟度や天候に影響されることが多い。
日時:特定の日と時刻を合わせた表現。例えば、2023年10月1日 12:00のように、日と時間を併せて示すことができます。
日:カレンダー上の1日を指し、具体的な日付を示します。例えば、1月1日や2月14日のように、特定の日を表します。
日付:カレンダー上の特定の日を指し、通常は年、月、日で構成されます。例えば、2023年10月5日などがこの例です。
年月日:年、月、日を組み合わせた表現で、正式な日付の書き方の一つです。例としては、2023年10月5日となります。
カレンダー日:カレンダーに記載されている日付を指します。特定のイベントや予定が記載されている場合もあります。
タイムスタンプ:特定の時間が記録された印のことで、文書やデータの作成・更新された日時を示すのに使われます。
日付情報:特定の日付に関するデータや情報を指します。イベントの日付や締切日など、さまざまな文脈で使われます。
時日:特定の時間、つまり「時」と「日」を合わせた言葉です。特に古典的な文脈で使われることが多い表現です。
カレンダー:日付を管理するための道具で、日々の予定やイベントを視覚的に確認することができます。
曜日:1週間を構成する日々の名称。月曜日から日曜日までの7日間を指します。
祝日:国家や地域で定められた特定の日で、一般的には休日として扱われます。
年号:特定の元号や西暦など、日付を表すための体系的な数字や名称のことです。
登録日:特定のデータやイベントが公式に記録された日付を指します。例えば、ブログ記事が公開された日など。
締切日:特定の提出や作業の終了が要求される日付のこと。プロジェクト管理などで重要です。
発行日:書類や出版物が公式に発行された日付のこと。新聞や雑誌に記載されています。
過去日:現在の日付よりも前の日付のこと。歴史や過去の出来事を論じる際によく使われます。
未来日:現在の日付よりも後の日付のこと。予定や計画について話すときに使います。
ISO 8601:日付と時間を表すための国際的な標準規格で、特にYYYY-MM-DDという形式がよく使用されます。
日付の対義語・反対語
該当なし