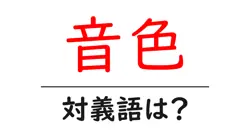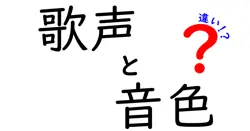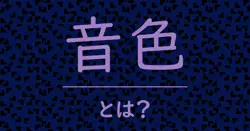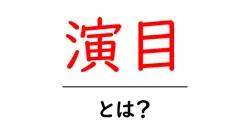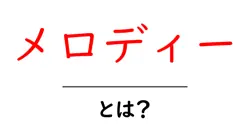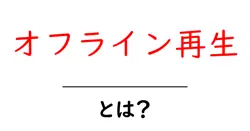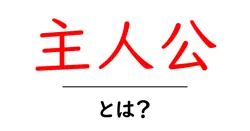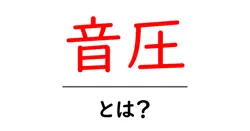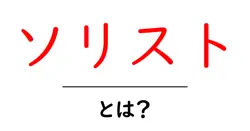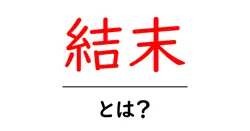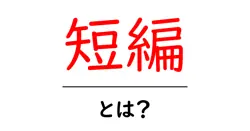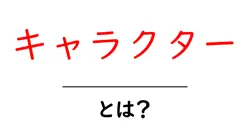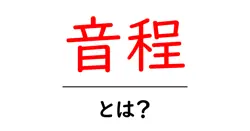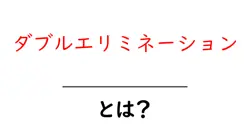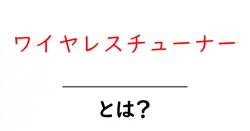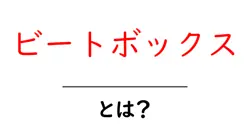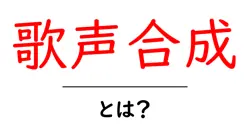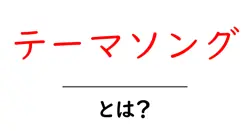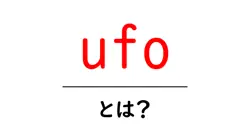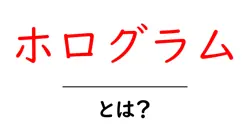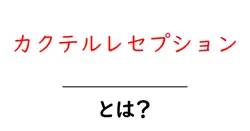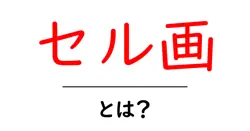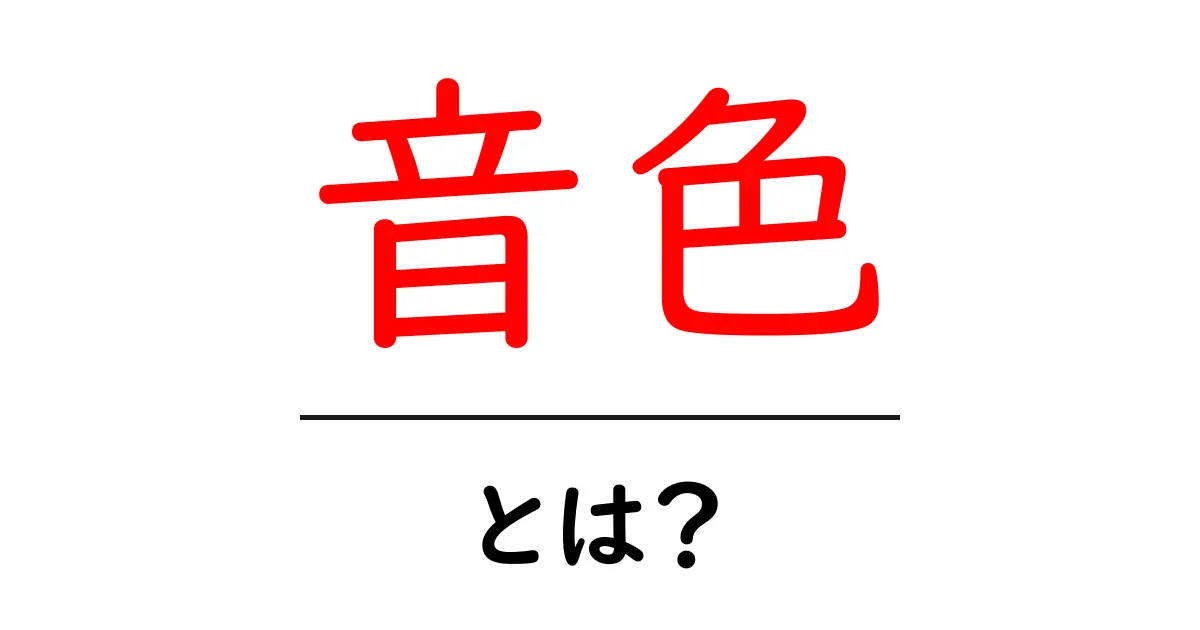
音色とは?音楽の奥深い魅力を探る
音色(おんしょく)という言葉、聞いたことがありますか?音楽を聴いているときに、楽器や声によって生まれる「響き」のことを指します。具体的には、同じ楽器で演奏しても、弾く人や技法によって全く違った印象を受けることがあります。それが音色の不思議なところです。
音色の重要性
音楽において音色はとても重要です。例えば、ギターの音色とピアノの音色は全然違いますよね。同じメロディでも、音色が変わると別の曲に聞こえることもあります。音色が持っている特有の温かさや冷たさ、明るさや暗さは、私たちの心にさまざまな感情を呼び起こします。
音色の種類
音色には大きく分けていくつかの種類があります。以下の表は、代表的な楽器の音色の例を示しています。
| 楽器 | 音色の特徴 |
|---|---|
| ピアノ | 柔らかく豊かな響き |
| ギター | アコースティックは温かみがあり、エレキはシャープ |
| サックス | 艶やかで表現力が豊か |
| バイオリン | 高音が透き通り、深い音色がある |
音色と感情
音色は私たちの感情に強く影響します。明るい音色は元気づけてくれますし、逆に暗い音色は悲しい気持ちにさせることもあります。音楽という芸術を感じるうえで、音色をうまく理解することが大切です。
音色は、私たちが音楽を通じて感じる一つの「色」のようなもの。この色を知ることで、音楽をもっと楽しむことができるでしょう。
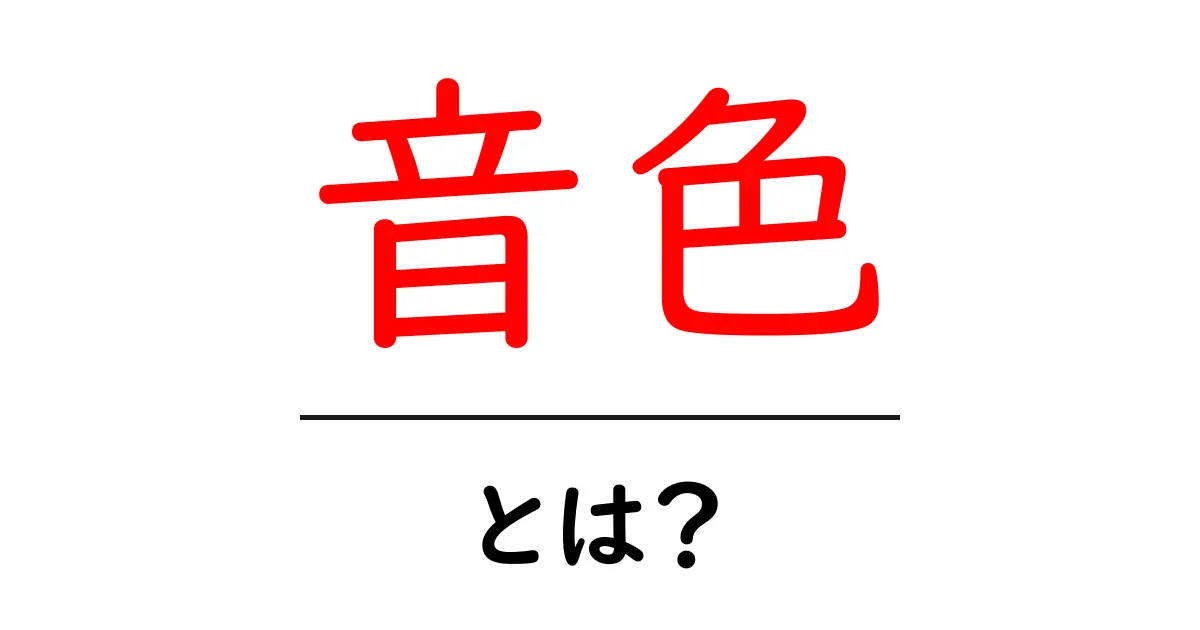
音色 とは 小学校:音楽の授業では、いろいろな楽器を使って音を楽しむことがあります。その中で「音色」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。音色とは、音が持つ独自の特徴や質のことで、楽器や声によって全く異なります。たとえば、ピアノの音とギターの音を比べてみると、どちらも音楽の一部ですが、その響きや感じ方はまったく違いますね。この違いが「音色」と呼ばれるものです。音色は、楽器の素材や構造、演奏の仕方、さらには演奏者の表現力によって変わります。音楽を聞いているときに、その曲が持つ感情や雰囲気を感じることができるのは、音色のおかげです。小学校では、いろいろな楽器の音色を楽しみながら、音楽の世界を広げていきましょう。ぜひ、自分の好きな音色を見つけて、音楽の授業をもっと楽しんでください!
音色 とは 簡単に:音色(おんしょく)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?音色は、私たちが楽器や声の音を聞いたときに感じる「その音の特徴」を指します。たとえば、同じ音の高さでも、ピアノで弾いた音とギターで弾いた音では、全く違った感じがしますよね。この違いこそが、音色の正体です。 音色は「音の質」とも言えます。音を出す楽器や声の違い、さらには弦の素材や形、大きさ、演奏者の技術など、さまざまな要素が音色に影響を与えます。実際、音楽を楽しむとき、私たちは音色の違いを敏感に感じ取ることができるのです。 例えば、温かい音色の楽器、冷たい音色の楽器、高い音色、低い音色など、さまざまな種類があります。また、同じ楽器でも弾き方によって音色が変わることもあります。このように、音色を理解することで、音楽の楽しみ方が広がります。音楽を聴くとき、今まで以上に楽器の音色に注目してみてください。新しい発見があるかもしれませんよ!
音色 とは 音楽:音色(おんしょく)とは、音楽で使われる音の「個性」を表す言葉です。同じ音の高さでも、楽器や声によって異なる音が聞こえます。この違いを作り出すのが音色です。たとえば、ギターの音とピアノの音が違うのは、同じメロディーでも楽器自体が持つ特性に基づいています。この特性には、楽器の材質や形、音を出す方法(弦を引いたり、鍵盤を叩いたり)などが影響します。音楽を聴くとき、私たちはさまざまな音色を感じ取ります。これにより、曲の雰囲気や感情も変わってきます。音色は、音楽にとって非常に大切な要素であり、作曲家や演奏者は、音色を工夫して曲をより豊かに表現しようとします。これが音楽の楽しさの一つでもあります。音色に注目して音楽を聴くと、新たな発見があるかもしれません。
音質:音色の特性やクオリティを指し、楽器や声の表現力や音のクリアさに関連します。
楽器:音色を生み出す道具で、ギター、ピアノ、バイオリンなど、さまざまな楽器が異なる音色を持っています。
メロディ:音の連なりや高低の変化を伴い、音色が独特のフィーリングを与える音楽の要素です。
ハーモニー:複数の音が同時に鳴ることによって生まれる音の組み合わせで、音色との組み合わせが楽曲の雰囲気を作ります。
トーン:音の高低や響きの特性を表現する言葉で、音色に深く関わっています。
アコースティック:自然な音や生音を指し、エレクトロニックな音ではなく、楽器のオリジナルの音色を重視します。
エフェクト:音色を変化させるために使用する音響効果や加工技術を指し、リバーブやディレイなどがあります。
ダイナミクス:音の強弱や音量の変化を表し、音色にも大きな影響を与える要素です。
フィルター:特定の周波数を強調またはカットすることにより、音色を調整するための道具や技術を指します。
音域:楽器や声が出せる音の範囲を示し、音色の多様性を生み出す要因です。
倍音:音色の複雑さに寄与する、基本音に対する追加的な周波数成分を指します。
音色(ねいろ):楽器や声などが発する音の特性を表す言葉で、音の質感や特徴を示します。例えば、弦楽器と管楽器では音色が異なるため、それぞれの楽器の個性を感じることができます。
トーン:音の高さや強さに関連した音の特定の特性を指し、特に音楽においては和音や音の響きを指すことが多いです。
音質(おんしつ):音の性質や特徴を示す言葉で、清らかさ、丸み、明瞭さなどが含まれます。音楽や音響において重要な要素です。
ハーモニー:複数の音が組み合わさって響く際の調和のこと。音色に深みや豊かさを与えます。
キャラクター:音の個性や特徴を示す言葉で、特に楽器の音色の個々の特長や印象を指して使われます。
フィーリング:音が持つ感情的な質のこと。音色によって聴く人に与える印象や感情が変わることを示します。
響き(ひびき):音が空間で伝わっていく際の広がりや効果を指します。音色によって響き方が異なるため、音楽の印象に大きな影響を与える要素です。
音色(おんしょく):音の特性や特徴を示す言葉で、楽器や声が出す音の質や雰囲気を表現します。音の高低や強さ、響きなどが影響し、同じ音でも異なる印象を与えることがあります。
音質(おんしつ):音の明瞭さやクオリティに関連する概念です。録音や再生機器、楽器などから出る音の良さや悪さを指し、クリアさや深み、ノイズの有無などが音質を決定します。
ハーモニー:異なる音が組み合わさった時に生まれる音の調和を指します。音色が豊かになることや、和音を形成することによって、音楽に深みや感動を与えます。
ダイナミクス:音の強弱、つまりボリュームの変化を指します。音色の特徴を引き立てる要因となる重要な要素で、強い音と弱い音のコントラストが音楽に表情を与えます。
音域(おんいき):音が出せる高低の範囲を指します。例えば、楽器や声のできる音の高さや低さの幅を示し、特徴的な音色を生み出す要因となります。
ラウドネス:音の大きさや強さの感覚を指します。音色に対する印象を左右し、時には感情を引き起こす要素にもなります。
アタック:音が発生した際の初期の立ち上がりの速さや形状を指します。アタックが鋭い音色は力強さを感じさせ、持続音や余韻に影響を与えます。
エンベロープ:音の強さの変化を時間的に示す曲線で、音の発生から消失までの過程を表します。音色の変化を理解するために重要な要素です。
テクスチャー:音や音楽の混ざり具合を表現します。単調な音色から複雑で層のある音色まで、テクスチャーによって音楽の印象が大きく変わります。
フレーヴァー:音色が持つ独特の雰囲気や特性を表現します。各楽器や声が持つ個性が音楽の味わいを引き立てる要因となります。