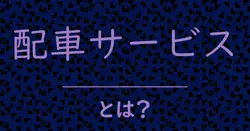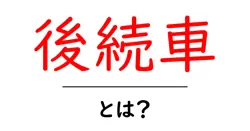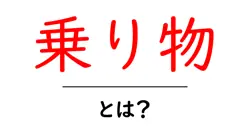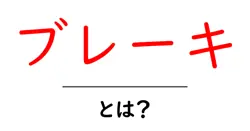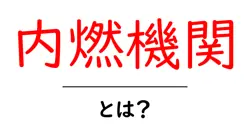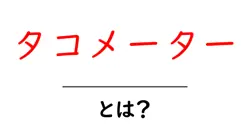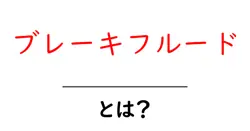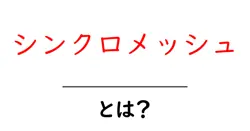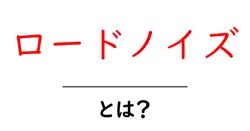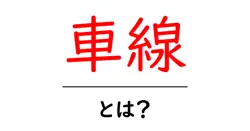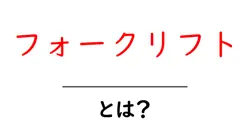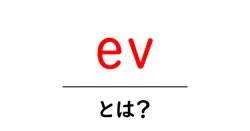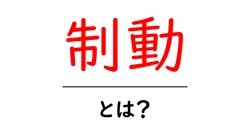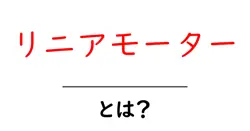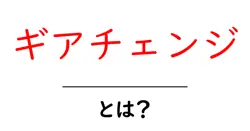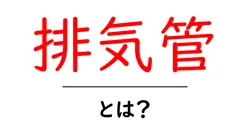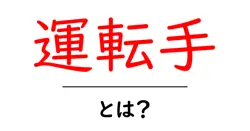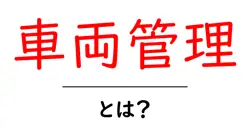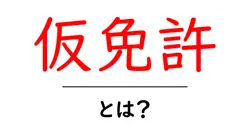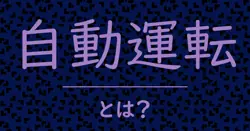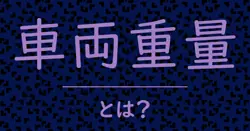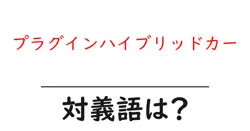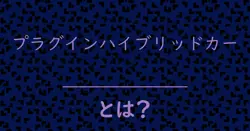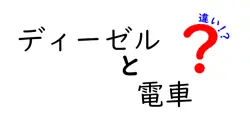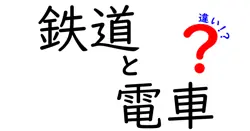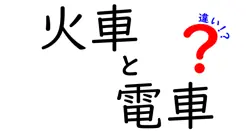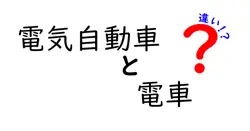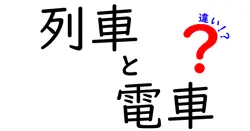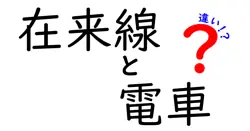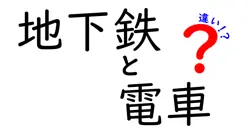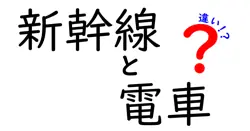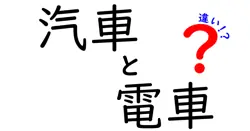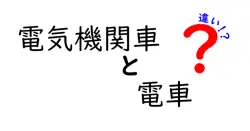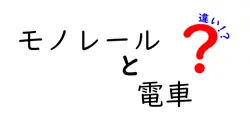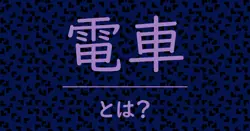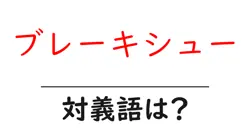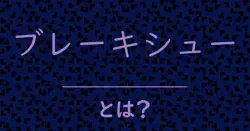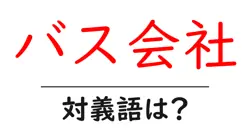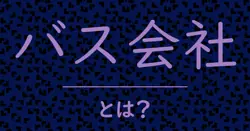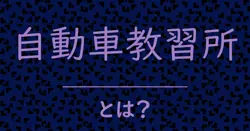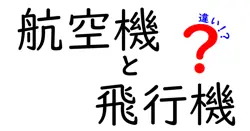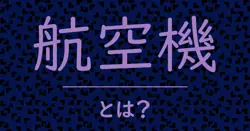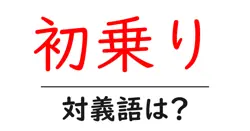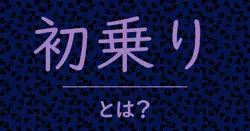航空機とは?
航空機とは、空を飛ぶために作られた乗り物のことを指します。航空機は空気力学の原理を利用して飛行し、人や物を地上から空へ移動させることができます。私たちが旅行をする際や、貨物を運ぶ際によく利用される大切な交通手段です。
航空機の歴史
航空機の歴史は、1903年にアメリカのライト兄弟が初めて動く飛行機を作ったことから始まります。これが「ライトフライヤー」と呼ばれるもので、12秒間の飛行を成功させました。その後、航空機は技術革新が進み、数十年で大型の旅客機や軍用機が開発されるようになりました。
航空機の種類
| 種類 |
説明 |
| 旅客機 |
多くの人を運ぶための航空機で、国内線や国際線で利用されます。 |
| 貨物機 |
物を運ぶための航空機で、主に輸送に使われます。 |
| 軍用機 |
軍事目的で使用する航空機で、戦闘機や偵察機があります。 |
航空機の構造
航空機は、主に以下の部分から成り立っています:
- 胴体:乗客や貨物を載せる部分です。
- 翼:飛行するための lift(揚力)を生み出します。
- 尾翼:安定性を保つための部分で、高さを微調整します。
- エンジン:航空機を前に進ませるための動力を生成します。
最新の航空機技術
近年、航空機の技術は進化し続けています。一つは、燃料効率の向上です。新しい素材の使用やエンジンの改良により、飛行機はより少ない燃料で長い距離を飛ぶことができるようになりました。また、自動操縦技術の導入により、パイロットの負担が軽減され、安全性も向上しています。
まとめ
航空機は私たちの生活に欠かせない重要な交通手段です。歴史や種類、構造、そして最新技術について理解することで、航空機の役割や便利さをより深く知ることができます。旅行の際や日常の中でも、航空機について考えてみると新たな発見があるかもしれません。
航空機のサジェストワード解説ahrs 航空機 とは:AHRS(Attitude and Heading Reference System)とは、航空機に装備されている重要なシステムです。このシステムは、航空機の姿勢や方向を測定し、正確に航行するための情報を提供します。つまり、航空機がどの位置にいるのか、どの向きで飛んでいるのかを把握するための役割を果たします。
AHRSは、主に加速度センサーやジャイロスコープを使っています。加速度センサーは航空機の動きを感知し、どちらの方向に傾いているのかを測定します。一方、ジャイロスコープは回転の速度を測定し、航空機がどの方向に向いているのかを知るために使われます。この二つのセンサーが連携することで、AHRSは非常に正確に情報を提供することができます。
航空機が安全に飛行するためには、AHRSが必要です。例えば、夜間や悪天候の時には、パイロットは視界が悪く、通常の目視では方向を確認できません。そこでAHRSの情報が大変重宝されます。これによって、パイロットは安心して航行し、目的地に安全に到着することができます。と言うわけで、AHRSは現代の航空機にとって欠かせないシステムなのです。
mro とは 航空機:航空機のMROは、Maintenance, Repair, and Overhaulの略で、日本語では「メンテナンス、修理、オーバーホール」と呼ばれます。航空機は安全で快適な空の旅を提供するために、定期的なメンテナンスが欠かせません。
MROでは、航空機の部品やシステムが正しく動作しているかを点検し、必要に応じて修理や交換を行います。例えば、エンジンや翼、コックピット機器など、多くの部分が正しく機能しているかを確認します。新しい機器が開発されると、古いものと交換することもあり、これがオーバーホールと呼ばれます。
特にMROは、航空機の安全を確保するために非常に重要です。事故を防ぐためには、定期的な点検が必要ですし、航空会社は、整備が行き届いている機体を使用することで、乗客に安心して旅を提供します。MROのプロフェッショナルたちは、この大切な仕事を日々行っています。航空機のメンテナンスの仕組みを理解することで、私たちの空の旅がどれほど安全に保たれているかを知ることができます。
海上保安庁 航空機 とは:海上保安庁(かいじょうほあんちょう)は、日本の海や空を守るための大切な組織です。その中でも、「航空機」は特に重要な役割を果たしています。海上保安庁の航空機は、主に海の安全を守るために使われます。たとえば、海での事故や遭難者の捜索、海洋の監視、密漁や不法入国者の取り締まりなど多くの業務があります。
海上保安庁の航空機には、ヘリコプターや固定翼機があり、それぞれの特徴があります。ヘリコプターは、狭い場所に着陸できるので、急な救助活動に使われることが多いです。一方、固定翼機は遠くまで飛行できるため、広範囲を監視したり、長距離の移動が必要なときに利用されています。
航空機による空からの監視は、海上の安全を確保するためにとても効果的です。悪天候の際でも、航空機は高い視点から海面をチェックすることができます。そのため、重大な災害を未然に防ぐのにも役立っています。海上保安庁の航空機は、海難救助や犯罪の防止に欠かせない存在です。私たちの安全を守るために、日々欠かさず活動しているのです。これからも、彼らの貢献を知ることが大切です。
航空機 ストリンガー とは:航空機のストリンガーとは、航空機の構造の一部分で、主に機体の強度を保つ役割を持っています。ストリンガーは、機体の外側に取り付けられた長い金属の棒やフレームのことで、主にアルミニウムなどの素材で作られています。ストリンガーは、航空機が飛行中に受けるさまざまな力や振動を吸収し、機体の強度を高めるために非常に重要です。具体的には、ストリンガーがあることで、航空機の外部の圧力や風の影響をうけにくくなり、同時に航空機の軽量化にも貢献します。これにより航空機の燃費も向上し、より効率的に空を飛ぶことができるのです。また、ストリンガーは、航空機の設計において重要な要素の一つであり、特に大型旅客機や貨物機ではその数が多くなります。つまり、航空機の安全性や性能を確保するためには、ストリンガーの設計と製造が欠かせません。
航空機 チェックイン とは:航空機のチェックインとは、飛行機に乗るための手続きのことを指します。旅行に行く前に、空港で搭乗手続きを行い、 boarding pass(搭乗券)を受け取ります。チェックインは主に二つの方法があります。一つは、空港の自動チェックイン機を使う方法です。自動チェックイン機に自分の予約番号やパスポートを入れると、搭乗券が発券される仕組みです。もう一つは、航空会社のカウンターでスタッフに手続きをしてもらう方法です。この場合、荷物を預けることもできます。チェックインの時間は、航空会社によって異なりますが、通常はフライトの2〜3時間前から開始されます。また、インターネットを使って自宅やスマートフォンで事前にチェックインをすることもできるので、便利です。チェックインを済ませたら、搭乗口に向かって、いよいよ飛行機に乗る準備が整います。これが基本的なチェックインの流れです。
航空機 フレア とは:航空機のフレアとは、主に飛行機が着陸する際に使用される技術や手法の一つです。フレアは、着陸直前に飛行機が高度を少し上げることで、機体の速度を減少させ、スムーズに着地するために行います。この操作は、映画やアニメで見かけるような派手なものでなく、実際には非常に重要な役割を果たしています。フレアが行われることで、機体の降下速度が緩やかになり、ランディングギアが接地する瞬間の衝撃が軽減されます。これにより、乗客や機材の安全が守られるのです。フレアは、パイロットが緻密に調整する必要があるため、経験が重要です。また、フレアによって、航空機は床に近づきながら自然な動きで着地することができ、航行の安全性が向上します。このように、航空機のフレアは、安全な着陸を支える大切な技術であり、多くの人々が安心して飛行機に乗るために欠かせない要素です。
航空機 マイル とは:航空機マイルとは、飛行機に乗ることで貯まるポイントのことです。多くの航空会社や提携するホテルなどで、マイルを貯めることができます。たとえば、旅行で飛行機に乗ると、その距離に応じてマイルがもらえます。また、友達や家族と一緒に旅行をすると、それぞれのマイルを合算できることもあります。貯まったマイルは、次回の旅行のために使えることが多く、特典航空券と交換したり、ホテルの宿泊に利用したりすることができます。さらに、マイルが貯まることで、割引や特別なサービスの提供も受けられます。航空機マイルは、賢く利用することで、よりお得に旅行を楽しむ手助けとなります。貯まったマイルがどんどん増えていくと、次の旅行が待ち遠しくなりますね。マイルを上手に活用する方法を学ぶことで、より充実した旅行を経験できます。ぜひ、飛行機に乗るたびにマイルを意識して貯めてみてください!
航空機 半券 とは:航空機半券とは、飛行機に乗るときに受け取るチケットの一部です。通常、航空券は出発前に購入し、空港でチェックインを行うと、搭乗券が渡されます。この搭乗券の下部にある部分が半券です。この半券は、乗客が飛行機に搭乗したことを証明するための重要な証拠となります。 旅の思い出として、半券を収集する人も多く、旅行記やアルバムに貼り付けて楽しむことができます。また、航空機に乗ったことを記録する良い方法です。特に海外旅行では、異国の航空会社の半券を見ることができ、旅行の思い出をより一層深めてくれます。半券には、搭乗日やフライト情報が記載されているため、後で振り返るとその時の思い出が鮮明に蘇ります。大切な思い出を形に残すために、自分だけの半券コレクションを作ってみるのも楽しいです。
航空機 型式 とは:航空機の型式とは、特定の航空機の設計や仕様を示す名前のことです。航空機にはたくさんの種類があり、それぞれの型式が異なる特徴を持っています。たとえば、ボーイング747やエアバスA320などが有名です。型式は数字や文字の組み合わせで構成されており、これによって航空機を区別することができます。
型式の名前は、航空機が開発された会社やモデルの計画段階での名称、さらにはその航空機が持つ特別な機能や意図に基づいて決まります。型式を知ることで、乗る航空機の性能や用途を理解しやすくなるのです。例えば、旅客機、貨物機、戦闘機など、それぞれに専門的な設計がされています。
航空機の型式は、航空機に乗る人にとっては安心感や期待感を与え、航空業界にとっては重要な情報です。私たちが飛行機を利用する際、型式が示されることでその航空機についての情報が得られ、より良い選択ができるのです。航空機の型式について知っておくことは、航空の世界を理解するための大切な第一歩です。
航空機の共起語飛行機:航空機の一般的な名称で、人や荷物を運ぶために空を飛ぶことができる乗り物です。
エンジン:航空機を動かすための機械装置で、推進力を生み出します。主にジェットエンジンやプロペラエンジンがあります。
操縦士:航空機を運転する専門家で、飛行の安全を確保し、航路を指示します。
空港:航空機が離着陸するための施設で、旅客や貨物の搭乗・降り立ちを行います。
航路:航空機が飛行する際の経路で、目的地までの最適な飛行ルートが設定されます。
搭乗手続き:航空機に乗るための手続きで、チェックイン、荷物の預け入れ、セキュリティチェックなどが含まれます。
フライト:航空機が空を飛ぶ過程や旅のことを指します。出発から到着までの全行程を指すことが多いです。
機体:航空機そのものの構造部分を指し、エンジン、翼、コックピットなどが含まれます。
空中給油:航空機が飛行中に他の航空機から燃料を補給する技術で、長距離飛行を可能にします。
航空券:航空機の搭乗を許可するためのチケットで、予約や購入が必要です。
航空機の同意語飛行機:空を飛ぶための乗り物で、定期便やチャーター便として運航されています。
航空機:一般的に空を飛ぶために設計された機械全般を指します。飛行機、ヘリコプター、無人機などが含まれます。
ジェット機:ジェットエンジンを搭載した航空機で、高速で飛行することができるため、短時間での移動が可能です。
グライダー:エンジンを持たず、空中の上昇気流を利用して滑空する航空機で、スポーツや訓練に用いられます。
ヘリコプター:回転翼を用いて、垂直に離着陸できる航空機で、狭い場所へのアクセスが可能です。
無人航空機:操縦士が搭乗せず、リモートで操縦される航空機で、ドローンとしても知られています。
気球:空気よりも軽いガス(例えばヘリウム)を利用して浮かぶ航空機で、観光やスポーツとして楽しまれることが多いです。
航空機の関連ワード飛行機:航空機の一般的な呼称で、空中を飛ぶための交通手段を指します。旅客機や貨物機を含む様々なタイプがあります。
操縦士:航空機を運転する人のことです。資格を持つ専門家で、飛行機の安全な操縦を行います。
航空会社:航空機を運航し、旅客や貨物を輸送する企業のことです。国内線や国際線のサービスを提供します。
ターミナル:空港内にある旅客が搭乗や降機を行う場所です。出発ロビーや到着ロビーが含まれます。
フライト:航空機が空を飛ぶこと、または具体的な航行を指します。特定の航路や時間帯での飛行がこれにあたります。
着陸:航空機が地面に降りる行為を指します。安全に行うことが求められる重要な操作です。
離陸:航空機が地面から空中に飛び立つことを指します。エンジンの力で上昇する際の動作です。
航空管制:航空機の安全な飛行を確保するための管理業務で、空港や空域内の航空交通を指導・監視します。
エンジン:航空機を推進するために必要な機器で、航空機の飛行性能を決定づける重要な要素です。
航空券:航空会社が発行する、航空機に乗るための乗車証明書です。搭乗時に必要となります。
空港:航空機が離着陸するための施設で、旅客の移動を支援するための様々な設備があります。
気象:航空機の運航に大きな影響を与える要素で、風速や雲の状態などが考慮されます。
アビエーション:航空機や航空産業に関するすべての活動や技術を指します。航空機の設計・製造から運航までを含みます。
パイロット:飛行機を操縦する職業の人で、航空の知識と技術が要求されます。
航空機の対義語・反対語
該当なし
航空機の関連記事
乗り物の人気記事
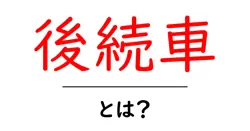
4776viws
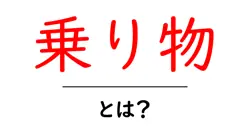
1550viws
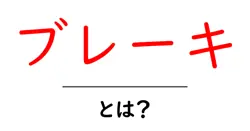
4730viws
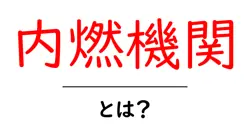
1924viws
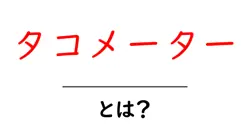
1092viws
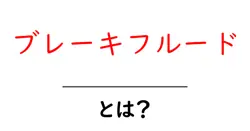
3405viws
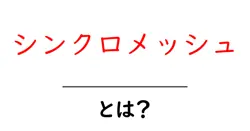
1180viws
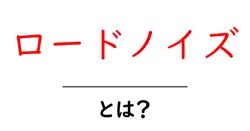
1669viws
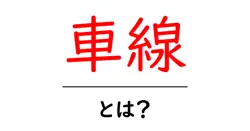
1178viws

1852viws
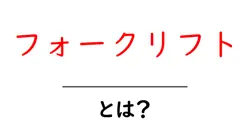
646viws
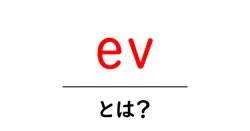
1536viws
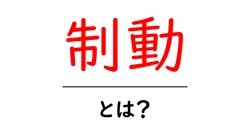
4025viws
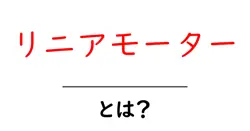
1473viws
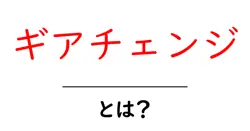
779viws
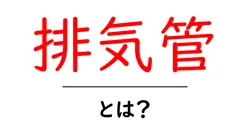
1925viws
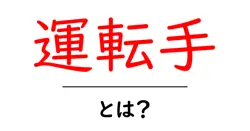
5191viws
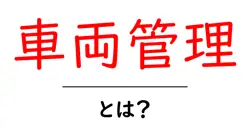
4923viws
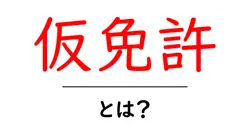
4720viws

5511viws