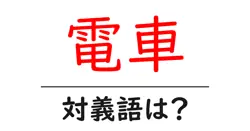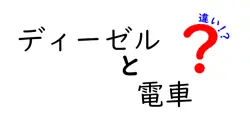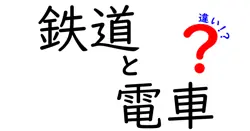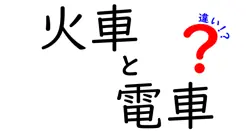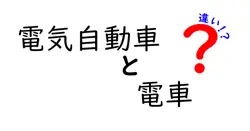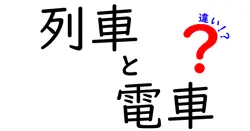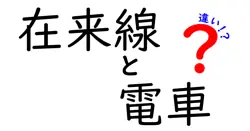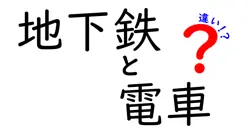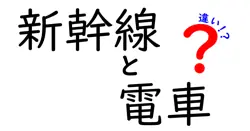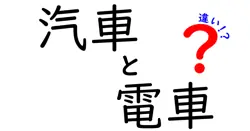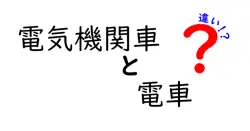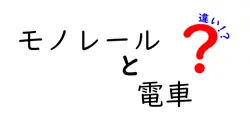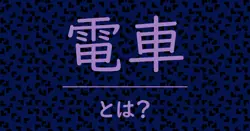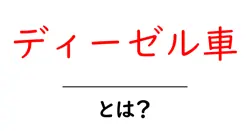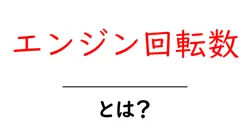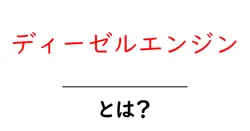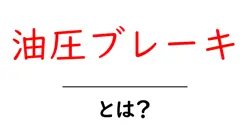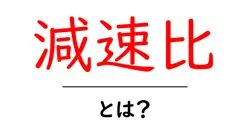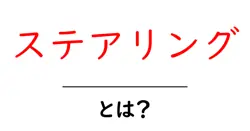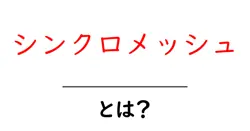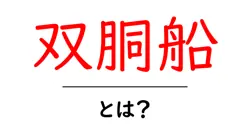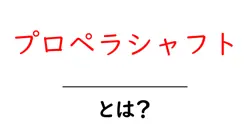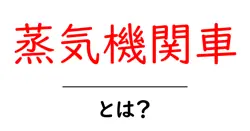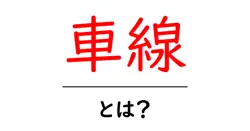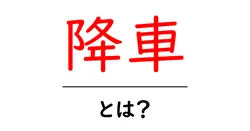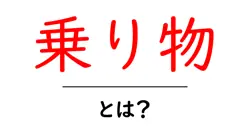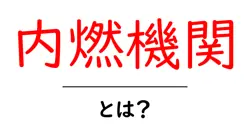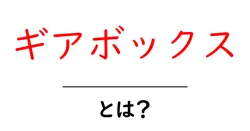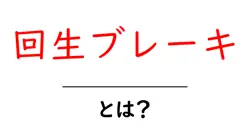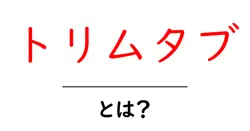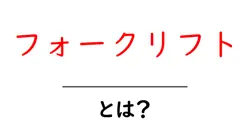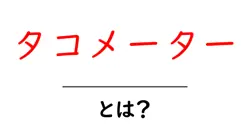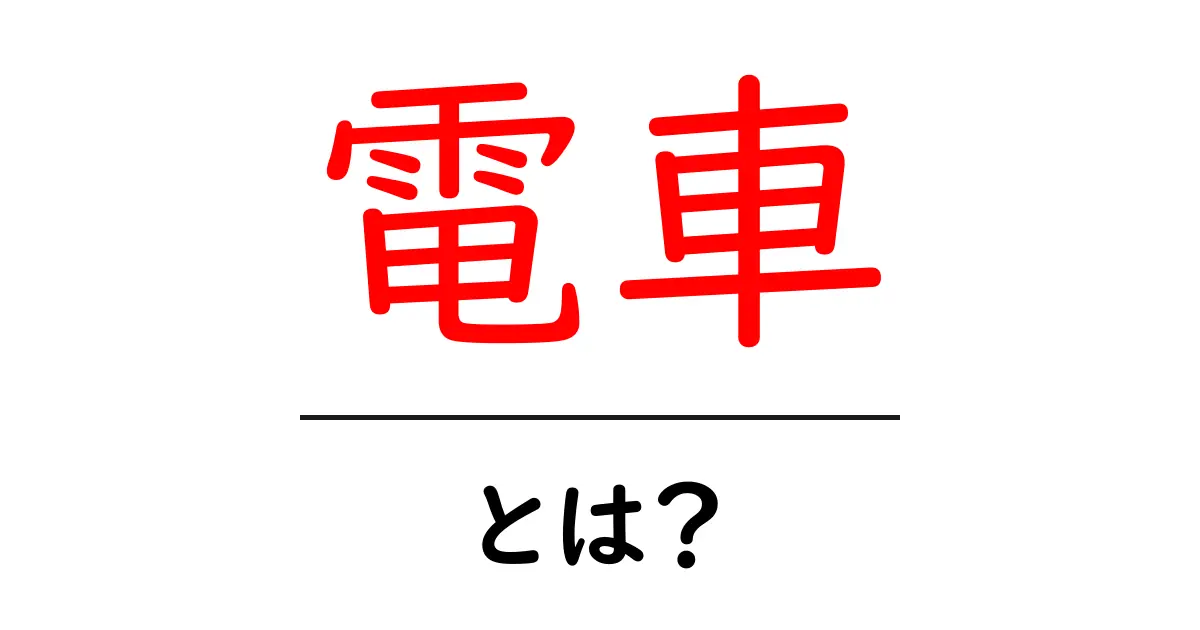
電車とは?
電車は、線路の上を走る交通手段の一つで、多くの人が利用しています。一般的には、都市間や地域間を結ぶために使用される公共の乗り物です。電車には、特急や急行、普通など、様々な種類があります。
電車の種類
電車には大きく分けて、以下の3つの種類があります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 特急電車 | 停車駅が少なく、速く目的地に着く |
| 急行電車 | 特急よりは停車駅が多いが、普通より速い |
| 普通電車 | すべての駅に停車するが、最も遅い |
電車の特徴
電車は、次のような特徴を持っています。
- 定時運行: 多くの電車は、運行時刻が決まっているため、時間通りに移動できる。
- 多人数輸送: 一度に多くの人を運ぶことができるため、混雑することもある。
- 経済的: 自家用車に比べて、移動コストが安く済むことが多い。
電車の歴史
電車の起源は、19世紀の初めにさかのぼります。最初の鉄道は、蒸気機関を使っていましたが、現在ではほとんどが電力で動いています。電車は、産業革命の影響を受けて発展し、都市の発展にも大きく寄与しました。
電車を利用する理由
電車は、以下の理由から多くの人に利用されています。
- 移動が簡単で便利。
- 渋滞に悩まされない。
- 環境に優しい交通手段とされている。
まとめ
電車は、私たちの生活に欠かせない交通手段です。多人が利用でき、環境にも配慮されています。電車の種類や特徴、歴史を理解することで、より利用しやすくなるでしょう。
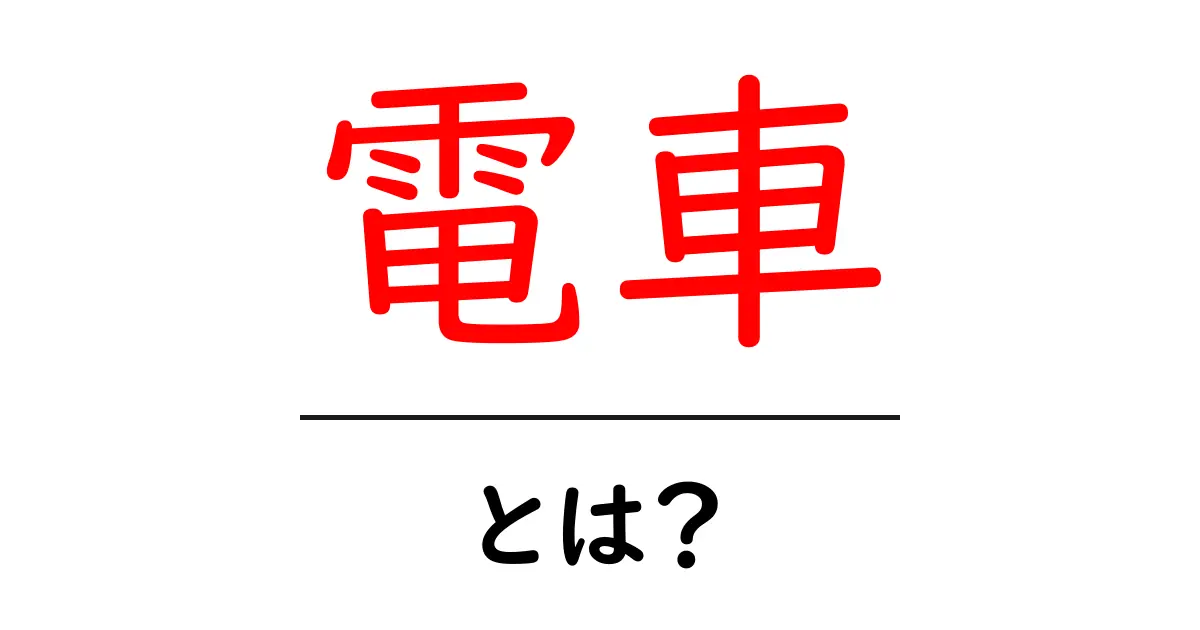
コミュニティ 電車 とは:コミュニティ電車とは、地域の住民を中心に利用される特別な電車のことです。普通の電車と違って、ただ人を運ぶだけでなく、地域のコミュニケーションを育てる役割も果たしています。例えば、ある町の住民がこの電車を利用してお祭りに行ったり、地元のお店を訪れたりすることで、地域のつながりが深まります。 この電車は、地元の風景や文化にあわせたデザインが施されていて、まるで地域の一部のような存在です。また、運行のスケジュールも地域のイベントに合わせて調整されることが多いので、利用者にとってとても便利です。さらに、乗客同士が会話を楽しむことができるスペースも用意されているため、より地域の人々との交流を促進します。 コミュニティ電車は、地域を結ぶ大切な交通手段として、住民が楽しく移動できる環境を提供しています。これからも地域に密着した交通の形として、多くの場所で広がっていくことが期待されています。快適で楽しい移動が実現できるコミュニティ電車、ぜひ利用してみてください!
ハイビーム 電車 とは:ハイビーム電車という言葉を聞いたことがある人は少ないかもしれません。まず、ハイビームとは車の光の強さのことを指しますが、電車にも同じような仕組みがあります。ハイビーム電車とは、特に夜間や暗い場所で運行するために、ライトの明るさを調整し、安全に運行するための技術です。これにより、運転士は遠くの状況をしっかり確認できるため、衝突や事故のリスクを減らすことができます。特に鉄道の運行においては、安全が非常に重要です。日本の国鉄や私鉄では、ハイビーム機能を持つ電車が運行されています。この技術のおかげで、運転士はより良い視界を得られ、乗客も安心して電車を利用できるのです。ハイビーム電車は、電車の作りや運行方法が進化していることを示す一例とも言えますね。
ワンマン 電車 とは:ワンマン電車とは、運転手が一人だけで運行する電車のことです。通常の電車は、運転手の他に車掌がいて、乗客の安全や運行の確認を行います。しかし、ワンマン電車では、運転手がすべての業務を一手に引き受けるため、乗客を乗せながら運転を行っています。この電車は特に地方の路線や利用客が少ない路線で多く見られます。レールの点検や運転の安全確認は、運転手が自ら行います。また、駅での運行もスムーズにするため、乗客が降りた後に運転手がドアを閉めることになります。ワンマン電車の導入により、運行コストが削減でき、利便性も高まります。運転手一人での運行ということで、運転手には大きな責任がありますが、安全運行が心がけられています。特に、駅での乗り降りや、事故防止のために、運転手は常に注意を払っています。
人身事故 電車 とは:人身事故とは、電車が走行中に人が関わってしまう事故のことを指します。例えば、駅のホームで人が転んで線路に落ちたり、故意に線路に飛び込んでしまうことがあります。これが起こると、列車は急停止し、乗客や運転士にとっても大変な状況になります。人身事故が発生すると、電車はすぐに運行を停止し、警察や救急隊が駆けつけることになります。このため、電車の運行が一時的に中止されてしまい、他の多くの乗客にも影響を与えることになります。加えて、人身事故は精神的なショックをもたらすこともあり、運転士や目撃者に深い心の傷を残すこともあります。また、電車の遅延によって通勤や通学に影響が出ることもあり、多くの人が困ってしまいます。私たちが安全に電車を利用するためには、逆に駅やホームの利用方法をしっかり守ったり、万が一事故が起こった場合には冷静に行動することが大切です。人身事故の原因やその影響を理解することで、より安全に電車を利用することができます。
回送 電車 とは:「回送電車」という言葉を聞いたことがありますか?回送電車とは、主に終点駅から次の始発駅へ向かう電車のことを指します。皆さんが普段利用している電車は、乗客を乗せて目的地に向かう目的のために運行されていますが、回送電車は乗客を運ぶのが目的ではありません。例えば、電車が運行を終えた後、車両基地や修理工場に戻るために走ることがあります。このように、電車が空の状態で運行することが回送です。また回送電車は、新しい路線試運転のためや、車両の移動など多くの理由があります。運行中の時刻表には回送電車が掲載されていないことが多いですが、実際には背後で多くの役割を果たしているのです。このように、回送電車は普段目にすることがないかもしれませんが、鉄道の運行をスムーズにするためにとても重要な存在です。電車の運営がどのように行われているのかを知ることで、鉄道の面白さや重要性が広がっていってほしいです。
快速 電車 とは:快速電車とは、都市間を結ぶために特に速く走る電車のことです。普通電車に比べて停車駅が少なく、主要な駅にのみ止まるため、目的地までの移動時間を短縮できます。たとえば、通勤や通学で混雑する朝の時間帯に、快速電車を利用することで、ストレスなく移動できることが多いです。日本の多くの鉄道路線では、快速電車が運行されており、特に大都市圏での人気があります。この電車は、特急電車や新幹線ほど速くはないものの、平均速度が高いため、利用することで時間を効率的に使えるのが魅力です。また、快速電車は料金が普通電車とほぼ同じか、少し高めですが、それを考慮しても速さや便利さを重視する人々に喜ばれています。例えば、全国津々浦々で利用されている「特別快速」や「新快速」などもあり、地域ごとに特有の快速電車があります。これらの電車は、多くの人々の日常生活に欠かせない存在と言えるでしょう。
特急 電車 とは:特急電車とは、普通の列車よりも速く、目的地に早く着くことができる特別な列車のことです。特急電車は通常、停車する駅が少なく、主要な都市や観光地を結ぶことが多いです。たとえば、新幹線も特急の一種です。特急電車は、駅に到着する時間が短縮されるため、仕事や旅行で必要な時間を大幅に節約できます。また、快適な車両や座席が用意されており、長時間の移動も快適に過ごせます。特急電車のチケットは、普通の列車よりも高めですが、迅速さと快適さを求める人には人気があります。特急電車には、いくつかの種類があります。たとえば、座席指定が必要な特急や、自由席の特急などがあります。特急電車を利用することで、効率的に移動できるので、ビジネスマンや観光客にとっては非常に便利な交通手段です。
直通 電車 とは:直通電車(ちょくつうでんしゃ)とは、ある路線から他の路線へ特に乗り換えをせずにそのまま進むことができる電車のことです。例えば、A駅からB駅に行くときに、途中で乗り換える必要がないととても便利ですよね。このように、直通電車があると、旅行や通勤が楽になります。直通電車は、特に大都市では多く運行されています。これにより、都市間や地域間の移動がスムーズに行えます。たとえば、東京から横浜に行く場合、直通電車を利用すれば、乗り換えなしでそのまま目的地に着くことができます。また、直通電車は、特急や快速などの速い列車に設定されることが多いです。これにより、速さと便利さの両方を実現しています。ただし、直通電車を利用する場合、その運行時間や行き先をしっかり確認しておくことが大切です。停車する駅や時間帯が異なることがあるからです。直通電車をうまく利用することで、移動がさらに快適になるでしょう。
駅:電車が停車する場所で、乗客が乗り降りするための施設です。
運賃:電車を利用する際に支払う料金のことです。距離や路線によって異なります。
ダイヤ:電車の運行スケジュールのことを指します。出発時刻や到着時刻が記載されています。
路線:電車が走るコースやルートのことです。各路線には名前や番号が付けられています。
乗換え:目的地に向かうために、異なる路線の電車に乗り換えることです。
ホーム:電車が停車するためのプラットフォームで、駅構内に設けられています。
車両:特定の路線で運行される電車そのもので、複数の車両が連結されて一つの列車を形成します。
乗車:電車に乗る行為のことです。電車に乗車することで、移動が可能になります。
発車:電車が駅を出発することを指します。発車時刻を守って出発します。
終電:その日の最終的な電車のことを指し、通常、夜の遅い時間帯に運行されます。
列車:鉄道を走る車両の総称で、定期的に運行されるものを指します。
トレイン:英語の「train」をカタカナ表記したもので、列車と同様の意味で使われることがあります。
オプション:異なるタイプの車両や特別なサービスを提供する運行を指すこともありますが、一般的には「選択肢」という意味です。
高速列車:新幹線など、短時間で長距離を移動するために設計された列車です。
通勤電車:主にビジネスパーソンが利用する、都市内外の通勤を目的とした電車のことです。
特急:急行よりも速く、停車駅が少ないため、目的地までの所要時間が短縮される列車のことです。
地下鉄:都市部での移動のために地上または地下で運行される電車で、公共交通機関の一部です。
市電:都市内を走る路面電車のことを指し、特に短距離の移動に利用されます。
鉄道:電車が走るためのレールとそれを支える施設のことを指します。鉄道は都市間や地域間の移動手段として重要な役割を果たしています。
駅:電車が停車する場所を指し、乗客の乗降を行うための施設です。駅内には改札口や待合室、売店などがあります。
運行:電車が定められたスケジュールに従って走ることを指します。運行ダイヤは各鉄道会社が定めています。
回送:乗客を乗せずに運転される電車のことです。主に空車での移動や、メンテナンスのために使用されます。
乗り換え:一つの電車から別の電車に乗り換えることを指します。結節点となる駅で行われることが多いです。
定期券:指定された区間を一定期間、何度でも利用できる乗車券です。通勤や通学に利用されることが多いです。
車両:電車を構成するための個々の車両のことです。客室車両や制御車、貨物車などがあります。
運賃:電車に乗るために支払う料金のことです。運賃は距離や路線によって異なります。
路線:電車が運行するための経路や線のことを指します。各路線には固有の名称と番号があります。
車掌:電車の運行において乗客の安全を確保し、サービスを提供する職員のことです。