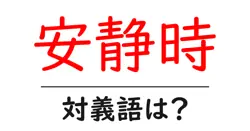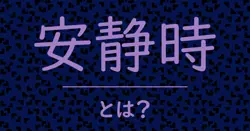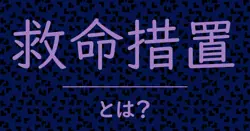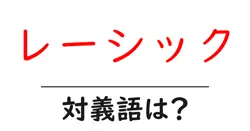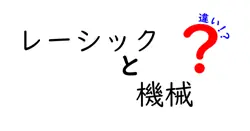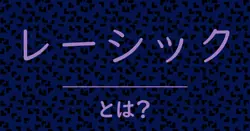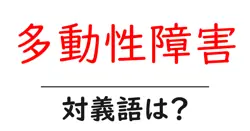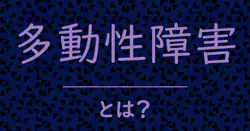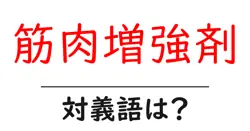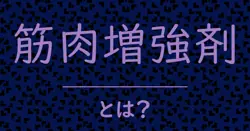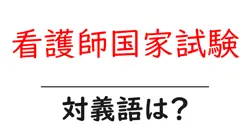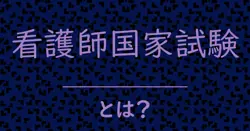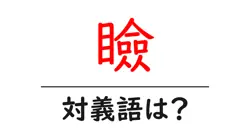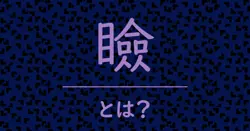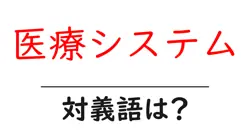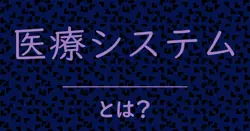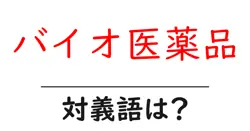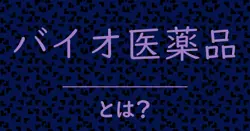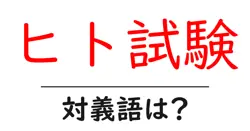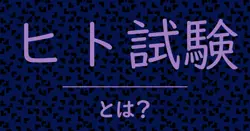安静時とは?
安静時とは、体や心を休めてリラックスする時間のことを指します。私たちの生活の中で、毎日何かと忙しくしていると、ついついこの大切な時間を忘れてしまうことがあります。しかし、安静時を持つことは、体や心の健康を保つために非常に重要です。
安静時の重要性
安静時は、ストレスを軽減する効果があります。ストレスが溜まると、体の免疫力が下がったり、集中力がなくなったりします。安静な時間を作ることで、これらの問題を和らげ、リフレッシュすることができます。
安静時の過ごし方
それでは、安静時をどのように過ごすことができるのでしょうか?以下は、安静時をリラックスして過ごすためのいくつかの方法です。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 深呼吸 | ゆっくりとした深い呼吸を行うことで、心が落ち着きます。 |
| ストレッチ | 体を軽く動かすことで、筋肉をほぐすことができます。 |
| 読書 | 静かな環境でお気に入りの本を読むことでリラックスできます。 |
| 瞑想 | 心を静めることで、リフレッシュ効果が得られます。 |
安静時を取り入れるメリット
安静時を取り入れることで、以下のようなメリットがあります。
- ストレス解消: リラックスすることで、ストレスが軽減されます。
- 集中力向上: 休むことで、頭をスッキリさせ、次の活動に集中できるようになります。
- 健康維持: 心身の疲れを癒すことで、健康を保つことができます。
まとめ
安静時は、体や心の健康を保つためにとても重要です。普段の生活の中に、少しでも安静な時間を取り入れて、リフレッシュしましょう。自分に合った方法で、しっかりとしたリラックスタイムを持つことが、日々のエネルギーを高める秘訣です。
安静時 fmri とは:安静時fMRI(安静時機能的磁気共鳴画像法)とは、私たちが何もしていないときの脳の活動を観察するための技術です。この方法では、頭に特別な装置をつけて、脳の血流の変化を計測します。なぜ血流かというと、脳が活動するときには、その部分にたくさんの血液が送られるからです。これによって、脳のどの部分が活動しているのかをリアルタイムで見ることができます。安静時fMRIは、特に心理学や神経科学の研究でよく使われていて、うつ病や不安障害などの精神的な病気の研究でも役立っています。この技術は、脳の健康を理解するためにとても重要です。将来的には、さらに多くのことが分かるようになり、脳に関する新しい治療法が開発されるかもしれません。
心拍数 安静時 とは:心拍数とは、心臓が1分間に何回拍動するかを示す数字です。特に「安静時心拍数」とは、私たちがリラックスしているとき、例えば座っている時や寝ている時の心拍数のことを指します。安静時心拍数は健康状態を知る大切な指標です。一般的に安静時心拍数は60〜80回/分が普通とされています。しかし、スポーツをよくする人や体力がある人は、この数字が60回未満になることもあります。安静時心拍数が高すぎると、心臓に負担がかかっている可能性があり、逆に低すぎると何らかの問題があるかもしれません。そのため、自分の安静時心拍数を知り、健康を管理することが大切です。日常的に測ることができるので、気軽にチェックしてみてください。心拍数を把握することで、生活習慣の改善や運動不足の解消にも役立ちます。自分の心を大切にして、健康的な生活を送るために、安静時心拍数を理解することは非常に重要です。
筋肉:身体を動かすための組織で、運動時に使われるが、安静時にも休息と修復の時間が必要。
心拍数:心臓が1分間にどれだけ拍動するかを示す数値で、安静時は通常低下し、リラックスした状態を反映する。
血圧:血液が血管内を流れる際にかかる圧力で、安静時と活動中で変動する。安静時は一般的に低めになる。
代謝:身体がエネルギーを生成し消費する過程で、安静時の代謝率は身体が必要とする最小限のエネルギーを示す。
リカバリー:運動やストレスから身体が回復する過程で、安静時によって体力の回復が促進される。
ストレス:身体や精神に圧力をかける要因で、安静にすることで緊張が緩和されることが多い。
呼吸:酸素を取り入れ二酸化炭素を排出するプロセスで、安静時は呼吸がよりゆっくりと安定する。
休息:身体や心を休め、リフレッシュさせる時間で、安静はその重要な要素。
集中:注意を特定の対象に向けることで、安静時には思考が整理されることが多い。
疲労:体や心の活動によって生じるエネルギーの消耗で、安静時にはその回復が図られる。
静止:動かずにそのままの状態でいること。特に、体を動かさずにいることを指します。
休止:活動を一時的に止めること。安静にすることで身体を休める状態を指します。
安息:心身の緊張を解き、リラックスしている状態のこと。主に、心が落ち着いていることを表します。
安静:体が動いていない状態や、リラックスしている状態を指します。1人の時間を持ち、心や体を休めることが重要です。
心拍数:1分間に心臓が拍動する回数を表します。安静時は通常、心拍数が低下し、リラックスしている状態を示します。
ストレス:心や体に負担をかける要因を指します。安静時はストレスを軽減し、休息を取ることに役立ちます。
回復:体や心が元の健康な状態に戻ることを意味します。十分な安静を取ることで、回復が促進されます。
筋肉のリラックス:筋肉が緊張せず、リラックスした状態にあることを指します。安静時には筋肉がリラックスし、血流が良くなります。
睡眠:体と心を休ませるために必要な自然なプロセスです。安静時の過ごし方や睡眠の質は、健康に大きな影響を与えます。
内分泌系:ホルモンを分泌する腺の集まりで、体の調整機能に関与します。安静時は、ストレスホルモンの分泌が抑えられ、体がリラックスします。
呼吸法:心を落ち着かせるための呼吸の仕方です。安静時に意識的に深い呼吸をすることで、リラックス効果が得られます。
緊張:体や心がストレスや不安で固くなっている状態を指します。安静時には、この緊張を解放することが重要です。