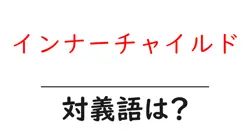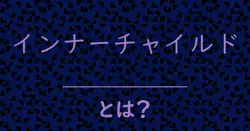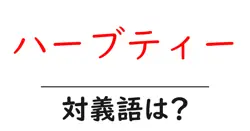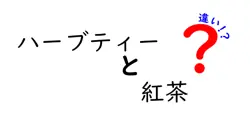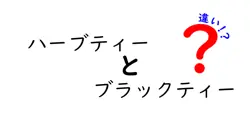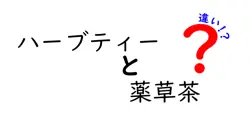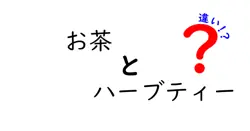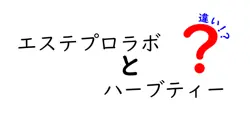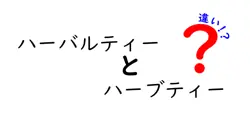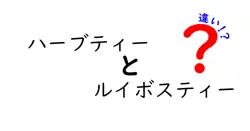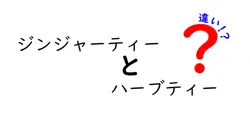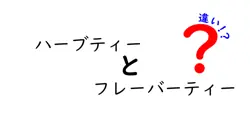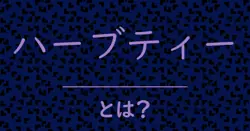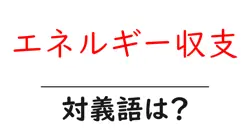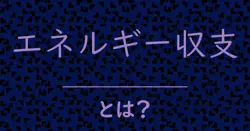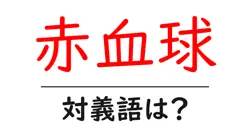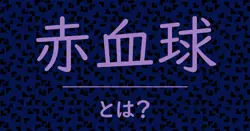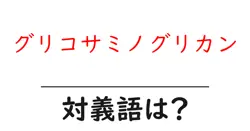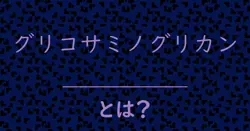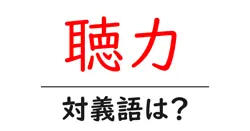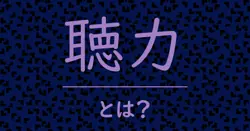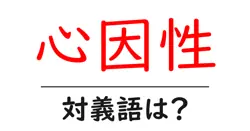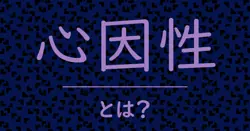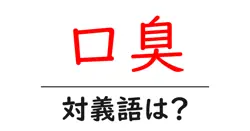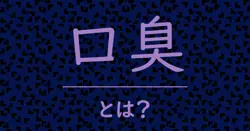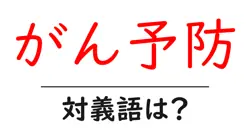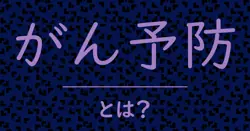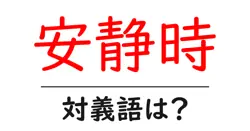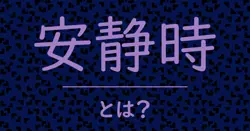インナーチャイルドとは?
「インナーチャイルド」という言葉を聞いたことがありますか?これは、自分の中にいる「内なる子ども」を指す言葉です。私たちの心の中には、子ども時代の経験や感情がしまわれていて、それが今の私たちの考え方や行動に影響を与えています。
インナーチャイルドの重要性
インナーチャイルドを理解することは、とても大切です。なぜなら、私たちの過去の感情や思い出が現在の行動や選択に影響するからです。例えば、子ども時代に何か怖い思いをしたことがあると、大人になった今も同じ状況で不安を感じたりすることがあります。
インナーチャイルドが持つ感情
インナーチャイルドは、喜びや悲しみ、怒り、恐れなど、様々な感情を持っています。これらの感情を理解し、受け入れることで、心の中のバランスを整えることができます。
インナーチャイルドを癒す方法
では、どうやってインナーチャイルドを癒すことができるのでしょうか?以下の方法を試してみてください。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 自分と向き合う | 静かな時間を作り、自分の感情を書き出してみましょう。 |
| 子どもの頃の思い出を振り返る | 楽しかったことや辛かったことを思い出し、自分に優しく接することが大切です。 |
| 専門家に相談する | カウンセラーや心理士に話を聞いてもらうことも効果的です。 |
まとめ
インナーチャイルドを理解することは、心の健康にとってとても重要です。自分の過去を受け入れ、癒すことで、今をより良く生きることができるようになります。自分自身を大切にするために、一度インナーチャイルドについて考えてみてください。
トラウマ:過去の経験や出来事によって心に残った傷や痛みのこと。インナーチャイルドに関連するトラウマは、幼少期の経験から来ることが多い。
自己肯定感:自分自身を大切に思い、価値があると感じる感覚。インナーチャイルドを癒すことで、自己肯定感が高まることがある。
感情:心の状態や反応を指す言葉。インナーチャイルドは未解決の感情を抱えていることがあり、その感情に向き合うことが重要。
癒し:心の傷や痛みを取り除き、リラックスした状態に戻すプロセス。インナーチャイルドの癒しは、過去の経験と向き合うことから始まる。
無意識:自覚できない心の働きのこと。インナーチャイルドは無意識の中で影響を与え、行動や感情に反映される。
成長:心や人格が発展し、成熟すること。インナーチャイルドを理解し、癒すことで、個人の成長が促進される。
親子関係:親と子の関係性。幼少期の親子関係がインナーチャイルドに大きな影響を与えることがあるため、この関係の理解が重要。
セルフケア:自分自身の心や身体を大切にするための行動や習慣。インナーチャイルドを癒すためには、セルフケアが欠かせない。
対話:自分自身の内面とのコミュニケーション。インナーチャイルドとの対話を通じて、その声を理解し、癒すことが目的。
ジャーナリング:日記を書くこと。自分の感情や思いを整理する手段であり、インナーチャイルドを理解するために役立つ。
内なる子供:インナーチャイルドの日本語訳で、心の中に存在する幼少期の自分を指します。
幼児期の自己:子供の頃の経験や感情を反映する自己の部分で、成長に影響を与えることがあります。
無邪気な自己:純真さや無邪気さを持つ、幼少期の感情や本能を表す自己の側面です。
感情的な子供:感情や感受性が豊かだった幼い自分を指し、現在の感情に影響を及ぼすことがあります。
精神的な子供:心の奥深くに潜む、幼少期の経験や願望を持つ部分のことです。
過去の自分:過去の経験を反映した自己を指し、特に幼少期のトラウマや記憶が関与します。
内的子供:人間の心理における思春期以前の自己を指し、感情面や人間関係に影響を与えることが多いです。
トラウマ:過去の辛い経験や出来事が心に残り、その影響を受け続ける状態。インナーチャイルドはこのトラウマによって形成されることが多い。
エモーショナル・アバンダンメント:感情的な放置や無視が招く状態。特に子供の頃に愛やサポートが不足すると、インナーチャイルドに影響を与える。
自己肯定感:自分自身を受け入れ、価値を感じる感覚。インナーチャイルドが癒されることで、自己肯定感が向上する可能性がある。
アダルト・チルドレン:子供の頃のトラウマや家庭環境が影響し、大人になってからもそれらを引きずる人々を指す。インナーチャイルドの概念と密接に関連している。
ヒーリング:心理的痛みや心の傷を癒す過程。インナーチャイルドを認識し、理解することで、ヒーリングが進むことが多い。
自己分離:自分の内面を探求する過程で、自分自身の異なる側面(例:インナーチャイルド)を理解し、受け入れること。
内的対話:自分の内なる声と対話すること。インナーチャイルドとの対話も含まれ、感情や思いを確認する手段となる。
セラピー:心理的な問題の治療や癒しを目的とする治療法。インナーチャイルドに関連する課題を扱うセラピーも存在する。
感情の解放:抑えられた感情(怒り、悲しみ、恐れなど)を表に出す行為。インナーチャイルドを癒すためには、これが重要なステップとなる。
養育:子供を育てる際に必要な愛情やサポートの供給を指す。インナーチャイルドは、この養育の欠如によって影響を受けることがある。