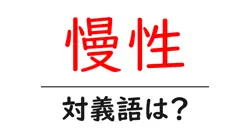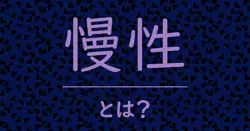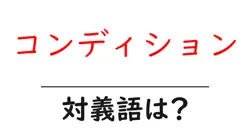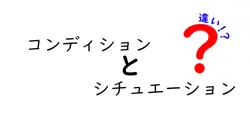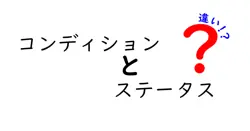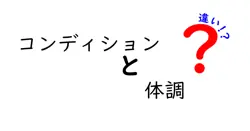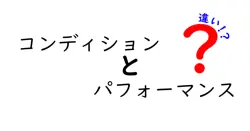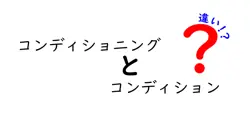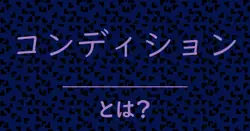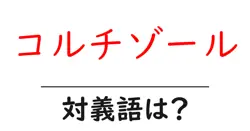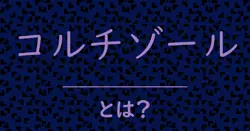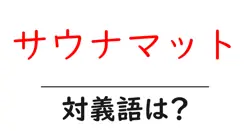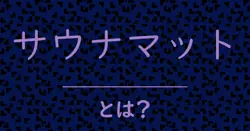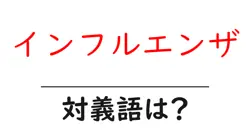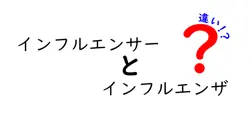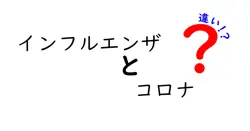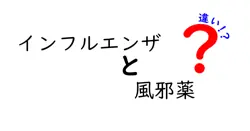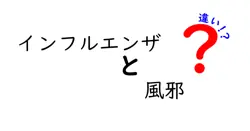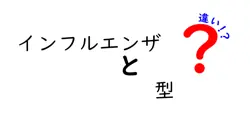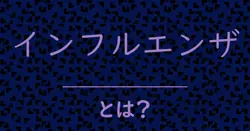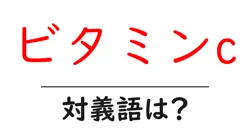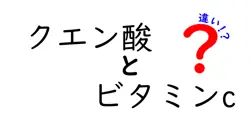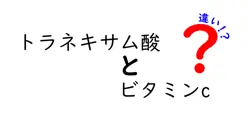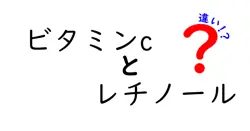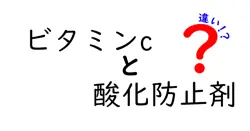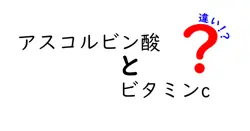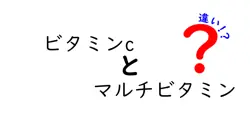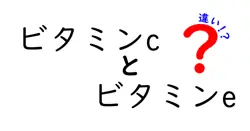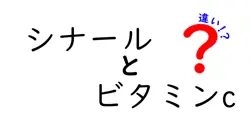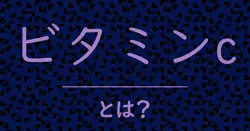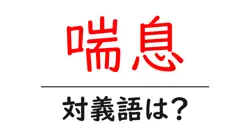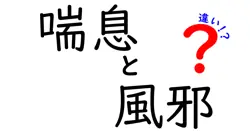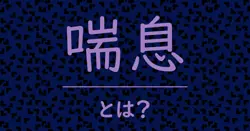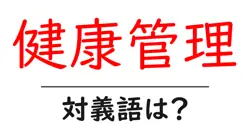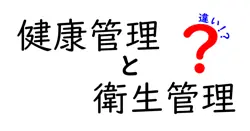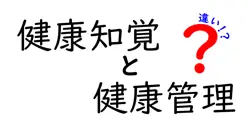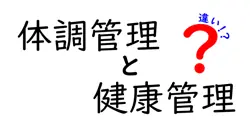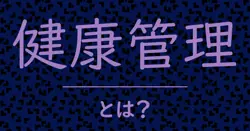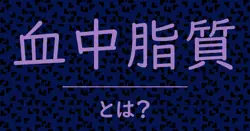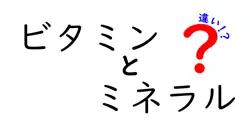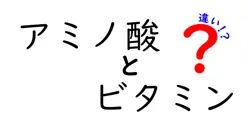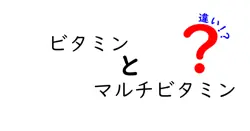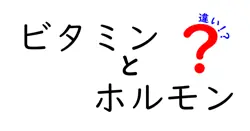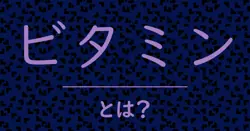慢性とは?
「慢性」という言葉は、主に病気や症状について使われる用語です。中学生の皆さんにわかりやすく説明すると、慢性は「長く続く状態」を意味します。たとえば、風邪は短期間で治りますが、慢性の病気は長い間治らないことが多いです。
慢性病の特徴
慢性病にはいくつかの特徴があります。具体的には:
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 長期間続く | 慢性病は、半年以上治療が必要なことが多いです。 |
| 期間による変化が少ない | 症状があまり変動せず、安定していることが多いです。 |
| 根本的な治療が難しい | 完治が難しい場合が多く、管理が必要です。 |
慢性病の例
以下はいくつかの慢性病の例です:
慢性病の管理方法
慢性病を持つ方は、定期的な診察や生活習慣を見直すことが重要です。また、薬を飲み続けたり、食事に気をつけたりすることが生活の質を改善します。
それでは、慢性病についての理解を深め、もし自分や周りの人がこのような病気にかかっていたら、どのように接すればいいのか考えてみましょう。
急性 慢性 とは:急性(きゅうせい)と慢性(まんせい)という言葉は、主に病気や症状の進行の速さを説明する際に使われます。急性は、「すぐに起こる」という意味で、症状が突然現れ、短期間で進行することを指します。例えば、急性の風邪や急性の痛みは、突然やってきて、数日から数週間で治ることが多いです。一方、慢性は「長い間続く」という意味で、症状がゆっくりと進行し、長期間かけて続く状態を指します。慢性病として知られるものには、糖尿病や高血圧などがあります。これらの病気は、一度かかってしまうと、治療を行っても長い間付き合っていかなければならない場合が多いです。このように、急性は急速で短期間、慢性は持続的で長期間の違いがあります。健康に気を付けるためには、これらの違いを理解することが大切です。もし、何かおかしいと感じたら、すぐに病院で相談することをおすすめします。
慢性 gvhd とは:慢性GVHD(慢性移植片対宿主病)とは、主に骨髄移植や臓器移植を受けた人に起こる病気です。この病気は、移植された細胞が受け取った人の体を攻撃することによって発生します。最初は急性GVHDという急性の症状が現れることがありますが、数ヶ月後に症状が続く場合、慢性GVHDになります。慢性GVHDの症状は多様で、皮膚にかゆみや湿疹(しっしん)が出たり、口の中が乾燥したり、目がかすんだりします。さらに、肺や消化器官にも影響を与え、呼吸がしにくくなったり、下痢を引き起こすこともあります。治療方法には、免疫を抑える薬や、症状を和らげるための薬が使われます。また、生活習慣を改善し、栄養バランスを考えた食事をすることも大切です。慢性GVHDは治療が難しい場合もありますが、医師と相談しながらケアすることが重要です。
慢性 とは 意味:「慢性」とは、ある状態や病気が長期間にわたって続くことを指します。この言葉は主に医学や健康に関連した文脈で使われますが、日常生活でも使われることがあります。たとえば、慢性疲労症候群や慢性の痛みなど、症状が長引くことを示しています。 慢性の反対は「急性」です。急性の病気は短期間で症状が現れ、すぐに治ることが多いのですが、慢性の病気はずっと続く場合が多いため、治療が必要になることがあります。慢性の状態は生活に大きな影響を与えることが多く、精神的にも辛いことがあります。 例えば、慢性的な頭痛がある人は、日常生活に支障をきたすかもしれません。このように、慢性は単に「続く」という意味だけでなく、それがどれだけ私たちに影響を与えるかも含まれています。 医者に相談することが重要で、適切な治療や対策を講じることで、慢性状態でも快適に過ごせる方法が見つかるかもしれません。まずは、自分の体の状態を理解することから始めましょう。
慢性 遅刻 症候群 とは:慢性遅刻症候群とは、いつも約束や学校、仕事などに遅れてしまう状態のことを指します。この状態の人は、遅れることが普通になってしまっているため、時間を守ることが難しくなってしまいます。まず、原因としては時間管理がうまくできないことや、注意力が散漫になっていることが考えられます。また、楽しいことがある場合、そこで時間を忘れてしまうことも関連しています。慢性遅刻症候群の対策としては、スケジュールを立てることが効果的です。時計を見ながら、準備にかかる時間を考えて、早めに行動を開始することが重要です。スマホのアラーム機能を活用して、行動開始の時間を決めるのも良い方法です。友達や家族に遅れることのないように協力をお願いするのも、一つの手です。少しずつ意識を変えていくことで、時間を守れるようになれます。
疾患:体に起こる病気や病状のことを指します。慢性疾患は、長期にわたって続く疾患のことを言います。
症状:病気や疾患によって現れる体の異常や不調のことです。慢性の症状は、長期間続くことが特徴です。
治療:疾患や病気を改善したり、治したりするための医療行為のことを指します。慢性疾患の場合、治療は通常長期にわたります。
管理:慢性疾患は治癒が難しい場合が多いため、症状を効果的に管理することが重要です。これには定期的な診察や生活習慣の改善が含まれます。
生活習慣:日常生活の中で行う習慣や行動のことを指します。慢性疾患においては、適切な生活習慣の改善が病状の管理において重要です。
活動制限:疾患の影響で日常生活や職業生活において行動が制限されることを指します。慢性疾患を持つ人はしばしば活動制限を経験します。
慢性痛:長期間続く痛みを指します。慢性疾患の一部には慢性痛が関連していることがあります。
再発:治療後も再び同じ疾患や症状が現れることを指します。慢性疾患は再発の可能性が高いことが特徴です。
心理的影響:慢性疾患は体だけでなく、心にも影響を与えることがあります。ストレスや不安感が増すこともあります。
リハビリテーション:機能の回復や向上を目的とした治療や訓練のことを指します。慢性疾患においてはリハビリが必要な場合があります。
予防:疾患を未然に防ぐための措置や行動のことを指します。慢性疾患の中には、生活習慣の改善によって予防できるものもあります。
持続的:長期間にわたって続くこと。通常は、特定の状態や症状が絶え間なく存在することを指します。
継続的:ある状態が途切れることなく続いている様子。慢性の状態では、病気や症状が長引くことを意味します。
反復的:同じことが繰り返し起こること。慢性の症状は、再発しやすいことからこの言葉が関連します。
慢性疾患:慢性疾患とは、長期間にわたって症状が続く病気のことを指します。例えば、高血圧や糖尿病などが該当し、治療は必要ですが、完治が難しい場合があります。
急性:急性は、症状が急に現れ、比較的短期間で進行する状態を指します。慢性の反対の概念で、急性の病気は突然発症することが一般的です。
炎症:炎症は、体の一部が感染や損傷に反応して発生する生理的なプロセスです。慢性炎症は、長期間続く炎症で、糖尿病や心疾患のリスクを高めることがあります。
治療法:慢性疾患の治療法には、薬物療法や生活習慣の改善、リハビリテーションなどが含まれます。慢性の状態を管理するために、患者には継続的なケアが必要です。
予防:慢性疾患の予防には、健康的な食生活や定期的な運動、ストレス管理が重要です。早期の生活習慣の見直しが効果的です。
生活習慣病:生活習慣病は、食事や運動、喫煙、飲酒といった生活習慣が原因で発症する慢性疾患のことを指します。心臓病や糖尿病、高血圧などがその例です。
認知症:認知症は、記憶や思考、行動に影響を及ぼす慢性の状態で、一般的に高齢者に多く見られます。特定の原因で進行する場合がありますが、完治は難しいとされています。
自己管理:慢性疾患を持つ患者は、自己管理が重要になります。これは、病気の症状や投薬、生活習慣を自分で管理し、医療機関と連携することを指します。
症状緩和:症状緩和は、慢性疾患において痛みや不快な症状を軽減するための治療に焦点を当てることです。このアプローチは、生活の質を向上させることが目的です。