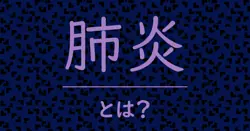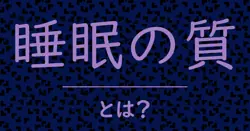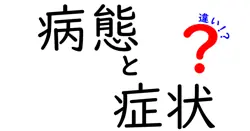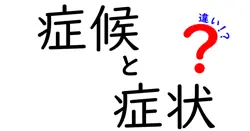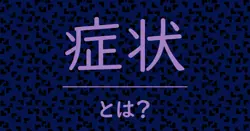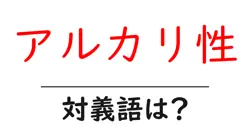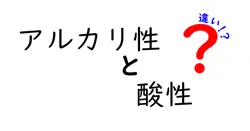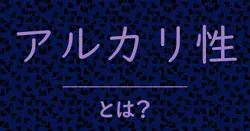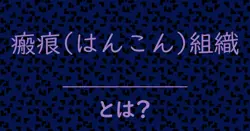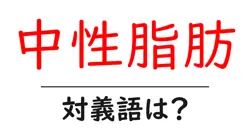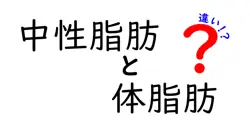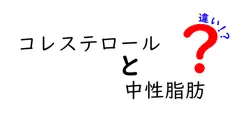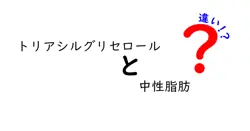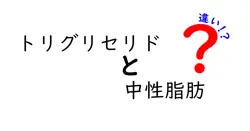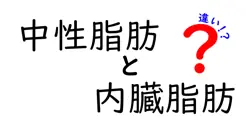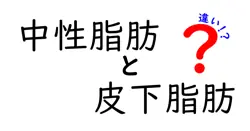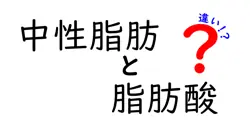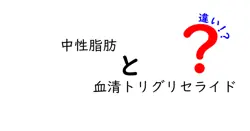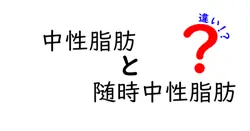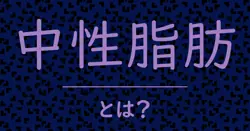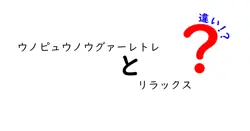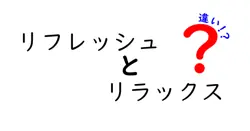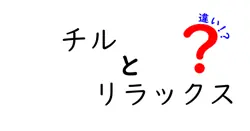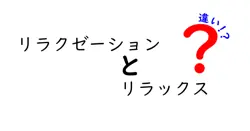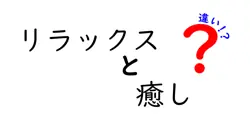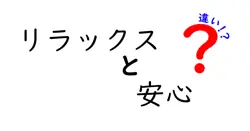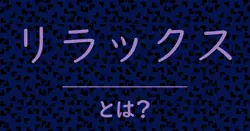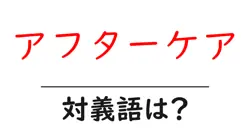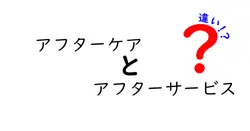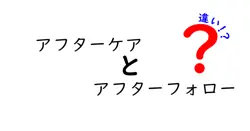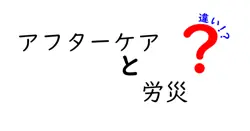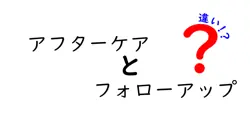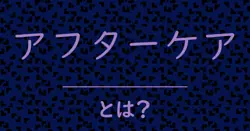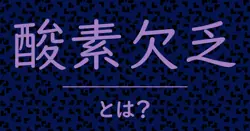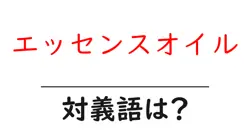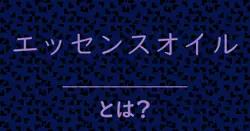肺炎とは?
肺炎は、肺の感染症で、特に肺に炎症が起こる病気です。ウイルスや細菌、真菌などによって引き起こされることがあります。これにより、呼吸が苦しくなったり、咳が出ることがあります。肺炎は子どもや高齢者に多く見られますが、若い人でもかかることがあるため、注意が必要です。
肺炎の主な症状
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 咳 | しつこい咳が続くことが多いです。 |
| 発熱 | 体温が上昇し、熱が出ることがあります。 |
| 呼吸困難 | 息を吸うのが苦しいと感じることがあります。 |
| 胸の痛み | 胸が痛むこともあり、特に咳をするときに感じることがあります。 |
肺炎の原因
肺炎は主に以下の原因によって引き起こされます。
予防法
- 手洗いの徹底:ウイルスや細菌を除去するためにこまめに手を洗うことが大切です。
- ワクチン接種:インフルエンザや肺炎球菌ワクチンを接種することで、感染を予防できます。
- 栄養管理:健康な食事を心がけ、体の免疫力を高めましょう。
まとめ
肺炎は、特に高齢者や子どもにとって危険な病気です。しかし、早期に発見し適切に治療すれば、回復することができます。予防法をしっかりと実行し、健康な生活を送ることが重要です。
肺炎 とは 症状:肺炎とは、肺の中に炎症が起こる病気です。感染症によって引き起こされることが多いですが、ウイルスや細菌、真菌によっても起こります。肺炎になると、息苦しさや咳、熱などの症状が現れます。特に、リンゴのように赤くなった痰が出ると、細菌性の肺炎である可能性が高いです。高齢者や子ども、持病のある方は特に注意が必要です。肺炎の主な症状としては、咳(かぜと似た症状)、熱(38度以上になることも)、息苦しさ、胸の痛み、倦怠感があります。これらの症状が見られたら、すぐに医療機関を受診しましょう。肺炎は早期発見が重要です。治療には抗生物質や抗ウイルス薬を使用することがあります。また、予防策としては、インフルエンザや肺炎球菌ワクチンを接種すること、手洗い・うがいを徹底すること、そしてバランスの取れた食事が効果的です。もしも何か気になる症状があった場合には、早めに医師に相談することが大切です。
肺炎 とは 看護:肺炎とは、肺に感染が起こる病気です。風邪やインフルエンザなどのウイルス、細菌、真菌によって引き起こされることがあります。特に高齢者や免疫力が低下している人にとっては、重い病気になることもあります。看護を行う際は、まず患者さんの呼吸状態を観察することが大切です。呼吸が浅かったり、苦しい様子があれば、すぐに医師に相談しましょう。また、体温や脈拍もチェックし、異常がないか確認します。看護師は、患者さんに十分な水分を摂取するよう促し、休息を取ることができる環境を整えることも重要です。食事についても、栄養のあるものを少しずつ取るようにアドバイスします。さらに、肺炎の予防として、手洗いやうがいを徹底し、患者さんが安静に過ごせるように心がけましょう。肺炎は早期発見・早期治療が大切ですので、異変を感じたらすぐに対応することが求められます。
感染:病原体が体に入ることで病気が発生すること。肺炎は、細菌やウイルスによる感染で引き起こされることが多い。
症状:病気や異常に伴う身体の変化。肺炎では、咳、発熱、呼吸困難などの症状が見られる。
治療:病気を治すための手段や方法。肺炎の場合、抗生物質やウイルスに対する薬剤などが用いられることがある。
予防:病気が発生するのを防ぐこと。肺炎の予防にはワクチン接種や、手洗い・うがいが重要とされている。
合併症:病気の進行や治療により、別の疾病が発生すること。肺炎は、特に高齢者や免疫力が低下している人において、合併症を引き起こすことがある。
重症化:病気が進行して、より深刻な状態になること。肺炎は、適切な治療を受けないと重症化する危険がある。
診断:病気の有無を確かめるための検査や判断。肺炎の診断には、身体検査や画像診断が用いられることが多い。
肺胞:肺の中にある小さな空気の袋。肺炎では、肺胞が炎症を起こして働きが悪くなる。
体温:身体の熱を示す指標。肺炎の際には、体温が上昇し発熱が見られることが一般的である。
肺:呼吸に使う器官で、肺炎はこの臓器に影響を及ぼす病気である。
ウイルス:微小な感染性の生物で、肺炎を引き起こす原因の一つ。インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどが肺炎の原因となることがある。
細菌:ウイルスと同様に小さな微生物で、肺炎の原因となることが多い。例えば、肺炎桿菌などが有名である。
咳:気道をクリアにするための反射行動。肺炎では、咳が頻繁に出ることがある。
呼吸:空気を取り入れ、体内から二酸化炭素を排出する過程。肺炎では、この呼吸が困難になることがある。
肺炎:肺の感染症で、炎症が起こることで呼吸困難や咳、発熱などの症状を引き起こします。
肺感染症:肺に細菌やウイルスが感染することによって引き起こされる病気の総称で、肺炎もこの中に含まれます。
呼吸器感染症:呼吸器系に感染する病気のことを指し、肺炎はその一部です。
気管支炎:気管支に炎症が起きる状態で、肺炎と関連することが多いですが、肺自体には炎症が生じていない場合もあります。
細菌性肺炎:細菌が原因で起こる肺炎で、特に高齢者や基礎疾患のある人に多く見られます。
ウイルス性肺炎:ウイルスによって引き起こされる肺炎で、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどが原因となることがあります。
細菌性肺炎:細菌によって引き起こされる肺炎で、一般的に肺の組織に感染が広がります。成人や高齢者に多く見られ、適切な抗生物質で治療が行われます。
ウイルス性肺炎:ウイルスが原因で発生する肺炎で、インフルエンザウイルスやRSウイルスなどが一般的です。細菌性肺炎に比べて症状が軽いことが多いですが、時に重症化することもあります。
アスペルギルス肺炎:真菌(カビ)であるアスペルギルスが原因で発生する肺炎です。免疫力が低下している人に多く見られます。
肺炎球菌:細菌性肺炎の主要な原因となる細菌です。特に高齢者や小児に多く見られ、ワクチン接種によって予防が可能です。
肺炎の症状:肺炎の主な症状には、発熱、咳、息切れ、胸の痛み、痰が含まれます。症状は原因によって異なることがあります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD):肺炎とは異なるが、慢性的な肺の病気であり、肺機能が低下するため、肺炎が合併することがあります。
胸部レントゲン:肺炎の診断に用いられる画像診断技術です。肺の状態を確認するために、胸部のX線写真を撮影します。
肺炎予防:肺炎を予防するためには、手洗い、煙草を吸わない、ワクチン接種、栄養管理などが重要です。
肺炎の対義語・反対語
該当なし