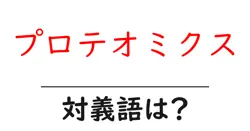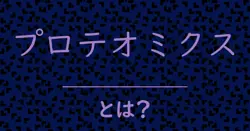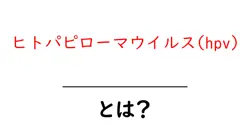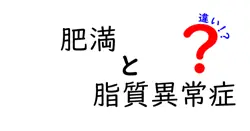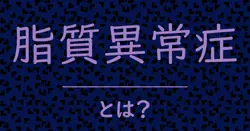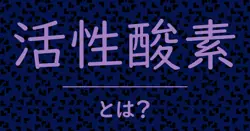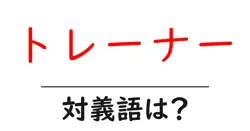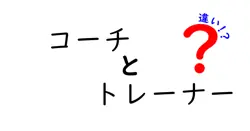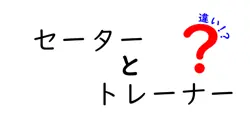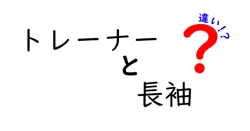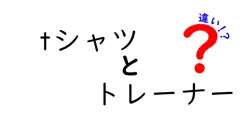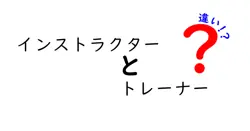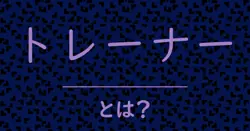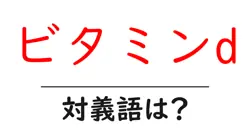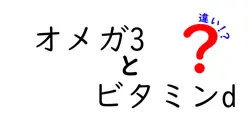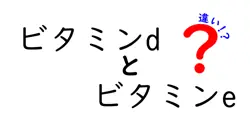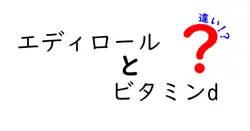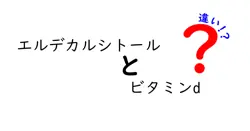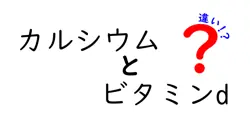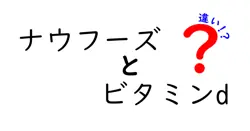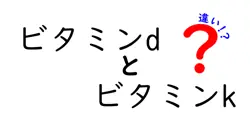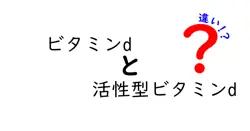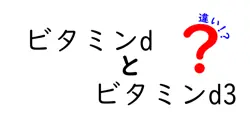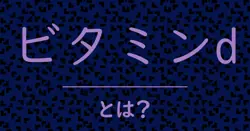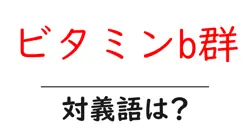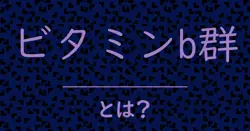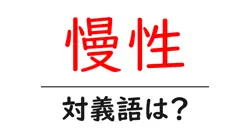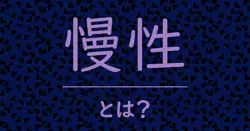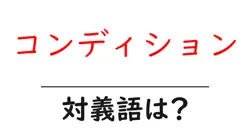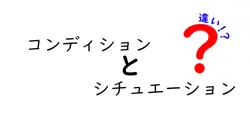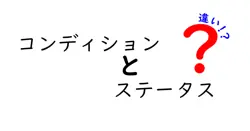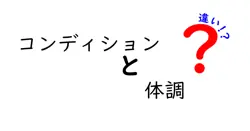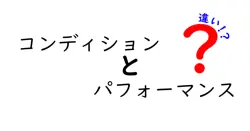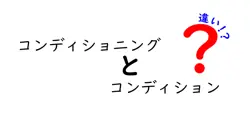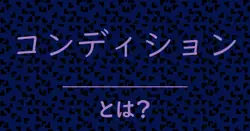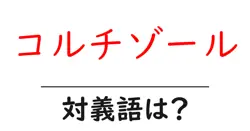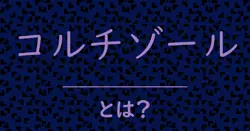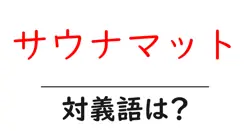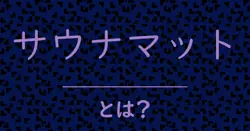トレーナーとは?
「トレーナー」という言葉は、主にスポーツやフィットネスの分野で使われることが多いです。トレーナーの役割や種類について理解することは、自分自身や他の人の健康や体力を向上させるために重要です。
トレーナーの役割
トレーナーは、運動やトレーニングに関する専門知識を持ち、それを通じて人々の健康や体力をサポートする役割を担っています。具体的には、以下のようなことを行います。
- オーダーメイドのトレーニングプラン作成:個々の目的や身体の状態に合わせて、最適なトレーニングメニューを考案します。
- 技術指導:正しいフォームやテクニックを教え、効果的にトレーニングができるようにします。
- モチベーションの向上:トレーニングが続くように励ますことも重要な役割の一つです。
トレーナーの種類
トレーナーにはさまざまな種類があります。主なものを以下に挙げます。
| 種類 | 説明 |
|---|
| パーソナルトレーナー | 個別にトレーニング指導を行うトレーナーで、専属のコーチとも言えます。 |
| フィットネストレーナー | ジムやフィットネスクラブでグループレッスンを行うことが多いトレーナーです。 |
| スポーツトレーナー | 特定のスポーツに特化し、選手をサポートするトレーナーです。 |
| 栄養トレーナー | 食事や栄養の面からトレーニングをサポートするトレーナーです。 |
トレーナーの重要性
トレーナーの存在がなぜ重要かというと、良い指導を受けることで、効率よくトレーニングができるからです。また、初心者の方でも安心して運動を始められます。トレーナーのアドバイスを受けることで、怪我のリスクを減らすこともできます。
まとめ
トレーナーは、私たちの健康や体力を支える大切な役割を持つ存在です。どのタイプのトレーナーが自分に合っているかを見つけ、よりよいトレーニングライフを送るために活用していくことが大切です。
トレーナーのサジェストワード解説アスレチック トレーナー とは:アスレチックトレーナーとは、スポーツ選手や運動をする人たちの健康やパフォーマンスを支える専門家のことです。彼らは怪我の予防やリハビリ、運動指導などを行います。部活動やスポーツクラブでは、アスレチックトレーナーが選手の練習や試合をサポートしています。特に怪我をした場合、彼らは治療や回復に向けたトレーニングを手伝います。アスレチックトレーナーはスポーツ医学の知識が豊富で、体の仕組みやケガの治し方、適切な運動方法を熟知しています。彼らがいることで選手は安心して練習や試合に臨むことができるのです。また、アスレチックトレーナーは健康づくりのアドバイスも行い、成長期の子どもたちにとっても大切な存在です。アスレチックトレーナーの仕事は、ただのサポートではなく、選手の未来を守る重要な役割を果たしています。
アスレティック トレーナー とは:アスレティックトレーナーとは、スポーツや運動をする人たちの健康を守る専門家のことです。彼らは、ケガの予防やリハビリをサポートする重要な役割を担っています。例えば、試合や練習中に怪我をした選手がいた場合、アスレティックトレーナーはすぐに応急処置を行います。また、選手が再びプレーできるように、ケガの回復を助けるメニューを考えたり、必要なストレッチやトレーニングを指導することもあります。アスレティックトレーナーは、スポーツ医学について深く学び、選手と密接にコミュニケーションをとりながら信頼関係を築いていきます。そのため、スポーツの現場では欠かせない存在です。最近では、学校のクラブ活動や地域のスポーツチームでもアスレティックトレーナーが活躍するようになっています。彼らがいることで、選手たちはより安心してスポーツを楽しむことができます。アスレティックトレーナーは、私たちの健康を支える大切な職業なのです。
ジム トレーナー とは:ジムトレーナーというのは、ジムで運動する人をサポートするプロのことを指します。彼らは、筋力トレーニングやエクササイズの指導を行い、個々の目標に応じたトレーニングプランを作成します。たとえば、体を引き締めたい人や、筋肉を増やしたい人、それぞれに合ったアドバイスをしてくれます。また、正しいフォームで運動をすることも大切で、トレーナーはそのポイントを教えてくれるのでケガを防ぐことができます。ジムトレーナーになるには特別な知識が必要で、フィットネスや栄養学に関する資格を持っていることが一般的です。さらに、体力やコミュニケーション能力も求められるため、トレーナーは運動を教えるだけでなく、利用者との信頼関係を築くことも重要なのです。初心者でも安心してトレーニングを始められるようにサポートしてくれる、心強い存在となっています。
トレーナー とは スポーツ:スポーツには多くの役割を持つ人たちがいますが、その中でも特に重要なのが「トレーナー」です。トレーナーは、選手が最高のパフォーマンスを発揮できるようにサポートする専門家です。具体的には、選手の体のケアやトレーニングの指導、怪我の予防などを行います。たとえば、サッカーの試合前に選手のストレッチを手伝ったり、練習後に筋肉の疲れをほぐすマッサージをしたりします。このように、トレーナーは選手の健康を守り、パフォーマンスを向上させる大切な役目です。また、トレーナーになるためには、専門的な知識や技術が必要ですが、スポーツが好きな人にはやりがいのある職業と言えるでしょう。トレーナーとしての仕事を通じて、多くの選手と接し、一緒に成長していく喜びも感じられます。みなさんも、トレーナーという仕事に興味を持ってみてください!
トレーナー とは ファッション:トレーナーとは、カジュアルな日常着として人気のある服の一種です。多くは綿素材やポリエステル、スウェット生地で作られており、柔らかくて着心地が良いのが特徴です。これにより、リラックスした雰囲気を持っているので、学校や友達との遊び、さらにはスポーツにもぴったりです。トレーナーは、シンプルなデザインからカラフルなプリント、さらには有名ブランドのロゴが入ったものまで様々な種類があります。これらのデザインは、あなたの個性を表現するのに役立ちます。また、トレーナーは季節を問わず着ることができ、特に冬や秋には重ね着としても活用できます。例えば、トレーナーの上にジャケットを羽織ったり、インナーとしてシャツと組み合わせることができます。このように、トレーナーはシンプルでありながらもファッション性が高いアイテムとして、多くの人々に愛されています。トレーナーを上手にコーディネートすることで、カジュアルでもおしゃれなスタイルを楽しむことができます。これからも、トレーナーの魅力をどんどん発見していきましょう!
トレーナー とは 仕事内容:トレーナーとは、スポーツやフィットネスの分野において、人々の体力や健康を向上させるために指導を行う仕事のことです。トレーナーは、運動や食事についてのアドバイスを提供し、個々の目標に合わせたプランを作成します。また、正しいエクササイズの方法を教えたり、モチベーションを高めたりする役割も果たします。具体的には、ジムでの個別指導や、チームスポーツのトレーニング、リハビリにおける指導など多岐にわたります。トレーナーには、運動生理学や栄養学の知識が求められ、体の仕組みを理解する必要があります。さらに、コミュニケーション能力や人を励ます力も大切です。自分の健康を向上させたいと思っている人や、体を鍛えたい人の力になれる非常にやりがいのある仕事です。トレーナーは単に運動を教えるだけではなく、クライアントとの信頼関係を築き、共に成長していくことが求められます。これがトレーナーという職業の魅力でもあるのです。
トレーナー とは 服:トレーナーとは、一般的にスウェット素材で作られたカジュアルな服のことです。特に冬や秋に人気があり、暖かさと快適さを兼ね備えています。トレーナーは長袖が多く、体を包み込むようなデザインが特徴です。運動をする時や、家でリラックスする時にも着やすい服です。トレーナーはさまざまなデザインやカラーがあるため、自分の好みに合ったものを選ぶ楽しさがあります。また、トレーナーには無地のものやプリントが施されたもの、フード付きのものもあり、自分だけのスタイルを楽しむことができます。そして、トレーナーは男女問わず着ることができるため、家族や友達とお揃いで着ることもできます。選ぶ際は、サイズやデザインだけでなく、着心地や素材にも気を付けると良いでしょう。お気に入りのトレーナーを見つけることで、日常生活がもっと楽しくなります。
パーソナル トレーナー とは:パーソナルトレーナーとは、個々の目的に合わせてトレーニングプログラムを提供したり、栄養や健康についてアドバイスを行ったりする専門家のことです。運動したいけれど、方法がわからないという人や、より効率的にトレーニングをしたいと考えている人にとって、パーソナルトレーナーは心強い味方です。
彼らは、お客様の体力や筋力、健康状態を確認し、それぞれに合った運動メニューを作成します。たとえば、体重を減らしたい人には、有酸素運動を中心とするプログラムを提供し、筋肉を増やしたい人には、ウェイトトレーニングに重点を置いたプログラムを組みます。このように、パーソナルトレーナーは個別にサポートをすることで、目標達成を手助けしてくれます。
さらに、トレーニング中には正しいフォームを指導してくれるため、怪我の予防にもなります。また、モチベーションを保つお手伝いもしてくれるので、一人では続けることが難しい人にも最適です。トレーナーに相談することで、自分自身の成長を感じることができ、楽しく運動を続けられるでしょう。
ポケモン トレーナー とは:ポケモン トレーナーとは、ポケモンバトルを行うためにポケモンを育てたり、戦わせたりする人物のことを指します。トレーナーは、ポケモンを捕まえて育てるだけでなく、他のトレーナーとの戦いであるバトルに挑むことが重要な役割となります。ポケモンにはそれぞれ特性や技があり、これをうまく活用することがトレーナーにとっての大切なスキルです。 例えば、あるポケモンは水タイプであるため、炎タイプのポケモンに強いという特性があります。このように、ポケモンのタイプを理解して戦略を立てることが求められます。また、ポケモンをトレーニングすることでレベルを上げ、新しい技を覚えさせたり進化させたりすることもトレーナーの役割です。トレーナーは旅をしながらジムリーダーと呼ばれる強いトレーナーに挑戦し、勝利することでバッジを集めることが目標の一つとなります。最終的にはポケモンリーグに挑戦し、チャンピオンを目指すのです。ポケモン トレーナーとしての旅は非常に楽しく、仲間となるポケモンとの絆を深めながら成長していくことができるのです。
トレーナーの共起語フィットネス:身体を健康に保つための運動やトレーニングのことを指します。トレーナーはフィットネスをサポートする役割を果たします。
パーソナルトレーニング:個人のニーズに合わせたトレーニングプランを提供することを言います。トレーナーが一対一で行う場合が多いです。
筋力トレーニング:筋肉を強化するためのエクササイズです。トレーナーは正しいフォームや効果的な方法を指導します。
ダイエット:体重を減らすための食事や運動の管理を行うことです。トレーナーはクライアントに適した食事や運動方法を指導します。
健康:身体的、精神的、社会的な良好な状態を指します。トレーナーはクライアントの健康目標を達成するためにサポートします。
コンディショニング:体の状態を整えるためのトレーニングやメンテナンスのことです。トレーナーが専門的なアプローチで行います。
モチベーション:トレーニングや目標に向かって努力するための意欲や気持ちです。トレーナーはクライアントのモチベーションを高めるためのサポートをします。
ストレッチ:筋肉を伸ばすエクササイズです。トレーナーは適切なストレッチ方法を指導して怪我の予防に貢献します。
リカバリー:トレーニング後の体の回復を促すことです。トレーナーは適切なリカバリー方法を指導します。
エクササイズ:体を動かす行為全般を指します。トレーナーは多様なエクササイズを提供して、クライアントの目標達成をサポートします。
トレーナーの同意語トレーニングコーチ:フィットネスやスポーツにおいて、トレーニングプログラムを指導する専門家。
指導者:特定の技術や知識を持っており、他者にそれを教える役割の人。
フィットネスインストラクター:健康や運動に関するプログラムを受講者に教え、指導する専門家。
パーソナルトレーナー:個別のニーズに応じてトレーニングプログラムを設計し、直接指導を行うトレーナー。
エクササイズコーチ:運動やエクササイズを取り入れた健康的なライフスタイルをアドバイスし、導く専門家。
トレーナーの関連ワードフィットネス:体力や健康を向上させるための運動やトレーニングのこと。トレーナーはフィットネスの専門家として、個々の目標に応じたトレーニングプランを提供します。
パーソナルトレーニング:個々のニーズに合わせたトレーニング指導を行う方式。トレーナーが一対一で指導し、効果的に目標達成をサポートします。
エクササイズ:体を鍛えるための運動全般のこと。トレーナーは、正しいエクササイズの方法や効果を理解し、それを指導します。
コンディショニング:身体の状態を向上させるためのトレーニングや調整のこと。トレーナーは、クライアントの身体を最適な状態に整えるためにコンディショニングを行います。
栄養指導:食事や栄養に関するアドバイスを提供すること。トレーナーは、運動と組み合わせて健康的なライフスタイルを提案します。
集団トレーニング:複数の人が一緒に行うトレーニング。トレーナーが指導することで、楽しみながら効果的に運動できます。
モチベーション:目標に向かって行動するためのやる気や意欲のこと。トレーナーは、クライアントのモチベーションを高める役割も担います。
リハビリテーション:怪我や病気から回復するためのトレーニングや治療。トレーナーは、リハビリ専門の知識を持つことで、適切なサポートを行います。
ストレッチ:筋肉を伸ばして、柔軟性を高める運動。トレーナーは、ケガ予防やパフォーマンス向上のためにストレッチの重要性を教えます。
トレーニングプラン:特定の目的に応じた詳細なトレーニングのスケジュールや内容のこと。トレーナーは、クライアントの状態に合わせたプランを作成します。
トレーナーの対義語・反対語
トレーナーの関連記事
健康と医療の人気記事

2222viws

1849viws

2203viws

1555viws

1668viws

1199viws

1440viws

2088viws

1392viws

966viws

2074viws

2147viws

3546viws

1639viws

1989viws

1417viws

2216viws

2047viws

1925viws
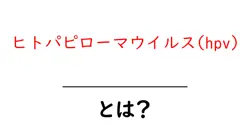
1348viws