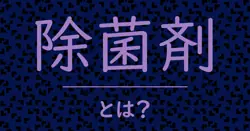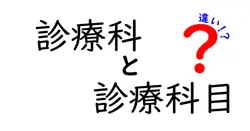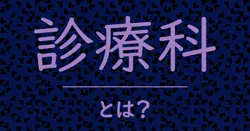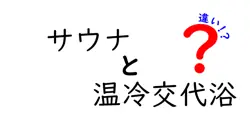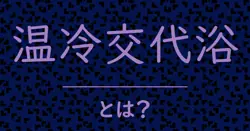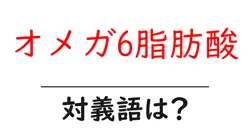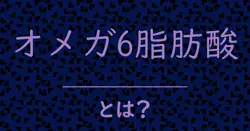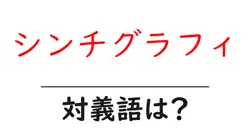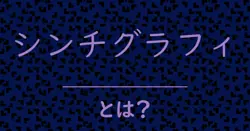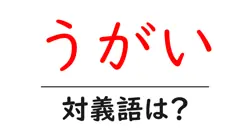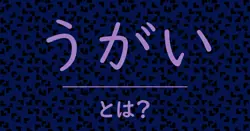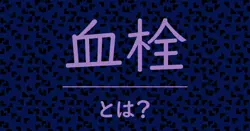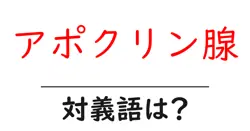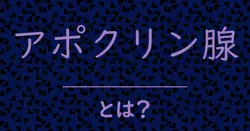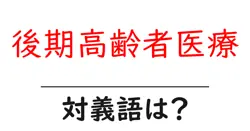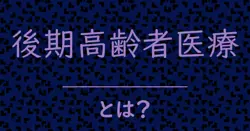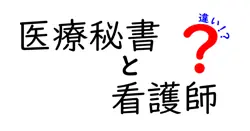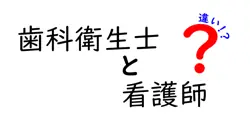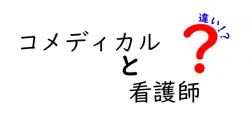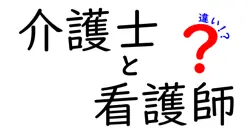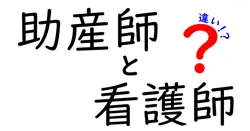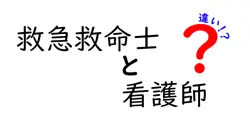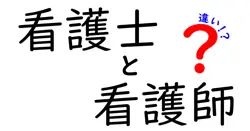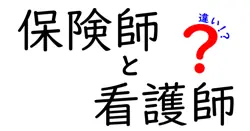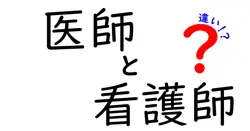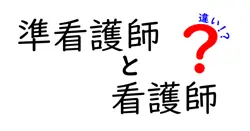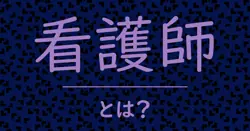除菌剤・とは?
私たちの生活の中で、清潔さを保つことはとても大切です。特に、病気を防ぐためには、手や周囲の環境を清潔に保つ必要があります。そこで登場するのが「除菌剤」です。
除菌剤の定義
除菌剤とは、細菌やウイルスを減少させるための製品です。通常、アルコール、塩素系成分、または天然由来の成分が含まれています。これらの成分が働くことで、手や物品から不必要な微生物を取り除いてくれます。
除菌剤の種類
| 除菌剤の種類 | 特徴 |
|---|---|
| アルコール系 | 速乾性があり、手指の除菌に最適 |
| 塩素系 | 広範囲の除菌に強いが、臭いが強い |
| 天然成分系 | 肌に優しく、環境にも配慮されている |
除菌剤の使用方法
除菌剤の使い方は簡単です。特に手指の場合は、適量を手に取り、指の間や爪の間までしっかりとこすり合わせます。乾くまで待ちますが、早ければ30秒ほどで効果が期待できます。
注意点
除菌剤を使う際にはいくつかの注意点があります。まず、目や口に入らないように気をつけることが大切です。また、肌が弱い人はテストを行うことをお勧めします。さらに、使用する場所によっては、強い成分が適していない場合もありますので、事前に確認しましょう。
まとめ
除菌剤は、私たちの健康を守るための強力な味方です。正しく使うことで、清潔で安心な生活を送ることができます。手軽に使えるので、ぜひ生活に取り入れてみましょう!
消毒:ウイルスや細菌を取り除くために、物体や空間に薬剤を使って清めることです。除菌剤と消毒剤は似ていますが、消毒はより広範囲な衛生管理を意味します。
抗菌:細菌の繁殖を抑える能力を持った物質や処置のことを指します。抗菌剤は除菌剤とは異なり、細菌を全て排除するのではなく、増殖を防ぐ役割を持ちます。
ウイルス:感染症の原因となる微細な病原体の一つであり、除菌剤はこのウイルスにも効果がある場合が多いです。特にインフルエンザウイルスやノロウイルスに対する対策が重要です。
衛生:健康を保つための清潔な状態を維持することを指します。除菌剤は衛生環境を保つための重要なツールです。
アルコール:除菌剤として広く使用される成分で、特にエタノールやイソプロパノールが多いです。これらのアルコールは細菌やウイルスを迅速に殺菌する効果があります。
スプレー:除菌剤の形態の一つで、液体を霧状にして対象にかけるものです。手軽に使用でき、多くの表面に均一に塗布できます。
清掃:除菌剤を使用する前に行う、物理的な汚れを取り除く作業のことです。掃除を行った後に除菌剤を使うことで、より効果的に衛生を保てます。
効果:除菌剤が持つ機能や効能のことです。効果的な除菌剤は、特定の菌やウイルスに対して高い効果を示します。
安全性:除菌剤を使用する際に考慮すべき重要な要素であり、体に対する影響や環境への配慮が求められます。
製品:市場に出ているさまざまな除菌剤のことを指します。各社から様々なタイプの除菌剤が販売されており、それぞれ成分や用途が異なります。
衛生管理:除菌剤を使用して、環境を清潔に保つために行う管理全般を指します。企業や家庭での衛生管理が重要視されています。
抗菌剤:細菌の増殖を抑えるために使用される薬剤で、主に感染症予防に役立ちます。
消毒剤:ウイルスや細菌を死滅させるための薬剤で、手や物品に使用されることが多いです。
殺菌剤:殺菌作用があり、細菌や微生物を排除するための薬品です。特に、医療現場でよく使われます。
クリーナー:汚れを取り除くための洗剤で、除菌成分が含まれているものもあります。日常的な清掃に使われます。
消臭剤:嫌な臭いを取り除くための製品で、除菌作用があるものも存在します。特に家庭や公共の場で使われます。
消毒:消毒は、病原菌やウイルスを殺したり、取り除いたりすることを指します。除菌剤を使用することで、表面や器具を安全に保つことができます。
ウイルス:ウイルスは病気の原因となる微小な病原体です。除菌剤は、特にウイルスを効果的に除去するために開発されている製品も多いです。
抗菌:抗菌は、細菌の増殖を抑える効果を持つことを指します。抗菌剤と除菌剤は似ていますが、除菌剤は既存の細菌を殺すことに対して、抗菌剤は増殖を抑えることに重きを置いています。
消毒液:消毒液は、抗菌や除菌の目的で使用される液体です。アルコールベースや次亜塩素酸ナトリウムを含むものなど、さまざまな種類があります。
次亜塩素酸:次亜塩素酸は、強力な除菌・消毒作用を持つ化合物で、主に水に溶かして使用されます。病院や食品加工業界などで広く使われています。
手指消毒:手指消毒は、手の表面を除菌する行為で、特にウイルスや細菌を防ぐために重要です。アルコール消毒剤を使用することが一般的です。
エタノール:エタノールは、主に消毒に使用されるアルコールの一種です。70%エタノールが最も効果的な濃度とされています。
除菌スプレー:除菌スプレーは、手や物の表面に直接スプレーして使用するタイプの除菌剤です。持ち運びに便利で、手軽に使用できます。
表面除菌:表面除菌は、テーブルやドアノブなど、接触部分を除菌することです。ウイルスや細菌の感染リスクを減らすために重要です。
強力除菌:強力除菌は、特に効果の高い除菌剤や方法を指します。通常、病院や公共施設など、感染予防が必要な場所で使用されます。
除菌剤の対義語・反対語
該当なし