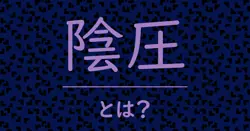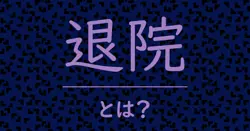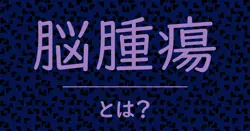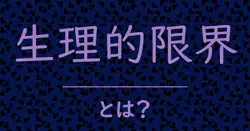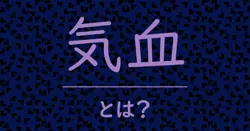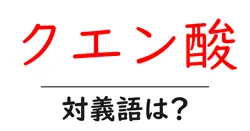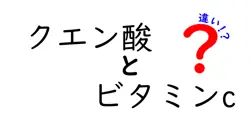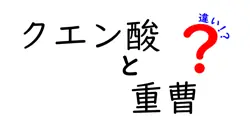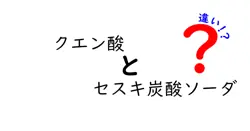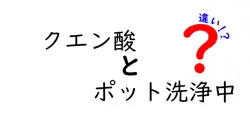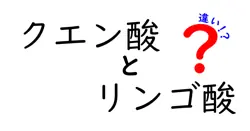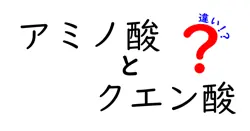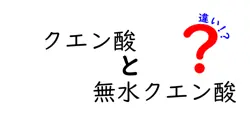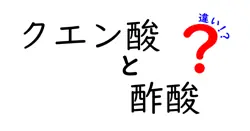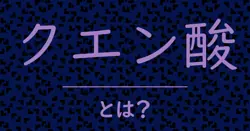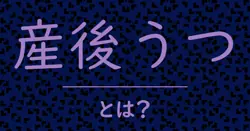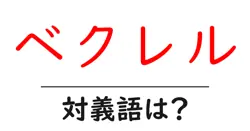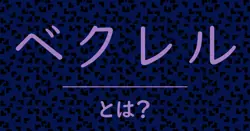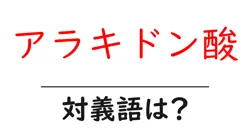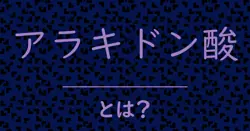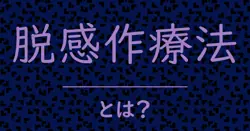陰圧とは?
陰圧(いんあつ)とは、ある空間や物体内の圧力が外部の圧力よりも低い状態を指します。この用語は、医学や工業など様々な分野で使われることが多いです。特に、病院などでは感染症予防のための陰圧室が設けられています。
陰圧の基本的な理解
空気は自然に高い圧力の場所から低い圧力の場所へ流れます。陰圧の状態では、内部の圧力が外部の圧力よりも低いため、空気がその内部に引き込まれようとします。この原理を利用することで、様々な用途で陰圧を利用することができます。
陰圧の利用例
以下に、陰圧の具体的な利用例を示します。
| 分野 | 用途 |
|---|---|
| 医療 | 感染症対策用の陰圧室 |
| 工業 | 真空抽出装置 |
| 研究 | 気体分析などの実験 |
陰圧室とは?
特に医療の分野で重要なのが陰圧室です。これは、感染症を持つ患者が他の患者に感染を広げないように、部屋の圧力を外部よりも低く保つ施設です。陰圧室では、室内の空気が特殊なフィルターを通って外部に排出されるため、ウイルスや細菌が外に漏れ出ることを防ぎます。
陰圧室の構造と機能
陰圧室の構造は、外部からの空気の流入を防ぎ、内部の空気を外に出すための仕組みがされています。この部屋は、他の部屋や空間と密接に繋がっておらず、圧力を維持するための特専用の換気システムが必要です。
まとめ
陰圧は、私たちの日常でも意外に多くの場面で利用されている概念です。医療現場での使用が特に知られていますが、工業や研究の分野でも重要な役割を果たしています。陰圧の仕組みや応用を理解することで、私たちの生活をより良くする手助けとなるでしょう。
吸引 陰圧 とは:「吸引 陰圧」という言葉は、医療の現場でよく使われる専門用語です。ここでいう「吸引」とは、体の中の液体や気体を取り除くことを指します。一方、「陰圧」は、周りの空気圧よりも低い圧力を意味します。これを使って、医療機器は特定の場所から不要なものを引き抜くことができます。たとえば、手術中には血液や体液を吸引する必要がありますが、このとき陰圧を利用します。こうすることで、手術がより安全に進められ、患者の回復が早まるのです。また、陰圧吸引は傷の治療にも使われます。傷口の中の感染を防ぐために、陰圧で汚れや余分な液体を取り除くことができるのです。このように、吸引陰圧は医療のさまざまな場面で重要な役割を果たしています。日常生活ではあまり目にすることがないかもしれませんが、医療を支える大切な技術なのです。
肺 陰圧 とは:肺陰圧とは、肺の中で生じる低い圧力のことを指します。私たちが息を吸うとき、胸が広がり、肺の中の圧力が周囲の空気よりも低くなります。この陰圧によって空気が肺に流れ込み、酸素を体内に取り込むことができるのです。逆に、息を吐くときには、胸が縮み、肺の圧力が高くなり、空気が押し出されます。このように、肺の陰圧は私たちの呼吸にとって非常に重要な役割を果たしています。もし肺の陰圧がうまく作れなかったり、何らかの理由で圧力のバランスが崩れると、呼吸が苦しくなったり、酸素が十分に取り込めなくなったりします。特に、肺炎や喘息などの病気があると、陰圧がうまく働かないことがあります。健康な呼吸は、肺の陰圧が正常に機能することによって支えられているのです。理解を深めるためには、実際に息を吸ったり吐いたりしてみるのも良いでしょう。自分の呼吸のメカニズムを感じ取ることが、肺陰圧についての理解をより深める助けになるはずです。
胸腔内圧 陰圧 とは:胸腔内圧(きょうくうないあつ)とは、私たちの胸の中の空間にかかる圧力のことです。普段、私たちは呼吸をするために息を吸ったり吐いたりしますが、その時に心臓や肺がどのように働いているのかを理解するには、この胸腔内圧を知ることが重要です。特に「陰圧」という言葉が関係しています。陰圧とは、周りの圧力よりも低い圧力のことを指します。つまり、胸腔内圧が陰圧の場合、肺は少ないエネルギーで空気を取り込むことができます。これにより、私たちは楽に呼吸ができるのです。たとえば、息を吸うとき、胸腔内圧が下がって陰圧が生じます。これを利用して空気が肺に入ってくるのです。また、息を吐くときは、胸腔内圧が上がって陰圧が失われます。このように、胸腔内圧と陰圧は、私たちの呼吸をスムーズにするために欠かせない大切な役割を果たしています。呼吸がしっかりできることは、元気に過ごすためにはとても大事ですね。
陰圧 とは わかりやすく:「陰圧(いんあつ)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?陰圧とは、ある空間の中の気圧が外側の空気圧よりも低くなっている状態を指します。例えば、掃除機の中は陰圧です。掃除機が動くと、空気が中に引き込まれます。このとき、掃除機の内部の気圧は外よりも低くなるからです。この状態を利用して、ゴミやほこりを効率的に吸い取ることができます。陰圧は医療の分野でも使われています。例えば、手術室では陰圧を保つことで、外部からの細菌やウイルスが室内に入るのを防ぎます。このように、陰圧は掃除機や医療現場など、私たちの生活の中で重要な役割を果たしています。少し難しく感じるかもしれませんが、身近な例で考えると理解しやすいですね!
陽圧 陰圧 とは 看護:看護の現場では、陽圧と陰圧という言葉が重要な意味を持っています。陽圧はある気体や液体が、管や器具から外に向かって押し出される圧力です。例えば、酸素マスクや人工呼吸器では、患者に酸素を供給するために陽圧が使われます。この仕組みによって、患者はより多くの酸素を吸収できるようになります。一方、陰圧は外部よりも圧力が低い状態を指します。陰圧は、傷口の治療や手術後の創部を管理する際に重要です。陰圧療法を使うことで、傷口の治癒が促進されます。看護師は、これらの圧力を適切に理解し、患者の状態に応じた治療を行うことが大事です。陽圧と陰圧の使い方を知ることで、より安全で効果的な看護が実現できます。現場では、圧力の管理が患者の健康に直接影響を与えるため、しっかりと学んでおく必要があります。
陽圧 陰圧 とは:「陽圧」と「陰圧」という言葉は、主に物理や気象の分野で使われます。まず、陽圧とは、圧力が周囲よりも高い状態を指します。例えば、風船を膨らませると、内部の空気圧が外部の空気圧よりも高くなります。この状態が「陽圧」です。一方、陰圧は周囲よりも圧力が低い状態のことです。例えば、真空状態の容器の中の圧力は周囲の空気よりも低く、この場合が「陰圧」にあたります。陽圧と陰圧は、気体や液体の動きに関わる重要な概念です。陽圧は物体を押し出す力を生み出し、陰圧は物体を引き寄せる力を生むため、風や水の流れを理解するのに役立ちます。この2つの概念を身近に感じる例としては、空気が押し出されることで起こる風の流れや、ストローを使って飲み物を吸い上げるときの陰圧の作用が挙げられます。陽圧と陰圧を知ることで、自然現象や機械の動きを理解する手助けになるでしょう。
気圧:周囲の空気が持つ圧力のこと。陰圧は気圧が低い状態を指す。
吸引:空気や液体を引き寄せること。陰圧は吸引の力を発生させる原因となる。
負圧:周囲の気圧に対して低い圧力の状態のこと。陰圧は負圧の一種でもある。
密閉:外部の空気が入らないように閉じられている状態。陰圧は密閉された空間で生じることが多い。
真空:空気がほとんど存在しない状態。極端な陰圧が真空を作り出すことがある。
圧力差:異なる場所の圧力の違い。陰圧は圧力差を生み出すことで、様々な現象を引き起こす。
機械:陰圧を利用する機器や装置(例:掃除機、真空ポンプなど)。
生理的:人間や動物の体に関連すること。陰圧は医療現場でも生理的な用途に使われることがある。
吸着:物質が他の物質に付着すること。陰圧は物質を吸着する助けになる場合がある。
バキューム:英語で「真空」を意味する言葉。陰圧に関連する技術や装置を指すことが多い。
負圧:周囲の気圧よりも低い圧力のこと。陰圧と同様に、内部の気圧が外部の気圧よりも低い状況を指します。
低圧:通常の圧力よりも低い圧力のこと。陰圧もこの一種で、特に陰圧は空気が引かれるような状態を示します。
真空:物質がほとんど存在しない状態、または非常に低い圧力の状態を指します。陰圧が強まると、真空に近づくことがあります。
減圧:圧力が下がることを意味します。陰圧を作り出すためには、通常の圧力から減圧する必要があります。
吸引:物体を引き寄せる力、または流体を引き込むことを指します。陰圧を利用して物体を吸引することができます。
負圧:周囲の大気圧よりも低い圧力のこと。陰圧の別名で、主に密閉された空間で使用される。
真空:空気や他の気体がほとんど存在しない状態。この状態では圧力が非常に低く、物質の性質が変化する。
圧力差:二つの場所の間の圧力の違い。陰圧状態では、周囲よりも内部の圧力が低くなっているため、圧力差が生まれる。
気密:気体が漏れ出すことのない状態。陰圧を維持するためには、気密性が強く求められる。
陰圧室:外部からの空気の侵入を防ぎ、内部の圧力を低く保つための特別な部屋。感染症対策などに利用される。
換気:室内の空気を新鮮なものと入れ替えること。陰圧を利用して、外部からの空気を引き込む方法もある。
ろ過:空気中の微細な粒子や雑菌を取り除く過程。陰圧室内では、ろ過装置を用いて清浄な環境を維持する。
エアロゾル:大気中に浮遊する微細な液体や固体の粒子。陰圧環境ではエアロゾルの影響を考慮する必要がある。
バイオハザード:生物由来の危険物質のこと。陰圧室は、バイオハザードを持つ物質を安全に取り扱うために設計されている。
インフルエンザ:ウイルス性の感染症で、陰圧環境がウイルスの拡散を防ぐために重要な場合がある。
陰圧の対義語・反対語
圧