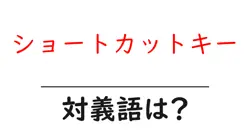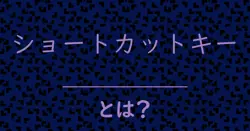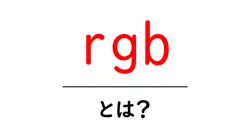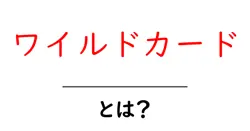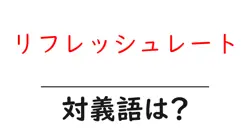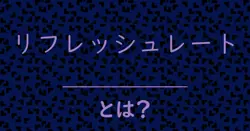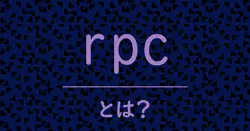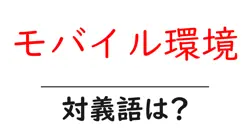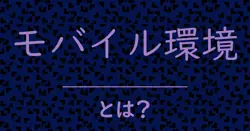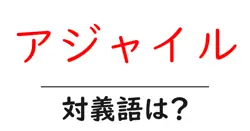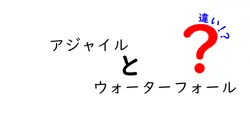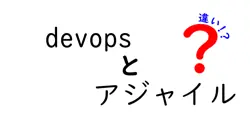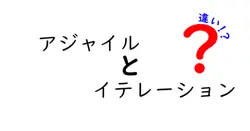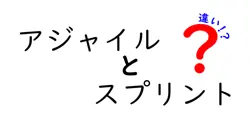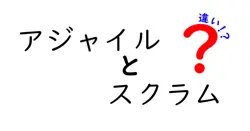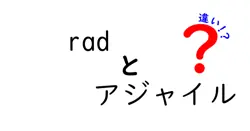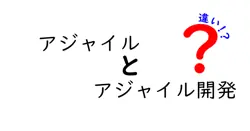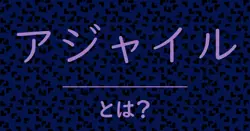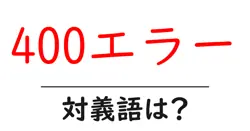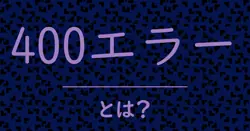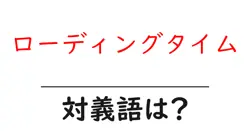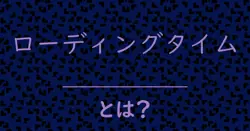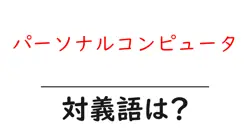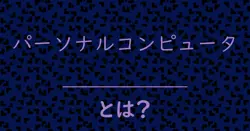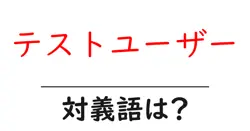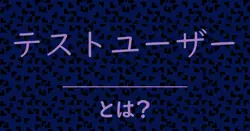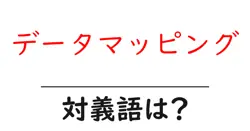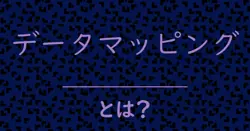皆さん、パソコンを使うとき、マウスだけでなくキーボードも使っていますよね。そのキーボードの特定の組み合わせを使うことで、操作を早くしたり簡単にしたりできる技のことを「ショートカットキー」と呼びます。
ショートカットキーのメリット
ショートカットキーを使うことで、以下のようなメリットがあります。
| メリット | 詳しい説明 |
|---|---|
| 時間の節約 | マウスを使うよりも早く操作できます。 |
| 効率的な作業 | 複数の作業を同時に行いやすくなります。 |
| 手首の負担軽減 | マウスを使わなくなるため、手首の疲れが減ります。 |
代表的なショートカットキー
初心者でも使いやすい、いくつかの代表的なショートカットキーを紹介します。
| ショートカットキー | 機能 |
|---|---|
| Ctrl + C | コピー |
| Ctrl + V | ペースト |
| Ctrl + Z | 元に戻す |
| Ctrl + S | 保存 |
| Alt + Tab | ウィンドウの切り替え |
まとめ
ショートカットキーは、パソコンを使う上で非常に便利な技術です。最初は覚えるのが難しいかもしれませんが、少しずつ練習していくことで、あなたの操作が驚くほどスムーズになります。ぜひ、この機会にいくつかのショートカットキーを覚えて、パソコン操作をもっと快適にしてみましょう!
pc ショートカットキー とは:PCを使う時、マウスだけではなくショートカットキーを使うと、作業が早く、便利になります。ショートカットキーとは、特定の操作を簡単にするためのキーボードの組み合わせです。例えば、文字をコピーする時は「Ctrl」キーと「C」キーを同時に押すだけで、簡単にコピーができます。また、「Ctrl」キーと「V」キーを押すと、コピーしたものをペースト(貼り付け)することができます。他にも、「Ctrl」キーと「Z」キーを押せば、間違えた時の操作を取り消せるので、とても便利です。パソコンの作業を効率よく進めたい方には必須の知識です。特に、学校の宿題やレポート作成の際に活用すると、時間を大幅に短縮できます。初心者でも簡単に覚えられるので、ぜひ試してみてください。これらのショートカットキーを覚えることで、作業がグッと楽になることでしょう。
エクセル ショートカットキー とは:エクセルのショートカットキーとは、操作を早くするための便利な鍵類のことです。例えば、コピーする時は「Ctrl + C」、貼り付ける時は「Ctrl + V」を使います。これらのショートカットキーを覚えることで、マウスを使うよりも素早く作業ができるようになります。動画作成やデータ分析で時間を節約したいなら、ショートカットキーを使うことが大切です。エクセルにはたくさんのショートカットキーがありますが、まずは基本のものから覚えましょう。例えば、ファイルを保存するための「Ctrl + S」や、印刷するための「Ctrl + P」もあります。これらを使うと、作業を効率的に進めることができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、何度も使ううちに自然に身につきます。日々の作業でこつこつと練習をし、自分のスピードを上げていきましょう。エクセルのショートカットキーを使いこなすことで、あなたももっと作業が早くなります!
パソコン ショートカットキー とは:パソコンを使っていると、ショートカットキーという便利な機能に出会うことが多いでしょう。ショートカットキーとは、特定の作業を簡単に行うためのキーの組み合わせのことです。例えば、コピーをする時には「Ctrl」キーを押しながら「C」キーを押すことで、選択したものを簡単にコピーできます。また、貼り付けるときは「Ctrl」キーを押しながら「V」を押します。このように、ショートカットキーを使うことで、マウスを使う手間が省け、作業効率がグッとアップします。初めは覚えるのが大変かもしれませんが、少しずつ使っていくうちに自然と身についてきます。よく使われるショートカットキーには、保存するための「Ctrl」+「S」やウィンドウを閉じるための「Alt」+「F4」などがあります。これらをぜひ試してみて、快適なパソコンライフを送りましょう!
キーボード:コンピュータやデバイスに文字や命令を入力するための装置。ショートカットキーはキーボード上で使用される。
操作:コンピュータなどの機器を使って目的の動作を行うこと。ショートカットキーは操作を効率化するための手段である。
効率:作業を行う際の時間や労力の使い方の良さ。ショートカットキーは操作の効率を上げるために使用される。
ウィンドウ:コンピュータの画面上に表示される作業領域の一つ。ショートカットキーを使うことで、ウィンドウの管理もスムーズになる。
アプリケーション:特定の目的を達成するために設計されたソフトウェア。各アプリケーションには専用のショートカットキーがあることが多い。
ショートカット:特定のコマンドや作業を簡単に実行できるようにするためのキーボードの組み合わせ。ショートカットキーはこの一部である。
ショートカットメニュー:特定の操作を迅速に行うために表示されるメニューで、通常は右クリックや特定のキー操作で開くことができる。
トグル:オンとオフの状態を切り替えることを指す。ショートカットキーでトグル操作が可能な機能もある。
設定:ソフトウェアやハードウェアの動作を変更するためのオプション。ショートカットキーも設定によってカスタマイズできる。
マウス:コンピュータを操作するための入力装置。ショートカットキーは、マウスを使うことなく操作を行うための重要なツールである。
キーボードショートカット:特定の操作を迅速に行うための、キーボードの特定のキーの組み合わせ。
ホットキー:特定のアプリケーションや機能を即座に呼び出すためのキーボードのショートカット。
ショートカット:コンピュータの操作において、通常よりも短い手順でアクションを実行するための方法。
キーコマンド:特定のキーやキーの組み合わせを使って実行するコマンドのこと。
キーボードコマンド:キーボードを使って直接入力する命令や操作。
ファンクションキー:F1からF12までのキーを指し、特定の機能に割り当てられることが多い。
アクセスキー:特定の操作を簡単に実行するために、選択されたアイテムにリンクするためのキーボード入力。
ショートカットメニュー:右クリックなどで表示される、特定の操作を迅速に行うことができるメニュー。
トグルキー:ある機能をオンまたはオフにするために使われるキーのこと。
ショートカットキー:特定の操作を簡単に実行するためのキーボードのキー組み合わせ。
キーボード:パソコンやデジタルデバイスに入力するための装置で、ショートカットキーはここで使われる。
ホットキー:特定のアプリケーションや機能に迅速にアクセスできるように設定されたショートカットキーのこと。
コピーペースト:データをコピー(複製)して、別の場所に貼り付ける操作を行う。ショートカットキーはCtrl+C(コピー)とCtrl+V(ペースト)が一般的。
マルチタスク:複数の作業を同時に行うこと。ショートカットキーを使うことで、効率的にマルチタスクを実現できる。
アプリケーション:特定の機能を持ったソフトウェアやプログラム。ショートカットキーは各アプリケーションごとに異なる場合がある。
オペレーティングシステム(OS):コンピュータやデバイスを動かすための基本的なソフトウェア環境。WindowsやMacOSなどのOSには、それぞれ特有のショートカットキーが存在。
カスタマイズ:ユーザーの好みに応じて設定を変更すること。一部のアプリケーションでは、自分専用のショートカットキーを作成できる。
ユーザーインターフェース(UI):ユーザーがデジタルデバイスと対話するための設計。ショートカットキーは、UI操作をよりシンプルにする手段でもある。
生産性:作業の効率や成果。ショートカットキーを使えば、作業を迅速に行うことが可能で、結果的に生産性が向上する。