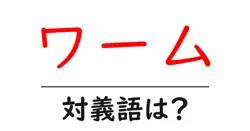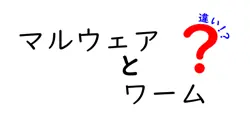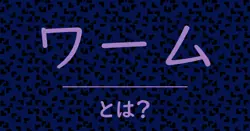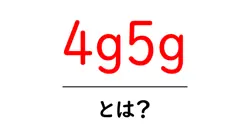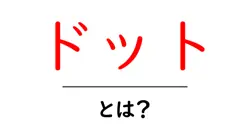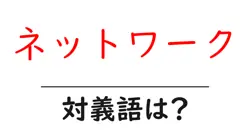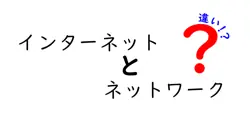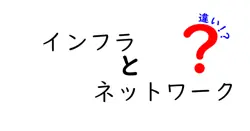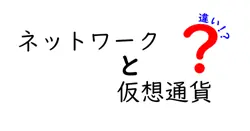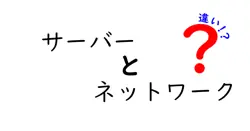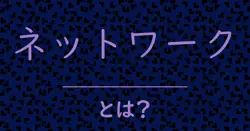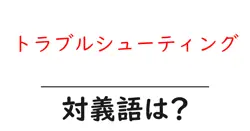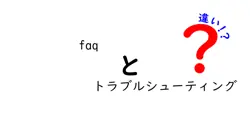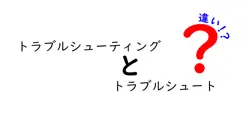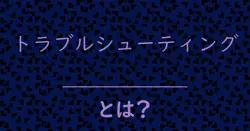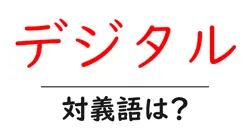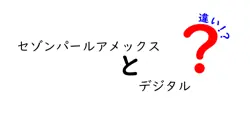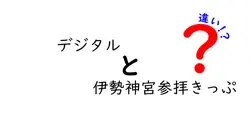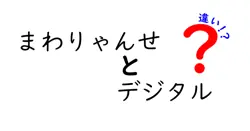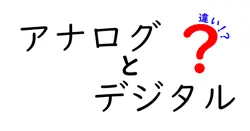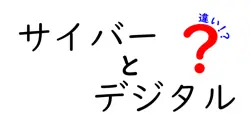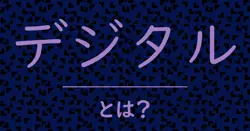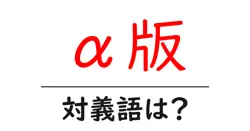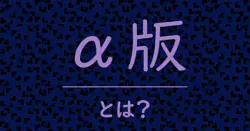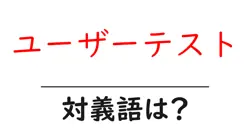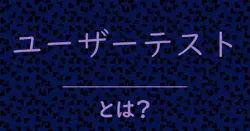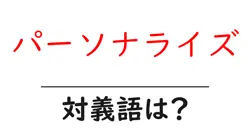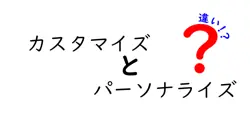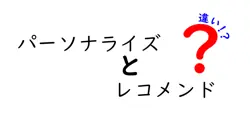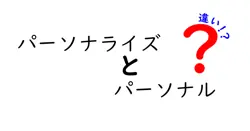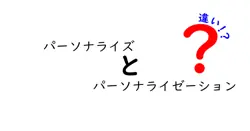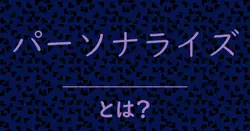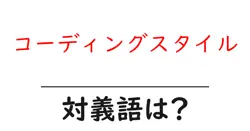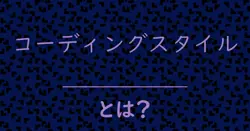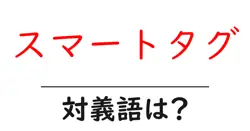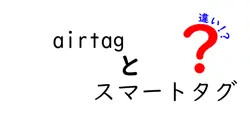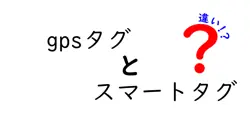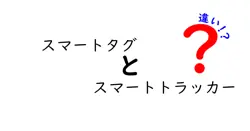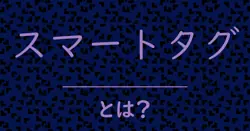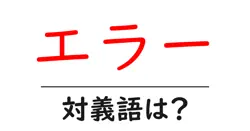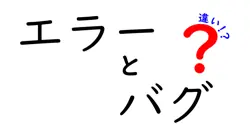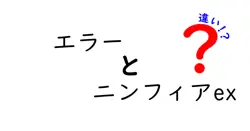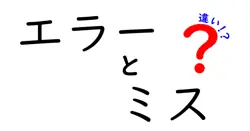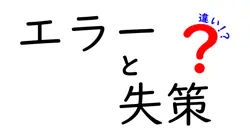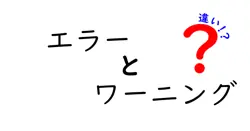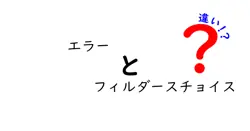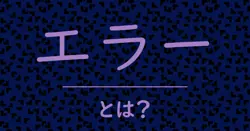「ワーム」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。特にインターネットやコンピュータを使うことが多い現代人にとって、このワームは無視できない存在です。ここでは、ワームの基本的な定義やその働き、さらには防ぎ方について詳しく解説します。
ワームの基本的な定義
ワームとは、悪意のあるプログラムの一種で、コンピュータやネットワークを通じて自己複製することができます。ウイルスと似ていますが、ウイルスは他のプログラムに寄生しながら増殖します。それに対して、ワームは単独で存在し、ネットワークを通じて他のコンピュータに広がります。
ワームの仕組み
ワームは、通常、電子メールの添付ファイルや特定のウェブサイトを通じて広がります。ユーザーがこれらのファイルを開いたり、リンクをクリックしたりすることで、ワームが自分のコピーを作成し、他のユーザーのコンピュータに感染します。これが繰り返されることで、瞬時に多くのコンピュータに広がるのです。
ワームの影響
ワームがコンピュータに感染すると、様々な悪影響を及ぼします。たとえば、システムの遅延やデータの消失などがあります。中には、情報を盗むために設計されたワームもありますので、注意が必要です。
ワームに感染しないための対策
ワームに感染しないための基本的な対策は以下の通りです:
| 対策 | 説明 |
|---|---|
| セキュリティソフトを導入する | 最新のセキュリティソフトを使うことで、ワームを検出し、削除することができます。 |
| 電子メールの添付ファイルに注意 | 知らない発信者からのメールには、安易に添付ファイルを開かないようにします。 |
| 定期的にソフトウェアを更新する | プログラムやオペレーティングシステムを最新の状態に保つことで、脆弱性を減らします。 |
まとめ
ワームは非常に危険な悪意のあるプログラムですが、適切な対策を講じることでその脅威を大きく減らすことができます。これからは、ワームについての理解を深めて、安全にインターネットを利用していきましょう。
コンピューターウイルス ワーム とは:コンピューターウイルスとワームは、どちらも私たちのパソコンに悪影響を与えるプログラムですが、実は性質が異なります。まず、コンピューターウイルスは、他のプログラムやファイルに感染して増えることが特徴です。ウイルスを持つプログラムを実行すると、そのウイルスがアクティブになり、他のデータに感染してしまいます。これに対し、ワームは独自に存在し、他のファイルに頼らずに自己複製を行います。ワームはネットワークを通じて広がることが多く、例えば、メールやインターネットを利用して他のコンピューターに感染するのです。ウイルスとワームは、いずれも私たちのデータやシステムに害を及ぼすため、注意が必要です。こまめなバックアップや、信頼できるセキュリティソフトの導入が大切です。また、不明なメールの添付ファイルを開かない、怪しいサイトにアクセスしないなど、基本的なルールを守ることで、感染リスクを減らすことができます。正しい知識を持って、コンピューターを安全に使いましょう!
トロイの木馬 ワーム とは:トロイの木馬とワームは、どちらもコンピュータのウイルスやマルウェアの一種ですが、それぞれ少し違う特徴があります。トロイの木馬は一見無害に見えるソフトウェアやファイルに隠れて侵入してきます。例えば、ゲームのプログラムやアプリをダウンロードする時に、実は悪意のあるコードが含まれていることがあります。これをインストールすると、知らないうちに個人情報が盗まれたり、他のコンピュータに感染を広げたりします。一方、ワームは自己複製する能力を持つウイルスで、他のコンピュータに自動的に侵入し、感染を広げます。つまり、ワームは一度感染すると、他の多くのデバイスにすぐに広がる危険があります。両者とも、私たちのデータやプライバシーを脅かす存在です。しっかりとしたセキュリティ対策を取ることが大切です。アンチウイルスソフトを使ったり、不審なメールやリンクに注意を払ったりすることで、これらの脅威から身を守ることができます。
マンゴー ワーム とは:マンゴー ワームとは、マンゴーの果実の中にいる小さな虫のことです。この虫は、実際には虫の幼虫で、果物の中に入り込んで成長します。ショッキングなことに、マンゴーを食べるときにこれらの虫がいることがありますが、通常は目に見えません。この虫は一般的には害虫とされていて、マンゴーを生産している農家にとっては大きな問題です。虫がマンゴーの内部にいると、果実が傷んでしまい、見た目も悪くなります。しかし、驚くかもしれませんが、マンゴー ワームは食べても害はないのです。多くの国では、マンゴーが栄養豊富で健康的な食べ物として人気があります。何が大切かというと、しっかりと洗ったり、状態の良いマンゴーを選んだりすることです。これにより、おいしいマンゴーを楽しむことができます。
ワーム とは 釣り:釣りをしていく上で、ワームという用語をよく耳にしますが、それは一体何を指しているのでしょうか?ワームとは、主に釣りの餌として使用される人工的なルアーの一種です。多くの場合、ゴムやビニールで作られた柔らかい素材でできており、形や色もさまざまです。ワームは特にバス釣りやトラウト釣りで人気があります。これを使用することで、よりリアルな餌に見え、魚を引き寄せやすくなります。使い方は簡単で、釣り糸やフックに装着するだけ。水の中で動かすことで、魚にとって自然な餌として感じられ、効果的にアプローチできます。また、ワームは軽量で持ち運びがしやすく、初心者でも扱いやすいのが魅力です。色々な種類があるため、自分の好きなスタイルや釣る対象の魚に応じて選んでみると良いでしょう。私たちが普段釣りを楽しむためには、こうした道具を知って使いこなすことが大切です。これからの釣りがもっと楽しくなるワームについて、ぜひ試してみてください。
ワーム ズル引き とは:ワームズル引きは、釣りのテクニックの一つで、主に淡水での釣りに使われます。ワームとは、魚を引き寄せるための疑似餌のことです。ズル引きは、ワームを水中で滑らせるように引く技術を指します。これにより、魚が自然に見える動きでワームに近づきやすくなります。初心者でも簡単に実践できるこの方法は、特にブラックバスや鯉釣りに効果的です。道具は、ルアーロッドとリール、ワームを固定するフックが必要です。まずは、ワームをフックに取り付け、ゆっくりと水中に投げ入れます。その後、リールを少しずつ引いて、ワームが地面を這うように動かします。これがズル引きの基本です。焦らず、ゆっくり引くことがポイントです。また、魚がかかったら、優しく引き上げるコツも大事です。初めての方でも、実際にやってみると楽しいので、ぜひ挑戦してみてください。
ワーム 夜光 とは:「ワーム 夜光」とは、夜になると光る不思議な生き物のことを指します。このワームは、自然の中で特別な化学物質を持っていて、それによって暗闇の中で青白く光るのです。夜光を放つことで、仲間を集めたり、捕食者から身を守るといった役割があります。多くの種類が存在し、それぞれ光の色や強さが異なります。ワームの光は、昆虫と同じように、生態系の中で重要な役割を果たしています。例えば、夜行性の動物がこの光を目印にして、食べ物を見つけることがあります。また、夜光を発するワームは、釣りにも利用されることがあります。釣り人たちは、夜光のワームを使って魚を引き寄せる方法をよく使います。光ることで魚にアピールできるため、非常に人気です。このように、「ワーム 夜光」は自然界での生き残り戦略の一部であり、人間にとっても興味深い存在になっています。今後もこの不思議な生き物について、もっと知っていくと面白いことがたくさんありそうですね。
情報セキュリティ ワーム とは:情報セキュリティにおいて「ワーム」という言葉をよく耳にしますが、これは一体何なのでしょうか。ワームとは、コンピュータやネットワークに感染し、勝手に自分をコピーして広がる悪意のあるソフトウェアのことです。ワームはウイルスと似ていますが、ウイルスは他のプログラムに寄生して存在しますが、ワームは単独で行動します。ワームが自分のコピーを作る過程で、ネットワークを通じて他のコンピュータに侵入していきます。これにより、データの破壊や勝手にネットワークの帯域を使ってしまうことがあり、企業や個人にとって大きな脅威になります。ワームは特にインターネットを通じて広がるため、無防備な状態でいるとあっという間に感染してしまうことがあります。私たちは、アンチウイルスソフトを使ったり、怪しいメールのリンクをクリックしないことで、ワームから身を守ることが重要です。ワームについて理解し、防御策を講じることで、情報セキュリティをしっかりと管理することができるのです。
マルウェア:コンピュータに悪影響を与えるソフトウェアの総称。ワームはこの中の一種で、自己複製を行い、他のコンピュータに感染する特性を持っています。
ウイルス:他のプログラムに寄生して自己複製を行う悪意のあるコードのこと。ワームと違って、ウイルスは参照元のプログラムと一緒に存在する必要があります。
トロイの木馬:見た目は無害なプログラムでありながら、実際にはデータを盗んだり、システムに悪影響を与えたりする悪意のあるソフトウェア。ワームとは異なり、自己複製の機能は備えていません。
ネットワーク:コンピュータ同士が相互接続されているシステム。ワームはこのネットワークを通じて広がるため、感染が迅速に拡大することがあります。
セキュリティ:システムやデータを外部の攻撃から守るための対策や技術のこと。ワームからの脅威を防ぐためには、適切なセキュリティ対策が必要です。
感染:ワームやウイルスがシステムに侵入し、動作を開始すること。感染が広がると、システムのパフォーマンスが低下することがあります。
ファイアウォール:ネットワーク上の不正アクセスを防ぐための技術やデバイス。ワームの侵入を防ぐために重要な役割を果たします。
スパム:無差別に送信される迷惑メールのこと。ワームは、スパムメールの添付ファイルとして広がることがあります。
システム:コンピュータのハードウェアとソフトウェアが組み合わさったもの。ワームによる感染は、システム全体に影響を及ぼす可能性があります。
駆除:感染したワームやウイルスを取り除くプロセス。専用のソフトウェアを使用することが一般的です。
アップデート:ソフトウェアやシステムを最新の状態に更新すること。定期的に行うことで、ワームなどの脅威からシステムを保護できます。
ウィルス:コンピュータやネットワークに感染し、自身をコピーして広がる悪意のあるプログラム。ワームの一種とも言えるが、主にユーザの操作を介して広がる。
トロイの木馬:一見無害なプログラムに見えるが、その実体は悪意のある機能をもつプログラム。ワームとは異なり、自己複製する能力はない。
マルウェア:悪意のあるソフトウェアの総称で、ウィルス、ワーム、トロイの木馬など、害を及ぼす目的で作られたプログラムを指す。
ボットネット:感染したコンピュータがネットワークで連携し、サイバー攻撃やスパムメールを送信するために利用されるプログラム群。ワームによって広がることが多い。
スパイウェア:ユーザーの行動を監視し情報を収集することを目的としたソフトウェア。ワームとは異なるが、悪意のあるプログラムとして同じく危険視される。
マルウェア:悪意のあるソフトウェアの総称で、ワームやウイルスなどが含まれます。コンピュータやネットワークに害を及ぼすことを目的としています。
ウイルス:他のプログラムに寄生しながら感染を広げる悪意のあるソフトウェア。ワームとは異なり、ホストファイルを必要とします。
トロイの木馬:見かけは無害なプログラムですが、実際には悪意のある機能を持ち、コンピュータのセキュリティを脅かすものです。
ボットネット:悪意のあるソフトウェアに感染した大量のコンピュータ(ボット)が連携して、攻撃や不正な活動を行うネットワークのことです。ワームがボットの一部として利用されることもあります。
セキュリティホール:ソフトウェアやシステムの脆弱性で、攻撃者がそれを利用して不正アクセスを試みることができます。ワームはしばしばこの脆弱性を利用して感染を拡大します。
パッチ:ソフトウェアのバグやセキュリティホールを修正するための更新プログラム。定期的に適用することで、ワームなどの攻撃から守ることができます。
ファイアウォール:ネットワークのセキュリティ設備で、不正なアクセスを防ぐために設置されます。ワームの感染を未然に防ぐ手段の一つです。
フィッシング:偽のウェブサイトやメッセージを使って、ユーザーから個人情報を騙し取る手法。ワームの感染を広げるために、フィッシング攻撃が利用されることもあります。
リモートアクセス:ネットワークを介して、離れた場所からシステムに接続すること。ワームはリモートアクセスを利用して、感染を拡大させることがあります。
サイバー攻撃:ネットワークやコンピュータに対する悪意のある行動を指します。ワームはさまざまなサイバー攻撃の一環として利用されることがあります。