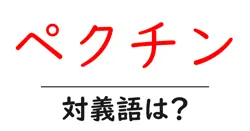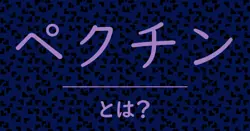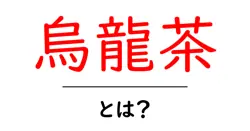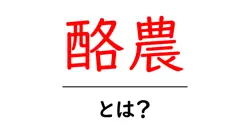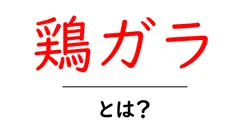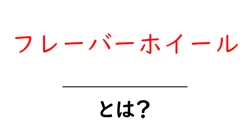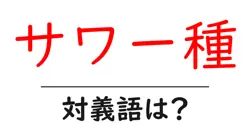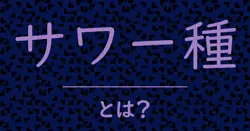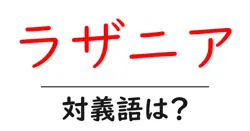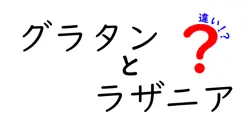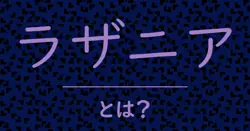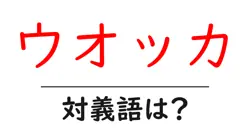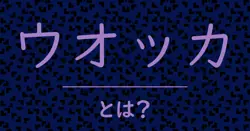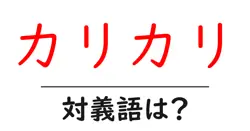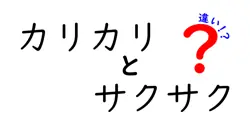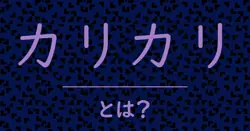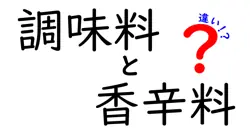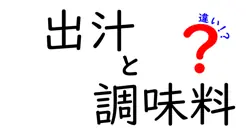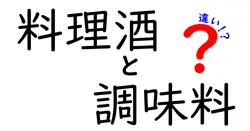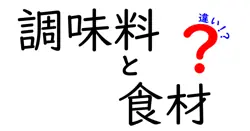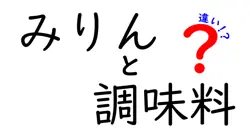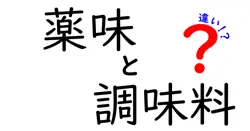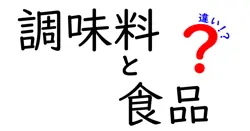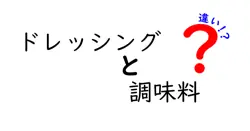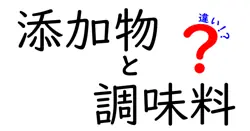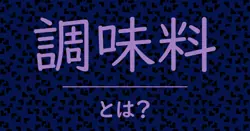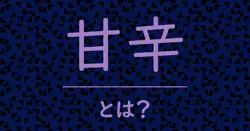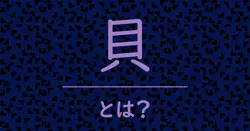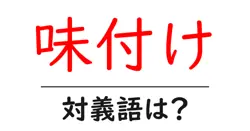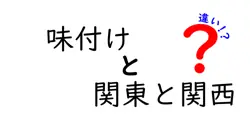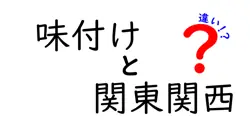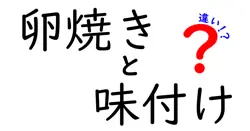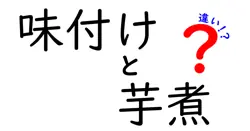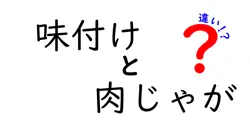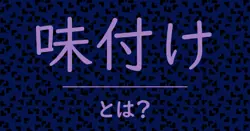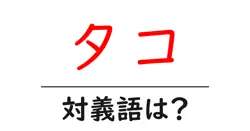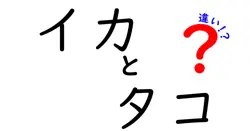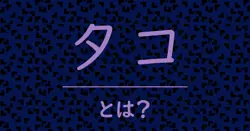ペクチンって何?その効果と使い方をわかりやすく解説!
皆さんは「ペクチン」という言葉を聞いたことがありますか?ペクチンは、果物や野菜に含まれる天然の成分で、特に果実の中に多く存在します。今回はこのペクチンについて、詳しく見ていきたいと思います。
ペクチンとは?
ペクチンは、植物の細胞壁を構成する成分の一つで、特に果実の中で果肉と種子をつなぎとめる役割を果たしています。ペクチンは、水と混ざるとゲル状になり、この性質を活かしてジャムやゼリーなどの食品が作られます。
ペクチンの主な効果
ペクチンにはいくつかの健康に良い効果があります。以下に主な効果をまとめました:
| 効果 | 説明 |
|---|---|
| 消化促進 | ペクチンは腸の働きを助け、便秘解消に役立ちます。 |
| コレステロールの低下 | ペクチンはコレステロールを吸着し、体外に排出するのを助けます。 |
| 血糖値の安定 | ペクチンは糖の吸収を遅らせるため、血糖値の急上昇を防ぎます。 |
ペクチンの使い方
ペクチンは料理やお菓子作りに非常に便利です。特にジャムやゼリーを作る際に、果物のペクチンを利用することが一般的です。また、家庭用のペクチンも市販されており、スーパーマーケットなどで簡単に手に入ります。使う際は、レシピに合わせて必要な分量を計算して使いましょう。
市販のペクチンを使った簡単なレシピ
ジャムを作る時は、果物、砂糖、市販のペクチンを用意します。果物を煮詰めてから砂糖とペクチンを加え、混ぜるだけでおいしいジャムが出来上がります。自分の好みに合わせて、レモン果汁やスパイスを加えても良いでしょう。
まとめ
ペクチンは、健康に良い効果があり、料理にも役立つ成分です。特にジャムやゼリー作りに最適で、自分自身で作れる楽しさもあります。ペクチンを上手に活用して、美味しい食生活を楽しみましょう!
ゲル化剤(ペクチン)とは:ゲル化剤の一つにペクチンという物質があります。ペクチンは主に果物の皮や種に含まれていて、特にリンゴやオレンジに多く見られます。料理やお菓子作りにおいて、ペクチンは特にジャムやゼリーを作る際に重要な役割を果たします。ペクチンを使うことで、液体が固まり、トロリとした良い食感になるのです。食材の中にあるペクチンが加熱と砂糖の影響で、ゲル状になり、私たちが知っている美味しいジャムやゼリーができるのです!また、ペクチンには健康に良い効果もあり、食物繊維として腸内環境を整える働きも期待されています。つまり、ペクチンは美味しさだけでなく、健康にも良い成分なのです。いろいろな果物を使って、あなたも自宅でジャムやゼリーを作ってみたくなりますね!ペクチンを使うことで、自分だけのオリジナルな味を楽しむことができます。ぜひ、ペクチンについてもっと興味を持って、食事に取り入れてみましょう!
セルロース ペクチン とは:セルロースとペクチンは、植物に含まれる非常に重要な成分です。セルロースは、植物の細胞壁を構成する主要な成分で、木や草などの硬い部分を作り出しています。これにより、植物は強い構造を持つことができ、成長を支えることができるのです。セルロースは私たちの体では消化できませんが、食物繊維の一種として健康に良い影響を与えます。 一方、ペクチンは果物の中に多く含まれている成分で、特にジャムやゼリーを作るときに重要な役割を果たします。ペクチンは果実の細胞の間にあるゲル状の物質で、甘みのある果物から抽出されることが多いです。ペクチンも食物繊維の一種であり、腸の健康に良い影響を与えてくれます。 これらの成分は、私たちの食生活や健康に欠かせない要素です。自然の食材から取れるこれらの成分を意識して食べることが、より良い健康につながるでしょう。
安定剤 ペクチン とは:安定剤ペクチンは、主に果物から抽出される天然の食品添加物です。特に、ジャムやゼリーの製造に使われており、食品のテクスチャーを改善する役割があります。ペクチンは、果物に含まれる多糖類の一種で、熱を加えたり、糖分と一緒に使ったりすることで、ゲル状になり、食品が固まるのを助けます。これにより、ジャムがしっかりとした食感になり、喉越しも良くなります。ペクチンは、体にも優しく、アレルギーを引き起こすことが少ないため、安心して使用できる添加物です。また、果物に多く含まれているため、自然のものを使ってエコロジーにも配慮されています。安定剤ペクチンは、スイーツや料理に使われるだけでなく、健康にも良い影響を与える可能性があります。これからの料理やお菓子作りで、ぜひペクチンの使い方を試してみてください。
野菜 ペクチン とは:ペクチンは、果物や野菜に含まれる成分で、特にリンゴや柑橘類に多く含まれています。ペクチンは、食物繊維の一種であり、私たちの体にとても良い影響を与えます。まず、ペクチンは腸内環境を整える働きがあります。これにより、便秘を改善したり、腸内のバランスを保つことができます。また、ペクチンは血糖値の上昇を抑え、糖尿病の予防にも役立つと言われています。そして、コレステロールを減少させる効果もあり、心臓病のリスクを低下させる助けになります。さらに、ペクチンが含まれている食べ物は、満腹感を感じやすくするため、ダイエット中の人にもおすすめです。このように、野菜に含まれるペクチンは、健康にとって非常に重要な役割を果たしています。普段の食事にもっと野菜を取り入れて、ペクチンの効果を実感しましょう。
果物:ペクチンは主に果物に含まれる成分であり、特にリンゴやオレンジ、ベリー類に多く含まれています。
ジャム:ペクチンはジャムやゼリーを作る際のゲル化剤として使われます。果物の糖分と反応し、食感を良くします。
ゲル化:ペクチンは水分と結びつくことでゲル状になる特性があり、食品の食感を変える役割を果たします。
食物繊維:ペクチンは水溶性の食物繊維であり、消化器官の健康をサポートし、便通を良くする効果があります。
栄養:ペクチンには、腸内環境を整える効果があり、栄養の吸収を助ける役割もあります。
薄荷:ペクチンは薄荷(ミント)のような香りを持つ場合があり、その香りを引き立てる作用もあります。
摂取:ペクチンを含む食べ物を摂取することで、健康に良い影響を与えることが期待できます。
ダイエット:ペクチンは満腹感を得やすくするため、ダイエット中のおやつとして選ばれることもあります。
食品添加物:商業用の食品には、ペクチンが食品添加物として使用されることが多く、保存性や風味を向上させます。
健康:ペクチンには整腸作用があり、健康的な生活をサポートする重要な成分です。
食品添加物:食品に風味や色、保存性などを加えるために使用される物質。ペクチンは果物や野菜から得られる天然の食品添加物の一例です。
ゲル化剤:液体をゲル状に変えるための物質。ペクチンはゼリーやジャムの製造において、液体を固める役割を果たします。
増粘剤:食品の粘度を増すために使われる物質。ペクチンはジャムやスムージーなどの粘度を調整する際にも利用されます。
食物繊維:消化されにくい植物由来の成分で、腸内環境を整える効果があります。ペクチンも食物繊維の一種で、健康に良い影響を与えます。
ゲル化:ペクチンが水分と結合して、ゼリー状や粘度のある構造を形成する現象です。果物のジャムやゼリーの制作に多く使用されます。
果実:ペクチンは主に果実に自然に含まれている多糖類です。特にリンゴや柑橘類に多く含まれており、果物を使った加工食品において重要な役割を果たします。
食品添加物:ペクチンは、食品に添加して食感を改善するための添加物としても使用されます。ジャムやデザートの粘度を高めるのに役立つ成分です。
ゼラチン:ペクチンとよく比較される物質で、動物性の成分から作られるゲル化剤です。ペクチンは植物由来なので、ビーガンやベジタリアンに好まれることが多いです。
溶解性食物繊維:ペクチンは水に溶けやすいタイプの食物繊維の一つで、腸内環境を改善する効果があります。健康的な食生活に取り入れることが推奨されています。
pH:ペクチンのゲル化にはpHが重要です。酸性の環境(pHが低い)で特にゲル化が進むため、果物の酸味が大切な要素となります。
糖類:ペクチンのゲル化には糖類が必要です。果糖やグルコースなどの糖が加わることで、ペクチンはより効果的に機能することができます。
保存料:ペクチンは保存料としての役割も果たします。ジャムやジュースの品質保持を助け、腐敗を防ぐ機能があります。
ペクチンの対義語・反対語
ペクチンとは?|ジャムの豆知識|知る・見る・体験する - アヲハタ
ペクチンとは?|ジャムの豆知識|知る・見る・体験する - アヲハタ