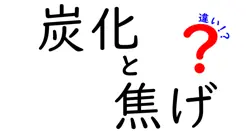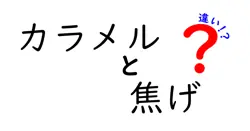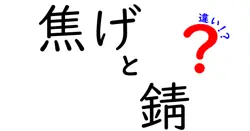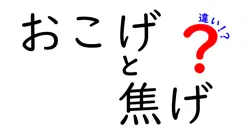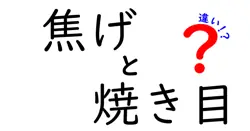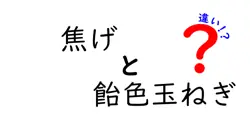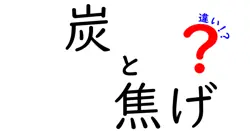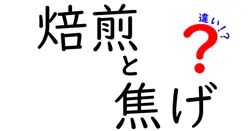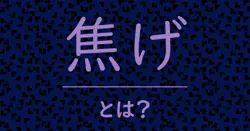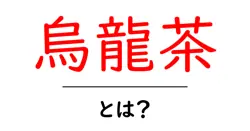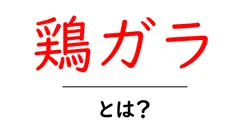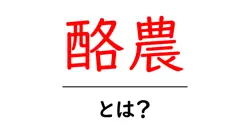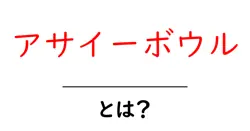焦げとは?
焦げとは、食材が焼かれる過程で、その表面が熱によって茶色く変わる現象のことを指します。特に、パンや肉、野菜などが高温で調理されることによって、焦げ目ができることが多いです。この焦げ目には特有の香ばしい香りや味があり、料理の見た目を引き立てる役割も果たします。
焦げができる理由
焦げができるメカニズムは、熱による化学反応にあります。食材の中に含まれる糖分やアミノ酸が加熱されることで、メイラード反応と呼ばれる現象が起こります。この反応によって、食材の色や味、香りが変わりますが、加熱しすぎると焦げてしまいます。
焦げの種類
| 焦げの種類 | 説明 |
|---|---|
| 軽い焦げ | 表面がわずかに茶色くなる程度。香ばしさが増す。 |
| 中程度の焦げ | 茶色が濃くなり、苦味が生じるが、香ばしさは残る。 |
| 強い焦げ | 真っ黒になり、食材の風味が失われる。苦味が強い。 |
焦げのメリットとデメリット
焦げにはメリットとデメリットがあります。以下のようにまとめられます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 香ばしい風味が加わる | 健康に良くない成分が生成される可能性がある |
| 食欲をそそる見た目になる | 食材によっては食べられなくなることがある |
焦げに関する注意点
焦げを避けるためには、焼き時間を短くしたり、温度管理をしっかり行うことが重要です。また、焦げた部分は健康に良くない場合があるため、食べない方が良いとされています。特に、焦げの成分が発がん性物質であることもあるため、注意が必要です。
まとめ
焦げとは食材が焼かれることで表面が変化する現象です。香ばしさを楽しむことができる一方で、健康への影響も考慮する必要があります。料理の際は焦げに注意しながら、美味しい食事を楽しむことが大切です。
焼き:食品を熱で調理すること。焦げは焼き過ぎた結果として現れることが多い。
炭:木や植物などが高温で燃焼してできる黒い物質。焦げた部分が炭化してできることがある。
香ばしさ:焼いたり焦がしたりすることによって生まれる、良い香りのこと。焦げは香ばしさを引き立てる場合もある。
煙:物質が燃焼することで発生する空気中の微細な粒子。焦げた物からは煙が出ることがある。
焦げ目:食品の表面にできる焼き色のこと。しっかりとした焦げ目は香ばしさを増すことがある。
クリスピー:食べ物の食感がパリッとしていること。焦げた部分がクリスピーな食感を生むことが多い。
カリカリ:食べ物が非常にパリパリとした食感を持つこと。焦げた部分にカリカリ感があることも多い。
焦がす:意図的または不注意により、食品や物体を高温で加熱しすぎて焦げさせることを指す。
グリル:食材を直火で焼く調理方法。焦げ目がつくことが特徴的。
オーブン:食材を内部で均等に加熱できる調理器具。焦げ目をつけるための焼き方にも用途がある。
焼け:物を熱で加熱して、表面が黒くなったり、色が変わった状態を示します。焦げる前の段階でも使われることがあります。
こげ:焼いたり煮たりした際に、焦げた部分を指します。特に焦げた部分が強調されることが多いです。
焦点:焦げる現象の中心を指す言葉で、焦げの発生点に焦点を当てた表現です。
黒ened:英語の「blackened(黒くなった)」をあえて和訳した表現で、特に強調して黒くなった部分を指すことが多いです。
こんがり焼けた:焼いたものが焦げる手前の、香ばしい焼き色がついた状態を指す表現。料理としては好まれる部位です。
焼き:焦げるプロセスを含む、食材が熱で変化する過程。焼くことで風味が増し、食感が変わる。
豪華な焦げ目:食材の表面にできる豪華な茶色の焦げ目。これにより、見た目が美しくなり、香ばしい味わいが生まれる。
カリカリ:焦げた部分がカリッとした食感のこと。特に肉や野菜の焦げた部分に多く見られ、食欲をそそる要素となる。
焦げ付く:調理中に食材が鍋やフライパンにくっついて焼けること。これを避けるために、油を適度に使ったり、火加減を調整することが必要。
焦げの味:食材が焦げた部分から出る独特の風味。この風味は、調理法によっては好まれることもあるが、過剰になると苦味を引き起こす可能性がある。
焦げを防ぐ:食材が過度に焦げないようにするための方法。適切な温度管理や、アルミホイルを使うなどの工夫が求められる。
焦げがつく:料理中に食材や鍋に焦げができてしまうこと。調理のタイミングを見極めることが重要。
焦げ取り:焦げついた部分を取り除く方法。ナイフやスチールウールを使うことができるか、適切な手入れ方法で防ぐことが基本である。
焦げの対義語・反対語
該当なし