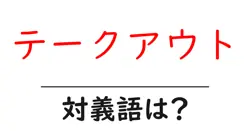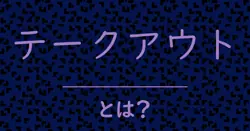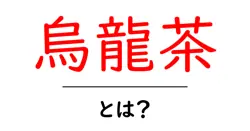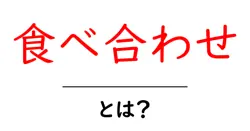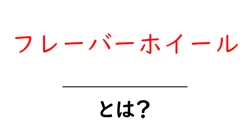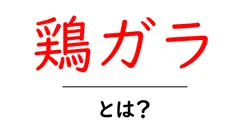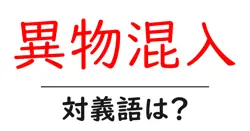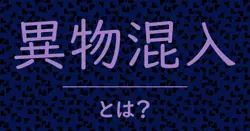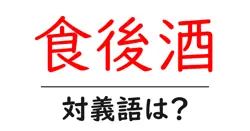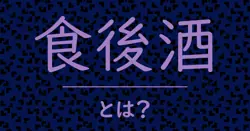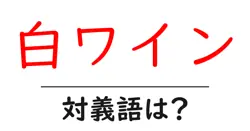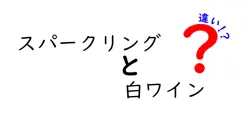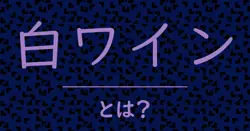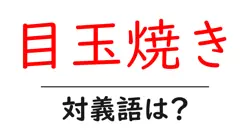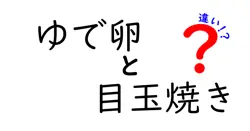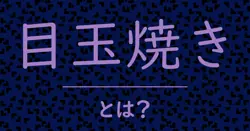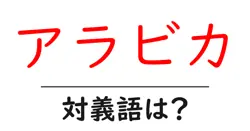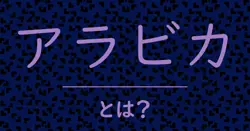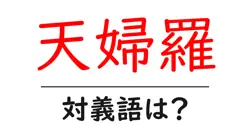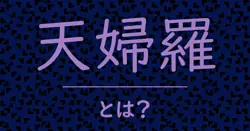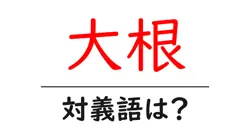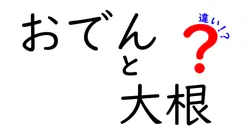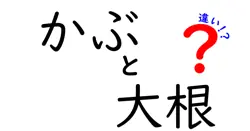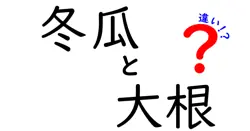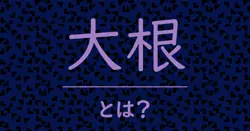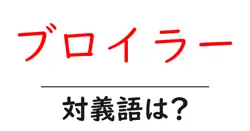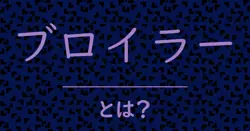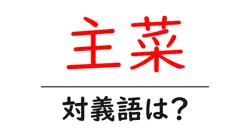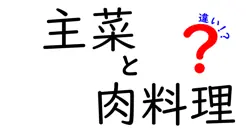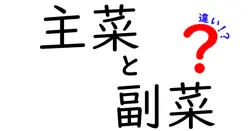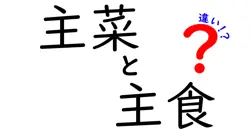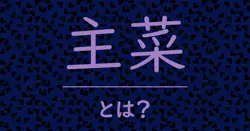大根とは?栄養と活用法を知ろう!
大根(だいこん)は、アブラナ科の根菜で、日本をはじめとする多くの国で広く栽培されています。この野菜は、主に白い長い根の部分が食べられ、サラダや煮物、漬物など様々な料理に使われています。今回は、大根の特徴や栄養、料理の方法について詳しく見ていきましょう。
大根の特徴
大根は、一般的に白くて細長い形をしていますが、品種によっては色や形が異なることもあります。たとえば、赤大根(あかだいこん)や青首大根などがあります。大根は土の中で育ち、根が大きくなることで知られています。また、冬に収穫されることが多く、寒さに強い野菜です。
栄養価
大根は低カロリーでありながら、ビタミンCやカリウム、食物繊維が豊富に含まれています。以下は、大根の主な栄養成分です。
| 栄養成分 |
含有量(100gあたり) |
| カロリー |
18 kcal |
| ビタミンC |
21 mg |
| カリウム |
400 mg |
| 食物繊維 |
1.2 g |
大根の利用方法
大根は、そのまま食べる以外にも様々な方法で利用できます。以下に代表的な料理を紹介します。
- サラダ: 千切りにしてサラダとして食べると、シャキシャキした食感が楽しめます。
- 煮物: 煮込み料理で味を染み込ませ、優しい味わいになります。
- 漬物: 漬物にすることで、大根の旨さを引き立てます。
- 汁物: 大根を入れた味噌汁や汁物が、体を温めてくれます。
まとめ
大根は、栄養価が高く、様々な料理に使える万能な野菜です。健康にも良い影響を与えてくれるので、普段の食事に取り入れてみるのをおすすめします!大根を使った料理を楽しんで、ぜひ色々なレシピに挑戦してみてください。
大根のサジェストワード解説おでん 大根 とは:おでんは日本の伝統的な料理で、さまざまな食材を煮込んだ温かい一品です。その中でも、大根は特に重要な役割を果たしています。大根は、約3〜4センチの厚さに切られて、おでんの出汁と一緒にじっくり煮込まれます。大根は煮ることで柔らかくなり、出汁を吸い込み、旨味が増します。これが、おでんの深い味わいを引き立てる要因の一つです。さらに、大根はその食感が楽しめるのも魅力です。しゃきしゃきとした部分と、ほろりと崩れる部分があり、食べるととても満足感があります。また、大根はビタミンやミネラルが豊富で、栄養価も高い食材です。健康にも良いため、おでんを楽しむ際にはぜひ大根をしっかり味わいたいですね。季節が寒くなると、おでんを囲んで温まる家庭も多いですが、その時に大根の存在がどれほど大切かを理解することができると思います。おでんを作る際には、ぜひ大根を主役にして、他の具材と一緒に楽しんでみてください。
すずしろ 大根 とは:すずしろ大根は、日本の伝統的な野菜の一つで、特にお正月の料理に欠かせない存在です。すずしろという名前は、この大根の白く美しい姿を指しており、清らかさを象徴しています。この大根は、一般的な大根よりも甘みが強く、身がやわらかいのが特徴です。生でサラダにして食べるのも良いですが、煮物やお漬物にすると、その美味しさがさらに引き立ちます。栄養価も高く、ビタミンCや食物繊維が豊富で、健康にも良い食材です。日本では、特に関西地方で多く栽培されていますが、全国的にも見かけることができます。すずしろ大根の収穫時期は冬から春にかけてで、旬の時期には新鮮で crunchy(カリッとした)食感が楽しめます。家庭菜園でも栽培が可能で、家庭で育てたすずしろ大根を使った料理は特別な味わいがあります。ぜひ、一度試してみて、その美味しさを実感してみてください。
大根 す とは:大根(だいこん)は、色々な料理に使われる根菜です。日本では、主に冬に食べられることが多く、料理の味を引き立てる役割を持っています。でも、「大根す」とは何なのでしょうか?
「大根す」は、大根のしぼり汁を指します。大根をおろして、その汁を絞ることをすることから生まれた言葉です。この汁は、形が平たくて薄い大根の切り身から取れるもので、料理に使うととても美味しい味わいになります。
例えば、大根すは、マリネやドレッシング、さらにはスープなどに使われます。この汁は、消化を助ける効果もあり、健康にもよいとされています。また、大根にはビタミンCや食物繊維が豊富に含まれているため、生活習慣病の予防にも役立ちます。
大根すを家庭料理に取り入れてみると、新しい発見があり、料理がもっと楽しくなるでしょう!
大根 すが入る とは:大根が「すが入る」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、大根の中心部分にできる白い筋のことを指します。この筋は、特に大根を切ったときに見えることが多く、放置すると苦みや硬さが増すこともあります。
この「す」が入る原因は、栄養分が大根の中心に集中するためと考えられています。また、収穫の時期や環境によっても影響されることがあります。特に冬の寒い時期に収穫された大根は、甘味が増す一方で、すが入ることがあるんです。
しかし、すが入った大根でも、工夫すれば美味しく食べられます。例えば、薄切りにして漬物にしたり、煮物に加えたりすると、味が引き立ちます。簡単な大根のスライスや千切りを使ってサラダを作るのもおすすめです。すが入ったところが気にならないように、他の具材と一緒に調理することで、全体の味が調和します。
もし、すが気になる場合は、丸ごと煮てしまって、大根の甘味を引き出すことも良い方法です。
大根の「す」にめげず、様々な料理で楽しんでみてください!
大根 とは 役者:「大根」と聞くと、野菜の中の一種として思い浮かぶことでしょう。しかし、実は「役者」との関係もあるのです。大根は日本の伝統文化や演劇、特に狂言の世界でもよく使われる表現があるのです。例えば、「大根役者」という言葉があります。この言葉は、演技が下手な役者を指すことが多いです。これは、大根のように固く、柔軟性がなく見えることから来ていると言われています。演技がぎこちない様子が、大根の硬いイメージと重なるため、このような表現が生まれました。こうして考えると、大根は単なる食材ではなく、文化や言葉に根付いた存在になっていることがわかります。また、大根は料理でも重要な役割を果たしており、煮物やサラダ、漬物などに欠かせない食材です。だからこそ、私たちの生活の中で大根は多様な形で関わっていると言えます。今度、大根を食べるときには、このような役者とのつながりも思い出してみてください。食材としてだけでなく、文化の一部としての大根を楽しむことができるでしょう。
大根 下茹で とは:大根の下茹でとは、主に料理をする際に大根を軽く茹でることを指します。この工程は、食材を柔らかくしたり、調理時間を短縮するために行われます。大根は生のままでも食べられますが、下茹でをすることで、味がなじみやすくなり、さらに消化も良くなります。下茹でのやり方は、とても簡単です。まず、大根を皮をむいて、食べやすい大きさに切ります。その後、鍋に水を入れて沸騰させ、大根を加えます。大体3〜5分ほど、中火で茹でてください。大根が柔らかくなるまで茹でたら、水を切るだけで下茹での完成です。下茹でした大根は、煮物やサラダ、お味噌汁の具材として使うと、とても美味しく仕上がります。さらに、下茹ですることで、苦みや辛みも和らいで、より食べやすくなります。お料理が苦手な方でも簡単にできるこのステップを取り入れて、ぜひおいしい大根料理を楽しんでみてください!
大根 面取り とは:「面取り(めんとり)」という言葉を聞いたことがありますか?これは、食材の角を丸くする技法のことです。特に大根の面取りは人気があります。料理の見た目が良くなるだけでなく、食感が柔らかくなり、味が染み込みやすくなる利点もあります。本来の大根の形を生かしながら、面取りをすることで、料理に使ったときの食べやすさが向上します。大根を使った料理の代表例には、おでんや煮物、サラダなどがありますが、面取りをすることによって、これらの料理が見た目にも美味しそうに仕上がります。面取りは、包丁を使って大根の角を45度の角度で軽く削ぎ落とすだけの簡単な技術です。最初は難しいかもしれませんが、練習すれば誰でもできるようになります。これから料理を作るときには、ぜひ大根の面取りを試してみてください。きっと、家庭料理がもっと素敵なものになるはずです。面取りを通じて、料理の楽しさや食への理解も深まりますよ!
大根の共起語野菜:大根は野菜の一種で、主に根を食べることができます。他の野菜と同様に、栄養を摂るために重要です。
栄養:大根にはビタミンCや食物繊維が多く含まれており、健康に良い栄養素が豊富です。
料理:大根はさまざまな料理に使われる食材です。煮物やおひたし、サラダなど、用途は多岐にわたります。
煮物:大根は煮物料理によく使われます。柔らかくなるまで煮ることで、甘みが引き出されます。
味噌汁:大根は味噌汁の具材として人気があります。だしの味と大根の風味が組み合わさって美味しいです。
漬物:大根は漬物としても食べられます。特に、キムチや浅漬けが代表的です。
辛味:大根には辛味があり、これは「大根おろし」やサラダに使用される際にアクセントになります。
旬:大根の旬は冬で、寒い季節に甘みが増し、特に美味しくなります。
保存:大根は比較的長持ちする野菜ですが、適切な方法で保存することが大切です。冷蔵庫で保存すると良いでしょう。
切り方:大根の切り方は用途によって異なります。薄切りや千切り、輪切りなどが一般的です。
大根の同意語大根:根菜の一種で、主に料理に使われる長い白い野菜。生で食べたり、煮物や漬物にすることが多い。
ダイコン:「大根」の英語表記で、主に和食で使用される根菜。水分が多く、シャキシャキとした食感が特徴。
白大根:一般的に流通している品種の大根で、白い色をしていることからこの名前が付いている。
青首大根:大根の一種で、根の上部が青緑色をしている。甘みが強く、生のサラダや煮物に適している。
葉大根:葉も食べられる大根の一つで、葉は栄養価が高く、炒め物やお浸しに利用される。
辛味大根:辛い味が特徴の大根で、主に薬味として使われることが多い。寿司や刺身に添えられることが多い。
大根の関連ワード野菜:大根は根菜類に分類される野菜の一つで、食材として広く使用されています。
根菜:根菜とは、土の中で育つ野菜のことを指し、大根や人参、じゃがいもなどがあります。
栄養:大根にはビタミンCや食物繊維が豊富で、健康維持に役立つ栄養素が含まれています。
料理:大根は煮物、サラダ、漬物など様々な料理に利用される versatile(多用途)な食材です。
血液サラサラ:大根には消化を助けたり、血液の循環を良くする効果があるとされています。
漬物:大根を塩や酢などで漬け込んだ=漬物は、日本の伝統的な保存食です。
辛味:大根は種類によって辛味があり、大根おろしにすると、その辛さが引き立ちます。
季節:大根は主に秋から冬にかけて旬を迎える野菜です。この時期が最も美味しく食べられます。
大根おろし:大根をすりおろしたもので、鮮やかさと風味を料理に加えるトッピングとして人気があります。
農業:大根は日本を代表する農作物の一つで、全国各地で栽培され、農業の重要な一部となっています。
大根の対義語・反対語
大根の関連記事
グルメの人気記事

1782viws

2024viws

3499viws

2026viws

2178viws

1404viws

1569viws

1391viws

1720viws

2025viws

3486viws

627viws

3439viws

5166viws

4106viws

1579viws
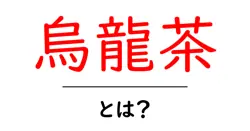
1308viws
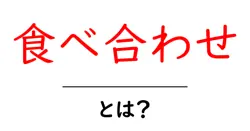
2025viws
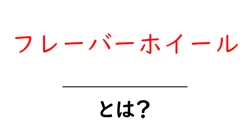
1891viws
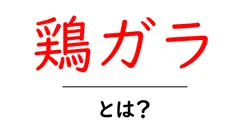
1758viws