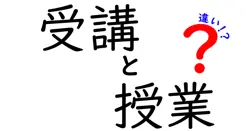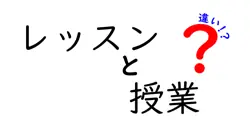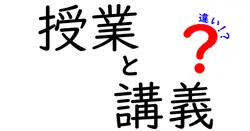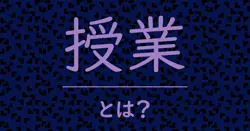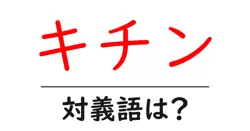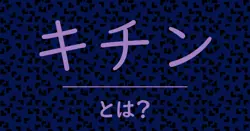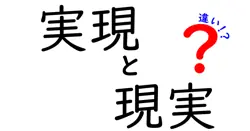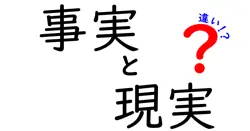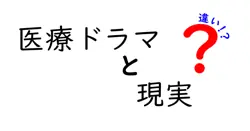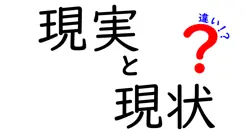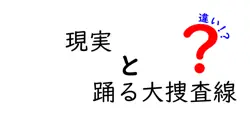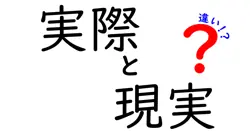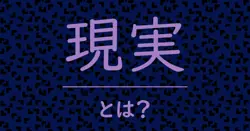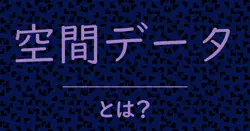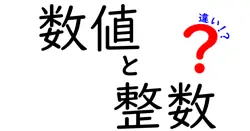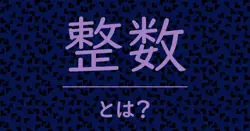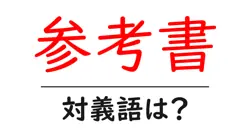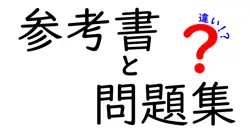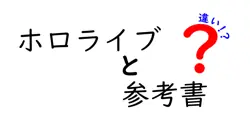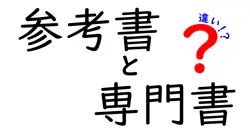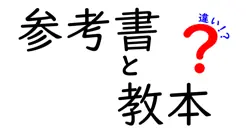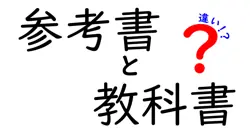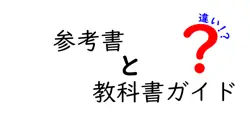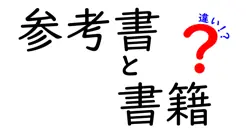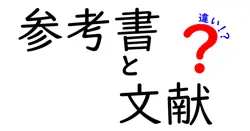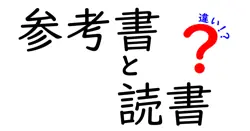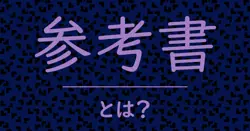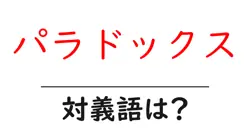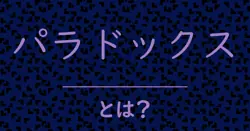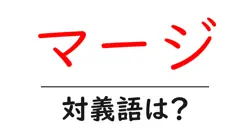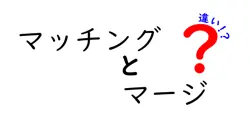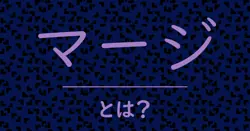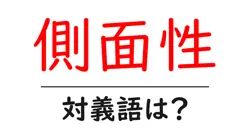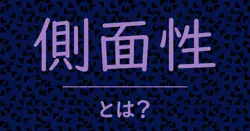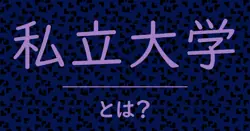授業とは?
授業(じゅぎょう)とは、学校や教育機関で行われる学びの時間を指します。生徒が教師から知識や技術を学ぶことを目的とした活動で、さまざまな科目に分かれています。授業は、教科書や参考書を使ったり、実際に実験をしたりと、多様な形で行われます。
授業の目的
授業の主な目的は、学生に必要な知識を提供し、社会で必要な技能を身に付けることです。また、授業を通じて思考力やコミュニケーション能力を育むことも大切です。具体的には、以下のような効果があります。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
授業の種類
授業にはいくつかの種類があります。以下は代表的な授業の形式です。
- 講義形式: 教師が一方的に教えるスタイル。一部の大学の授業などでよく見られます。
- 対話形式: 教師と生徒が会話をしながら進めるスタイル。疑問をぶつけ合うことで深い理解を促します。
- 実践形式: 実際に手を動かして行う授業。美術や理科の授業で多く見られます。
授業の進め方
授業は大きく分けて、導入・展開・まとめの流れで進められることが一般的です。
<dl><dt>導入dt><dd>授業のテーマを紹介し、興味を引きます。dd><dt>展開dt><dd>実際に内容を学んでいく時間です。教師が説明したり、生徒がグループで取り組んだりします。dd><dt>まとめdt><dd>授業を振り返り、重要なポイントを整理します。dd>dl>以上のように、授業はただの勉強時間ではなく、多くのことを学べる貴重な時間です。授業を大切にし、積極的に参加することが、将来への準備となります。
div><div id="saj" class="box28">授業のサジェストワード解説
コマ 授業 とは:コマ授業とは、学校で行われる授業の形態の一つで、通常の授業が教科ごとに区切られているのに対して、特定の教科やテーマに集中して授業を行う方法です。この授業形式では、例えば数学や英語に特化した時間を設けて、その科目に深く取り組むことができます。コマ授業のメリットは、理解を深めるためにじっくり学べることです。また、興味のある教科に多くの時間を割くことができるため、学びをより楽しく感じることができます。しかし、逆に言うと、他の教科の時間が少なくなることもあり、バランスが重要です。コマ授業は特に中学校や高等学校でよく取り入れられており、効果的な学習方法として注目されています。学校によっては、コマ授業の代わりに通常授業と入れ替えることもあるので、自分の学校のスタイルを知っておくことが大切です。
ツイステ 授業 とは:『ツイステ』は、大人気のスマートフォン向けゲームで、プレイヤーは魔法の世界でキャラクターたちと共にさまざまなストーリーを楽しむことができます。その中で重要な要素の一つが「授業」です。授業は、キャラクターを育てるための大切なステップであり、プレイヤーは授業を通じてキャラクターのスキルや能力を向上させることができます。授業の魅力は、緊張感のあるバトルや、楽しいミニゲームを通じて新しい戦略を学ぶところです。また、授業を行うことで得られる報酬も多く、キャラクターの成長を実感できるのが大きな楽しみです。さらに、授業にはストーリー要素も含まれていて、キャラクター同士の関係性が深まるきっかけにもなります。こうして、プレイヤーは授業を進めることで、自分の好きなキャラクターをどんどん強くしていき、物語をより楽しむことができるのです。もしあなたが『ツイステ』をまだプレイしていないなら、授業の要素をぜひ体験してみてください!
内職 とは 授業:内職とは、自宅で行う仕事のことを指します。例えば、通販のための商品の梱包や、手作りの工芸品を作ることなどが当てはまります。最近では、インターネットを通じて自宅でできる仕事が増えてきているため、内職はより身近な存在になってきています。では、内職を授業で学ぶ意味は何でしょうか? まず、自分の時間を有効に使えるという点が重要です。学校の授業や部活動の合間に、自宅で少しずつ仕事をすることができるので、自由な時間を持ちながらも収入を得るチャンスがあります。さらに、内職を通じて自分の特技や趣味を活かすことも可能です。こうした体験を授業で学ぶことによって、将来のキャリア選択の幅が広がります。また、経済的な自立を図るチャンスにもなるため、内職について知っておくことはとても大切です。教育の場でこうした新しい働き方について学ぶことで、これからの社会により適応できる力を身につけることができるでしょう。
授業 とは 意味:授業とは、学校などで行われる教育の一環です。主に教師が生徒に知識や技術を教える時間を指します。授業の目的は、生徒が様々なことを学び、成長していくことです。例えば、国語の授業では文章を読んだり、書いたりしますし、数学では計算や図形を学びます。授業は教室だけでなく、実験室や体育館などでも行われ、さまざまな教科の内容を学ぶことができます。授業はまた、生徒同士が話し合ったり、協力しあったりする場でもあり、コミュニケーション能力を高めることにも役立っています。授業がこうして行われることで、社会で必要なスキルを身につけたり、将来の夢に向かって進むための基礎を築くことができるのです。授業は単なる知識の詰め込みだけではなく、実生活に役立つ力を養う重要な時間なのです。
授業 めあて とは:授業の「めあて」とは、その授業で何を学ぶのか、どのようなことを理解するのかを示す目標のことです。授業が始まる前に先生が「今日はこのめあてを達成するために、いろんなことを学びますよ」と言うことがあります。めあてを知ることで、生徒は授業を受ける意義を理解しやすくなります。 たとえば、数の計算を学ぶ授業のめあてが「掛け算の意味を理解する」と設定されているとします。このめあてがあることで生徒は、どのような知識が必要で、何を目指すのかを考えることができます。授業の最後には、めあてが達成できたかどうかを振り返る時間もあります。これにより、生徒自身が自分の学びを評価しやすくなり、次の課題に取り組む意欲も湧きます。 いかにたくさんの知識を得るかも大切ですが、授業のめあてを意識することで、より深く考えることができるようになります。」 授業のめあては、学びを明確にし、達成感を得るための大切なガイドラインとなります。
授業 切る とは:「授業を切る」という言葉は、授業を受けずに学校を休むことを指します。例えば、友達と遊ぶために学校を休んだり、授業がつまらないからといってさぼったりすることがこれに当たります。嫌なことから逃げたい気持ちがあるかもしれませんが、実際には授業を切ることにはいくつかのリスクがあります。授業を欠席すると、その内容を理解する機会を失ったり、成績が下がる原因になることがあります。さらに、学校のルールに反してしまうこともあるため、注意が必要です。もしどうしても授業を受けられない場合は、親や教師に相談するのが良いでしょう。授業を切るのは短期的には楽しいかもしれませんが、長い目で見ると、しっかりと学んだ方が自分のためになります。
授業 飛ぶ とは:「授業 飛ぶ」という言葉は、学校の授業をサボったり、途中で抜け出したりすることを指します。この行為は友達と遊びたい気持ちや、授業が退屈に感じることから起こることが多いです。しかし、授業を飛ぶことはあまりおすすめできません。まず、授業を受けないことで学ぶべき知識を失ってしまうからです。特に中学生のうちは、基礎的な学力を身につける大切な時期です。さらに、授業を飛ぶと先生や友達との信頼関係にも悪影響を与えるかもしれません。授業を飛ぶよりも、友達と一緒に勉強して遊ぶ時間を作ったり、授業中に自分の興味を持つ話題を見つけるなど、ポジティブな方法で学校生活を楽しむことが大切です。そして、時にはどうしても授業に集中できない時もあるかもしれません。そんな時は、先生に相談してアドバイスをもらうのが良いでしょう。授業を飛ばすのではなく、どうすれば授業をもっと楽しくするかを考える方が良い結果につながります。
知識伝達型 授業 とは:知識伝達型授業は、先生が生徒に知識や情報を直接教えるスタイルの授業です。この方法では、教師が主に話し、生徒はその内容を聞いたり、ノートに取ったりします。例えば、数学の授業で先生が問題の解き方を説明し、生徒はその方法を理解するためにメモを取るという形が典型的です。このスタイルの良い点は、難しいことを短時間で理解する手助けとなるところです。特に新しい知識を学ぶときには、教師からの直接的な指導が効果的です。ただし、知識を受け取るだけではなく、生徒自身が考える時間も大切です。つまり、知識伝達型授業は効果的ですが、それだけでは不十分で、自分で考える力を育てることも必要です。授業で理解した内容をどう活用するかも、今後の学びにとって重要なポイントです。
道徳 授業 とは:道徳授業は、私たちの生活や人生にとって非常に重要な内容を学ぶ時間です。学校の授業の中で、道徳とは何か、どういったことを大切にするべきなのか、他の人とどう接するべきなのかを考える機会になります。この授業では、例えば友情や思いやり、責任感など、心の成長に役立つ価値観について話し合います。 道徳授業では、実際の事例をもとに、どのように行動すれば良いのかを考えるワークショップやディスカッションがよく行われます。また、物語や絵本を通して、他者の気持ちを理解することの大切さも学びます。たとえば、友達が困っているときに手を差し伸べることや、約束を守ることの大切さについて話し合うことで、具体的な行動につなげていきます。 このように、道徳授業はただの知識ではなく、実際の生活においてどう行動するべきかを考えるための大切な教科です。自分自身を成長させる機会にしたいですね。
div><div id="kyoukigo" class="box28">授業の共起語教育:授業は教育の一環として行われるもので、知識や技能を身につけるための活動です。
学習:授業を通じて生徒や学生は学習を行い、新しい情報や考え方を習得します。
先生:授業を担当する人を指し、知識を教えたり、生徒の質問に答えたりします。
生徒:授業を受ける側の人々で、知識を吸収し成長を目指します。
教科:授業は様々な教科(国語、数学、理科など)に分かれて行われ、それぞれ特定の内容を扱います。
カリキュラム:授業の内容や進行の計画を指し、学年ごとに設定されています。
評価:授業の結果を測るために行われるもので、試験や課題などによって行われます。
教材:授業で使用される教科書や参考書、資料のことを指します。
時間割:授業のスケジュールを示し、各教科がいつ行われるかを管理します。
アクティブラーニング:受動的ではなく、学生が主体的に参加する授業スタイルのことを指します。
div><div id="douigo" class="box26">授業の同意語講義:大学や専門学校などで行われる授業のこと。教師が生徒に対して専門的な知識を教える形式。
レッスン:特定のスキルや知識を習得するための授業や指導のこと。音楽やスポーツなど、特化した分野でよく使われる。
クラス:一定の時間に指定された場所で行われる授業の単位を指す。学年や科目に応じて、同じ目標を持つ生徒が集まる。
セミナー:少人数で行われる討論形式の授業のこと。参加者がテーマについて意見交換を行いながら学ぶ。
ワークショップ:実践的な活動を通じて学ぶ形式の授業。参加者が実際に手を動かして学ぶため、より深く理解できる。
指導:先生や指導者が生徒に対して知識や技能を教えること。ただし、授業に限らず、個別指導やグループ指導など幅広い形態を含む。
カリキュラム:教育課程全体を指し、特定の科目の授業内容やその進め方を含む。授業はその一部として組み込まれている。
div><div id="kanrenword" class="box28">授業の関連ワード教育:授業は教育の一環であり、知識やスキルを学生に教えるプロセスを指します。
カリキュラム:授業の計画や内容をまとめたもので、教育機関が提供する科目や学習内容の一覧を含みます。
授業計画:特定の授業の目標や内容、進行の流れを事前に定めた文書で、教師が授業を効果的に進めるために使用します。
教師:授業を行う人。学生に知識を伝える役割を持ち、授業を運営します。
クラス:同じ授業を受ける学生たちを指し、通常は1つの教室で授業が行われます。
授業時間:授業が行われる時間のこと。通常、学校や教育機関での授業は決められた時間枠内で行われます。
アクティブラーニング:学生が主体的に学ぶことを重視した授業スタイルで、ディスカッションやグループワークを取り入れることが多いです。
宿題:授業で学んだ内容を復習するために与えられる課題。学生が自宅で取り組むことが求められます。
評価:授業の成果を測るための方法で、テストやレポートなどを通じて行われます。
授業形式:授業をどのように進めるかに関する方法論で、講義形式、実習形式、オンライン授業などがあります。
フィードバック:授業中に学生や教師が互いに評価し合うこと。授業の改善や学習の促進を目的としています。
div>授業の対義語・反対語
該当なし