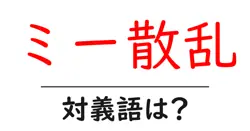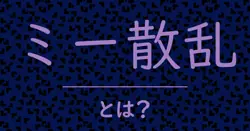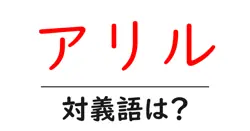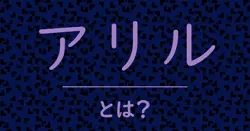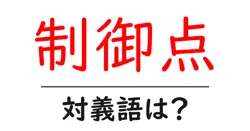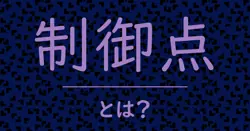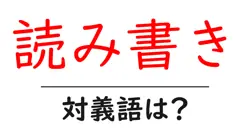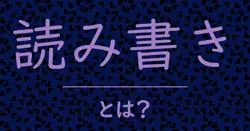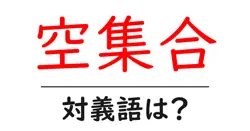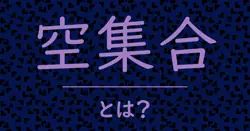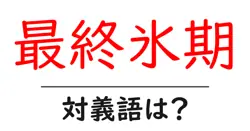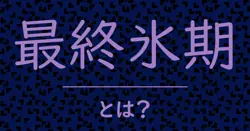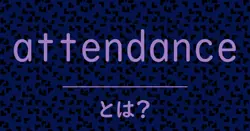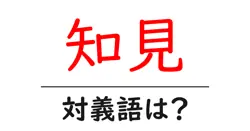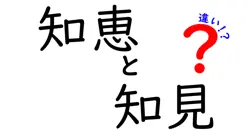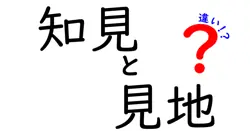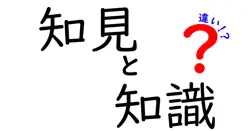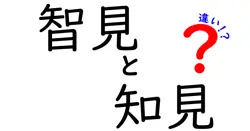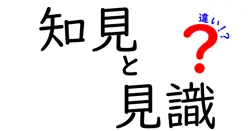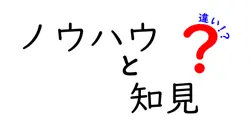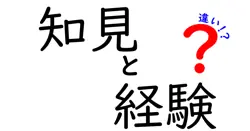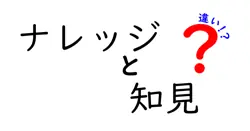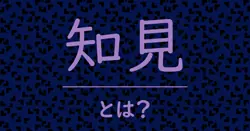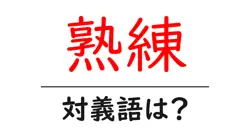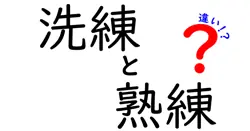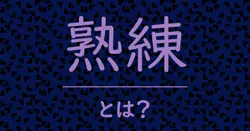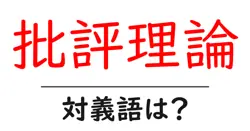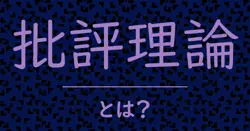ミー散乱とは?
「ミー散乱(ミーさんらん)」という言葉を聞いたことがありますか?これは、光や音が小さな粒子によって散乱される現象の一つです。この現象は、日常生活の中でも分かりやすく見ることができるので、知っておくと面白いかもしれません。
ミー散乱の基本
ミー散乱は、1860年代に物理学者のジョージ・ガブリエル・ミーによって最初に説明されました。基本的に、ミー散乱は、光が小さな粒子とぶつかることで、その光がさまざまな方向に散らばってしまう現象を指します。
ミー散乱の例
例えば、晴れた日の空が青く見えるのは、ミー散乱が関係しています。太陽の光が大気中の微小な塵や水滴に当たることで、波長の短い青い光が散乱され、空が青く見えるのです。
ミー散乱の特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
ミー散乱の影響
ミー散乱は、日常生活の中でさまざまな影響を与えています。特に、写真を撮る時の光の状態や、天体観測時の効果など、科学だけでなくアートの分野でも重要です。
まとめ
ミー散乱は、私たちが普段目にする空の色や、音の響きにも影響を与える現象です。理解しておくことで、宇宙や自然の不思議を深く知る手助けになるでしょう。ぜひ、身の回りの景色や自然を観察し、ミー散乱を感じてみてください。
div><div id="kyoukigo" class="box28">ミー散乱の共起語
散乱:物質やエネルギーが無秩序に分散することを指します。ミー散乱では、光や粒子が不均一な媒質や物体によって散乱される現象を示します。
光:目に見える波長の電磁波で、ミー散乱では特に可視光が媒質によって散乱される現象に関係しています。
粒子:物質の基本的な単位であり、ミー散乱では粒子のサイズや形状が散乱の特性に影響を与えます。
媒質:光や粒子が通過する物質のことを指し、ミー散乱の理解には媒質の特性が重要です。
角度:散乱が起こる方向に関連する要素で、ミー散乱では光がどの角度で散乱されるかが観察されます。
波長:光や粒子のエネルギーの単位で、ミー散乱では波長によって散乱の程度が異なります。
干渉:異なる波が重なり合う現象で、ミー散乱の場合は散乱光同士の干渉が観察されることがあります。
粒径:粒子のサイズを示す指標であり、ミー散乱の結果に大きく影響します。特に、粒径が波長に近い場合に現象が顕著になります。
div><div id="douigo" class="box26">ミー散乱の同意語散乱:光や粒子が各方向に拡がり分散する現象を指します。
分散:物質や情報が一か所に集中せず、広がっている状態のことを言います。
散布:何かを広い範囲に広げて配置することを意味します。
拡散:物質やエネルギーが広がっていく現象を示し、特に粒子や気体が空間に広がることを指します。
ばらまき:何かを無造作に広げること、特に細かいものを広範囲に散らすことを指します。
散発:ばらばらに発生すること、特に不規則に起こることを意味します。
div><div id="kanrenword" class="box28">ミー散乱の関連ワード散乱:光や粒子が、何らかの物体にあたって、その進行方向が変わる現象。ミー散乱においては、特に小さな粒子による散乱を指します。
ミー散乱:特定のサイズの粒子が光を散乱させる現象で、光の波長に近い大きさの粒子に関して発生します。この現象により、空が青く見えたり、霧の中で光が広がったりします。
光:目に見える範囲の電磁波で、さまざまな波長を持つ。ミー散乱は、この光が粒子によってどのように散らばるかを理解するのに重要です。
波長:光の性質を示す値で、光の色や散乱の仕方を決定します。ミー散乱では、波長と粒子の大きさの関係が重要です。
粒子:物質の最小単位で、ミー散乱の研究や応用においては、特に小さな粒子が議論されます。風や水中の微粒子による現象がミー散乱を引き起こします。
赤外線:目に見えない波長の光で、ミー散乱は特に可視光までの波長に関係がありますが、赤外線の散乱も重要な現象です。
光学:光の性質やその挙動を研究する科学の一分野です。ミー散乱は光学の重要な現象の一つで、多くの応用があります。
空気中の微粒子:空気中に浮遊する非常に小さな粒子で、ミー散乱によって雲や霧、青空などの現象を引き起こします。
散乱係数:媒質における光の散乱の程度を示す数値で、ミー散乱の研究において重要な役割を果たします。
div>