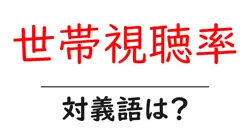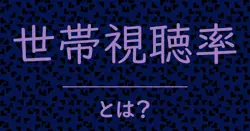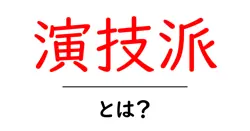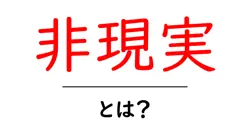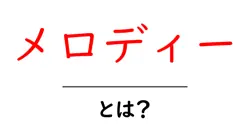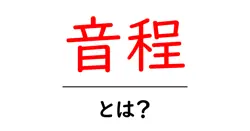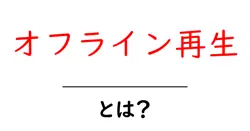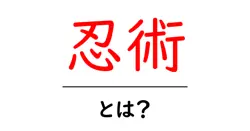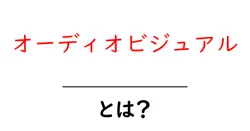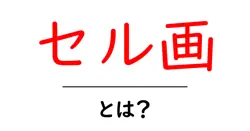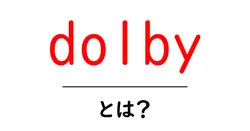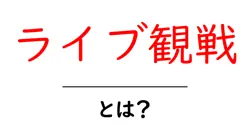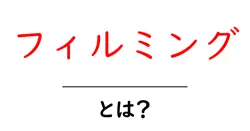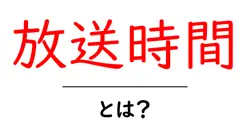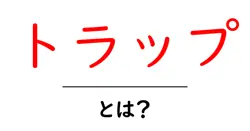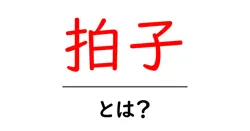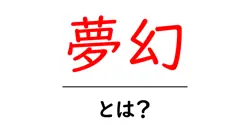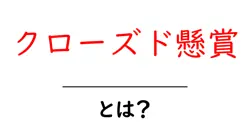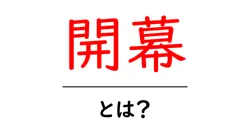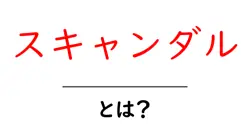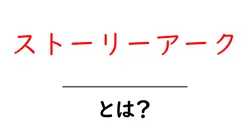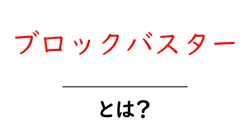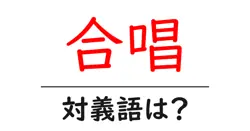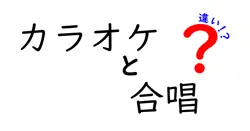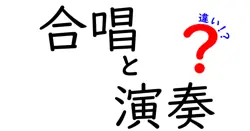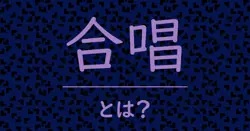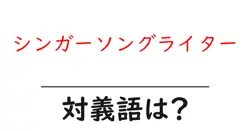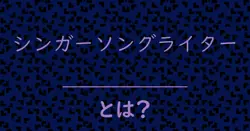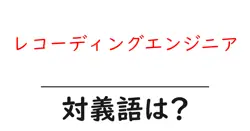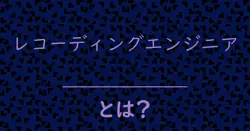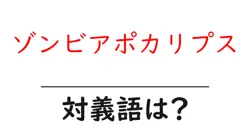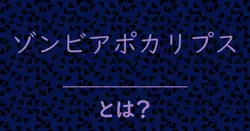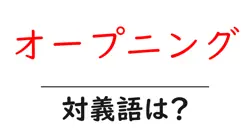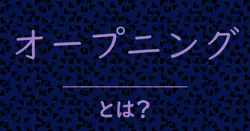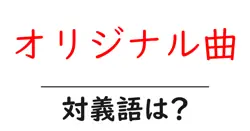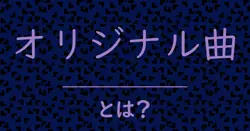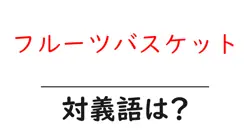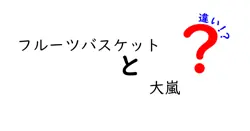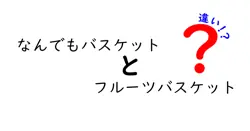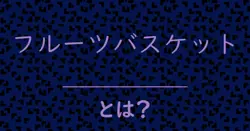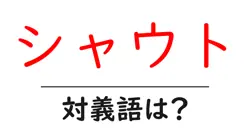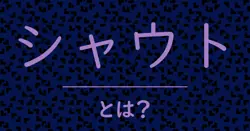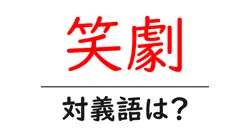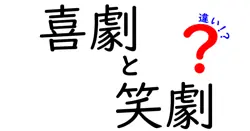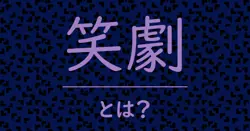合唱とは?
合唱(がっしょう)は、複数の人々が声を合わせて歌う音楽のスタイルの一つです。一般的には、男性と女性がそれぞれ異なるパートを歌うことで、調和の取れた美しいハーモニーを作り出します。合唱は学校の音楽の授業や地域の音楽活動として広く行われており、年齢や経験を問わず誰でも参加できます。
合唱の歴史
合唱の歴史は古く、古代ギリシアの時代から行われてきました。当時から人々は祭りや宗教行事の際に歌を歌い、喜びや悲しみを共有していました。さらに、中世ヨーロッパでは教会音楽の一環として合唱が重要視され、様々な音楽様式が生まれました。
合唱の種類
| 合唱の種類 | 特徴 |
|---|
| 混声合唱 | 男性と女性の声が含まれる合唱 |
| 女声合唱 | 女性だけで構成される合唱 |
| 男声合唱 | 男性だけで構成される合唱 |
合唱の種類には、混声合唱、女声合唱、男声合唱の3つがあります。混声合唱は、男女が共に歌うもので、曲により多様なハーモニーが楽しめます。女声合唱や男声合唱は、それぞれの声の特性を生かした音楽が表現されます。
合唱の楽しみ方
合唱を楽しむ方法はたくさんあります。まずは、地域の合唱団に参加することがおすすめです。仲間と一緒に練習し、発表会に向けて一生懸命取り組むことで、達成感が得られます。また、音楽の勉強にもなり、音楽への理解が深まります。
合唱に必要なもの
合唱を始めるにあたって、特別な道具は必要ありませんが、次のようなものがあると便利です。
- 楽譜:歌う曲の楽譜が必要です。
- 譜面台:楽譜を置くための台があると使いやすいです。
- 運動靴:練習をする際には動きやすい靴が良いでしょう。
合唱のサジェストワード解説アルト とは 合唱:合唱は多くの人が一緒に歌う活動で、とても楽しいものです。その合唱の中でも「アルト」は重要なパートの一つです。アルトは主に女性の声の低い部分を担当し、ハーモニーを作る役割があります。合唱の中で、アルトはメロディーを歌うだけでなく、他のパートと一緒に歌うことで、美しい響きを生み出します。たとえば、ソプラノが高い音を歌っているとき、アルトはその低い音を支え、全体の音を豊かにします。このようにアルトの声があることで、合唱に深みや広がりが生まれるのです。また、アルトには柔らかく落ち着いた声が求められることが多いので、美しい音色を出す練習も必要です。合唱に参加することで、音楽の楽しさだけではなく、仲間と一緒に何かを作り上げる喜びも味わえます。アルトパートを歌うことができれば、合唱の一員として大きなやりがいを感じることができるでしょう。歌うことが好きな人や、合唱を始めたいと思っている人には特におすすめです。
テノール とは 合唱:合唱と聞くと、みんなで歌う姿をイメージする人が多いでしょう。その中で「テノール」という言葉を聞いたことはありますか?テノールとは、男性の声の種類の一つで、音域が高いのが特徴です。テノールの声は、合唱団の中でメロディーを担当することが多く、明るく響く音色がとても魅力的です。合唱では、一般に四つの声部がありますが、それはソプラノ(女性の高い声)、アルト(女性の低い声)、テノール(男性の高い声)、バス(男性の低い声)です。テノールは、特に高い音域を出すため、しっかりとした声量と表現力が求められます。合唱の中でテノールが歌うことで、楽曲に深みや情感が加わります。テノールの役割は、リーダーシップを持ったり、他の声部とハーモニーを作り出すことで、合唱全体を引き立てることです。テノールパートを担当することで、合唱に参加する楽しみが増えるだけでなく、自分の音楽的な表現力を高めることにもつながります。これから合唱に参加する方は、ぜひテノールの声部にも注目してみてください。
ハミング とは 合唱:ハミングとは、声を使ってメロディを歌う時に、歌詞を言わずに音を鼻から出すことを指します。合唱では、ハミングを使うことで、楽器のように声を重ね合わせることができます。特に、合唱の中でのハミングは、他のパートのメロディを引き立てたり、ハーモニーを作ったりするのに役立ちます。例えば、合唱団が歌う時に、一部のメンバーがハミングをすることで、全体の音がもっと美しく、豊かに響きます。ハミングは、歌詞を使わなくてもメロディを楽しむことができるので、歌い手自身も自由に音楽を表現することができます。また、ハミングはリラックス効果もあり、ストレスを軽減するのに役立つと言われています。音楽を楽しむ際には、ぜひハミングにもトライしてみてください。合唱の中でのハミングは、楽しい経験を広げてくれるはずです。
合唱 とは 意味:合唱(がっしょう)は、複数の人が声を合わせて歌うことを指します。学校の音楽の時間や合唱団などでよく見られる活動です。合唱は、1つのメロディーをみんなで歌うだけでなく、人数やパートに分かれて歌うこともあります。例えば、ソプラノやアルトなどのパートに分かれ、それぞれ異なるメロディーを歌うことで、ハーモニーが生まれます。このハーモニーが合唱の大きな魅力の一つです。また、合唱を通じて友達と一緒に何かを成し遂げる体験や、音楽に対する理解を深めることもできます。合唱は心を一つにし、協力することを学ばせてくれます。音楽が好きな人や仲間と一緒に歌いたい人には、特におすすめです。自信を持って歌うことで、だんだんと成長できる楽しさも合唱のいいところです。
合唱 ソリ とは:合唱ソリとは、合唱において特定のパートや歌い手がソロで歌う部分のことを指します。例えば、大人数の合唱団の中で、特定の人が一人で歌うことで、その部分が強調され、音楽に深みを与える役割を果たします。合唱は、全員が一緒に歌うことで和音やハーモニーが生まれますが、その中でソリの部分があることで、曲に変化や感情を加えることができます。合唱ソリは、バラードや感動的な曲で特によく用いられます。なぜなら、ソロが入ることで、聴く人に強い印象を与えるからです。また、ソロを歌う人にとっても、自己表現の場となり、自信や技術を高める素晴らしい機会です。合唱ソリは、合唱の中で重要な要素ですが、パートのバランスや全体の音楽性を損なわないように気をつける必要があります。それぞれの歌い手が協力し合いながら、素晴らしいハーモニーを作り上げることが合唱の楽しさでもあります。
合唱 ハーモニー とは:合唱は、たくさんの人が一緒に歌うことを意味します。その中でも特に大切なのが「ハーモニー」です。ハーモニーとは、異なる音が重なり合って美しい響きを作り出すことを指します。合唱の楽しさは、みんなの声が一つになることで生まれることです。一人では出せないような豊かな音色を作り、聴く人の心に響く曲が出来上がります。たとえば、同じ歌を歌う時に、一つのパートを一つの音で歌うのではなく、違う声の高さや音を重ねて歌います。これがハーモニーです。また、ハーモニーは感情を表現する手段でもあります。歌の持つメッセージをより深く伝えるために、ハーモニーを意識することが大切です。合唱を通して、仲間と一緒に音楽を楽しみ、ハーモニーの美しさを感じることで、心が豊かになります。そして、合唱は楽しいだけでなく、協力やコミュニケーションの大切さも教えてくれます。みんなで同じ目的に向かって努力し合うことが、さらに美しい音楽を生み出すのです。合唱でのハーモニーの力を体験してみませんか?
合唱 ユニゾン とは:合唱や音楽の世界では「ユニゾン」という言葉をよく聞きます。ユニゾンとは、複数の歌手や楽器が同じメロディーを同時に歌ったり演奏したりすることを指します。たとえば、みんなで同じ歌を歌う時、どの声も同じ音を出している場合、これがユニゾンです。ただし、ユニゾンは単なる一致だけではなく、全員が力を合わせて一つの大きな声を作り出すことが重要です。合唱でユニゾンを使うことで、まるで一つの生き物のように大きな音を響かせることができます。たとえば、みんなで歌ったときのあの迫力ある声やハーモニーは、ユニゾンによって生まれるものです。合唱団は、さまざまな音の高低やリズムを持った声が融合することで、より美しい音楽を作り上げますが、ユニゾンはその基盤として非常に重要な役割を果たしています。つまり、ユニゾンは「みんなで同じ音を歌う」という基本的な方法であり、合唱における心を一つにする大切な要素なのです。音楽を楽しむためには、このユニゾンを知り、上手に使いこなすことが大切です。
合唱 同声 とは:合唱とは、たくさんの人が集まって歌うことを指します。その中でも「同声」という言葉はとても大切です。同声合唱とは、同じ音域の声が同じパートを歌うスタイルのことを意味します。例えば、みんなが高い声のパートを歌う「同声」の合唱があれば、声が揃ってとても美しいハーモニーを作り出します。このように、同声合唱は、特に初心者や小さい子どもたちが参加する合唱団でよく見られます。例えば、小学校の合唱団では、男女の声を分けずにどちらも同じパートを歌うことが多いです。同声合唱は、歌の楽しさを感じたり、みんなで協力して美しい音楽を作り上げたりする良い機会になります。また、同声で歌うことで、初めて歌を学ぶ人たちが音楽に自信を持つきっかけにもなるのです。声が揃った時の感動は、とても特別な経験になります。合唱を通じて、友達と仲良くなったり、一緒に何かを成し遂げたりする楽しさも感じられるでしょう。
合唱 掛け合い とは:合唱の「掛け合い」とは、2つ以上のパートが同時に歌うスタイルのことを指します。たとえば、ある声部が歌っている間に別の声部が別のメロディを歌うことで、音楽に深みや動きを与えます。この掛け合いがうまくできると、聴いている人にとっては、とても楽しい体験になります。曲によっては、掛け合いが特に重要な部分になることもあります。例えば、クラシック音楽やポピュラーソングでよく見られ、一つのメロディの上に異なる声が重なることで、色彩豊かなハーモニーが生まれます。また、掛け合いのパートを練習することは、歌う力だけでなく、音楽全体の中での自分の役割を理解するのにも役立ちます。合唱を楽しむためには、この掛け合いの基本をおさえておくことが大切です。これから始める方も、掛け合いの楽しさをぜひ体験してみてください。歌の中で感じる、他のパートとのつながりや共鳴は、一緒に歌う仲間がいるからこその醍醐味です。
合唱の共起語音楽:合唱は歌を通じて表現されるアートであり、音楽の一部を形成します。
合唱団:合唱を行うためのグループで、通常は複数の声部で構成され、一緒に歌うことを目的としています。
指揮者:合唱の演奏を指導する役割を持つ人で、テンポや表現を決定します。
ハーモニー:異なる音が組み合わさって美しい響きを作り出すことを指し、合唱の魅力の一つです。
声部:合唱において、各パートを指す言葉で、通常はソプラノ、アルト、テノール、バスの4つがあります。
アンサンブル:合唱を行うときの協調や演奏の一体感を指します。全員が同じ音楽の一部となることが重要です。
レパートリー:合唱団が演奏するために用意している曲の一覧のこと。様々なジャンルやスタイルの曲が含まれます。
練習:合唱団がパフォーマンス向上のために行う繰り返し練習のこと。技術や表現力を高めるために欠かせません。
発声:合唱において正しい声の出し方の技術を指し、美しい音色を生み出すために重要です。
コンサート:合唱団が一般に発表する際の公演のことで、観客に音楽を楽しんでもらう場です。
合唱の同意語合唱団:複数の人々が集まり、合唱を行う団体。
歌唱:歌を歌うこと。合唱は複数で行う場合が多いが、歌唱は一人でも可能。
合奏:楽器を使って複数の人が一緒に演奏すること。歌唱と似ているが、音楽の演奏が主。
歌の競演:複数の歌手や合唱団が一緒に歌ったり、同じ場で演奏すること。
コーラス:特に合唱の西洋のスタイルを指し、通常は複数の声部に分かれて歌う。
ハーモニー:異なる声や楽器が組み合わさることで生じる心地よい響き。合唱でも重視される要素。
合唱の関連ワード合唱団:合唱を行うためのグループ。声楽を専門に学ぶ団体であることが多い。
合唱祭:合唱グループが集まって自分たちの演奏を披露するイベント。
合唱音楽:複数の声部が重なり合って歌われる音楽のスタイル。
ハーモニー:異なる音が同時に鳴ることで生じる調和。合唱では重要な要素である。
パート:合唱で歌われる声の種類。一般的にはソプラノ、アルト、テノール、バスの4つに分けられる。
指揮者:合唱やオーケストラの演奏を指導し、全体のバランスを取る役割の人。
リハーサル:本番の前に行う練習。合唱においても重要な準備の一環である。
声楽:歌唱に関する技術や芸術のこと。合唱は声楽の一形態である。
アカペラ:楽器なしで人の声だけで演奏される音楽スタイル。合唱でよく使われる技法。
ボイストレーニング:声を鍛えるための練習。合唱に参加する前に多くの人が行う。
合唱の対義語・反対語
合唱の関連記事
エンターテインメントの人気記事
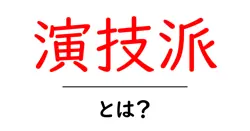
4367viws
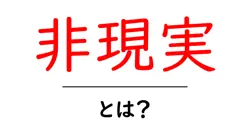
1842viws
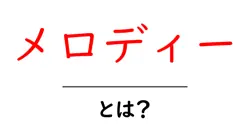
1480viws
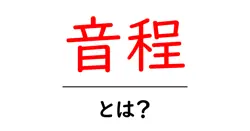
3411viws
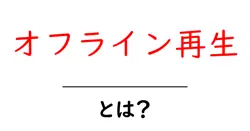
1994viws
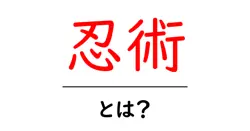
1686viws
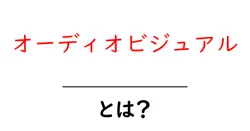
1658viws
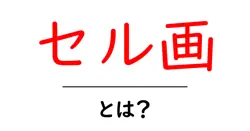
809viws
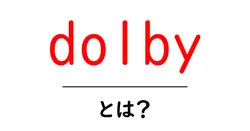
2004viws
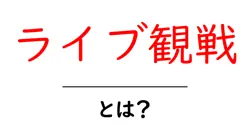
2090viws
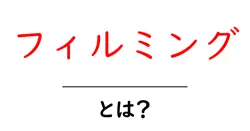
5104viws
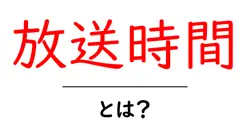
3280viws
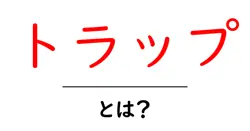
5053viws
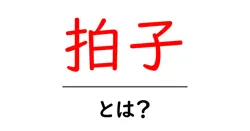
640viws
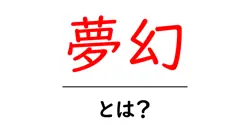
4107viws
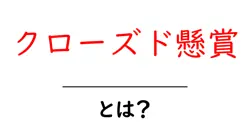
3092viws
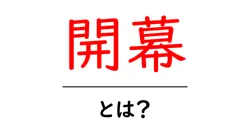
2078viws
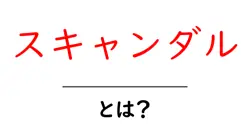
5178viws
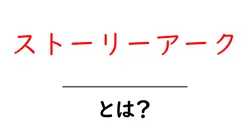
2481viws
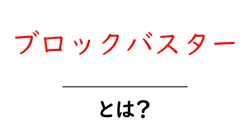
5057viws