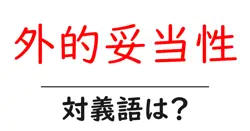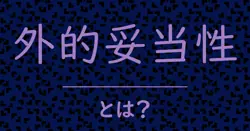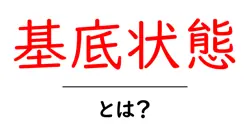外的妥当性とは?
外的妥当性(がいてきだとうせい)という言葉は、主に研究や実験の結果がどれだけ一般的に適用できるか(外部の状況での適用可能性)を指します。例えば、ある実験で得られた結果が特定の人々や条件にだけ当てはまるのであれば、その結果の外的妥当性は低いと言えます。逆に、多くの人や状況に適用できるようであれば、高い外的妥当性を持っていると評価されます。
外的妥当性の重要性
研究や実験の結果は、単にその場での発見だけでなく、より広い社会や異なる状況にも応用できることが大切です。たとえば、医療の研究において新しい治療法が特定の患者に効果があったとしても、その結果が他の患者群や異なる環境でも同じように効果があるかどうかが、外的妥当性によって判断されます。
外的妥当性を高めるための方法
外的妥当性を高めるためには、以下のような方法が考えられます:
| 方法 | 説明 |
|---|---|
まとめ
外的妥当性は、研究結果を広く適用できるかどうかを考える上で非常に重要な概念です。このような外的妥当性を考慮することで、我々はより信頼性のある知識を得ることができ、人々の生活に貢献することができます。
div><div id="kyoukigo" class="box28">外的妥当性の共起語
内部妥当性:研究の結果が実際にその研究の条件下で起こったことを示す度合い。
サンプリング:調査や実験に必要なデータを選び取るプロセス。適切なサンプルを選ぶことで結果の信頼性を高める。
一般化:特定のケースから得られた結論を他のケースにも適用できるかどうかの評価。
外的要因:研究結果に影響を与える可能性のある、研究以外の外部の要素。
リサーチデザイン:研究の構造や方法を計画すること。外的妥当性を考慮することでより信頼できる結果が得られる。
コントロールグループ:実験において比較のために設けられる基準のグループ。外的妥当性を評価するために重要。
結果の再現性:同じ条件で行った研究が、同じ結果をもたらすかどうかの確認。再現性が高いと外的妥当性が強い。
因果関係:一つの要因が他の要因に与える影響。外的妥当性を確保するためには因果関係の理解が必要。
フィールドスタディ:実際の環境で行われる研究。外的妥当性が高いとされる。
対象集団:研究の対象となる集団。外的妥当性はこの集団の特性に依存する。
div><div id="douigo" class="box26">外的妥当性の同意語外的妥当性:特定の研究結果が、他の状況や集団でも当てはまるかどうかの信頼性を表す概念です。つまり、実験や調査の結果が、異なる場所や時期においても同じように適用できるかどうかを指します。
一般化可能性:ある研究の結果を、異なる状況や集団に当てはめて利用できるかどうかを示す言葉です。研究結果が他の文脈でも有効なら、一般化可能性が高いと言えます。
外的妥当性の強さ:研究の外的妥当性が高いと、結果が多様な条件下で信頼できることを示します。逆に、外的妥当性が低ければ、特定の条件下でのみ結果が有効ということになります。
フィールド妥当性:研究の成果が、実際の生活環境や現実の状況においても適用できる程度を示す言葉です。つまり、実験室で得られたデータが、現実の場面でも有効であるかどうかを見極めます。
div><div id="kanrenword" class="box28">外的妥当性の関連ワード内的妥当性:研究や実験がその造成した結果の原因を正確に特定できているかどうかを示す指標です。内的妥当性が高いと、実験条件が影響を与えていることが確実になります。
外部妥当性:研究結果が異なる状況や他の集団に対してどれだけ一般化できるかを示す指標です。外部妥当性が高いと、研究結果をさまざまな文脈において適用することが可能です。
サンプルサイズ:研究においてデータを収集する際に用いる対象者の数です。大きなサンプルサイズは結果の信頼性を向上させ、外的妥当性を高める助けになります。
実験デザイン:研究を進めるための計画や方法を指し、どのようにデータを収集し分析するかを決定します。適切な実験デザインは外的妥当性を向上させることができます。
代表性:研究対象となる集団が、調査したい集団をどれだけ正確に反映しているかを示す重要な概念です。代表性が高いと外的妥当性も高まります。
エコロジカル妥当性:研究結果が日常生活や現実の環境にどれだけ適用できるかを示します。特に、実験がラボという制御された環境ではなく、実際の世界で行われた場合に重要です。
再現性:他の研究者が同じ条件で実験を行った際に同じ結果が得られるかどうかを示す概念です。再現性が高い研究は外的妥当性も高いと言えます。
div>