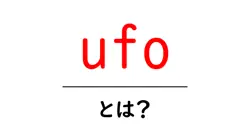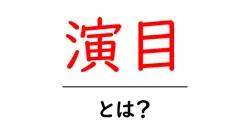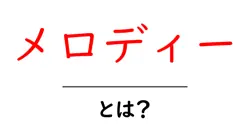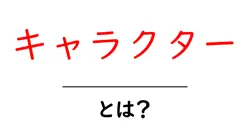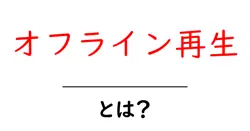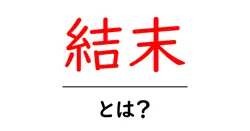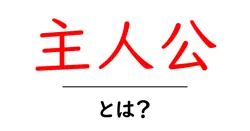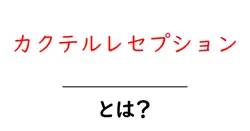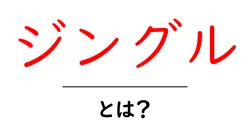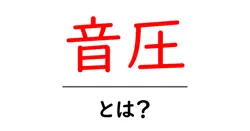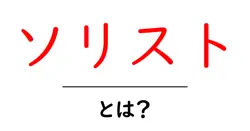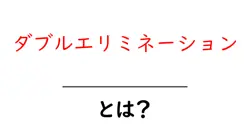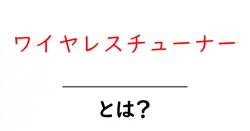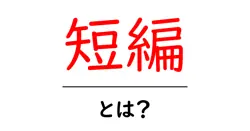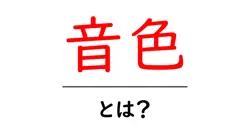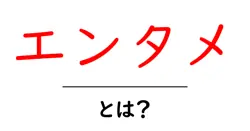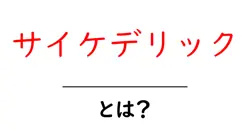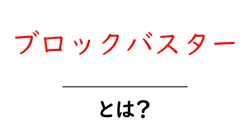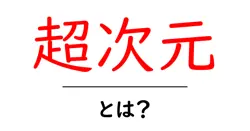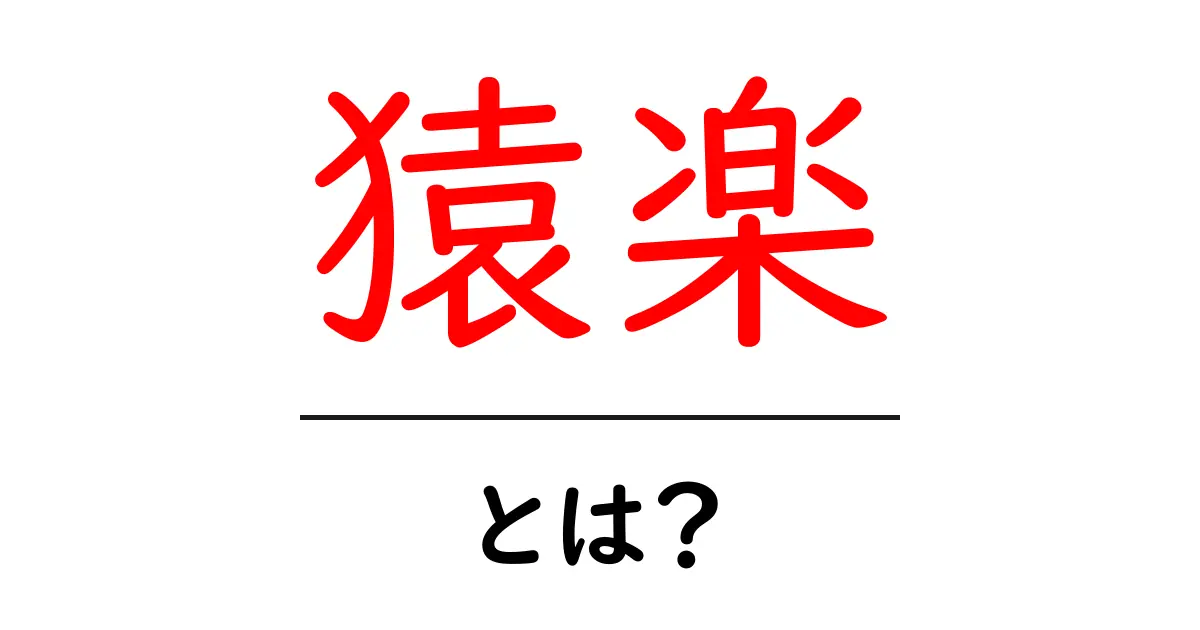
猿楽とは?
猿楽(えんがく)は、古代日本において発展した伝統的な演劇の一種です。特に、平安時代や鎌倉時代において非常に重要な文化として知られていました。この芸能は、猿のようなパフォーマンスを行うことから名前が付けられたとされていますが、実際には人間が演じる劇のスタイルなのです。
猿楽の歴史
猿楽の起源は非常に古く、平安時代には貴族たちの間で好まれる遊びや娯楽として行われていました。特に、神社での祭りや儀式の中で演じられることが多く、神々への奉納行事としても重要な役割を果たしていました。
猿楽と能楽の関係
猿楽は、後に能楽として発展していく基盤となりました。能楽は、猿楽のスタイルをさらに洗練させ、より厳格な形式と美しさを追求した演劇です。猿楽が能楽への橋渡しを果たしたことで、今日まで続く日本の伝統芸能が生まれたのです。
猿楽の特徴
猿楽の演出には、歌、舞、しかし、何よりもユーモアが含まれています。また、衣装や小道具もとても独特で、観客を楽しませるために工夫されています。
猿楽の楽しみ方
猿楽を見る際には、色彩豊かな衣装や、ユーモアあふれる演技に注目してみると良いでしょう。また、時に観客が舞台に参加できるような仕掛けもあったりして、とても楽しめる体験です。特に、伝統的な祭りに合わせて行われる猿楽は、実際の体験としても非常に味わい深いものとなります。
まとめ
猿楽は日本の伝統的な演劇の一つで、その歴史や魅力は奥が深いものです。現代でも猿楽は多くの人々に親しまれており、伝統を継承するためのイベントも開催されています。ぜひ一度、猿楽の魅力に触れてみてください!
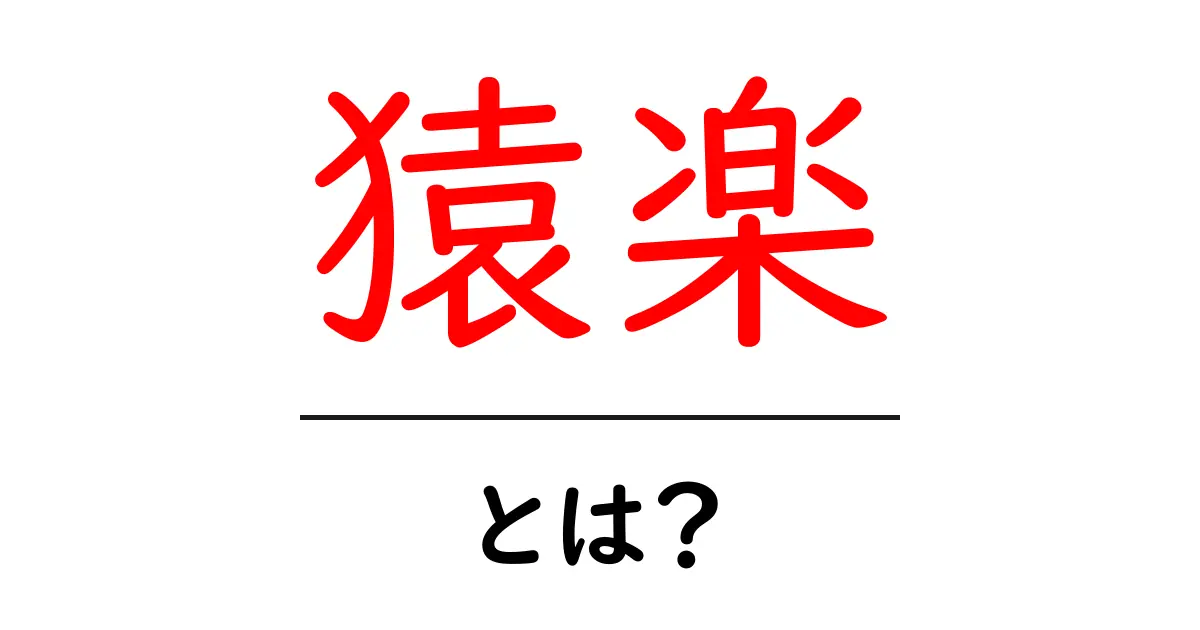
田楽 猿楽 とは:田楽(でんがく)と猿楽(さるがく)は、日本の古くからある伝統文化ですが、実は全く違うものです。まず、田楽とは田んぼで収穫した作物を使って作った料理のことを指します。特に、味噌を塗った豆腐や焼き物が人気です。田楽は、収穫を祝うお祭りや、収穫時期の料理として食べられています。一方、猿楽は、音楽や舞いを含む演劇の一種で、江戸時代から始まったとされています。猿楽では、人間と猿が絡む楽しい演技や、民話を元にしたお話が上演されます。田楽は食に関するもので、猿楽は舞台芸術の一種といえるでしょう。日本の文化にはこうしたユニークなお祭りや演目があり、どちらも風情があります。田楽を食べてお祭りの雰囲気を楽しみ、猿楽を見て日本の伝説や物語を感じる。これらを通じて、私たちは日本の素晴らしい伝統文化を感じることができるのです。ぜひ、田楽と猿楽の違いを知って、もっと日本の文化を楽しんでみてください!
日本:猿楽は日本の伝統的な舞台芸術の一つであり、日本文化の一部です。
能:能は猿楽から発展した日本の古典劇で、歌舞伎や他の舞台芸術の基礎ともなっています。
舞:猿楽では演者が舞を通じて物語を表現します。この舞は非常に重要な要素です。
音楽:猿楽では演奏される音楽が重要な役割を果たし、舞の雰囲気を盛り上げます。
伝統:猿楽は日本の伝統的な芸術で、長い歴史を有しています。
祭り:猿楽は祭りや行事の際に演じられることが多く、地域文化と密接に関連しています。
演技:猿楽においては演技が観客に感動を与える重要な要素です。
古典:猿楽は古典芸能の一つであり、そのスタイルや演技が今も受け継がれています。
衣装:猿楽の演者は特別な衣装を着用し、それが演技の雰囲気を盛り上げます。
フォークロア:猿楽は日本のフォークロア(民間伝承)と深く結びついており、地域の物語を表現することが多いです。
サル楽:猿楽のカジュアルな表現。猿が演じる楽器・音楽やパフォーマンスに関連することを指すことがあります。
猿の劇:猿楽は、猿が人間の真似をしたり、特定のキャラクターを演じる劇を指す場合があります。
猿の芸:猿楽は、猿が行う芸やパフォーマンスにも使われることがあり、伝統的なエンターテイメントとして楽しむことができます。
猿の舞:猿楽は、舞台上での猿の動きや表現を含むことがあり、視覚的なエンターテイメントを指すこともある。
人形劇:猿楽に似た形式のエンターテイメントとして、人形を使った劇があり、演じる人形が猿を模している場合もある。
猿楽:日本の伝統的な舞台芸術で、主に平安時代から鎌倉時代にかけて流行しました。猿の面をかぶった演者が踊ることから名付けられ、神社や寺院での祭りに用いられました。
能楽:猿楽の流れを汲む日本の伝統舞台芸術で、舞と音楽が組み合わさった形式です。能と狂言の2つのジャンルがあり、より洗練された形に発展しました。
舞楽:古代日本の宮廷音楽と舞踊を指します。猿楽は舞楽から影響を受けており、猿楽が神社で演じられたことによって神楽とも関連付けられています。
神楽:神道の儀式で演じられる舞や音楽を指します。猿楽は神楽から派生した側面があり、神楽の中にも猿楽の要素が見られます。
讃美歌:猿楽の演目の一部として古くから行われてきた宗教的な歌です。神々を称えるために歌われ、猿楽の背景に深く根付いています。
面:日本の伝統的な舞台芸術で用いる仮面のこと。猿楽では特に猿の顔を模した面が多く使われ、演者の表現を豊かにします。
舞台:猿楽や能楽が演じられる特定の空間。伝統的には神社や寺院の境内で行われることが多く、観客に向けて演者がパフォーマンスを行います。
演者:猿楽や能楽に出演し、演技を行う人。演者は特に技術と表現力が求められ、その訓練は長い時間を要します。
技芸:猿楽を含む多くの伝統芸能において、習得された技能や技術のこと。演者は独自の技芸を磨くことで、より高い表現力を得ます。
伝承:猿楽やその関連芸能は、代々の師匠から弟子へと口伝えや実演によって伝えられてきました。このプロセスは文化の保全において重要です。
猿楽の対義語・反対語
該当なし