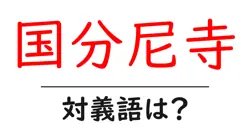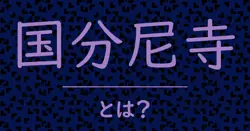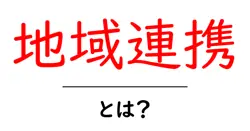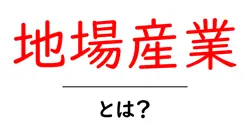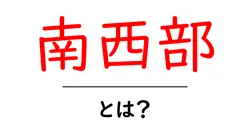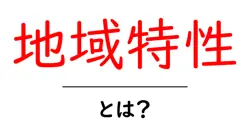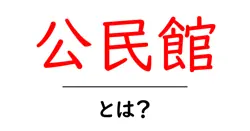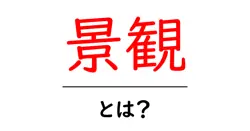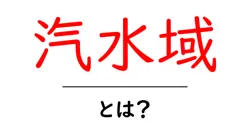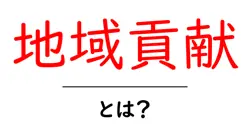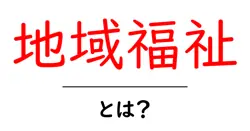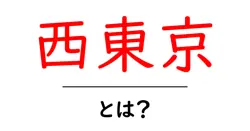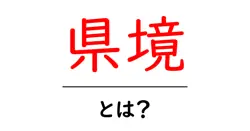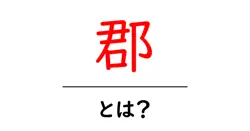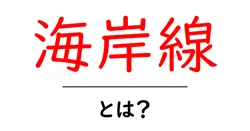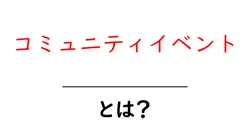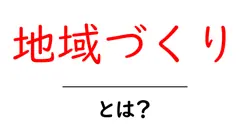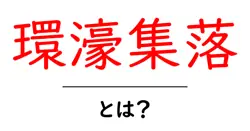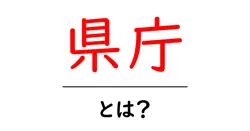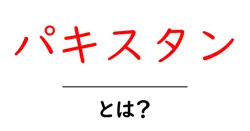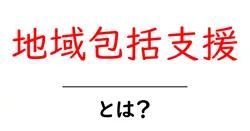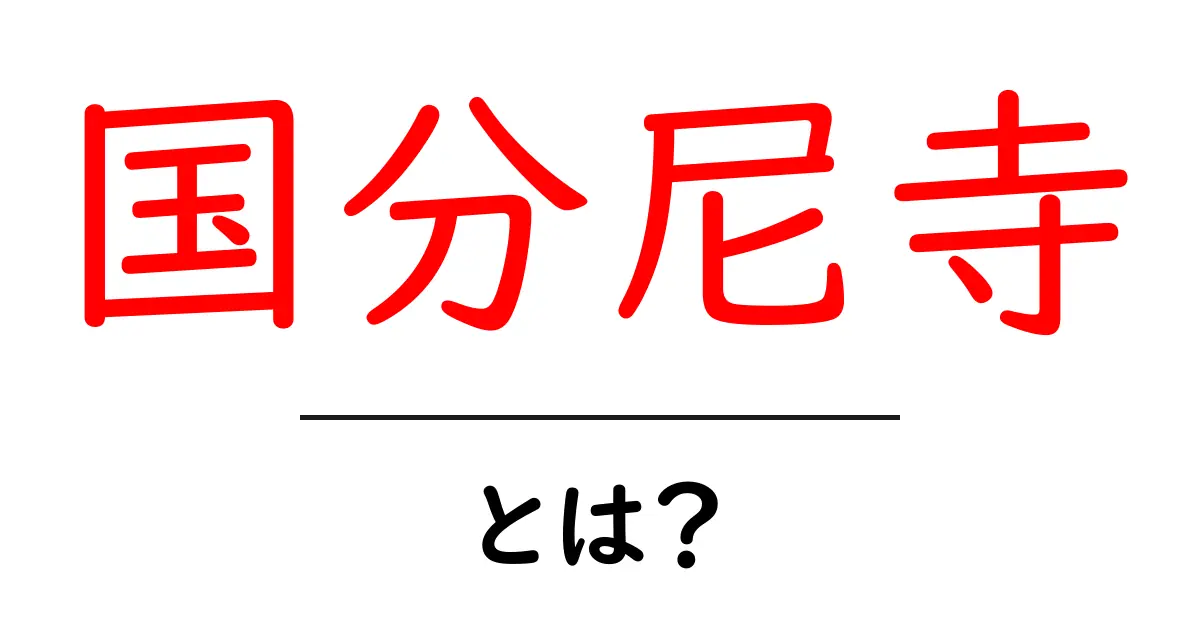
国分尼寺とは?歴史と魅力を解説!
国分尼寺(こくぶんにじ)は、日本の奈良時代に建てられた仏教寺院の一つです。この寺院は奈良県にある国分寺とともに、当時の政治や文化に深く関わってきました。今回は、国分尼寺がどのような場所で、どんな歴史があるのか、一緒に見ていきましょう。
国分尼寺の歴史
国分尼寺は、740年に建立されました。この寺院は、奈良時代の皇室の影響を受けて作られたもので、仏教を広める役割がありました。国分寺とともに、地域の人々の信仰の場となりました。国分尼寺は、日本最古の尼寺とされており、女性が仏教を学び、修行する場として重要な位置づけがありました。
国分尼寺の建築様式
国分尼寺の建物は、当時の建築様式を色濃く反映しています。特に注目すべきは、金堂や講堂の美しいデザインです。これらの建物は、仏教彫刻や装飾が施されており、訪れる人々を魅了しています。
国分尼寺の魅力
国分尼寺の魅力は、歴史的な価値だけでなく、観光地としての楽しさもあります。美しい庭や静かな雰囲気は、心を落ち着ける場所です。また、毎年行われるお祭りや行事も多く、地域の人々と触れ合う良い機会となっています。
国分尼寺の訪れ方
国分尼寺へ訪れるには、最寄りの駅からバスや徒歩でアクセスすることができます。周囲には観光スポットも多く、観光のついでに立ち寄るのもお勧めです。
まとめ
国分尼寺は、奈良時代から続く歴史ある寺院であり、女性が仏教を学ぶ場としても知られています。また、観光として楽しむこともできる場所です。歴史に触れながら、静かなひとときを過ごすのにぴったりのスポットですね。
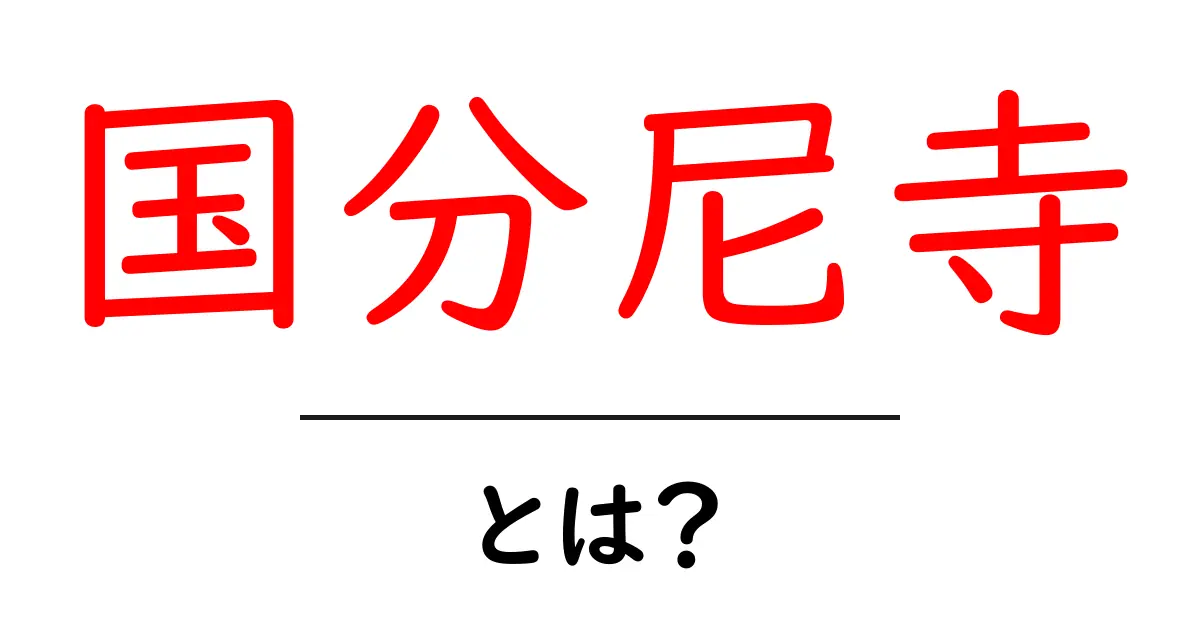
国分寺 国分尼寺 とは:国分寺(こくぶんじ)と国分尼寺(こくぶんにじ)は、奈良時代に日本で建てられたお寺です。国分寺は、国の中心となるお寺で、主に仏教の教えを広める役割を持っていました。一方、国分尼寺は、女性の僧侶が住むお寺で、女性たちの修行の場でもありました。これらの寺が建てられた背景には、当時の天皇や政府が仏教を推進しようとした理由があります。国分寺は、全国に約60か所あると言われていますが、それぞれの地域で多くの文化や歴史が詰まっています。たとえば、東京にある国分寺市には、現在もその名残を残す美しい風景が広がっています。また、国分尼寺は、特に女性の宗教活動が盛んであり、現在も多くの参拝者が訪れています。国分寺と国分尼寺は、ただの古い建物ではなく、私たちに歴史や文化についての大切な教訓を教えてくれる存在です。今日では、観光地としても人気がありますので、ぜひ訪れてみてください!
国分寺:国分尼寺と同じように、国家の安寧を祈るために建設された寺院ですが、主に男性僧が修行するための場所です。
仏教:国分尼寺は仏教に基づいて建てられた寺なので、仏教に関連する教義や哲学が深く関わっています。
奈良時代:国分尼寺が創建されたのは奈良時代であり、この時期は国の寺院が多く建設された重要な時代です。
仏像:国分尼寺には仏像が祀られており、信仰の対象となっています。仏像は仏教の教えを具現化したものです。
修行:国分尼寺では僧侶たちが修行を行い、精神的な成長や知識の習得を目指します。
僧侶:国分尼寺には僧侶が住み込み、仏教の教えを広めたり、信者の支援を行ったりします。
文化財:国分尼寺は歴史的な価値があり、様々な文化財が残されています。国家や地域の文化の一部を形成しています。
参拝:国分尼寺を訪れる信者や観光客が行う、仏に祈りを捧げる行為を指します。
歴史:国分尼寺は日本の歴史の中で重要な役割を果たしており、その歴史や伝承は多くの人々に知られています。
行基:国分尼寺の建立に関わった僧侶で、地域の発展に寄与した人物として知られています。
国分寺:国分尼寺と同様に、国家が建立した寺院で、仏教の普及を目的としたものです。ただし、国分寺は僧侶が住むための寺院であるのに対し、国分尼寺は女性の信者や尼僧が所属する寺院です。
尼寺:女性が修行や宗教活動を行うための寺院を指す言葉で、国分尼寺もその一つです。一般的に女性専用の仏教施設として、地域の信者や尼僧たちの拠り所となります。
仏教寺院:仏教を信仰する人々のために建立された寺院全般を表します。国分尼寺は、その一例であり、仏教の教えを広める役割を担っています。
尼宗:尼宗は、女性の僧侶や信者が中心となって活動する仏教の宗派や流派を指します。国分尼寺はこのような尼宗の一環であり、女性のための修行や信仰の場を提供しています。
信仰の場:信者が宗教的な活動や礼拝を行うための場所を指します。国分尼寺は、信者が集まり、仏教の教えを学び、共に修行するための重要な場とされています。
国分寺:国分尼寺と同じく、奈良時代に創建された寺院で、全国に一つずつ設けられたとされています。国分寺は男性僧侶が住むための寺で、国分尼寺とセットで考えられることが多いです。
奈良時代:日本の歴史の一時期で、710年から794年までの時代を指します。この時代には仏教が盛んに広まり、多くの寺院が建設されました。
仏教:アジアに起源を持つ宗教で、釈迦(しゃか)を教祖とし、悟りや輪廻をテーマにした教義が展開されています。国分尼寺などの寺院は仏教の教えを広めるための場所として重要な役割を果たしています。
僧侶:仏教の教えを学び、実践する人々を指します。国分尼寺では、僧侶たちが修行を行い、仏教の教えを伝えています。
講堂:寺院内で教えを説くための建物で、僧侶が仏教の教義を学び、信者が集まる場でもあります。国分尼寺にも講堂が存在し、重要な儀式や教えの伝達が行われました。
経典:仏教の教えをまとめた書物のことを指します。国分尼寺では、経典を読誦(どくじゅ)し、学ぶことが僧侶の重要な活動の一つです。
巡礼:信者が聖地を巡る行為のこと。また、国分尼寺は信者たちにとって重要な巡礼先の一つとされています。
文化財:歴史的または芸術的に価値のある物品や建物のことを指します。国分尼寺はその歴史的価値から、文化財として保護されています。
寺院:仏教の信仰を行うための建物や施設のことです。国分尼寺は、寺院の一つであり、信者が集まり、祈りや修行を行う場所です。