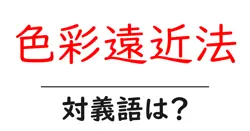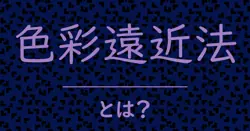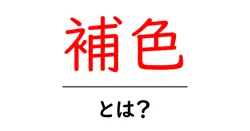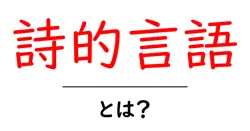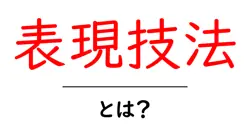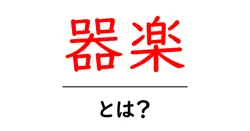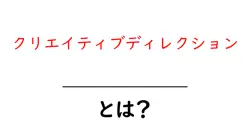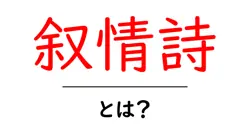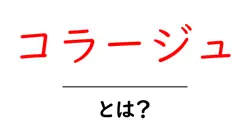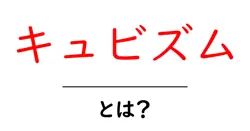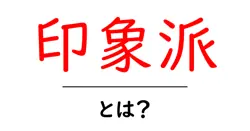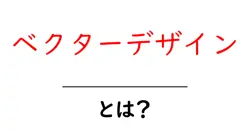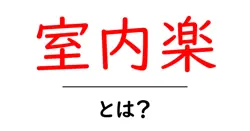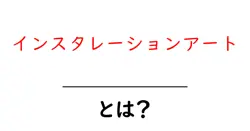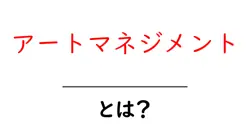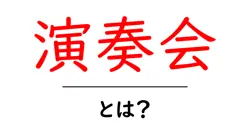色彩遠近法とは?
色彩遠近法(しきさいえんきんほう)とは、絵画やデザインにおいて、色の使い方によって距離感や立体感を表現する技術のことです。この技法を使うことで、平面の中に奥行きや立体感を感じさせることができます。例えば、遠くのものを薄い色、近くのものを濃い色で描くことによって、見る人に「これは遠い、これは近い」と感じさせることができるのです。
色彩遠近法の原理
色彩遠近法は、色の明るさや鮮やかさ、さらには温かさに基づいています。次の表は、色彩遠近法に関連する要素をまとめたものです。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 色の明るさ(明度) | 遠くのものは色が薄く、近くのものは色が濃い。 |
| 色の鮮やかさ(彩度) | 近くのものはより鮮やかな色、遠くは鈍い色に見える。 |
| 色温度 | 暖色系(赤、オレンジなど)は前に出てきやすく、寒色系(青、緑など)は奥に引っ込む感じを与える。 |
色彩遠近法の使い方
この技法は絵画だけでなく、写真やグラフィックデザインでも使われます。例えば、風景写真で遠くの山を青く、手前の木を緑で描写することで、自然の奥行きを表現しています。このように、色彩遠近法を工夫することで、アートやデザインに深みを持たせることが可能です。
実際の例
実際に、印象派の画家たちは色彩遠近法を巧みに使い、自然の美しさを捉えていました。彼らは光の変化を色で表現し、特に風景画においてこの技法の効果を最大限に引き出しました。例えば、ルノワールの作品には色彩遠近法が多用されています。
色彩:視覚的な属性で、物体の光の波長によって決まる、色のこと。色彩はデザインやアートにおいて重要な役割を果たします。
遠近法:物体のサイズや位置を、視点からの距離によって変化させる技法。遠近法を用いることで、立体感を表現します。
視覚:目を通じて情報を受け取り、認識する感覚。色彩遠近法は視覚的な効果を利用して、絵画やデザインに奥行きを加えます。
奥行き:空間の深さのこと。色彩遠近法を使うことで、フラットな画像に立体感が生まれ、奥行きを感じさせることができます。
コントラスト:異なる色や明るさを組み合わせた際の対比のこと。強いコントラストは、遠近感を強調する要素として利用されます。
デザイン:物事を視覚的に構成する工程。色彩遠近法は、デザインにおいて魅力的な視覚効果を生み出すための重要な技術です。
パースペクティブ:遠近法を用いた視覚表現の技術。特に、絵画やデジタルアートで広く使われます。
陰影:物体の形を際立たせるための影や光の使い方。陰影は、色彩遠近法での奥行き感を出すために重要です。
景観:自然や都市の美しい視覚的構成。色彩遠近法は、景観表現において重要な要素となります。
カラーパースペクティブ:色を使った遠近感の表現技法。色の明るさやトーンの変化を利用し、物体の距離感を感じさせる方法。
色彩の遠近法:色彩を使って遠近を表現する技法で、物体が遠ざかるにつれて色が薄くなったり、青みがかって見える現象を活用する。
色彩表現法:色を使って視覚的な印象を与える手法の総称で、遠近感の演出も含まれる。
空気遠近法:空気中の微細な粒子や湿度の影響で遠くの物体の色合いや明るさが変わる現象を利用し、遠近感を表現する技術。
視覚的遠近法:視覚的な手法を用いて、物体の距離感や形状を印象づける技術のひとつ。色の使い方が重要な役割を果たす。
遠近法:絵画や写真において、物体の遠くにあるものを小さく、近くにあるものを大きく描く技法。これにより、奥行きや立体感を表現することができる。
色彩:目で perceiving できるさまざまな色。色彩は物の見え方や印象に大きな影響を与え、組み合わせや配色によって情感や雰囲気を創り出す。
色彩理論:色の組み合わせや配色に関する原則や法則を示す理論。色輪や補色、類似色、トーン、シェードなどの概念を含む。
アスペクト比:画像や画面の横と縦の比率。色彩遠近法で描かれる物体のサイズ感や位置関係を理解する際に重要な要素である。
視覚的トリック:視覚の特徴を利用して、見る人の脳に様々な印象を与える技術。色彩遠近法も視覚的トリックの一種で、色を用いた空間の感覚を錯覚させることができる。
明暗:物体の明るさや暗さの度合い。色彩遠近法では、遠くのものは淡く、近いものは濃く描くことで遠近感を強調する。
色相:色の持つ種類を示す概念で、赤、青、緑などの色の区別を表す。色彩距離や印象においても重要な役割を果たす。
視覚効果:視覚に基づいて生じる効果で、色彩遠近法を用いて物体の位置や距離感を表現する際に用いられる技術。
パースペクティブ:遠近感を生むために、物体の描き方に工夫を加える技法。色彩遠近法は、このパースペクティブを色彩によって強調する方法の一つである。