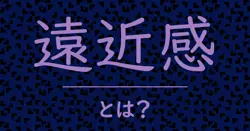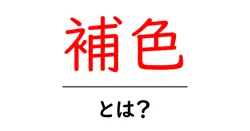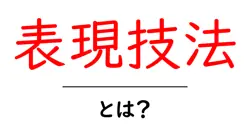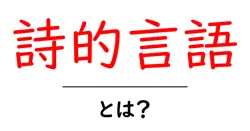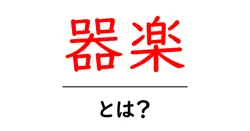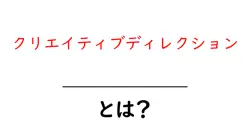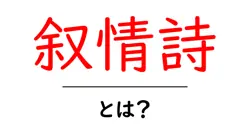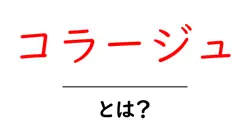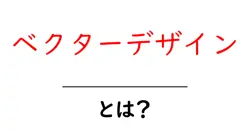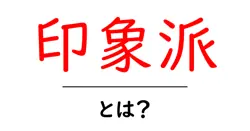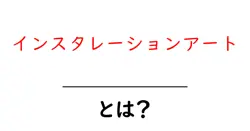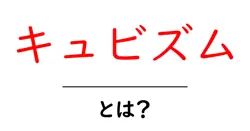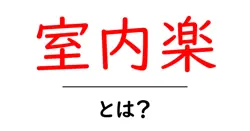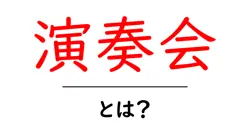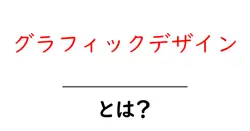遠近感とは?立体感を引き出す視覚の不思議
私たちの目は、さまざまな物体の距離や大きさを感じ取ることができます。この能力を「遠近感」と呼びます。遠近感は、物体の実際の大きさや距離によって異なる見え方をすることで、私たちに立体感を与えます。では、具体的に遠近感がどのように働くのかを見ていきましょう。
遠近感の仕組み
遠近感は、いくつかの要素によって成り立っています。その主なものは以下の通りです。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 相対的サイズ | 近くにある物体は大きく、遠くにある物体は小さく見える。 |
| 重なり | ある物体が別の物体を部分的に隠すことで、遠近感を感じる。 |
| 透視法 | 平行線が遠くで収束するように見えることから、距離を感じ取る。 |
| 空気遠近法 | 遠くの物体は色がぼやけたり、暗く見えることから距離を感じる。 |
遠近感があるとどうなるの?
遠近感があると、私たちは周りの景色を立体的に認識できます。例えば、山や建物を見るとき、その距離感を理解することで、実際の距離を把握しやすくなります。これが遠近感の効果です。
遠近感とアート
アートの世界でも、遠近感は非常に重要です。絵画や写真において、遠近感をうまく利用することで、よりリアルで魅力的な作品を作り出せます。たとえば、絵画では遠くの物体を小さく描くことで、奥行き感を表現します。
このように、遠近感は私たちの日常生活や芸術において不可欠な要素なのです。
立体感:物体が奥行きを持っているように感じさせる感覚。遠近感と密接に関連しており、視覚的に空間を理解する手助けをする。
視界:目に見える範囲や空間のこと。遠近感を理解するためには、視界が重要な要素となる。
奥行き:物体や空間の前後の距離を示す概念。遠近感を感じるためには、奥行きの認識が必要。
パースペクティブ:遠近法のことで、物体が遠くに行くほど小さく見える現象。絵画や写真などで特に重要な技法。
比例:物体のサイズや距離をどの程度縮小するかを示す関係。遠近感を生み出す際には、比例が必須。
視点:視覚情報を得るために立っている位置。視点によって遠近感は大きく変わる。
コントラスト:色や明暗の違い。遠近感を強調するために、近くの物体と遠くの物体のコントラストが重要となる。
色温度:光の色合いの感じ方。遠くにある物体は一般的に青白く見え、色温度も遠近感の認識に影響を及ぼす。
視覚的効果:目に映るものが持つ影響力。遠近感の演出には、様々な視覚的効果が用いられる。
空気遠近法:遠くの物体が霞んで見える現象。これは遠近感を強調するための技術の一つ。
距離感:物体や景色の距離を理解し、どのくらい離れているかを感じ取る感覚のことです。
奥行き感:空間が持つ深みや広がりを感じる能力のことで、特に平面での表現において重要です。
立体感:物体が三次元的に見えるように感じられること、つまり高さ、幅、奥行きがあるように認識することです。
景深:ある範囲内での焦点距離による視覚的な効果で、近くの物体と遠くの物体が明確に見える度合いを指します。
パースペクティブ:遠近法に基づいた視点のことで、物体が視点からの距離によってどのように見えるかを表現する技法です。
パースペクティブ:物体の遠近感を表現する技法で、特に絵画や写真において、近くの物体は大きく、遠くの物体は小さく見えるという原理を使って立体的に見せることを指します。
焦点:視覚において、物体が鮮明に見える点を表します。遠近感では、焦点がどこにあるかが視覚の印象に影響を与え、近くの物体と遠くの物体を区別する手助けとなります。
奥行き:三次元の空間における物体の前後の距離感を指します。遠近感を理解するためには、奥行きを感じ取ることが重要です。
前景・中景・背景:視覚的な構成を考える際に使う用語です。前景は画面の手前に位置する部分で主題を強調します。中景はその中間に位置し、背景は遠くの景色を描写する部分です。これらを組み合わせることで遠近感が生まれます。
視点:観察者がどこから物を見ているかという位置を示す言葉です。視点によって遠近感が大きく変わり、同じ物体でも異なる印象を与えます。
スケール:物体の大きさの比較を示します。遠くにある物体は小さく見えるため、スケールを意識することで遠近感を感じやすくなります。
空気遠近法:遠くの物体が色が薄く、ぼやけて見える現象を利用して、遠近感を強調する技法です。特に風景画などでよく用いられます。
重なり:物体が互いに重なり合うことで、前後関係が明確になります。重なりを見ることで、物体の距離感を感じ、遠近感が強まります。
遠近感の対義語・反対語
該当なし