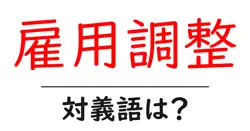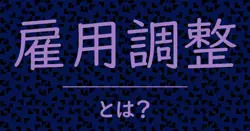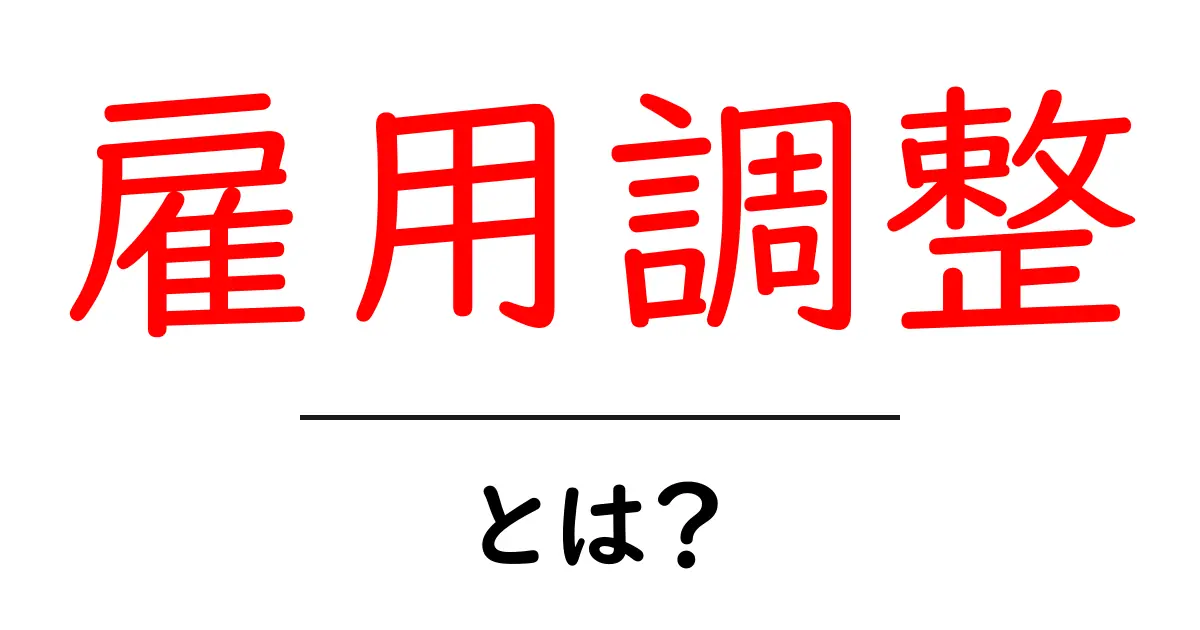
雇用調整とは?
雇用調整(こうようちょうせい)とは、企業が従業員の雇用を維持し、必要に応じて人員配置や労働時間を調整することを指します。これは特に景気の変動や企業の業績に影響を受けた際に行われることが多いです。
雇用調整の必要性
経済の不況や突発的な出来事(例:自然災害、パンデミック)によって、企業の収益が減少することがあります。このような状況下では、多くの企業が人員削減を検討することが一般的ですが、雇用調整を行うことで社員を解雇せずに済む場合があります。
主な手段
雇用調整には、以下のような手段があります:
| 手段 | 内容 |
|---|---|
| 雇用の維持 | 社員を解雇せず、休業や休暇を提案する。 |
| 労働時間の調整 | 労働時間を短縮して、必要に応じてフルタイムをパートタイムに変更する。 |
| 配置転換 | 別の部署に配置換えを行い、実際の業務量に応じた作業を行わせる。 |
雇用調整のメリット
雇用調整には以下のような利点があります:
- 社員の雇用を守る:解雇を防ぐことで、社員に安定した職場を提供できます。
- 企業イメージの向上:人員削減よりも社員を守る姿勢が企業への信頼を高めます。
- スキルの維持:社員が退職しないことで、企業の持つ技術やノウハウを維持できます。
雇用調整のデメリット
一方で、雇用調整にはデメリットも存在します:
まとめ
雇用調整は、企業が厳しい環境においても社員を守る重要な手段です。その実施には利点と欠点の両面がありますが、正しく活用すれば企業にとって非常に有意義な選択肢となるでしょう。多くの企業がこの方法を用いて、社員と共に乗り越えていく姿勢を持っています。
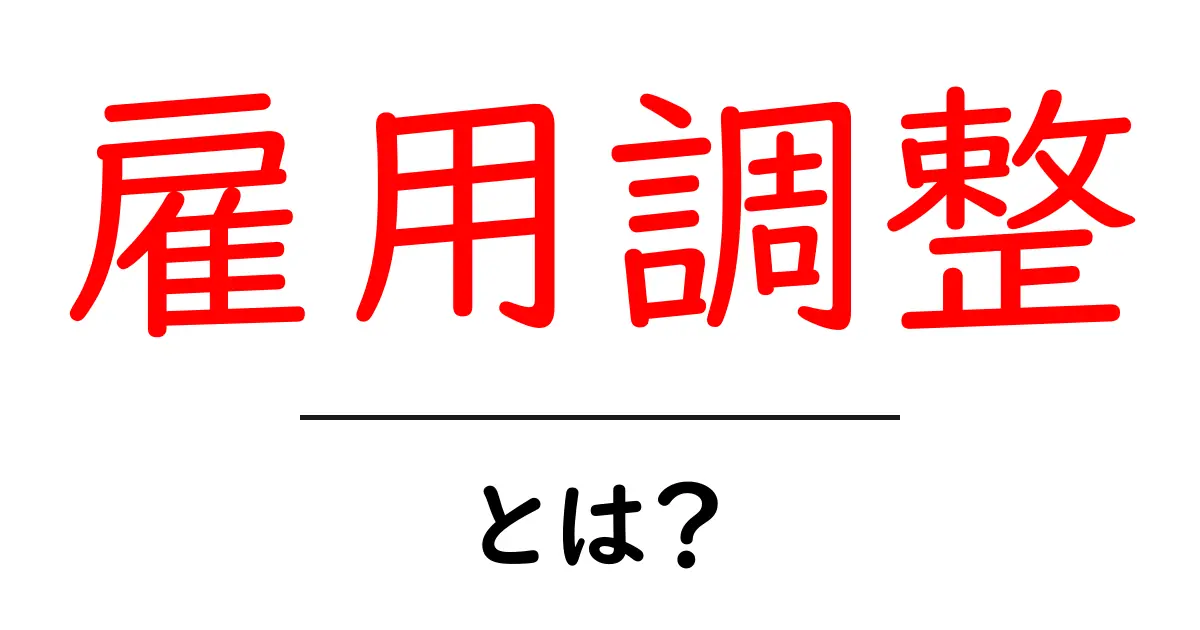 人材管理とその重要性を学ぼう!共起語・同意語も併せて解説!">
人材管理とその重要性を学ぼう!共起語・同意語も併せて解説!">雇用保険:失業した場合に支給される保険金や資金を提供する制度。雇用の安定を図るために設けられています。
労働者:働いている人のこと。企業や団体に雇われている人を指し、雇用調整の影響を受けることが多いです。
休業手当:労働者が仕事ができない期間に給与の一部を保障するために支給される手当。雇用調整の一環として支給されることがあります。
企業:商品やサービスを提供するために人々が集まり活動する組織。雇用調整は企業が経営状況に応じて実施することがあります。
人件費:従業員に支払われる給与や手当を含む、雇用にかかるコスト全般。雇用調整の場面で削減対象となることがあります。
景気:経済全体の状態を示す指標。景気が悪化すると企業が雇用調整を行うことが増えます。
労使協議:労働者と企業の間で行われる話し合いのこと。雇用調整に関する合意を得るために重要なプロセスです。
リストラ:企業がコスト削減や効率化を目的に、従業員の減少を図ること。雇用調整の一形態と言えます。
経済対策:政府が景気や雇用を支えるために行う施策のこと。雇用調整の影響を軽減するために導入されることがあります。
雇用維持:従業員の雇用を続けること。企業が労働力を確保するために、解雇や契約終了を避けることを指します。
人員調整:組織内の人員数や配置を見直し、最適な状態を保つこと。これには、雇用の維持や一時的な休業が含まれます。
雇用保護:法律や制度によって、雇用者が解雇されにくくなるような保護策のことです。危機的な状況で雇用を守るために重要です。
労働調整:労働時間や労働条件の見直しを通じて、従業員の負担を軽減し、企業の業務を円滑にすることを指します。
業務調整:業務の運営方法を見直し、最適化すること。これにより人員の配置や労働効率を改善しようとする取り組みです。
雇用調整助成金:企業が一時的に経営が厳しくなったときに、従業員の雇用を維持するために支給される助成金です。昨今の不況や災害時に労働者の雇用を守る手助けをします。
リストラ:経営の効率化を図るために、従業員を減らすことを指します。雇用調整の一環として行われることもあるが、雇用を守るための施策とは逆の意味を持ちます。
雇用保険:失業した場合に、一定期間給付金が支給される制度です。雇用調整の際には、この保険を利用して雇用を持ちこたえることができます。
休業手当:業務が一時的に停止している間に支給される手当のことです。雇用調整を行う際、業務停止に伴う収入の減少を緩和するために支給されます。
労働環境:職場における労働者の条件や環境のことです。雇用調整の施策が行われる際、労働環境を見直すことも必要です。
経済危機:市場や経済全体が悪化し、企業や個人の経済的な厳しさが増す状況を指します。このような状況では、雇用調整が求められることが多くなります。
雇用調整の対義語・反対語
雇用調整とは<労1>|人材育成用語集 - セゾンパーソナルプラス
雇用調整(こようちょうせい)とは? 意味や使い方 - コトバンク