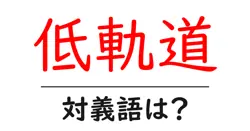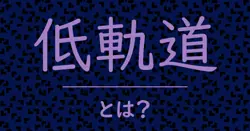低軌道とは?
「低軌道」という言葉は、宇宙に関する用語で、地球の周りを回る衛星や宇宙船が飛ぶ道のことを指します。具体的には、地球から約200キロメートルから2,000キロメートルの高さにある軌道を指します。この低い位置で動いている物体の例として、国際宇宙ステーション(ISS)や地球観測衛星があります。
低軌道の特徴
低軌道にはいくつかの特徴があります。まず、地球に近いため、通信や観測がしやすいという利点があります。衛星が近ければ近いほど、地上との通信距離が短く、より高品質なデータを送ることができます。また、地球の重力の影響を受けやすく、軌道速度も速くなります。このため、低軌道にある物体は、数時間ごとに地球を一周することができます。
低軌道の利用例
低軌道は、さまざまな目的で利用されています。以下にその例を挙げてみます。
| 利用例 | 説明 |
|---|---|
まとめ
低軌道は、宇宙のさまざまな活動において重要な役割を果たしています。宇宙開発が進む中で、私たちの日常生活にも影響を与える楽しみや利便性が広がっています。今後も、多くの技術革新が期待される分野です。
div><div id="kyoukigo" class="box28">低軌道の共起語
軌道:物体が初期の運動状態を保ちながら、重力の影響を受けて進む経路のこと。
人工衛星:地球の周りを回るために人間が作った衛星で、通信や気象観測、GPSなど様々な目的で使われる。
地球:私たちが住む惑星であり、低軌道はこの地球の周りを回る軌道の一つを指す。
オービット:物体がある天体の周りを回る運動を表す言葉。低軌道はオービットの一種。
高度:地表からどれだけ上の位置にあるかを示す数字で、低軌道は地表から数百キロメートルの範囲。
放射線:宇宙空間には様々な放射線が存在し、低軌道にいる人工衛星はこれらにさらされることがある。
ISS:国際宇宙ステーションの略で、低軌道に位置し、様々な科学実験が行われている。
重力:物体を地球に引きつける力で、低軌道においても影響を与え続ける。
軌道制御:人工衛星や宇宙船が目的の軌道を維持するために行う操作や技術。
リモートセンシング:人工衛星を利用して地表の情報を取得する技術で、低軌道での衛星が多く使われている。
div><div id="douigo" class="box26">低軌道の同意語低地軌道:地球の表面から低い位置を周回する軌道のこと。主に400km未満の高度を指します。
LEO:Low Earth Orbitの略で、低軌道を指す英語の言葉です。主に通信衛星や国際宇宙ステーションがこの軌道を使用しています。
サブ軌道:低軌道の一つとされる、地球の重力圏の中での周回運動を行う軌道です。
近地軌道:地球に近い軌道を指し、主に低軌道と同義として使われます。
低軌道衛星:低軌道を周回する衛星のこと。この衛星は地球に近いため、地上との通信が非常に迅速です。
近地球軌道:地球の近くを周回する軌道を示し、低軌道とほぼ同じ意味で使われます。
div><div id="kanrenword" class="box28">低軌道の関連ワード軌道:物体が重力などの影響を受けて動く経路のこと。宇宙空間においては、惑星や人工衛星などが描く円や楕円の形状を指す。
低軌道衛星:地球の表面から約160kmから2,000kmの高さを飛ぶ衛星のこと。地球と近い位置にあるため、通信や観測などの用途で多く利用されている。
LEO (Low Earth Orbit):「低軌道」の英語表現で、2000km以下の高度を指す。LEOは特に通信衛星や地球観測衛星に好まれる軌道。
軌道速度:衛星がある軌道を維持するために必要な速度のこと。低軌道の衛星は、地球に近いため高い速度で移動する。
静止衛星:地球の赤道上空約35,786kmに設置され、地球の自転と同じ速度で運動する衛星。低軌道とは異なり、高軌道に分類される。
宇宙産業:宇宙に関連する技術やサービスを提供する産業。特に低軌道衛星の需要が増え、これは商業利用や科学研究に影響を与えている。
再利用型ロケット:打ち上げや帰還の際に部品を再利用できるように設計されたロケット。低軌道への定期的な打ち上げを可能にし、コスト削減に寄与している。
衛星通信:衛星を利用してデータを送受信する技術。低軌道の衛星は地上との直線距離が近いため、通信遅延が少ない特徴がある。
div>