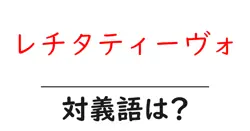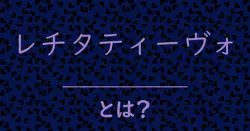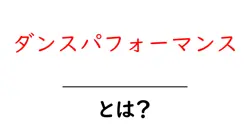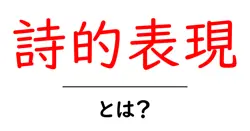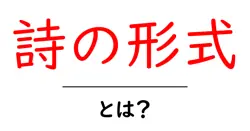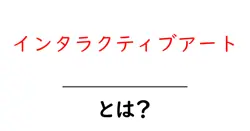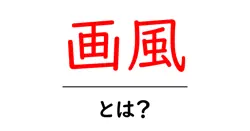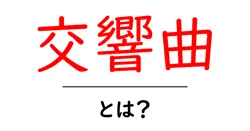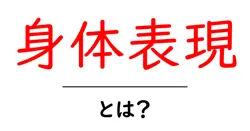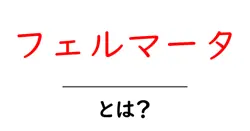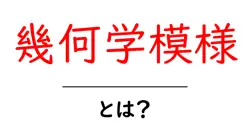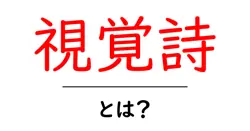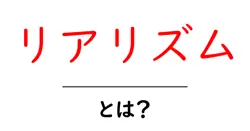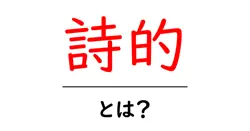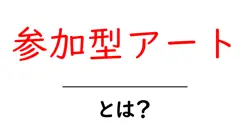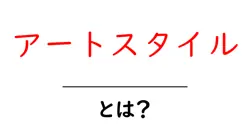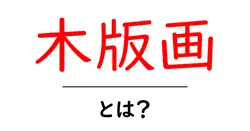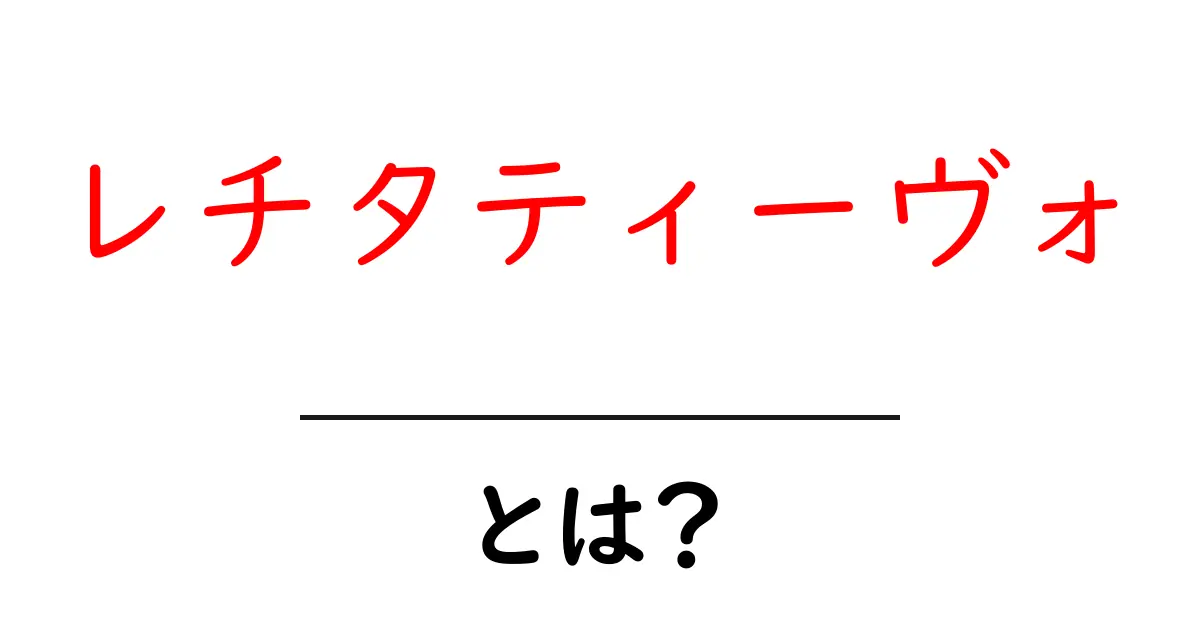
レチタティーヴォとは?
レチタティーヴォは、オペラやオラトリオなどの作品の中で使われる音楽の形式の一つです。この言葉は、イタリア語の「recitativo」から来ていて、直訳すると「朗読すること」という意味です。レチタティーヴォは、主に歌の部分と話す部分を橋渡しする役割を果たします。この形式は、歌詞が語られるように歌われるため、物語を進めるための非常に重要な技術です。
レチタティーヴォの特徴
レチタティーヴォにはいくつかの特徴があります。まず、歌のメロディーは通常とても自由で、感情を強く表現します。次に、伴奏は比較的シンプルで、オーケストラ全体ではなく、少数の楽器によって演奏されます。このようにすることで、歌手が言葉の意味をより明確に伝えられるようになります。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 表現力 | 感情を豊かに表現するための自由なメロディー |
| 伴奏 | 少数の楽器によるシンプルな伴奏 |
| ストーリーテリング | 物語を進めるための重要な技術 |
レチタティーヴォの種類
レチタティーヴォには、大きく分けて2つの種類があります。それは、レチタティーヴォ・セッコ(乾燥したレチタティーヴォ)とレチタティーヴォ・アッレグロ(活発なレチタティーヴォ)です。
- レチタティーヴォ・セッコ:シンプルな伴奏で、主に声の表現に重きを置いています。
- レチタティーヴォ・アッレグロ:伴奏がより豊かで、速いテンポの部分が多いです。
まとめ
レチタティーヴォは、音楽における重要な部分であり、物語を語る役割を担っています。オペラやオラトリオを聴いた際は、レチタティーヴォがどのように使われているのか意識してみてください。あなたも、音楽をより楽しむことができるはずです。
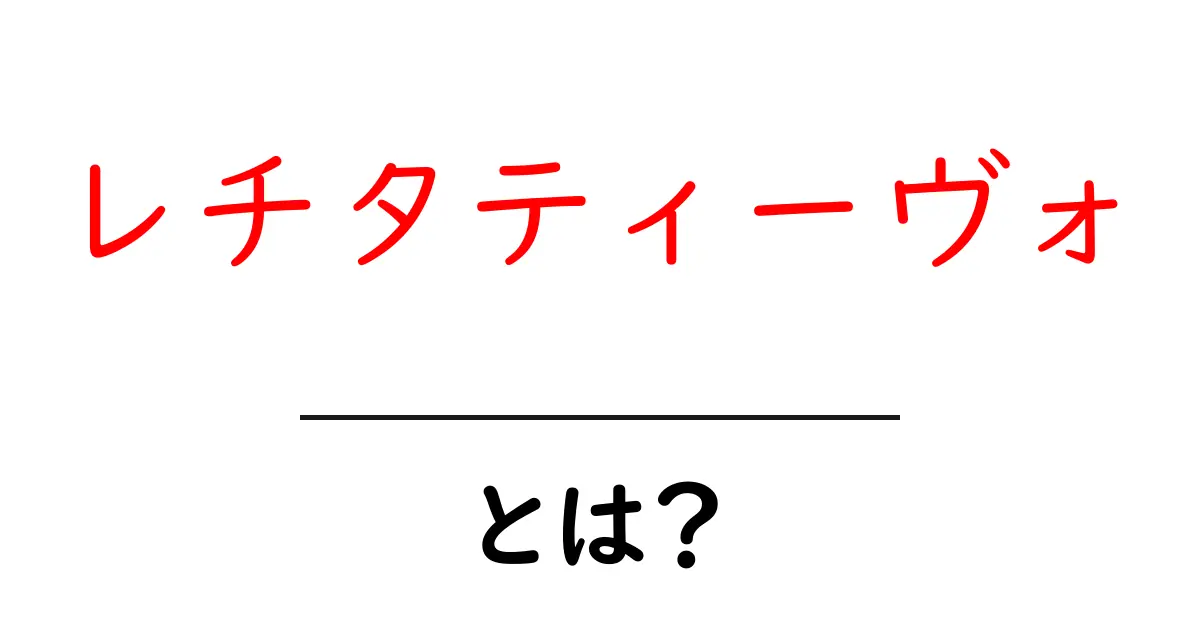
オペラ:音楽と演劇が融合した表現形式で、多くの部分が歌われる。レチタティーヴォはオペラの中で台詞に似た形で歌われる部分を指す.
アリア:独唱の形式で、感情や思いを表現するための歌。レチタティーヴォの後に続くことが多い.
バロック:17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパの音楽様式。レチタティーヴォはこの時期に特に重要な役割を果たした.
セリフ:話し言葉のこと。レチタティーヴォは音楽に乗せてセリフのように歌うスタイル.
楽器伴奏:レチタティーヴォを支えるための楽器による演奏。主にチェンバロやハープシコードが使われる.
ドラマ:物語や俳優の演技に関連する要素。レチタティーヴォは物語を進行させる重要な部分.
即興:その場で創作すること。レチタティーヴォでは歌手が即興で表現することもある.
表現力:感情や意図を効果的に伝える能力。レチタティーヴォは表現力が求められる部分.
抑揚:音楽や声における高低や強弱の変化。レチタティーヴォでは特に抑揚が重要.
ロマン派:19世紀の音楽様式で、感情表現が重視される。レチタティーヴォもこの影響を受ける.
独白:一人の人物が自分の内面的な思いや感情を語る形式。
朗唱:歌唱と話を組み合わせて表現する形式。歌詞を語るように歌うことから、歌の一部を話すように演じることが特徴的。
セリフ:劇やオペラで登場人物が話す言葉。特にキャラクターの意図や感情を伝えるために用いられる。
ナレーション:物語や出来事を説明するために話す言葉。特に、視聴者や観客に情報を提供する役割を果たす。
語り:物語や詩を語りかける形式。文学作品の朗読などに使われ、感情を込めて表現することが重視される。
オペラ:レチタティーヴォは、一般的にオペラの中で用いられる音楽形式の一つです。オペラは、歌と演技を組み合わせた舞台芸術です。
アリア:アリアは、オペラの中での歌唱部分の一つで、感情や状況を表現するための独立した歌です。レチタティーヴォは、アリアに比べてセリフに近いスタイルです。
バロック音楽:レチタティーヴォは、バロック音楽の時代に特に発展した形式で、当時のオペラにおいて重要な役割を果たしました。
セリフ:レチタティーヴォは、音楽とともにセリフを歌う形式であるため、話し言葉に近いスタイルの表現が特徴です。
ドラマ:レチタティーヴォは、オペラやリリカル作品において物語を進行させるための手法であり、感情や筋書きを強調するために重要です。
歌詞:レチタティーヴォの歌詞は、物語の進行やキャラクターの感情を表現するために使われます。そのため、内容が理解しやすいような言葉選びがされています。
リリック:リリックは、特に感情的な内容を持つ音楽作品を指しますが、レチタティーヴォもその一部として感情を表現します。
演出:レチタティーヴォは、演出の中で話の流れをつなぐ役割があり、視覚的な要素と音楽が相乗効果を生んでいます。
音楽劇:音楽劇とは、音楽が物語の中心となる劇の形式で、レチタティーヴォはその一部として活用されることが多いです。